
ススキの名がついてますが、ススキやイグサの仲間ではありませんでした。

その前に 西浦海岸のご紹介。
愛知県には伊勢湾と三河湾および衣浦湾の3つの湾がありますが、西浦海岸は 三河湾に突き出た西浦半島の先端の海岸です。蒲郡市に属しますが、「離島を除いては蒲郡市内で海岸線に自然が残る唯一の場所」(三河の植物観察・観察地案内「西浦海岸」)ということです。
ヒトモトススキは西浦海岸の橋田鼻遊歩道(↑写真参照)にあります。
「西浦半島先端の橋田鼻一帯の海岸に造られた遊歩道です。西側には松島遊歩道が続き、知多、渥美の両半島と大海原を眺めながら散策を楽しめる他、イシガニ、イソガニなど海浜生物を観察できるのも魅力。
「いづくにか船はてすらむ安礼の埼 こぎだみ行きし棚無しの小舟」(高市連黒人作、『万葉集』収)
という歌の通り、一帯は万葉時代から風光明媚な景勝地として知られていました。」(東三河県庁のポータルサイト「橋田鼻遊歩道」)

橋田鼻遊歩道を歩いていると、こんな(簡単に言うと、ガマの穂みたいな)植物が生えていました。 スマホの Google Lensアプリで検索しても イグサの仲間かな?という程度くらいしか分かりません。 でも イグサは穂が茎の一か所につくのですが、この植物は それが「段々咲き」しています。イグサの仲間ではなさそうです・・・

帰ってからパソコンで検索していて、ひょんなことから 上に引用させてもらった「三河の植物観察・観察地案内「西浦海岸」」に行きつき、その記事にしっかりと この植物の写真が載っていたのでした (^^)/ (写真は載っていたけれど、写真の植物の名は出てきません。 ほんとうに ヒトモトススキという名が分かるまでは もう一回りしなければなりませんでした)

「関東地方・新潟県以西〜九州の海岸に生える。植物体は叢生し、大株を作り匐枝がある。(岡山県カヤツリグサ科植物図譜)」(松江の花図鑑)
ヒトモトススキの 「ヒトモト」は「一本」と書き、一株から多数の葉を出す形態からの命名だといいます。
ヒトモトススキの 「ススキ」は ススキの仲間ということでなく、単にススキに似て叢生してるから、ということです。
ススキの仲間でもイグサの仲間でもなく、 カヤツリグサの仲間ということでした。

検索していく中で、面白い記事に出会いました。
ヒトモトススキは wiki にもあるとおり 「分布は広く、中国からインド、マレーシア、オーストラリアまで広がる。日本では関東南部から四国、九州、琉球まで。 海岸近くに多く、海岸では海浜植物などの後方、淡水がわいているような場所に生える。」とあり、特別 珍しい植物ではありません。なのに 東大阪市では このヒトモトススキが市の天然記念物に指定されているというのです。

ヒトモトススキは海岸近くに生える植物です。 そのことに気づくと、 東大阪市をご存じの方は 「はは~ん」 とくるかもしれません。 東大阪市ではこの植物は日下新池という山の中の池の畔に生えています。
現在は 大阪湾は河内平野のむこうにありますが、 地質年代で言えば「つい最近まで」 日下新池のあたりまで大阪湾でした。 「つい最近まで」すなわち、 奈良の纏向の大和政権発足当時には、 河内平野は海原で、奈良盆地には大和湖という大きな湖があり、大和川は信貴山南で急流となって大阪湾に流れ込んでいたのです。
「ヒトモトススキはこの場所で生き続け、結果として昔の海岸の位置を示す指標となり、その学術的価値が市に認められたのです。」(東大阪市天然記念物)
瀬戸内海を抜け、難波の海(今の河内平野)にたどりついた中国商人が、 ヒトモトススキの群落を横目に見ながら、大和川を両岸から船を曳き、生駒山地と金剛山地の間にある「亀の瀬」の渓谷を船で遡り、大和湖から旧大和川を便って (現在の桜井市の)初瀬川河畔の海柘榴市(つばいち、古代市)で おそらく 大和朝廷が胴元だった 宇陀の水銀(辰砂(しんしゃ)) を買い付ける・・・
そんなこと考えながら、海岸近くの湧水のある沢に群生するヒトモトススキを見るのもいいかもしれません (^^♪
〔付記〕
大阪湾の変遷を Gifアニメにした画像がありましたので、お借りしました。
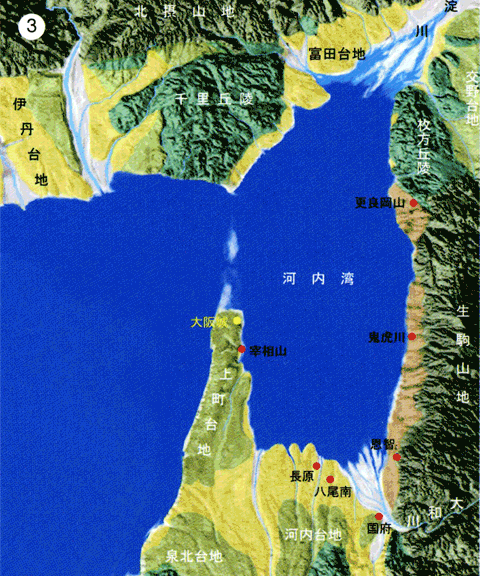
日下新池の現在標高は 90mくらいあり、この標高では いつの時代も海岸線から離れていたことになるのですが、地質的には扇状地地形なので、かつての標高は もっと低かったのでしょう。 縄文海進の時の海面標高は 今の45m付近と言われています。

その前に 西浦海岸のご紹介。
愛知県には伊勢湾と三河湾および衣浦湾の3つの湾がありますが、西浦海岸は 三河湾に突き出た西浦半島の先端の海岸です。蒲郡市に属しますが、「離島を除いては蒲郡市内で海岸線に自然が残る唯一の場所」(三河の植物観察・観察地案内「西浦海岸」)ということです。
ヒトモトススキは西浦海岸の橋田鼻遊歩道(↑写真参照)にあります。
「西浦半島先端の橋田鼻一帯の海岸に造られた遊歩道です。西側には松島遊歩道が続き、知多、渥美の両半島と大海原を眺めながら散策を楽しめる他、イシガニ、イソガニなど海浜生物を観察できるのも魅力。
「いづくにか船はてすらむ安礼の埼 こぎだみ行きし棚無しの小舟」(高市連黒人作、『万葉集』収)
という歌の通り、一帯は万葉時代から風光明媚な景勝地として知られていました。」(東三河県庁のポータルサイト「橋田鼻遊歩道」)

橋田鼻遊歩道を歩いていると、こんな(簡単に言うと、ガマの穂みたいな)植物が生えていました。 スマホの Google Lensアプリで検索しても イグサの仲間かな?という程度くらいしか分かりません。 でも イグサは穂が茎の一か所につくのですが、この植物は それが「段々咲き」しています。イグサの仲間ではなさそうです・・・

帰ってからパソコンで検索していて、ひょんなことから 上に引用させてもらった「三河の植物観察・観察地案内「西浦海岸」」に行きつき、その記事にしっかりと この植物の写真が載っていたのでした (^^)/ (写真は載っていたけれど、写真の植物の名は出てきません。 ほんとうに ヒトモトススキという名が分かるまでは もう一回りしなければなりませんでした)

「関東地方・新潟県以西〜九州の海岸に生える。植物体は叢生し、大株を作り匐枝がある。(岡山県カヤツリグサ科植物図譜)」(松江の花図鑑)
ヒトモトススキの 「ヒトモト」は「一本」と書き、一株から多数の葉を出す形態からの命名だといいます。
ヒトモトススキの 「ススキ」は ススキの仲間ということでなく、単にススキに似て叢生してるから、ということです。
ススキの仲間でもイグサの仲間でもなく、 カヤツリグサの仲間ということでした。

検索していく中で、面白い記事に出会いました。
ヒトモトススキは wiki にもあるとおり 「分布は広く、中国からインド、マレーシア、オーストラリアまで広がる。日本では関東南部から四国、九州、琉球まで。 海岸近くに多く、海岸では海浜植物などの後方、淡水がわいているような場所に生える。」とあり、特別 珍しい植物ではありません。なのに 東大阪市では このヒトモトススキが市の天然記念物に指定されているというのです。

ヒトモトススキは海岸近くに生える植物です。 そのことに気づくと、 東大阪市をご存じの方は 「はは~ん」 とくるかもしれません。 東大阪市ではこの植物は日下新池という山の中の池の畔に生えています。
現在は 大阪湾は河内平野のむこうにありますが、 地質年代で言えば「つい最近まで」 日下新池のあたりまで大阪湾でした。 「つい最近まで」すなわち、 奈良の纏向の大和政権発足当時には、 河内平野は海原で、奈良盆地には大和湖という大きな湖があり、大和川は信貴山南で急流となって大阪湾に流れ込んでいたのです。
「ヒトモトススキはこの場所で生き続け、結果として昔の海岸の位置を示す指標となり、その学術的価値が市に認められたのです。」(東大阪市天然記念物)
瀬戸内海を抜け、難波の海(今の河内平野)にたどりついた中国商人が、 ヒトモトススキの群落を横目に見ながら、大和川を両岸から船を曳き、生駒山地と金剛山地の間にある「亀の瀬」の渓谷を船で遡り、大和湖から旧大和川を便って (現在の桜井市の)初瀬川河畔の海柘榴市(つばいち、古代市)で おそらく 大和朝廷が胴元だった 宇陀の水銀(辰砂(しんしゃ)) を買い付ける・・・
そんなこと考えながら、海岸近くの湧水のある沢に群生するヒトモトススキを見るのもいいかもしれません (^^♪
〔付記〕
大阪湾の変遷を Gifアニメにした画像がありましたので、お借りしました。
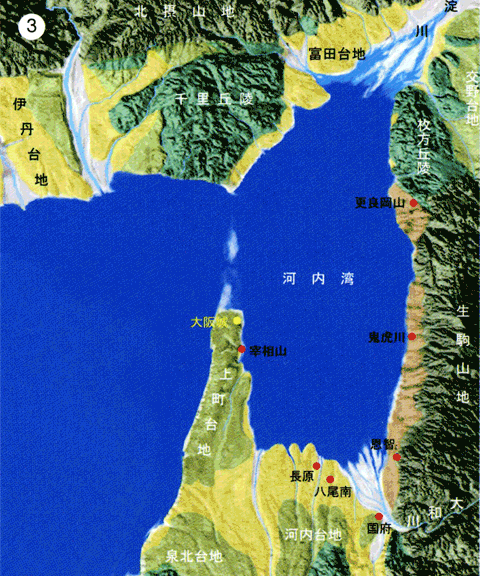
日下新池の現在標高は 90mくらいあり、この標高では いつの時代も海岸線から離れていたことになるのですが、地質的には扇状地地形なので、かつての標高は もっと低かったのでしょう。 縄文海進の時の海面標高は 今の45m付近と言われています。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます