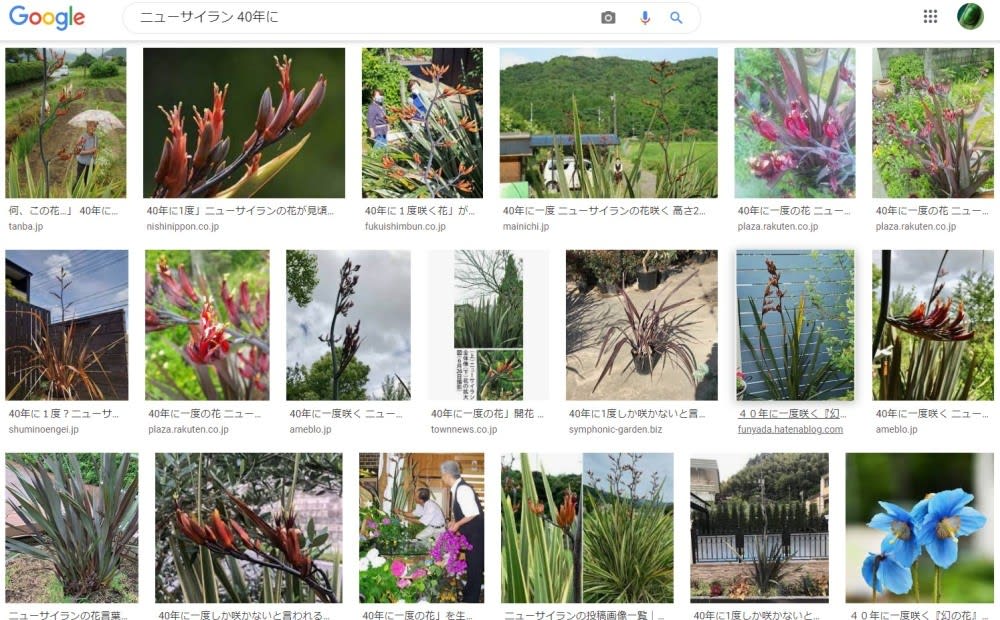この記事は 当初(2019-07-14 10:36)「なんというユリ」と題して投稿していました。
(初出: 2019-07-18 )

デンパークのビール館前の花壇に植えてあった 巨大な蕊をもったユリです。
至近距離で 撮っています。

少し 下がって。
ユリなんですが、その名前8が分かりません。
ラッパが横を向いて咲いているので、スカシユリでないことは分かるのですが。

オニユリなら、花弁の内側に 点々がついてますよね。
〔後記〕「点々」じゃなく、「スポット」っていうんですね


全体はこんな風で、背丈は 2m以上あります!
何という ユリでしょう?
【追記】
えー、なつみかんさんと うたかた花詩さんから、さっそくレスをいただきました \(^o^)/
カサブランカ あるいは イエローカサブランカ(コンカドール)かな?
ということで、さっそく カサブランカとは なんぞや と、少し調べてみたのですが・・・
カサブランカは 「ユリの女王」と言われ、オリエンタルハイブリット系(オリエンタル百合) 不動の一番人気品種!なんですってね。
カサブランカ(Lilium ‘Casa Blanca’)はユリの中でも、
オリエンタル・ハイブリッドという園芸品種群の中の1品種です。(カサブランカとユリの違いは?)
カサブランカは、花が大きくて白くて豪華で、
香りも強くて良いということで、とても人気があります。(同上)
そもそもカサブランカは、スペイン語で「白い家」という意味がついているので、
白色が特徴とされています。(同上)
ということは、典型的なカサブランカではなく、新手のオリエンタル・ハイブリッドの一種ということでしょうか
他のユリ品種によくある、花弁の内側のスポット(斑点)がほぼありません。
スポットがないことで、さらに花弁の白さが際立ちます。
また、とても花が大きく、豪華ながら気品のある雰囲気を放ちます。(同上)
この花弁にスポットがないことは たしかに 大きな特徴ですね。私も 気がつきましたから(^^
それから 別の記事にこんなことが書いてありました:
カサブランカは 花弁の内側に スポットがない。代わりに、花の内側ににツンツンと小さな突起がある!
どういうものか、文章ではよく分からないので、それが分かる画像へのリンク を示します。
カサブランカ(モロッコの都市)がスペイン語で 白い家 を意味してたことを考慮すると、元祖カサブランカというよりも
イエローカサブランカ(コンカドール)
なのかもしれません。
↑
上記で検索すると、ほぼそっくりのユリの画像が出てきます\(^o^)/
長々とすみません。確認してから タイトル変更します。
【後記】2019-7-18
デンパークさんより 返信がありました。
「ユリですが、コンカドールと言う品種と思われます。
(イエローカサブランカとも言われる時もあります)」
【追記】2025-07-07
★コンカドール(Conca d'Or)
元はイタリア語で〈コンカ・ドーロConca d'Oro〉は「黄金の盆地」の意味だそうです。特に、シチリア島のパレルモ周辺の肥沃な平原を指し、オリーブ,かんきつ類,ブドウ酒,硫黄などが主要産物の土地を「コンカドーロ」と呼ぶのだそうです。この名をフランス語圏で「金色のカサブランカ」の愛称として用いるようになったのだそうです。
(初出: 2019-07-18 )

デンパークのビール館前の花壇に植えてあった 巨大な蕊をもったユリです。
至近距離で 撮っています。

少し 下がって。
ユリなんですが、その名前8が分かりません。
ラッパが横を向いて咲いているので、スカシユリでないことは分かるのですが。

オニユリなら、花弁の内側に 点々がついてますよね。
〔後記〕「点々」じゃなく、「スポット」っていうんですね


全体はこんな風で、背丈は 2m以上あります!
何という ユリでしょう?
【追記】
えー、なつみかんさんと うたかた花詩さんから、さっそくレスをいただきました \(^o^)/
カサブランカ あるいは イエローカサブランカ(コンカドール)かな?
ということで、さっそく カサブランカとは なんぞや と、少し調べてみたのですが・・・
カサブランカは 「ユリの女王」と言われ、オリエンタルハイブリット系(オリエンタル百合) 不動の一番人気品種!なんですってね。
カサブランカ(Lilium ‘Casa Blanca’)はユリの中でも、
オリエンタル・ハイブリッドという園芸品種群の中の1品種です。(カサブランカとユリの違いは?)
カサブランカは、花が大きくて白くて豪華で、
香りも強くて良いということで、とても人気があります。(同上)
そもそもカサブランカは、スペイン語で「白い家」という意味がついているので、
白色が特徴とされています。(同上)
ということは、典型的なカサブランカではなく、新手のオリエンタル・ハイブリッドの一種ということでしょうか
他のユリ品種によくある、花弁の内側のスポット(斑点)がほぼありません。
スポットがないことで、さらに花弁の白さが際立ちます。
また、とても花が大きく、豪華ながら気品のある雰囲気を放ちます。(同上)
この花弁にスポットがないことは たしかに 大きな特徴ですね。私も 気がつきましたから(^^
それから 別の記事にこんなことが書いてありました:
カサブランカは 花弁の内側に スポットがない。代わりに、花の内側ににツンツンと小さな突起がある!
どういうものか、文章ではよく分からないので、それが分かる画像へのリンク を示します。
カサブランカ(モロッコの都市)がスペイン語で 白い家 を意味してたことを考慮すると、元祖カサブランカというよりも
イエローカサブランカ(コンカドール)
なのかもしれません。
↑
上記で検索すると、ほぼそっくりのユリの画像が出てきます\(^o^)/
長々とすみません。確認してから タイトル変更します。
【後記】2019-7-18
デンパークさんより 返信がありました。
「ユリですが、コンカドールと言う品種と思われます。
(イエローカサブランカとも言われる時もあります)」
【追記】2025-07-07
★コンカドール(Conca d'Or)
元はイタリア語で〈コンカ・ドーロConca d'Oro〉は「黄金の盆地」の意味だそうです。特に、シチリア島のパレルモ周辺の肥沃な平原を指し、オリーブ,かんきつ類,ブドウ酒,硫黄などが主要産物の土地を「コンカドーロ」と呼ぶのだそうです。この名をフランス語圏で「金色のカサブランカ」の愛称として用いるようになったのだそうです。