(初出:2021-07-08 )

ホルトノキに花が付いているのをはじめてみました。(@安城デンパーク)

ホルトノキという面白い名前は、「平賀源内が、この木をオリーブと間違え、「ポルトガルの木」と呼んだことから。」(樹木図鑑「ホルトノキ」)
花を見てオリーブと間違えたのではなく、秋に実る果実がオリーブの実に似ていたから、というのですが・・・
果実はまだ見ていないので、較べようもありません。

ただ、花は非常にユニークな花です。白い花弁がか細かく糸状に裂けているのです。
そして、 真っ赤に紅葉した古い葉が1年を通して見られます(ということです)。
デンパークの2本あるこの個体はそうでもないのですが、他の方のホルトノキの画像を見ますと、ユズリハに似た樹形をしています。

「梅雨明け頃に開花。」(福原のページ「ホルトノキ(ホルトノキ科)」)

「雌雄同株」としているページがありますが (mirusiru.jp「ホルトノキ」)・・・

イネ科のおしべのような雄しべと子房上位のめしべが一緒にあるから「両性花」(三河の植物観察)でしょう。

繰り返しますが、 イネ科のような雄しべです。ユニークです。
雌しべの花柱は花弁よりも長いようです。

雄しべたちは花粉を出すと単独で ポロポロ落下します。

この花は 一本だけ 雄しべが残っていますが、他はすべて落下しました。
オレンジ色は 蜜を出す花盤のようです。

雌しべと花盤だけになった花。

ホルトノキに花が付いているのをはじめてみました。(@安城デンパーク)

ホルトノキという面白い名前は、「平賀源内が、この木をオリーブと間違え、「ポルトガルの木」と呼んだことから。」(樹木図鑑「ホルトノキ」)
花を見てオリーブと間違えたのではなく、秋に実る果実がオリーブの実に似ていたから、というのですが・・・
果実はまだ見ていないので、較べようもありません。

ただ、花は非常にユニークな花です。白い花弁がか細かく糸状に裂けているのです。
そして、 真っ赤に紅葉した古い葉が1年を通して見られます(ということです)。
デンパークの2本あるこの個体はそうでもないのですが、他の方のホルトノキの画像を見ますと、ユズリハに似た樹形をしています。

「梅雨明け頃に開花。」(福原のページ「ホルトノキ(ホルトノキ科)」)

「雌雄同株」としているページがありますが (mirusiru.jp「ホルトノキ」)・・・

イネ科のおしべのような雄しべと子房上位のめしべが一緒にあるから「両性花」(三河の植物観察)でしょう。

繰り返しますが、 イネ科のような雄しべです。ユニークです。
雌しべの花柱は花弁よりも長いようです。

雄しべたちは花粉を出すと単独で ポロポロ落下します。

この花は 一本だけ 雄しべが残っていますが、他はすべて落下しました。
オレンジ色は 蜜を出す花盤のようです。

雌しべと花盤だけになった花。














































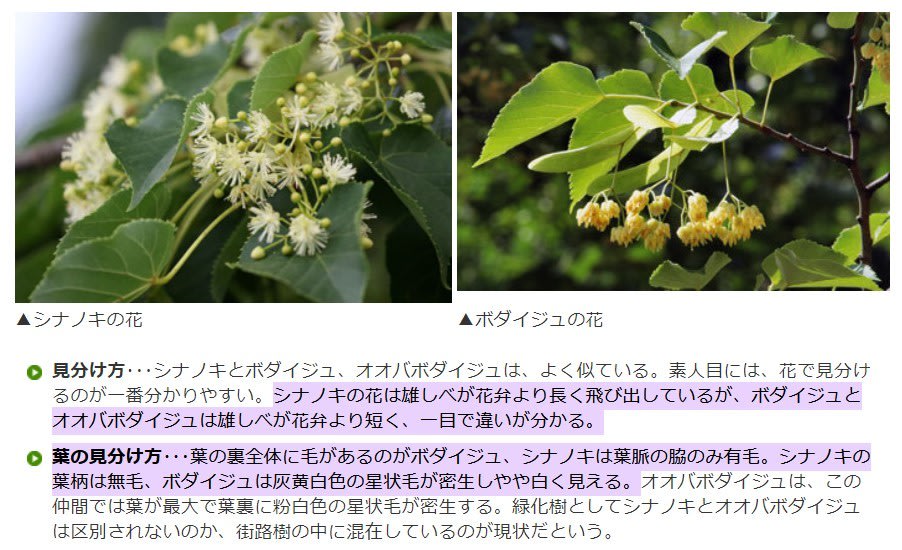












































 タイトルの「ムクゲ、ブッソウゲ」というのは 語呂がいいから。 ふつうなら「ムクゲ、ハイビスカス」というところです (´∀`)見出し画像はずっとまえの9月富山の氷見市海浜植物園で撮......
タイトルの「ムクゲ、ブッソウゲ」というのは 語呂がいいから。 ふつうなら「ムクゲ、ハイビスカス」というところです (´∀`)見出し画像はずっとまえの9月富山の氷見市海浜植物園で撮......

























