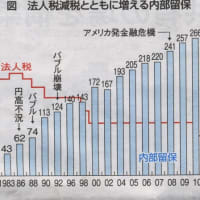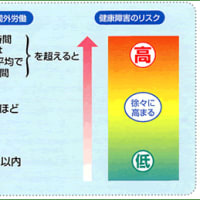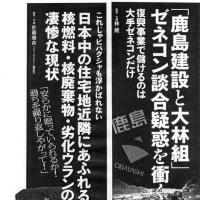前回の図書案内の続きです。
クリスティーンさん(以後、クリスティーンと呼ぶ)は、当初アルツハイマー病と診断され、そう信じて居られたのですが、認知症の原因となる病気には、いろいろなタイプがあるようです。
一般的に多いと云われているのが、「アルツハイマー型認知症」と「脳血管性認知症」だそうでが、例えば、NHK『ためしてガッテン』で紹介された「特発性正常圧水頭症」による認知症は、治療によって症状が改善する可能性があるとの事です。
アルツハイマー型認知症の場合は、残念ながら回復の見込みがなく、クリスティーンの言葉を借りて言うと、「アルツハイマー病は死の原因になる」と云う事です。
彼女はアルツハイマー病について、次のように解説しています。
>アルツハイマー病は、進行はゆっくりだが決してよくなることがない、脳に見られる器質的損傷の結果である。そして、脳が少しずつ損傷を受けていくにつれ、その人の日常生活にも徐々に影響が及ぶようになる。(略)このような意味では、「私たちを明るく引き立ててくれる」ものはない。(略)最後には、生きていくのに必要な普通の身体的な機能が働かなくなるまでに脳が減少してしまうので、いわば死に至る一方通行の道を歩んでいるといってもよいだろう。だから、私たちは精神の病なのではなく、脳の病気なのだということをどうか忘れないでいてほしい。また、辛抱強く接していただくこと、注意深く私たちの話に耳を傾けていただくこと、ゆっくりと物事を進めること、私たちの介護にあたってくれている人たちをできるだけ助けてもらうこと、によって私たちはもっと暮らしやすくなるだろう。
だから、彼女が「私が言える唯一の『奇跡の治療』とは神である」と云うのでしょう。
しかし、彼女は幼少のころから「宗教に目覚めて」いたわけではないようです。
>地元のバプテスト教会の日曜学校へ親友が行っていたので私も行き、学校では聖書を習ったことぐらいだった。その時の印象では、これらはすべて歴史の講義であって、生活を変えるような「今、ここにある」体験ではなかった。
>今では、どんなに私が信仰を必要としていたか、よくわかる。以前は、「自分一人でできる、助力はいらない」という私の自尊心が、何にでもじゃまをした。子どもの時のニックネームは「私できるもん!」だった。
>この先の何年間か、私がどんなにこの信仰を必要とするだろうか、そして、「神のジェットコースター」にやっと間に合うように乗りこんだのだということを(略)私の信仰は、ちょうどジェットコースターのカートのように、しっかりとレールにくっついて人生の起伏やループを通っている。
クリスティーンは、『神』について次のように語っています。
>自分の中にいる神に聞くことはとても大事です。(略)ほとんどのカウンセリングでは精神的なことや魂や神のことは話されないと指摘しました。精神的なこととは、単に宗教のことではなく、自分の生命にとって何が有意義であるのか、という精神状況を探っていくことなのだと思います。人によってそれが、宗教であったり、釣りであったりするのです。自分にとって大事なことを聞いていく。そこから生きていく意味、人生の希望がつかめるのです。
>何が大事かというと、痴呆症によって、感情がかき乱されたとしても魂が大切だと思います。難しいのは、お年寄りが仕事やお金のことばかり考えている場合です。でもそれはなくなってしまうものです。そのような人は、アルツハイマー病と診断されたとき、私よりも衝撃が大きいかと思います。知的能力がなくなり、すべてが消えてしまうでしょう。本当の能力は魂です。それは消えてしまうものではありません。
クリスティーンは、再婚して姓が「ボーデン」から「ブライデン」に替わりました。夫のポール・ブライデンさんは、インタビューに次のように答えています。
(前回紹介したhp「画像メッセージ」のクリスティーンの隣の男性が、ポールさんです)
>精神性(Spirituality)の重要性についても知りました。これは、宗教に限らないことです。私の精神性はキリスト教にもとづいていますが、他の人にとっては、心の平和(平穏)を感じさせているものが何かということです。それは、芸術であったり、絵であったり、歩くことである人もいるでしょう。それに値するものがないまま認知症になると大変な人生を送っていたであろうと言えるようなものです。病に焦点をあてるものではなく、人に焦点をあてることが大切です。(略)クリスティーンの長所をみることが大切です。(略)普通の人は、欠陥ばかりに目が向いてゆきます。私は、長所を励ましています。私はクリスティーンの介護者ではありません。友人であり、夫であり恋人です。(略)彼女は、いままでできたことを失ってゆきますが、あきらめたことに再びチャレンジしています。できるだけ家族の一員として居られるように、何でも一緒にどんどんするよう励ますことが大切だと思っています。(略)今日のことがわかることが大切です。
最終章の第23章「死ぬことを恐れているか?」の書き出しを紹介します。
>人生のジェットコースターの最終回転は、死であるはずだ。多くの人は、それを終わりとして見る。私にとっては、それは天国での生活の始まりで、その時、すべての人々は完全になり、―私でさえも完全なものとなる。もう、個人的な葛藤もなく、悲しみもなく、非難や痛みもない…。だから、私は死を楽しみにしている―というより、死という経験そのものにはとても不安があるのだが、少なくとも死の向こう側にあるものに期待している。
京都大学教授のカール・ベッカー氏は、古くからの日本人の「死」との向き合いについて、次のように語っています。
>人は何年生きたのではなく、何をしたのかです。
物質だけをみていると、死がすべての終わりだと思うかもしれませんが、生きていることは、精神・心・魂を中心とするものであるとわかっていれば、体がなくなることはべつに心や魂がなくなるということではない事を昔の人は知っていたのです。
カール・ベッカー氏によると、昔の日本の家族は、父母が働き手で幼子をみておれないため、祖父母が幼子を育てていた。幼子は大きくなると、今度は病に伏せている祖父母の介護をする。生活の糧を父母が担い、子と祖父母は互いの面倒をみる。それは自然な事で当然な事として機能していたようです。従って、「死」は恐れるものではなかったとカール・ベッカー氏は云います。
だから、祖父母が残念ながら亡くなったとしても、おじいちゃん、おばあちゃんの生き様、知識、声などは今も記憶にあり、仏前で手を合わせ祖父母と対話をする。そして、「おじいちゃん、これから○○へ行ってくるね」等と自然に云えるのでしょう。
カール・ベッカー氏は、それを「先祖の生き様、知識、声なども知っているのだから、それを心で聴いて、それに基づいて生きるのが文明ではないか」と云います。
米国の宗教心理学者デニス・クラスは、これを『続く絆』(continuing bonds)と呼んでいるそうです。
先に、ポール・ブライデンさんの次の言葉「…心の平和(平穏)を感じさせているものが何かということです。それは、芸術であったり、絵であったり、歩くことである人もいるでしょう。…」と精神性の重要性を語っていましたが、カール・ベッカー氏は高齢者の価値について次のように語っています。
>日本では、体力ではなくて、芸・美・人格・精神力にウエートをおいていた。芸・美・精神力に人間の価値をおいている限り、いくら年をとってもまだまだ明日がある。
最後に、小澤勲氏(精神科医)の言葉で、閉めとします。
>これまでは認知症を病む人が私たちを、そしてこの世界をどう見ているかにこころを寄せるという視点が欠けていたのではあるまいか。(略)とすれば、これまでの認知症ケアは、認知症を病む人たちにとってどこか的はずれになっていたに違いない。(中略)認知症を病むということが、人の手を借りて生きざるを得ないということであるとすれば、希望は人と人とのつながりに求められねばなるまい。希望に誘うその手は優しさに加えて認知症を病むことの困難を知り尽くしていなければならないだろう。(略)私たちはこの書によって、ようやくそのスタートラインに立ったと思う。
クリスティーンさん(以後、クリスティーンと呼ぶ)は、当初アルツハイマー病と診断され、そう信じて居られたのですが、認知症の原因となる病気には、いろいろなタイプがあるようです。
一般的に多いと云われているのが、「アルツハイマー型認知症」と「脳血管性認知症」だそうでが、例えば、NHK『ためしてガッテン』で紹介された「特発性正常圧水頭症」による認知症は、治療によって症状が改善する可能性があるとの事です。
アルツハイマー型認知症の場合は、残念ながら回復の見込みがなく、クリスティーンの言葉を借りて言うと、「アルツハイマー病は死の原因になる」と云う事です。
彼女はアルツハイマー病について、次のように解説しています。
>アルツハイマー病は、進行はゆっくりだが決してよくなることがない、脳に見られる器質的損傷の結果である。そして、脳が少しずつ損傷を受けていくにつれ、その人の日常生活にも徐々に影響が及ぶようになる。(略)このような意味では、「私たちを明るく引き立ててくれる」ものはない。(略)最後には、生きていくのに必要な普通の身体的な機能が働かなくなるまでに脳が減少してしまうので、いわば死に至る一方通行の道を歩んでいるといってもよいだろう。だから、私たちは精神の病なのではなく、脳の病気なのだということをどうか忘れないでいてほしい。また、辛抱強く接していただくこと、注意深く私たちの話に耳を傾けていただくこと、ゆっくりと物事を進めること、私たちの介護にあたってくれている人たちをできるだけ助けてもらうこと、によって私たちはもっと暮らしやすくなるだろう。
だから、彼女が「私が言える唯一の『奇跡の治療』とは神である」と云うのでしょう。
しかし、彼女は幼少のころから「宗教に目覚めて」いたわけではないようです。
>地元のバプテスト教会の日曜学校へ親友が行っていたので私も行き、学校では聖書を習ったことぐらいだった。その時の印象では、これらはすべて歴史の講義であって、生活を変えるような「今、ここにある」体験ではなかった。
>今では、どんなに私が信仰を必要としていたか、よくわかる。以前は、「自分一人でできる、助力はいらない」という私の自尊心が、何にでもじゃまをした。子どもの時のニックネームは「私できるもん!」だった。
>この先の何年間か、私がどんなにこの信仰を必要とするだろうか、そして、「神のジェットコースター」にやっと間に合うように乗りこんだのだということを(略)私の信仰は、ちょうどジェットコースターのカートのように、しっかりとレールにくっついて人生の起伏やループを通っている。
クリスティーンは、『神』について次のように語っています。
>自分の中にいる神に聞くことはとても大事です。(略)ほとんどのカウンセリングでは精神的なことや魂や神のことは話されないと指摘しました。精神的なこととは、単に宗教のことではなく、自分の生命にとって何が有意義であるのか、という精神状況を探っていくことなのだと思います。人によってそれが、宗教であったり、釣りであったりするのです。自分にとって大事なことを聞いていく。そこから生きていく意味、人生の希望がつかめるのです。
>何が大事かというと、痴呆症によって、感情がかき乱されたとしても魂が大切だと思います。難しいのは、お年寄りが仕事やお金のことばかり考えている場合です。でもそれはなくなってしまうものです。そのような人は、アルツハイマー病と診断されたとき、私よりも衝撃が大きいかと思います。知的能力がなくなり、すべてが消えてしまうでしょう。本当の能力は魂です。それは消えてしまうものではありません。
クリスティーンは、再婚して姓が「ボーデン」から「ブライデン」に替わりました。夫のポール・ブライデンさんは、インタビューに次のように答えています。
(前回紹介したhp「画像メッセージ」のクリスティーンの隣の男性が、ポールさんです)
>精神性(Spirituality)の重要性についても知りました。これは、宗教に限らないことです。私の精神性はキリスト教にもとづいていますが、他の人にとっては、心の平和(平穏)を感じさせているものが何かということです。それは、芸術であったり、絵であったり、歩くことである人もいるでしょう。それに値するものがないまま認知症になると大変な人生を送っていたであろうと言えるようなものです。病に焦点をあてるものではなく、人に焦点をあてることが大切です。(略)クリスティーンの長所をみることが大切です。(略)普通の人は、欠陥ばかりに目が向いてゆきます。私は、長所を励ましています。私はクリスティーンの介護者ではありません。友人であり、夫であり恋人です。(略)彼女は、いままでできたことを失ってゆきますが、あきらめたことに再びチャレンジしています。できるだけ家族の一員として居られるように、何でも一緒にどんどんするよう励ますことが大切だと思っています。(略)今日のことがわかることが大切です。
最終章の第23章「死ぬことを恐れているか?」の書き出しを紹介します。
>人生のジェットコースターの最終回転は、死であるはずだ。多くの人は、それを終わりとして見る。私にとっては、それは天国での生活の始まりで、その時、すべての人々は完全になり、―私でさえも完全なものとなる。もう、個人的な葛藤もなく、悲しみもなく、非難や痛みもない…。だから、私は死を楽しみにしている―というより、死という経験そのものにはとても不安があるのだが、少なくとも死の向こう側にあるものに期待している。
京都大学教授のカール・ベッカー氏は、古くからの日本人の「死」との向き合いについて、次のように語っています。
>人は何年生きたのではなく、何をしたのかです。
物質だけをみていると、死がすべての終わりだと思うかもしれませんが、生きていることは、精神・心・魂を中心とするものであるとわかっていれば、体がなくなることはべつに心や魂がなくなるということではない事を昔の人は知っていたのです。
カール・ベッカー氏によると、昔の日本の家族は、父母が働き手で幼子をみておれないため、祖父母が幼子を育てていた。幼子は大きくなると、今度は病に伏せている祖父母の介護をする。生活の糧を父母が担い、子と祖父母は互いの面倒をみる。それは自然な事で当然な事として機能していたようです。従って、「死」は恐れるものではなかったとカール・ベッカー氏は云います。
だから、祖父母が残念ながら亡くなったとしても、おじいちゃん、おばあちゃんの生き様、知識、声などは今も記憶にあり、仏前で手を合わせ祖父母と対話をする。そして、「おじいちゃん、これから○○へ行ってくるね」等と自然に云えるのでしょう。
カール・ベッカー氏は、それを「先祖の生き様、知識、声なども知っているのだから、それを心で聴いて、それに基づいて生きるのが文明ではないか」と云います。
米国の宗教心理学者デニス・クラスは、これを『続く絆』(continuing bonds)と呼んでいるそうです。
先に、ポール・ブライデンさんの次の言葉「…心の平和(平穏)を感じさせているものが何かということです。それは、芸術であったり、絵であったり、歩くことである人もいるでしょう。…」と精神性の重要性を語っていましたが、カール・ベッカー氏は高齢者の価値について次のように語っています。
>日本では、体力ではなくて、芸・美・人格・精神力にウエートをおいていた。芸・美・精神力に人間の価値をおいている限り、いくら年をとってもまだまだ明日がある。
最後に、小澤勲氏(精神科医)の言葉で、閉めとします。
>これまでは認知症を病む人が私たちを、そしてこの世界をどう見ているかにこころを寄せるという視点が欠けていたのではあるまいか。(略)とすれば、これまでの認知症ケアは、認知症を病む人たちにとってどこか的はずれになっていたに違いない。(中略)認知症を病むということが、人の手を借りて生きざるを得ないということであるとすれば、希望は人と人とのつながりに求められねばなるまい。希望に誘うその手は優しさに加えて認知症を病むことの困難を知り尽くしていなければならないだろう。(略)私たちはこの書によって、ようやくそのスタートラインに立ったと思う。