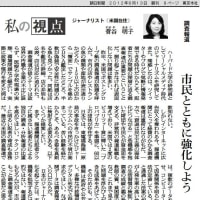ハーバードのデザインスクール(建築大学院)のLoeb Fellow(特別研究員)で、Sweetenという家のリノベーションを支援するサイトを立ちあげ、ニューヨーカー誌で、2011年に最もイノベーティブな試みのひとつ、と評価されているニューヨークの建築家と、フィラデルフィアの建築評論家の三人で、素晴らしいお天気のもと、レストランのテラスでランチ。発想が柔軟でクリエイティブなふたりとは、去年の秋にケネディスクールのメディア関係の授業で知り合い、意気投合。彼女たちが企画したシンポジウムなども、触発されるものばかり。何より、これまでなかったものを、次々に生み出して行く姿勢に、とても共感できる。とりわけ、このところ、ジャーナリストには、クリエイティブな思考が欠けているのではないか、と思う出来事に遭遇することが多く、前向き思考の人といると、かなりほっとする自分に気がついた。
さて、自分のことはさておき(汗)、ニーマンフェローのジャーナリスト仲間は、人の批判や突っ込みを入れることは得意とするけれど、新しい発想を生み出すことはかなり苦手だと思っていたのだが、それを再認識したランチでもあった。ジャーナリストは基本的に、社会のウォッチドッグとして、権力を監視するのが仕事という使命があり、そのように訓練されてきたからなのかもしれないが、特にメディア環境が大きく変っている今、既存のものに対して、批判しているだけでは、斜陽産業となったジャーナリズムに、新しい血を注入して、イノベーションを起こすことは難しいのではいかと思ってしまう。
例えば、セミナーに、デジタルネットワーク環境を活かして、新しいジャーナリズムの実践を行っている人などがゲストで来ることはよくあるのだけれど、基本的に、多くのジャーナリスト仲間たちは、自分たちが行って来た伝統的なジャーナリズムの手法が最良、という姿勢があるので、議論がなかなか発展しないことが少なくない。一番多いのは、客観性、真実の追求、お金を出す側との中立性の関係といった点。勿論、これらはジャーナリズムにおいては非常に大切なことなのだけれど、メディア環境が変わっている今、基本を抑えつつも、トライ&エラーを繰り返しつつ、新しいあり方を探って行くことは大事だと思うので、良い点も評価しつつ、応援する姿勢も大事だと思うのだけれど、なかなかそういう方向に行かず、自己防衛的になりがちの人が少なくない。
先日もあるワークショップで、某フリーランスジャーナリストが、ソーシャルファンドのキックスターターを使って、数日で4000ドルを集め、イスラエル関連の記事を執筆して、記事が高い評価を受けたという報告があった。記事の詳細は明示せず大枠だけで資金を募集し、また、資金提供者による、記事の内容への介入もなかったようだが、結局、論点は、寄付してくれた人が匿名の場合、その人との政治的利害が明確にならないので、クラウドファンディングは論外、というようなものとなった。
この日のディスカッションのテーマは、世界の様々なところで起こっている、「市民が考えるべき重大な問題」が、新聞社等の予算削減で報道されなくなってきているが、そのオルタナティブとして、資金をどう調達すべきだか、というものだった。余談だが、こういう話しでも、読者の存在が全く無視されているところも気になる。
本来であれば、こうした機会にアイディアをどんどんを出して、ブレインストーミングし、新しいモデルを考え出して行くべきだと思うのだけれど、なんとなく記者会見風となり、テーマに対しての突っ込みだけで終わってしまうというパターンが多いのがとても残念に思える。どうも、「ジャーナリストは「良い記事」を書くことだけに専念し、他のことは切り離して考えるべきだ」という発想だけが強すぎる気がするが、「良い記事」とは何なのか、読者との関係は、そして何より、記事を書くだけでなく、それをどう読んでもらえるようにするのか、という流通の点まで、考える必要があると思うのだけれど、そういう発想はどうも「邪道」とみなされてしまう。また、大手メディア企業に所属する人は、危機感が少ないために、新しいメディア環境にも敏感とは言いがたい。また、フェロー仲間の三分の一近くがピューリッツアー賞受賞など、ジャーナリズムの「メインストリーム」にいることも、関係しているのかもしれない。
こういう議論を聞くにつれ、ぼやぼやしている間に、最近の「ジャーナリズム」には、「外部」から様々な取り組みがあるというのに、と冷や冷やしてしまう...。アマゾンが出版社ではなかったように、「革命」はジャーナリズムが予想もしない新規参入者によって起きるのかもしれない。特権的パワーを持った組織や人々が、ネットにより様々な形で揺さぶられていることと、その中核にいる人たち動きの鈍さを改めて感じている。
私はジャーナリムズの大事さは十分に理解しているつもりだけれど、従来のジャーナリズムのあり方を「保護」することには関心はない。ジャーナリズムが市民のためにどうあるべきなのか、そしてメディア環境が大きく変わっている今、その形を変える必要があるとも思っている。仮にそれがジャーナリズムと呼ばれるものでなくても、一番大事なことは、今の時代にあった「機能」が果たせるものを生み出して行くことだと思う。
というわけで、ちょっと、最近、もやもやしているものを抱えていただけに、クリエイティブな人たちとの会話は、触発されるものが多く、とても楽しめた。
「守りに入ったらおしまい。やはりいつも攻めに出ていたい」。
そして、少なくとも自分は、過去の遺産にすがるのではなく、ポジティブに進化していきたい、との意を新たにした(ちと大げさですがw)午後でした☆
さて、自分のことはさておき(汗)、ニーマンフェローのジャーナリスト仲間は、人の批判や突っ込みを入れることは得意とするけれど、新しい発想を生み出すことはかなり苦手だと思っていたのだが、それを再認識したランチでもあった。ジャーナリストは基本的に、社会のウォッチドッグとして、権力を監視するのが仕事という使命があり、そのように訓練されてきたからなのかもしれないが、特にメディア環境が大きく変っている今、既存のものに対して、批判しているだけでは、斜陽産業となったジャーナリズムに、新しい血を注入して、イノベーションを起こすことは難しいのではいかと思ってしまう。
例えば、セミナーに、デジタルネットワーク環境を活かして、新しいジャーナリズムの実践を行っている人などがゲストで来ることはよくあるのだけれど、基本的に、多くのジャーナリスト仲間たちは、自分たちが行って来た伝統的なジャーナリズムの手法が最良、という姿勢があるので、議論がなかなか発展しないことが少なくない。一番多いのは、客観性、真実の追求、お金を出す側との中立性の関係といった点。勿論、これらはジャーナリズムにおいては非常に大切なことなのだけれど、メディア環境が変わっている今、基本を抑えつつも、トライ&エラーを繰り返しつつ、新しいあり方を探って行くことは大事だと思うので、良い点も評価しつつ、応援する姿勢も大事だと思うのだけれど、なかなかそういう方向に行かず、自己防衛的になりがちの人が少なくない。
先日もあるワークショップで、某フリーランスジャーナリストが、ソーシャルファンドのキックスターターを使って、数日で4000ドルを集め、イスラエル関連の記事を執筆して、記事が高い評価を受けたという報告があった。記事の詳細は明示せず大枠だけで資金を募集し、また、資金提供者による、記事の内容への介入もなかったようだが、結局、論点は、寄付してくれた人が匿名の場合、その人との政治的利害が明確にならないので、クラウドファンディングは論外、というようなものとなった。
この日のディスカッションのテーマは、世界の様々なところで起こっている、「市民が考えるべき重大な問題」が、新聞社等の予算削減で報道されなくなってきているが、そのオルタナティブとして、資金をどう調達すべきだか、というものだった。余談だが、こういう話しでも、読者の存在が全く無視されているところも気になる。
本来であれば、こうした機会にアイディアをどんどんを出して、ブレインストーミングし、新しいモデルを考え出して行くべきだと思うのだけれど、なんとなく記者会見風となり、テーマに対しての突っ込みだけで終わってしまうというパターンが多いのがとても残念に思える。どうも、「ジャーナリストは「良い記事」を書くことだけに専念し、他のことは切り離して考えるべきだ」という発想だけが強すぎる気がするが、「良い記事」とは何なのか、読者との関係は、そして何より、記事を書くだけでなく、それをどう読んでもらえるようにするのか、という流通の点まで、考える必要があると思うのだけれど、そういう発想はどうも「邪道」とみなされてしまう。また、大手メディア企業に所属する人は、危機感が少ないために、新しいメディア環境にも敏感とは言いがたい。また、フェロー仲間の三分の一近くがピューリッツアー賞受賞など、ジャーナリズムの「メインストリーム」にいることも、関係しているのかもしれない。
こういう議論を聞くにつれ、ぼやぼやしている間に、最近の「ジャーナリズム」には、「外部」から様々な取り組みがあるというのに、と冷や冷やしてしまう...。アマゾンが出版社ではなかったように、「革命」はジャーナリズムが予想もしない新規参入者によって起きるのかもしれない。特権的パワーを持った組織や人々が、ネットにより様々な形で揺さぶられていることと、その中核にいる人たち動きの鈍さを改めて感じている。
私はジャーナリムズの大事さは十分に理解しているつもりだけれど、従来のジャーナリズムのあり方を「保護」することには関心はない。ジャーナリズムが市民のためにどうあるべきなのか、そしてメディア環境が大きく変わっている今、その形を変える必要があるとも思っている。仮にそれがジャーナリズムと呼ばれるものでなくても、一番大事なことは、今の時代にあった「機能」が果たせるものを生み出して行くことだと思う。
というわけで、ちょっと、最近、もやもやしているものを抱えていただけに、クリエイティブな人たちとの会話は、触発されるものが多く、とても楽しめた。
「守りに入ったらおしまい。やはりいつも攻めに出ていたい」。
そして、少なくとも自分は、過去の遺産にすがるのではなく、ポジティブに進化していきたい、との意を新たにした(ちと大げさですがw)午後でした☆