前回は休みました。前々回(7/10)は、戯作者・平賀源内の作品『風流志道軒伝』(一七六三)の新しさについて、の話題でした。この作品は主人公深井浅之進(後の志道軒)の遍歴譚ですが、源内以前のそれといえば「地獄極楽を遍歴して因果の理を悟るとか、日本国内を色道修業に回る」とかの話に決まっていました。源内の新しさは、どこを遍歴させるか、それを外国に求めた着想にあったのです。ではそこでいう「外国」とはどこか、といえば当時知りえたオランダその他の西洋の国々ではなく、『和漢三才図会』は『増補華夷通商考』などに見えるお伽話のレベルの国々(大人国や小人国など)か、古来の民間伝承のなかの国々(女護が島など)、つまり架空の国々でありました。しかし、日野龍夫「近世文学に現われた異国像」で、著者は源内の描く深井浅之進の遍歴体験はお伽話に終わっていないこと、そこには平賀源内の「知識人としての海外認識」が反映されている、と指摘していました。その海外認識とはどのようなことを指しているのか、今回はこれを紹介してみます。
≪源内は、本草学の実用化の功をあせって、エレキテルの製作や鉱山の採掘に東奔西走、結局オランダ語の習得という地道な努力をしなかった人であるから、青年時から交際のあった杉田玄白のようなまともな蘭学者ではない。しかし、西洋の新奇な文物に接して、新奇であるがゆえにそれを警戒嫌悪するのではなく、新奇であるがゆえにそれに関心を寄せるという精神の柔軟さと、我流ではあっても、それをなんとか実用面に応用しようと努める旺盛な意欲と、封建制の枠内に安住して新しいことを何一つしようとしない世間に対する苛立ちとは、新奇な文物の背後には日本と異なった文化が存在するということをおのずから源内に悟らせ、その地平から照射することによって、自分の住む近世中期の日本の文化を相対化することを可能にさせた。/知識人の海外認識とは、このことをいう。『風流志道軒伝』における海外の架空の国々は、そのお伽話の非現実性が日本の現実を相対化するという役割を源内から与えられているのである。読物としての取っつきやすさ、ないし作者としての滑稽な誇張のしやすさという都合もあって、『和漢三才図会』や『増補華夷通商考』でお馴染みの国々が持ち出されてはいるが、それらはいわば西洋の国々を代行していると解される。≫(前掲論文)
『風流志道軒伝』が、架空の外国の遍歴譚であるのにもかかわらず、その数々の「外国」体験が単なるお伽話に終わっていないのはなにゆえか。そこに源内の「知識人としての海外認識」がみてとれるからです。それは、「西洋の新奇な文物に接して、新奇であるがゆえにそれを警戒嫌悪するのではなく、新奇であるがゆえにそれに関心を寄せるという精神の柔軟さと、我流ではあっても、それをなんとか実用面に応用しようと努める旺盛な意欲と、封建制の枠内に安住して新しいことを何一つしようとしない世間に対する苛立ちとは、新奇な文物の背後には日本と異なった文化が存在するということをおのずから源内に悟らせ、その地平から照射することによって、自分の住む近世中期の日本の文化を相対化することを可能にさせた」認識のことです。長文なので、順に見ていきます。まず源内の三つの見方・考え方です。①と②は資質といっていいかもしれません。
①新奇であるがゆえにそれに関心を寄せるという精神の柔軟さ
②実用面に応用しようと努める旺盛な意欲
③封建制の枠内に安住して新しいことを何一つしようとしない世間に対する苛立ち
簡単にいえば、以上の三つの見方・考え方は、以下の「知識人としての海外認識」を生みだす土台と捉えることができます。これを簡略して、①「新奇なものに対する精神の柔軟さ」、②「実用化への意欲」、③「世間への苛立ち」と言い直せます。では、以上の三つは源内の認識をどう変えたというのでしょう。
④新奇な文物の背後には日本と異なった文化が存在するということをおのずから源内に悟らせた。
⑤その地平から照射することによって、自分の住む近世中期の日本の文化を相対化することを可能にさせた。
ということになります。これを砕いて言えば、④新奇なものの背景には自文化とは異なる文化が存在すること、(このようにみれば)⑤自国の文化は絶対ではありえないし、他の多様な文化の一つであることに心づく、ということだと言えます。今風に一言にしてしまえば、「文化相対主義」あるいは「多文化主義」ということになります。一方、「知識人」としての認識を、ここでは民衆的想像力(認識)との対概念と捉えますと、源内の、時代に対する批評家としての特徴という面が問題になってくると思われます。それゆえ、続いて著者は他の蘭学者の海外認識と比較していく作業に入ります。ここは次回に。
ところで先ほど私は、源内の三つの見方・考え方を「知識人としての海外認識」を生みだす土台としてを位置づけました。このうち①の「新奇なものに対する精神の柔軟さ」とは、紛れもなく子供の認識的な特徴、あるいは大人になっても失わない子供性と呼ぶことができます。ここに出てきた「新奇なもの」とは、単に見かけのうえでの新奇さばかりを意味しているわけではありません。そこには一寸した問いかけた実験によって、日常の見方をくつがえす小さな発見をもたらすような試みが当然含まれています。「精神の柔軟さ」とはそういうことです。従来の固定した・絶対的な見方を相対化するには、認識上の「子供性」が必要なことを示唆しているようです。














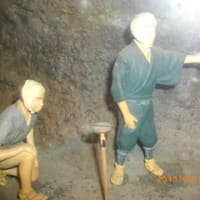




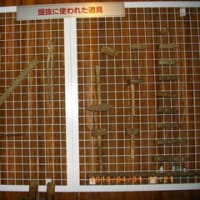
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます