前回(2/4)で、岡倉由三郎に代って執筆した福原麟太郎の「英語教育の目的と価値」を読み終りました。今回は昭和十三年三月号の『文藝春秋』誌に発表された藤村 作「中学英語科全廃論」を紹介しようと一読してみました。一読後これは以前(昨年9/10ブログ)読んだ戦後の加藤周一「信州の旅から──英語の義務教育化に対する疑問──」(昭和三〇)によく似た議論であることに心づきました。昭和三〇年は、戦後の英語教育批判の議論が登場した年です。そこには二つの批判的潮流がありました。一つは加藤周一らの英語の義務教育化に対する批判です。二つは実業界からもっと役立つ英語教育をして欲しいという批判的要望でした。後者は戦後の高度成長の担い手を期待してのことであり、前者はそのような体制に適応させる教育への疑問だったということが出来ます。総じて双方の英語教育論が時代の変化というものに敏感に反応していたことは同じです。
敗戦をはさんでホンの二十年前の話です。昭和十一年師走の前掲福原論文(英語教育擁護論)は昭和初期からくすぶっていた「英語教育廃止論」に対して周到に準備された文章でした。では、今回の昭和十三年三月の藤村論文「中学英語科全廃論」はどうでしょうか。タイトルからして「時代の変化」に敏感に反応した文章であることがわかります。戦前の議論は戦後のそれの原型だと考えてもいいとすれば、ここでもっとはっきりと時代の変化を捉える必要があると考えます。これから(いや現在かも)反復されるかもしれない時代変化と英語教育論争の関係を自覚する手がかりになると考えるからです。今回の藤村 作「中學英語科全廃論」の冒頭段落はその関係が色濃く反映された文章です。
≪(一)教科目再検討の必要
教育審議会が出来て、達識の諸子がこの国家の重大問題に予(アズカ)っての経験と見識とを傾けて、審議を重ねていられることであろう。教育制度の全般的改革、義務年限の延長、専門学校大学までの修業年限の短縮、教科目の整理、教科内容の改善、等々、国家の必要としている教育刷新のことは多々ある。併(シカ)し現今の初中等学校に於ける教科目を検討して、その不備不合理を訂正するところの教科目整理は、他の問題と連関して必ず十分に考慮されなければならないことである。何となれば、仮に現在の教科目がすべて欠くべからざるものであり、それには現行の時数を必要とするとすれば、修業年限の短縮は程度を下げなければ不可能に近かろう。又若し現行の小学校教科目の中に削られるべきものがあり、又その時数を減じて可なるものがあるとするならば、義務年限の延長も必ずしも今一般に考えられている八年を必要としないことになるかも知れない。こういうことがいろいろあるから、我々は教育制度改革の行われようとするに当って、ここに教科目について再検討をなし各科目の教育価値を十分に再吟味して時間数をも定め、それから自然に定まるところの教育年限がもっとも合理的な年限となる筈である。初めから年限短縮を定めてかかるような審議になると、国家文運の発展を阻害する結果を将来しないとは保障されない。又初めから義務年限延長を決めてかかると、無益な経費の負担を国民に強うることともなろう。この意味に於て余は現行制度中の各教科目の教育価値に就いて再検討をなすことを望むものである。そうしてもっとも必要の感ぜらるる教科目は、中等学校に於ける英語科と、初中等学校に於ける数学科であろうと思う。≫(川澄哲夫編『英語教育論争史』 五三〇~一頁)
引用中には当時における教育改革の動向が描かれています。「教育審議会」「国家の重大問題」「教育制度の全般的改革、義務年限の延長、専門学校大学までの修業年限の短縮、教科目の整理、教科内容の改善、等々、国家の必要としている教育刷新」などの言葉に表れている動向を一言でいえば、「戦時教育体制の進行」です。また藤村作が中等学校における英語科の問題に言及していくまでの記述は、前掲の福原の議論とくらべ、スキがなく論理的に考えればこうなるでしょ。こう考えるしかないでしょ、こういう圧力を感じる文章です。それは福原のように、長い歴史的存在としての英語からはじまって英語教育の目的と価値について意を尽して述べた意見、それゆえ読者に考えさせる文章とは受ける印象がまるで異なっています。たとえば「仮に現在の教科目がすべて欠くべからざるものであり、それには現行の時数を必要とするとすれば」という条件設定の物言いです。だれも普段はそんなことなど考えてはいない場合を故意に設定して、「修業年限の短縮は程度を下げなければ不可能に近かろう」などと、本当に教育の質が低下してしまうかも知れないという不安を煽る物言いです。何だかそうなってしまうと思い込ませる緊張感が感じられます。この必然性を装った言葉は、架空の状態を想定したときに得られる想像の一つにすぎません。だから本質的に嘘です。こういう物言いは煽動者のプロパガンダにしばしば見られる現象です。気をつけなければいけません。














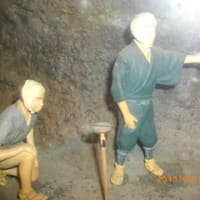




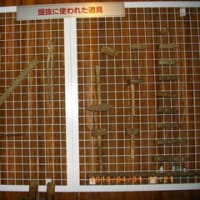
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます