前回(2/15)は、柳田國男「昔の国語教育」の最終章ともいうべき「後記」を読みました。ここでの話題は「二種類の敬語」と「伝承としての国語教育の謎」の二つあります。前者の敬語の話題はまだ途中で、どこまで読みとったかというと、こうです。まず敬語の教育には「共同共用敬語」から「比較敬語」へと二段階あったこと。後者の敬語については、必ずしも子供にとっては学びやすい言葉ではないことが説かれていました。にも拘らず、世の中の交際が盛んになると、それまで気軽だった関係にも敬語(晴の言葉)が入ってくることになりました。こうなると、さほどの敬語を使ってきたわけでもない目上の相手にも敬意を表す必要がでてきて、自分の家族を話題にする時には「わざと卑しめる言葉遣いをすることが多くなって」きたのです。そのためにさらに一段と学びにくくなってきたというわけです。これが「比較敬語」が抱える問題です。そして敬意を表すべき人の前で第三者のことをどう言えばいいのか、この問題は未解決です。今回は、これについての柳田の考えを紹介しましょう。以下の引用は前回からの続きです。(段落は私の方で区切ったものです)
≪支那では弊邦(へいほう)だの寡君(かくん)だのと、わが国わが主をも卑しめていう辞令が元は普通だったが、これだけは我々はもうやらぬことにしている。わが村の鎮守や家の氏神(うじがみ)なども、いくら長者に対してでも謙遜(けんそん)して悪くいうことはないが、親や兄姉などの最もわが身に近い人のことは、さほど貴い相手に向かってでもなくとも、まずは遠慮して内々の敬語を、差し控えるのが今日までの通則になっていた。日頃は父母を敬えと教えられる児童が、他人に対する時だけは粗末にいう方がよいということに、合点の行かぬのももっともであり、また読本(トクホン)にもそうは書いていないのである。この微妙なる自他の境目は、実は日本語の最も歴史的なるもの、精神文化というものの成長を痕(あと)づけている部分であるが、悲しむべし今は混乱に陥ろうとしている。
それから今一つの誤りのもとは、敬語と良い言葉との差別を知らぬ者が、だんだんに多くなって来たことである。なるほど上品なよい生活をしている人々の間に、敬語は最も発達し複雑になっていることは事実だが、これはある時代の必要がそうさせたというに止まり、こうなくてはならぬという理由は別にないことは、今後もし修正を加えるとすれば、まずこの部分に省くべきものが多いのを見てもわかる。また現在もすでにどしどしと、この方面の物言いが、廃れもしくは改まっても行くのである。良い言葉の標準は、必ずしも敬語の分量でないことに気づかねばならぬのである。人が心の内に持つ自然の敬意が、十分に表われるということの方がそれよりも大切である。しかも何人(なんぴと)を敬すべきかということは、言葉ばかりでは指導せられない。他人を敬うあまりに自分の心から貴重する者を、粗末にいう習わしにも批判の余地がある。現に東京では女房が人の前で、わが夫を呼棄(よびす)てにする風は久しく行なわれていたが、関西では様附けにしたり、少しの敬語を添えたりすることは珍しからぬのみか、こちらでも今はだんだんと亭主呼棄てをよい趣味とは考えぬようになりかかっている。
截然(せつぜん)たる法則はおそらくは立てられまい。結局は程度問題に帰着するのかも知らぬが、少なくとも現在はよその人の前で、家の目上を敬称して説くことは、幼児のほかには許されていないのである。しかるに読本に「おとうさまが何々とおっしゃいました」などと書いて、これが同輩ばかりの共同の敬語だということを教えない結果は、たちまち髭男(ひげおとこ)が人の前に出て、緑児同様の口のきき方をする者を生ずる。全く第二種敬語の人により場合によって、細かく変るものなることに心づかず、これを絶対の良い言葉のごとく思い込ませた災いであった。一つの国語のかくまで発達した機能を、殺して伝えるということは国語教育でない。しかもこの弱点を補強する手段といってもそう面倒ではなく、つまり私の考えているようなことを。もう少し精確に突き留めて、それを誰にもわかるように、平易に説明してやればそれでよいのである。≫(柳田國男「昔の国語教育」/ちくま文庫版『柳田國男全集』第二二巻 一二三~四頁)
柳田國男の解決策は、彼が考えていることを「もう少し精確に突き留めて、それを誰にもわかるように、平易に説明してやればそれでよい」というものです。なんと、柳田の文章が読んですぐわかるものだったら、こうして解読を綴らなくてもいいわけで、アンタがやらないでどうするのか、と憤慨したくなります。それにしても、『岩波講座 国語教育』(昭和十二年)の一巻をなす作品としてはだいぶ大胆なことを書いたものです。紙数が不足したために必要な説明も省略したのでしょう。不足していると思われる説明をいくつか挙げてみます。
一つは、「親や兄姉などの最もわが身に近い人のことは、さほど貴い相手に向かってでもなくとも、まずは遠慮して内々の敬語を、差し控えるのが今日までの通則になっていた」とあるが、なぜ「今日までの通則」になることができたのか。二つ、「この微妙なる自他の境目は、実は日本語の最も歴史的なるもの、精神文化というものの成長を痕(あと)づけている部分であるが、悲しむべし今は混乱に陥ろうとしている」とあるが、「微妙なる自他の境目」だの「精神文化というものの成長」だの、もっと具体的に説いてもらわなければ伝わらない。三つめは、「今一つの誤りのもとは」の一句が突然出てきて戸惑いが隠せないことです。だいぶ端折って書いたなと感じさせる箇所です。私なりに解釈するとこうなります。比較敬語が盛んに使われるようになると、児童がこれをどう言えば分からなくて困る、と、これは教育としては誤った事態です。「誤り」の原因になったのは、「比較敬語」がさかんに用いられる中で、自他の境目が混乱してしまったことにあります。もう一つの原因は「敬語と良い言葉との差別を知らぬ者が、だんだんに多くなって来たことである。」と叙述が続くと受けとればいい。
ならば、はずせないポイントはどこだったのか。それは今述べた、敬語と良い言葉とを区別できない者がだんだん多くなってきた、というくだりから導かれることです。良い言葉とは敬語のことだと思いこんでいると、敬語をジャンジャン使えばいいという発想になりがちです。こうなると形式的な適用が多くなり、おかしな言い間違いも増えることでしょう。こうではなく、敬語は良い言葉の一つであって、その本質は「人が心の内に持つ自然の敬意が、十分に表われるということ」にあるはずです。そうであれば、肝腎なのは「敬意」の存在です。敬意のないところに敬語は成立しない。この当たり前のことを自覚すること以外に敬語教育の原点はありえません。流石に柳田國男です。──と、ここまで書いて今朝の東京新聞の第一面を目にしました。柳田説の正しさを裏づける文章に出会いました。
≪▼・・・四月に新設され、首相夫人の安倍昭恵さんが名誉校長を務める大阪の私立小学校は、教育理念に「日本人としての礼節を尊び、それに裏打ちされた愛国心と誇りを育て」ることを掲げる▼だが、この学校をつくる学校法人が運営する幼稚園は保護者に「よこしまな考え方を持った在日韓国人や支那人」と記した文書を配っていたという。隣人への憎悪をあおる言葉を使うのが「日本人としての礼節」なのか。それはどんな愛国心や誇りにつながるというのだろう≫(「筆洗」)
こういう幼稚園や小学校で、敬語教育の原点を見つけだすのはおそらく難しいでしょう。「敬語を教えるのは良い学校」という観念は一度疑ってかかる必要があります。














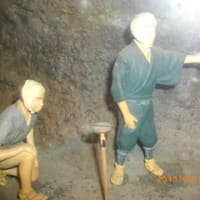




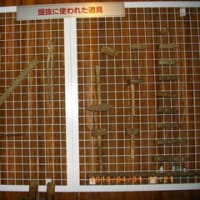
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます