
昔というより50年前の頃であったと思う、当時ECMレーベルの音質が良いと言われ、筆者が記憶するは当時のスイングジャーナル誌でピアニスト、チック・コリア演奏のリターン・トゥ・フォーエヴァー(Return to Forever)を絶賛していた、チック・コリア演奏のECM配信レコード盤はヨーロッパを代表する名門ジャズ・レーベルでもあった事を記憶する。
ECMは1969年にマンフレート・アイヒャーがドイツのミュンヘンに創設。アイヒャーはクラシック音楽とジャズの演奏家として活動した後、20代半ばでECMを立ち上げた。ECMは「Edition of Contemporary Music」の略。勿論当時はオトキチの仲間では話題のネタであった。爽やかな感じがする鳥が飛んでいるレコードジャケットも印象的でした。

透明感のあるサウンドと澄んだ音質、洗練された美しいジャケット・デザインが特徴的で、レーベルのカラーとなっている。その後キース・ジャレットの1975年にケルン・オペラ・ハウスで録音されThe Köln Concert(ケルン・コンサート)も良い音がしたアルバムでもあった。その後キース・ジャレットによるバッハ録音第1弾となったアルバム。この頃からは筆者の聴く音楽がバロック音楽に変化し徐々にジャズから離れ始めた頃でもあった。
チェンバロで弾く平均律クラヴィーア曲集は新鮮いい意味で期待を裏切られたので興味は持つ様になった、チック・コリア、ゲイリー・バードン、キース・ジャレットと其れ程好きでもない演奏者が並ぶECMレーベルは気にはならなかったと言う事であろう。

平均律クラヴィーア曲集 第1巻
平均律クラヴィーア曲集 第1巻
初回限定盤/ECM50周年記念/日本独自企画
録音年:1987年2月/
収録場所:ケイヴライト・スタジオ、ニュージャージー州
そして2022.2に購入した雑誌stereoと言う雑誌を何気なく見るとECMとオーディオに着いての特集記事が掲載されている、多分この記事が見たい為に購入してのであろう、かなりの枚数が記事内容と掲載され今頃になって改めて目を通してみた。1969年設立以降、未だに存続する稀有な存在でもある。

キース・ジャレットは、アメリカ合衆国出身のジャズ、クラシック音楽のピアニスト、作曲家。 ジャズ・ピアニストとして知られているが、クラシック音楽のピアニストでもある。演奏楽器もピアノ以外に、ソプラノサックス・パーカッション・ハープシコード・リコーダーなども演奏できるマルチ・プレイヤーでもある。
大変自然な演奏で、テンポもいいし、ここにやさしく語りかけているようで、心にしみいってきます。長い曲だけど、全然飽きない、一応バッハのすばらしさがわかります。を聴くたびに涙が出てくる。きっとα波もいっぱい出ているのだろう。体内にがん細胞があったら、どんどん消えてってるんじゃなかろうか・・・。
しかし冷静になってキース・ジャレットの演奏を聴き比べて解るが前にも述べたが、彼の音楽はやはりジャズピアノの演奏者である様に思う。
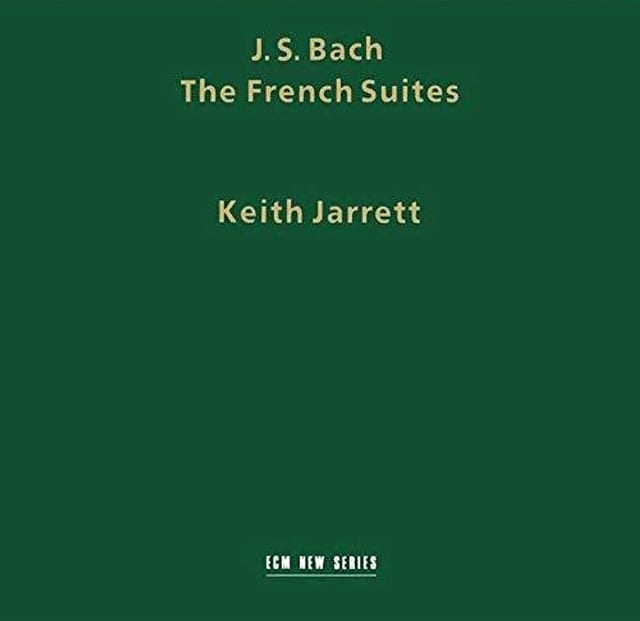
French Suites: Keith Jarrett
JSバッハ:フランス組曲 全曲 BWV.812-817
キース・ジャレット(チェンバロ)
https://www.youtube.com/watch?v=EqE6Pivwnr0&list=PLfdMKJMGPPtzP2rCLnprTF2lq5YcBQJ2Q
キース・ジャレット(チェンバロ)
https://www.youtube.com/watch?v=EqE6Pivwnr0&list=PLfdMKJMGPPtzP2rCLnprTF2lq5YcBQJ2Q
J.S.バッハ:
01フランス組曲第1番ニ短調BWV812
02フランス組曲第2番ハ短調BWV813
03フランス組曲第3番ロ短調BWV814
04フランス組曲第4番変ホ長調BWV815
05フランス組曲第5番ト長調BWV816
06フランス組曲第6番ホ長調BWV817
録音時期:1991年9月
録音場所:ケイヴライト・スタジオ、ニュージャージー州
録音場所:ケイヴライト・スタジオ、ニュージャージー州
録音方式:ステレオ(デジタル/セッション)
ピアニストのキース・ジャレットのチェンバロ演奏による、バッハのフランス組曲を収録(91年録音)。バッハを得意とするジャレットが古楽器を演奏し、作品本来の音色を引き出す。バッハ作品の魅力を再考できる一枚ではあった。

さて前書が長くなったがここからが本題であろう・・・?しかし筆者はここで大御所 グスタフ・レオンハルト(Gustav Leonhardt )の演奏を聴きたくなる。筆者が初めてバッハの音楽に触れた演奏者がレオンハルトの鍵盤楽器でもあり、勿論今も教科書的大御所的存在でもあった、しかしそれ以外の演奏者のバッハが聴きたく未だに目につくと試聴している事が現状でもある。
バッハ音楽の聴き始め当初から細々とレオンハルトのレーコードを収集し、勿論バッハ:カンタータ全集も所有するが、今も新しいセットのCDが発売されれば購入する、レオンハルトファンでもある。
先日もバッハ: 鍵盤作品集成 / グスタフ・レオンハルト(Gustav Leonhardt )1962年から1988年にかけて録音したバッハの鍵盤楽器が20枚組でまとめられた、2009年発売のアイテム。申し分ない内容であり、初出時のライナーノーツを全て収録した立派な日本語(日本限定盤なので当然だが・・)ブックレットも付属している。録音毎の使用楽器等の詳細なデータも記載されているので、大変参考になる。
改めて言う、演奏の音質、聴かせ方、如何にもバッハらしい実に納得出来る音質であり、品格さえ違って感じた実に安心してバッハ音楽が聴ける。

確かに筆者の部屋は狭いが、ある程度の重みのある安定したGOODMANS AXIOM 80の箱に入れた10吋タンノイIIILZ Monitor Goldユニットと中でも比較的安価な真空管300Bパワーアンプだが流石三極管の織りなす音は、何故比べるのかとも言われている様にも感じる。
確かに当初はオーケストラ、オペラ、パイプオルガン等の音は大変重量感の音で満足するが、聴き慣れるとチェンバロ等の低音はたまたグランドピアノ独特の音を体感すればミニのスピーカーでは得られない音圧が感じる、此れは一度体験すれば病みつきになる事間違い無い様である。写真しか見て事なない頑丈なエンクロージャーが有名なアメリカタンノイは如何なる音がするか益々興味が湧く。
このレオンハルトの演奏を聴いていると、ピアノ演奏よりチェンバロの方が断然良いという人の気持ちもわかる。決して急がず、ゆったりとしたタメを設けながら、独自の影の濃い存在感のある響きを引き出している。
バッハは6曲の舞曲「フランス組曲」を聴いている。バッハ自身は「クラヴィーアのための組曲」と名付けており、「フランス組曲」なる命名者は判っていない、おそらく、この組曲がお洒落な要素も含み優雅で親しみやすく洗練された音楽になって、如何にもフランス的な感覚が多く盛りこまれているためにこう呼ばれるようになったものだろうと言われているそうだ。
作曲年代についてもはっきりしていないが、1722年頃と推定されている。それは、バッハが最初の妻と死別後、2度目の妻アンナ・マグダレーナと1721年に結婚し、彼女に最初に贈った曲集「クラヴィーア小曲集」(1722年)に、このフランス組曲の第1~5番の5曲が含まれているという理由からである。
いずれも数曲の舞曲より構成され、アルマンド、クーラント、サラバンドと続き、最後はジーグで締めくくる。これら4つの舞曲は、17世紀後半に確立された鍵盤組曲の古典的定型を成す。バッハは当時の慣習に従い、これらの舞曲がすぐにそれと判るような典型的な音型や語法を曲の冒頭から用いている。第1番と第2番は、1725年の「アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳(第2集)」に含まれており、少なくともこの2つの組曲については改訂が行われたそうです。

キース・ジャレットがバッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻をジャズマンがバッハに挑戦するのは今ではそう驚くことではないが、平均律とは並み大抵ではない演奏でもある。だが、キースのはソフト・タッチで優しく柔和だ。真正面から取り組んではいるが、肩ヒジ張った謹厳で威圧的なバッハとは無縁の、柔軟で叙情的なバッハでもある。
しかしグスタフ・レオンハルトと比べるとはいくらなんでも可哀想である。しかしこれが現実であり深い芸術の世界でもある様に思う。
この事かも当時バッハが新しい妻アンナ・マグダレーナ・バッハの為に第1番と第2番は、1725年の「アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳(第2集)」に含まれており1723年頃作った愛を込めた優しい曲でもある。 全6曲。 名称は、フランス風の舞曲の構成をもつことに由来する。
バッハは6曲の「フランス組曲」を書いている。 バッハ自身は「クラヴィーアのための組曲」と名付けており、「フランス組曲」なる命名者は判っている。 おそらく、この組曲が優雅で親しみやすく洗練された音楽になっており、フランス的な感覚が盛りこまれているためにこう呼ばれるようになったものだろう。

フランス組曲(全曲)
J.S.バッハ:フランス組曲 BWV.812-817
1. 第1番ニ短調 BWV.812
2. 第2番ハ短調 BWV.813
3. 第3番ロ短調 BWV.814
4. 第4番変ホ長調 BWV.815
5. 第5番ト長調 BWV.816
6. 第6番ホ長調 BWV.817
演奏:グスタフ・レオンハルト(チェンバロ)
使用楽器:デイヴィッド・ルビオ、オックスフォード、1973年(2,5)、1975年(1,3,4,6)/パスカル・タスカン・モデル
録音時期:1975年12月(1,3,4,6)、1975年2月(2,5)
録音場所:ハールレム、ドープスヘヅィンデ教会

レオンハルトが目指すはバッハ自身の感動の現実の音の中に描き出す事であり、それらの音を作り出すのはレオンハルト自身の感度やとファンタジーに他ならないっと述べている。これぞバッハが自分の作品をどの様に演奏したか・・それは永遠の謎であろうがレオンハルトは精神の中に没入しようとして真正なるもが呈示されるという感動を聴き手に与える、聴き終わり納得したり安心したりこの演奏の違いは確かに異次元の違いを感じた、はるかにグスタフ・レオンハルトのフランス組曲は優しく。清らかで神々しいのである。
J.S.バッハの音楽性、当時愛しいアンナ・マグダレーナ・バッハの練習曲として捧げた優しいリズムが描かれてれているかの様である、確かにこれを聴けば納得出来る曲なのであろう。人間バッハに触れた瞬間かもしれない、ブラボー!




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます