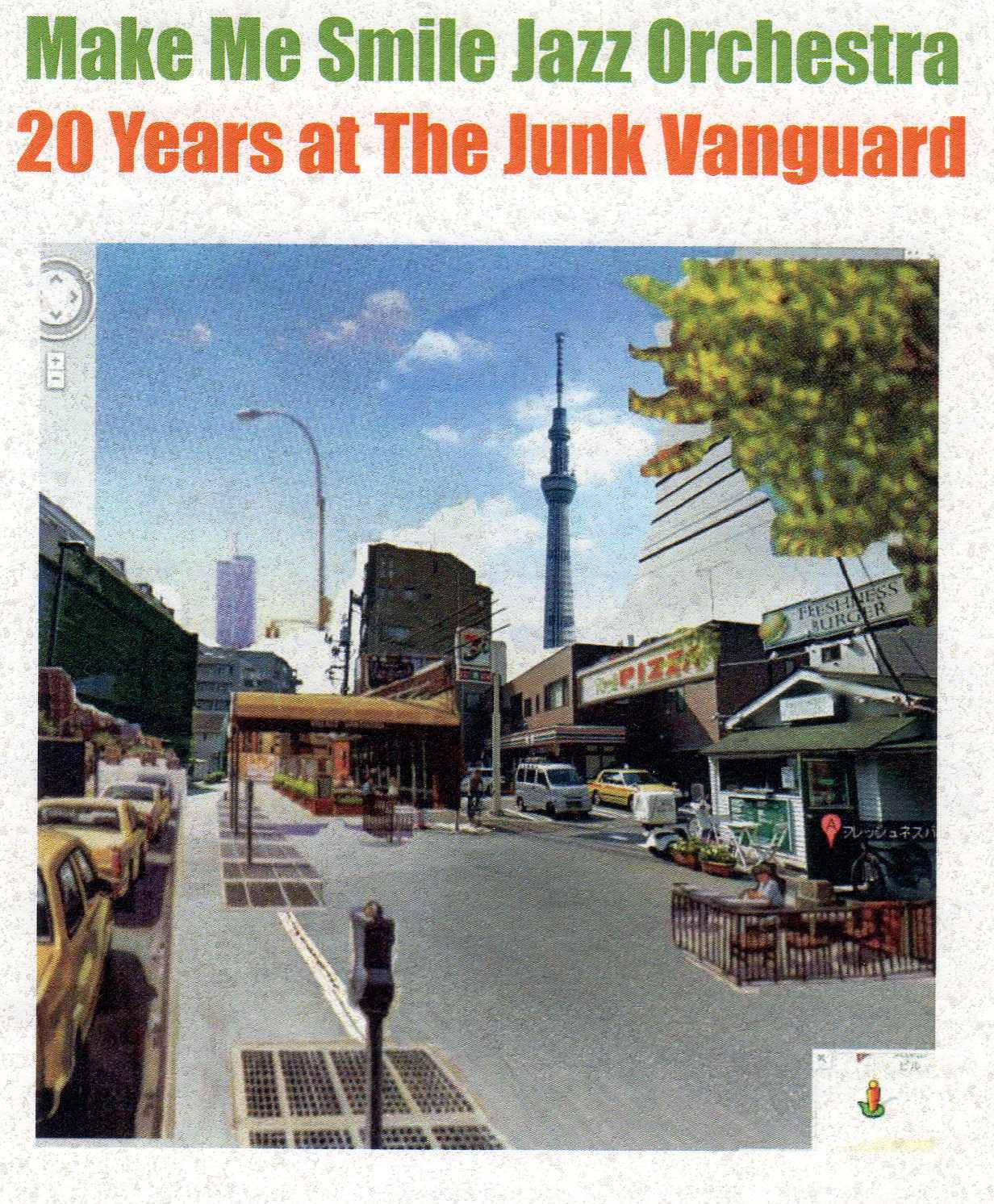At Home / Around the World / David Amram
ペッパーアダムスが参加しているアルバムを追いかけていると、今まで見たことも聴いた事が無いアルバムに出くわす。これもその一枚だが、それだけアダムスが色々なセッションに加わっていたという事だろう。
マルチタレントというのは何の世界にもいる。音楽の世界だと、演奏と作編曲の両方が得意であったり、色々な楽器を演奏出来たり、ジャズとクラシックの両刀使いであったり。プレーヤーが作編曲家やプロデューサーに転じる例は良くある。畑違いのジャズからクラッシクの世界に転じて成功した第一人者はアンドレプレビンだろう。
才能ある者はどの世界で活動してもそれなりの実績を残すことができる。その中で、ひょっとしてこのデイビットアムラムはジャズ奏者から他の畑に転じた中で、活動の幅の広さはナンバーワンかもしれない。
元々はラテンバンドでホルンとパーカッションの一奏者からスタートしているが、80歳を超えた今でもジャンルを超えて活躍しているようだ。自分がこのアムラムを知ったのは、ペッパーアダムスの参加していたアルバムを通じて。その活躍の一端を知るだけだが、彼は「現在音楽のルネサンス・マン」と呼ばれているそうだ。活動のすべてを知っている人にはその超人ぶりが理解できるのであろう。
ジャズの世界で活躍していた1950年代はホルン奏者としての活動が中心であった。ミンガスのワークショップにも参加し、ファイブスポットにも出演していた。多分、この頃アダムスと出会ったのであろう。パーカーの信奉者であったが酒もドラッグもやらない彼がいつも屯していたのはビレッジ周辺。音楽だけでなく、詩人や絵画、そして映画の世界へと興味も交友関係も広がっていった。
さらに作編曲に興味を持つと音楽活動の幅はクラシックにも広がった。そんなアムラムが、1977年に当時国交を断絶していたキューバにディジーガレスピーを団長とするジャズの親善使節団に一メンバーとして参加した。その時の演奏の一部、そしてその後今度はキューバからのミュージシャンをニューヨークに招いた時のセッションにも参加し、アルバム”Habana New York”に残されている。得意のラテンリズムがアメリカと現地のミュージシャンの橋渡し役となっている。
元々パーカッションも演奏しラテンバンドにもいたこともあったアムラムは、元々世界各国の音楽に興味を持っていたそうだが、これを機に改めてラテン音楽にも目覚めることになる。一口にラテンと言っても国や民族によってリズムや使う楽器も違う。アムラムは自ら現地に足を運んでそれらを順次ものにしていった。そして、中南米だけでなく、探訪の旅はアフリカや中近東など世界各地に広がった。いつの間にか世界の民族楽器を何十種類も演奏できるようになっていた。現場で身に付けたリズム感、これがアムラムの強みであろう。
このアルバムは、ジャズの世界で育ったアムラムが、世界中を廻って体得した民族音楽を彼なりの解釈で披露するある種のハイブリッドアルバムだ。タイトルもそのままAt Home / Around the Worldとなっているが、アルバムのA面がジャズを基本に、B面が世界の音楽といった感じだ。
1曲目は77年5月にガレスピーと一緒にキューバに渡る船の中で2人のディスカッションで生まれた曲。ラテンのリズムで始まるオリジナルのブルースでペッパーアダムスがいきなりソロをとり、アムラムのホルンが続く。
2曲目は55年にパリに行った時に書いた曲、フルートの音色を鳥の鳴き声に模した曲だが、世界各国の笛が賑やかに登場する。次はジェリーダジオンのアルトをフィーチャーしたバラード。続く2曲はトラディショナルだが、リズムの使い方が、ジャズの4ビート、8ビートは違ったアムラムの世界だ。その中でアダムスのソロも再び登場するが、周りの変化には我関せずといった感じでいつものペースだが、演奏自体は妙にしっくりくる。
このアムラムとアダムスは気が合うのか良く一緒に演奏している。このアルバムの録音の前にもアムラムのテレビ出演があったが、アダムスも一緒に出演している。アムラムの音楽はクラシックからジャズまで何が出てくるか分からないが、どんな曲でもアダムスの低音の魅力がアムラムには不可欠だったようだ。
そして、B面は、パキスタン、エジプト、グアテマラ、パナマ・・・と、アメリアッチ風の演奏から、神秘的なサウンドまで世界各国の音楽のオンパレード。笛と太鼓がメインになるのはどの国でも同じようだ。こちらにはアダムスはソロでは参加していない。
アムラム本人は、プロデュース、作曲に加え、演奏もホルン、ピアノに加え、各種パーカッション、フルート&各種の笛を駆使して大活躍。他の人にはなかなか真似のできないユニークなアルバムだ。
1. Travelling Blues David Amram / T. Johnson 4:57
2. Birds of Montparnasse David Amram 2:33
3. Splendor in the Grass David Amram 4:23
4. Sioux Rabbit Song Traditional 1:43
5. Home on the Range Traditional 4:22
6. Kwahare (Kenya) Traditional 3:33
7. Pescau Traditional 2:38
8. Homenaje a Guatemala David Amram 2:30
9. From the Khyber Pass David Amram 1:39
10. Aya Zehn (Egypt) Traditional 6:43
David Amram (arranger, composer, Dumbek, Flute, French Horn, Guitar, Ocarina, Orchestration, Pakistani Flute, Penny Whistle, Percussion, Piano, Piccolo)
Pepper Adams (bs)
Jerry Dodgion (as)
George Barrow (ts)
Wilmer Wise (tp)
Mohammed El Akkad (Kanoon)
Ramblin' Jack Elliott (g,Yodeling)
Ali Candido Hafid (Dumbek)
Ray Mantilla (conga,per)
Nicky Marrero (per,timbales)
George Mgrdichian (Oud)
Hakki Obadia (violin)
Johnny Dandy Rodrigues (bonbo,per)
Victor Venegas (b,elb)
Floyd Red Crow Westerman (chant, ds,Sioux)
Steve Berrios (ds,per)
Candido (conga)
Odetta (vol)
Libby McLaren (vol)
Angela Bofill (vol)
Patrica Smyth (vol)
llana Marillo (vol)
Produced by Glenda Roy & David Amram
Engineer : Joe Cyr
Recorded at Variety Sound, New York City on October 17 1978
ペッパーアダムスが参加しているアルバムを追いかけていると、今まで見たことも聴いた事が無いアルバムに出くわす。これもその一枚だが、それだけアダムスが色々なセッションに加わっていたという事だろう。
マルチタレントというのは何の世界にもいる。音楽の世界だと、演奏と作編曲の両方が得意であったり、色々な楽器を演奏出来たり、ジャズとクラシックの両刀使いであったり。プレーヤーが作編曲家やプロデューサーに転じる例は良くある。畑違いのジャズからクラッシクの世界に転じて成功した第一人者はアンドレプレビンだろう。
才能ある者はどの世界で活動してもそれなりの実績を残すことができる。その中で、ひょっとしてこのデイビットアムラムはジャズ奏者から他の畑に転じた中で、活動の幅の広さはナンバーワンかもしれない。
元々はラテンバンドでホルンとパーカッションの一奏者からスタートしているが、80歳を超えた今でもジャンルを超えて活躍しているようだ。自分がこのアムラムを知ったのは、ペッパーアダムスの参加していたアルバムを通じて。その活躍の一端を知るだけだが、彼は「現在音楽のルネサンス・マン」と呼ばれているそうだ。活動のすべてを知っている人にはその超人ぶりが理解できるのであろう。
ジャズの世界で活躍していた1950年代はホルン奏者としての活動が中心であった。ミンガスのワークショップにも参加し、ファイブスポットにも出演していた。多分、この頃アダムスと出会ったのであろう。パーカーの信奉者であったが酒もドラッグもやらない彼がいつも屯していたのはビレッジ周辺。音楽だけでなく、詩人や絵画、そして映画の世界へと興味も交友関係も広がっていった。
さらに作編曲に興味を持つと音楽活動の幅はクラシックにも広がった。そんなアムラムが、1977年に当時国交を断絶していたキューバにディジーガレスピーを団長とするジャズの親善使節団に一メンバーとして参加した。その時の演奏の一部、そしてその後今度はキューバからのミュージシャンをニューヨークに招いた時のセッションにも参加し、アルバム”Habana New York”に残されている。得意のラテンリズムがアメリカと現地のミュージシャンの橋渡し役となっている。
元々パーカッションも演奏しラテンバンドにもいたこともあったアムラムは、元々世界各国の音楽に興味を持っていたそうだが、これを機に改めてラテン音楽にも目覚めることになる。一口にラテンと言っても国や民族によってリズムや使う楽器も違う。アムラムは自ら現地に足を運んでそれらを順次ものにしていった。そして、中南米だけでなく、探訪の旅はアフリカや中近東など世界各地に広がった。いつの間にか世界の民族楽器を何十種類も演奏できるようになっていた。現場で身に付けたリズム感、これがアムラムの強みであろう。
このアルバムは、ジャズの世界で育ったアムラムが、世界中を廻って体得した民族音楽を彼なりの解釈で披露するある種のハイブリッドアルバムだ。タイトルもそのままAt Home / Around the Worldとなっているが、アルバムのA面がジャズを基本に、B面が世界の音楽といった感じだ。
1曲目は77年5月にガレスピーと一緒にキューバに渡る船の中で2人のディスカッションで生まれた曲。ラテンのリズムで始まるオリジナルのブルースでペッパーアダムスがいきなりソロをとり、アムラムのホルンが続く。
2曲目は55年にパリに行った時に書いた曲、フルートの音色を鳥の鳴き声に模した曲だが、世界各国の笛が賑やかに登場する。次はジェリーダジオンのアルトをフィーチャーしたバラード。続く2曲はトラディショナルだが、リズムの使い方が、ジャズの4ビート、8ビートは違ったアムラムの世界だ。その中でアダムスのソロも再び登場するが、周りの変化には我関せずといった感じでいつものペースだが、演奏自体は妙にしっくりくる。
このアムラムとアダムスは気が合うのか良く一緒に演奏している。このアルバムの録音の前にもアムラムのテレビ出演があったが、アダムスも一緒に出演している。アムラムの音楽はクラシックからジャズまで何が出てくるか分からないが、どんな曲でもアダムスの低音の魅力がアムラムには不可欠だったようだ。
そして、B面は、パキスタン、エジプト、グアテマラ、パナマ・・・と、アメリアッチ風の演奏から、神秘的なサウンドまで世界各国の音楽のオンパレード。笛と太鼓がメインになるのはどの国でも同じようだ。こちらにはアダムスはソロでは参加していない。
アムラム本人は、プロデュース、作曲に加え、演奏もホルン、ピアノに加え、各種パーカッション、フルート&各種の笛を駆使して大活躍。他の人にはなかなか真似のできないユニークなアルバムだ。
1. Travelling Blues David Amram / T. Johnson 4:57
2. Birds of Montparnasse David Amram 2:33
3. Splendor in the Grass David Amram 4:23
4. Sioux Rabbit Song Traditional 1:43
5. Home on the Range Traditional 4:22
6. Kwahare (Kenya) Traditional 3:33
7. Pescau Traditional 2:38
8. Homenaje a Guatemala David Amram 2:30
9. From the Khyber Pass David Amram 1:39
10. Aya Zehn (Egypt) Traditional 6:43
David Amram (arranger, composer, Dumbek, Flute, French Horn, Guitar, Ocarina, Orchestration, Pakistani Flute, Penny Whistle, Percussion, Piano, Piccolo)
Pepper Adams (bs)
Jerry Dodgion (as)
George Barrow (ts)
Wilmer Wise (tp)
Mohammed El Akkad (Kanoon)
Ramblin' Jack Elliott (g,Yodeling)
Ali Candido Hafid (Dumbek)
Ray Mantilla (conga,per)
Nicky Marrero (per,timbales)
George Mgrdichian (Oud)
Hakki Obadia (violin)
Johnny Dandy Rodrigues (bonbo,per)
Victor Venegas (b,elb)
Floyd Red Crow Westerman (chant, ds,Sioux)
Steve Berrios (ds,per)
Candido (conga)
Odetta (vol)
Libby McLaren (vol)
Angela Bofill (vol)
Patrica Smyth (vol)
llana Marillo (vol)
Produced by Glenda Roy & David Amram
Engineer : Joe Cyr
Recorded at Variety Sound, New York City on October 17 1978
 | At Home Around the World |
| クリエーター情報なし | |
| Flying Fish Records |