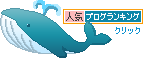キンダーガーデンのクラスに行った時に、生き物の人形が大量に箱に入っていたんだけど、あまりこれを活用している様子が見られず
子供達がどんな風に遊ぶかな。。。と、実験的に試してみた遊び

最初は、トレーのそれぞれの部分に、一匹ずつ、異なる種類の動物を置いて、それ以外は、箱に入れたまま、近くにトングをいくつか置いておきました
朝、子供達が教室に入ってくると、それぞれ 遊びたい物を見つけて活動を始めますが、最初は3−4人だったと思います。
テーブルに集まっていて、動物の名前を言ったり、箱の中に沢山ある動物人形を見て、仕分け作業を自発的に始めました
私の目論見通りの展開😁
仕分けをしながら、この動物は何だと名前をお互いに話しています。
そこで、1つ思いついた事がありました
最近特にキンダー2年目のSK (Senior kindergarten)の子達が、スペルに興味を示していて、ごっこ遊びで図書館やお店を作ると「図書館ってどう書くの?」「店が閉まってるってどう書くの?」。手紙やカードを作ると「お母さん、お父さん、大好き」ってどう書くの?などと聞いてくる子達が多いので、動物の単語を書いてみたんです
そして、子供達に例えば「どっちが猫だと思う?」と聞いて「Cats /Pigs」の2択で見せてみたんです
すると、ほとんどの子達が「Cat」を選びました。
そこで、ただ、「正解」というのではなく
少し驚いた表情を見せて 「どうしてこっちがCatだと思ったの?」
と、聞いてみるんですね。
ちなみに、こういうタイプの質問は、必ずしも答えは1つである必要はなく、自分がそう思った事を伝えられたら、花丸です。
すると「Cat はC(発音)だから!」と教えてくれるではありませんか!」
クラスのサークルタイムではA,B,Cの歌のように、アルファベットのレターとしての読み方を学ぶ他に、単語の例を出して「音」も学ぶんですね。
なので、「C」だから 「Catが猫!」という答えが返ってきたわけです
結構感動でしたよ😊
中には 同じように「どうしてこっちがCatだと思ったの?」と聞くと
「え〜。正解って知らなかったけど、なんとなくこっちかなーと思ったから!」なんて答えもあります。
その時も「いい選択だったね!」とか褒めてあげると、子供達継続してニコニコ参加してくれます。
そして、側で「C」だから 「Catが猫!」とクラスメイトが発言してる事から学べる場合もあるんですね。
もし、わからない様子の場合は、私だったら「こっちが猫だよ。C A Tで猫だよ」と、スペルを1つ1つ指さしながら さらりと伝えるだけにします
そして、ちょっとひっかけで 「猫(cats)と牛(cows)を見せて」 どっちが猫だと思う?と聞くと
う。。。。。。。ん。。。。と、迷う子達も多かったです。
他の動物でも同じように問いかけてみると、やはり、同じように最初の音と文字で選ぶ様子が見られました
この子達は、単語の最初の文字と、音で単語のスペル認識しているんだな。と言うことがわかりました。
でも、これがわかっているだけでも大した物です。
この遊びから
トングという小道具を上手に使う手先の運動
物を同じカテゴリー別に分ける認識と力
動物の名前の認識
名前と単語スペルの認識
文字と音の認識
クラスメイトと一緒に活動する力
大人の質問に対して答えられる(自分の考えや意見を述べる)力
などを育むことができます
日本語でも他の言語でも応用できる遊びだと思います
日本の幼稚園で、ひらがなやカタカナの文字の導入をする際に
こう言った遊びも楽しく取り組めると思います
24名いたクラスで、半分ちょっとの子達が興味を持って自分から取り組んでいました。
全員ではないけれど、それはそれで、その子のその時の興味と発達段階があるので、強要する必要はないし、これに興味を示さなかった子が興味を持っている別の遊びの中に、文字や言葉の導入をすると、別の形で学べます
大人はそんな環境づくりができると、子供達は自発的に様々な事を学ぶことができます