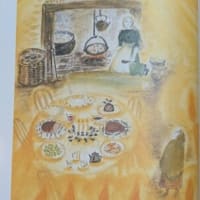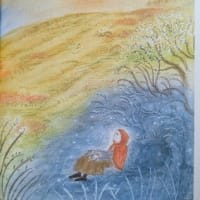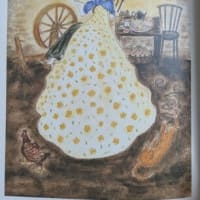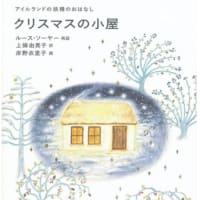過去のノートにある映画感想メモシリーズ。
part2からのつづき。
若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪
なお、あらすじはなるべく省略しています。
■『beauty and harmony』@オーチャードホール

vocal:吉田美和
♪DARLIN'、バイバイ、冷えたくちびる、泣きたい、パレードは行ってしまった、奪取、つめたくしないで、
A HAPPY GIRLIE LIFE、生涯の恋人、beauty and harmony
やっぱ彼女にゃかなわない! NYでレコーディングしてコンサートは日本か?
海外にしちゃ前の席がチラッと映った時、日本人ばっかり。
私たちが知らないだけで'60年代からの大物アーティストが集まっているらしい。
ジャズあり、ポップスあり、ブルースあり、何でもござれのめーいっぱい詰まった超豪華なコンサート。
これをライヴで聴けた人はなんて特別な体験をしたことか!
国内じゃこれほどのパワフルでハイクオリティなステージは見れないもんね。やっぱTIME誌飾るだけある。
今までたくさんのアルバムを出して、記録作って、ツアー回ってきた現在の美和さんだから完成できたステージ。
海外でも充分通じるよね、これなら。メンバーも手放しの褒めよう。
海外で活躍する日本人の話を聞くのが好きなんだな、私たちは。
彼女は客を魅了すると同時に、過剰なほどメンバーも楽しませる。
ハイテンションな明るさでレコーディング中も、ライヴ中も200%元気印。メンバーの力をベスト以上に引き出す。
ギターソロには涙。メンバーに感謝の歌まで歌って、ラストの美しいアカペラでも涙。中村正人氏も同行。
「クリエイトしなくなったらメンバーじゃない」って言ったのってドリカムだったっけ?
かなりプロ志向も強い。ロバータ・フラックやエラ・フィッツジェラルドと比較されるくらいだから、相当なもの。
ライヴ前には「1人でも多く幸せにできますように」てお祈りする。
ビッグスターでもステージと観客全体を統合させられるヒトは少ないもんね。
まさにピーク絶好調の美和さんがめいっぱい詰まった究極の1本。
■『七人の侍』(1954)

監督:黒澤明 出演:三船敏郎、志村喬、加東大介、木村功、千秋実、宮口精二、稲葉義男 ほか
<前編>
やっぱ“世界のクロサワ&ミフネ”だわ。この活劇の面白さ+百姓と武士のドラマは世界のヒトにも通じると思う。
カラーだったら? 美しい青年武士が花畑に誘われるシーンは美しいけど、その他はむさいだろうね。
'54時点でここまで戦国時代をリアルに再現して、時代検証も苦労したことだろう。
三船のダイナミックな野性味あふれる活気ある演技に魅了された。
武士の無用なプライド、百姓の最低層の暮らし。同様に貧しい商人は、百姓より一応身分は上。
同情しつつもあざ笑う、それぞれの階級がハッキリ伝わってくる。
次々と7人が揃っていくいきさつ、村の地理を利用して野武士から守る計画をたてるまでのストーリーも面白い。
「百姓はずる賢い。でも、そんな風にしたのは、お前らが奴らから奪い、女を漁り、田畑を踏み潰してきたからだ、チクショー」
「人を守れる者は自分も守れる。人も守れない者は、自らも滅ぼす。今日から心するように」
「男のくせに花など摘んで」て自分も花枝を持ってるシーンも笑う。ちゃんと笑いのツボも分かってるよね。
<後編>
「また生き残ってしまった。また負け戦だった。勝ったのは百姓で私たちではない」
侍同士を共倒れにさせたという皮肉ながらもどこか爽快なラストがイイ。
死ぬ覚悟で離れの水車に残った長老を連れ戻しに戻った夫婦と子どもの様子を見に行ったFは、
子どもが助かり皆殺しにされたと知って、子どもを泣きながら抱きしめ、「俺も同じだった!」と素性を明かす。
侍に両親を殺され、復讐からか、同じ運命を嫌ってか、自らも侍の道を選んだが、
百姓の心を忘れきれず、両方に引き裂かれていた男の複雑なキャラクターを三船が見事に体現。
村男の妻が野武士に遊ばれ、火がついた家で叫ぶのをやめるシーンも強烈。
夫に不意に再会し、復縁よりプライドを守って火に身を投じるという悲惨なドラマも見所。
天才侍も飛び火には勝てない。戦争の歴史において、銃がより簡単に大量虐殺することに貢献したことがよく分かる。
戦がどれほど無意味で非生産的かということに比べ、農民たちは虐げられながらも高いプライドがあり、
ユーモラスでマヌケなうわべの下に、したたかで強い生命力があって驚いたと同時に嬉しい気がした。
追。後半、なぜ三船はつねにお尻丸出し状態なんだろう??w
■『魔界世紀ハリウッド』(1994)
監督:ポール・シュレイダー 出演:デニス・ホッパー、ジュリアン・サンド ほか
荒唐無稽ではあるけど、ハリウッドなら違和感ない。
実際、映画のマジックで今作もまるで現実のように描かれているし、
私たちの目もだんだんそれに慣れてきちゃって、ちょっとやそっとじゃ驚かなくなってる。
■『羅生門』(1950)


監督:黒澤明 出演:三船敏郎、森雅之 、京マチ子、志村喬、千秋実、加東大介 ほか
、京マチ子、志村喬、千秋実、加東大介 ほか
今年の年末WOWOWは黒澤シリーズ。ビデオもひと通りそろって海外向けのタイトルまでついて、
原題のローマ字表記でそのまま使っているのはカッコいい。
どの作品も確かに名作。ヒッチコックら他の巨匠に劣らない。
淀川さん他の世代の映画関係者も神と崇めた気持ちが分かる。
1つの殺人事件が真相とは別に、それぞれの関係者の勝手な言い分で複雑化し、どれが本当か分からなくなる。
貧困からくる悪心か? 人が生まれながらに持つといわれる原罪か?
でも、そこにはかすかに良心と情もあることに救いがあるのだと思う。
■『アステロイド』(1997)
監督:ブラッドフォード・メイ 出演:マイケル・ビーン、アナベラ・シオラ ほか
本当に見分けがつかない世紀末パニックムーヴィたちだが、それぞれ高収益のヒットになっているのは、
やはり人々の間に徐々に現実問題としての危機感が差し迫ってる表れか?
リアルなパニック映画をたくさん観れば、対策やイメージトレーニングできるかも!?
とりあえず地下シェルターが欲しいぞ。M.ビーンは久々見た。
いつでもヘリを調達できるって、持つべきものは権力あるBFってとこか?
一般市民のAは命はって家族より他人を優先してるのに、パニックで子どもを失った父に撃たれた救助隊員も悲劇。
銃社会のアメリカなら充分起こりうる。災害よりも、いつでも人を殺せる銃などによる人災のほうが怖い。
こーゆー時ってやっぱ女だけじゃ乗り切れないものなのかな?
ここでも主人公は常にアメリカ。まるでアメリカから引力が出ているように全部の隕石がアメリカめがけて落ちてゆくシーンはスゴイ。
ぜひ今作を参考にして隕石本体も破片も落ちてこないように今から備えといてほしい。
■『白痴』(1951)

原作:ドストエフスキー 監督:黒澤明
出演:三船敏郎、森雅之、原節子、久我美子、志村喬、東山千栄子、村瀬幸子、千石規子、柳永二郎 ほか
<第1部 愛と苦悩>
「皮肉だが、この世で真に善良であることは白痴に等しい」
なんだか最初から狐につままれたようなフシギな感じ。原作の長い前章でもカットしたのか、
それぞれ主要人物の重要なはずのそれまでのいきさつが描かれないままドラマはどんどん深刻なことになってゆく。
それでまた引きこまれているのかもしれない。
現代劇になるとちょっと様子が違う。でも、この頃の俳優って今よりずっと雲の上の存在でオーラが上品で違う。
噂に聞いていた原節子もE.バーグマンやG.ガルボに負けない艶っぽい美しさ。
皆、表情1つの動きで全てを語れる大物役者ばかり。これが欧米映画ならどうなるだろうと想像してみる。
原作本も気になる。まずは後半観てから。
<第2部 恋と憎悪>
「私たちのほうが白痴なのかもしれない」
ワンクッション置かないと、かなり重いテーマで受け留められるようになるまで容易じゃない。
亀田がまるで占い師か超能力者のように人の心を読み、未来を読むのがフシギ。
一切の欲を捨て、第三の眼でも開いたのか? 結局彼は男の友情を選んだ。死刑を迎えた時、
「なぜ皆にもっと優しくしてやれなかったのか、もし助かったらそうしてあげたい」と言っていた。
彼にとっては最高の幸福だったかもしれない。
白痴=知能がひどく劣っていること。今でいう精神薄弱者のことか?
人の脳はあまり強烈なストレス(恐怖、ショック)に耐えられなくなるとストップしてしまうらしい。
それでこれほどピュアで正直になれるなら、知能はあまり身に着けないほうがいいいようだ。
「ドフトエフスキーは真に純粋な男を描きたかった」
と冒頭のテロップに流れた。私は男が正直なゆえに悲劇に見舞われた話というより、
悲劇によって正直になった男が幸福になった話ととらえたい。
今や黒澤ファミリーとでも言えるおなじみのメンバーによって、これほど違った様々なドラマを観れるのは実に有意義。
男女の愛憎、哲学。世界の名作をシンプルながら劇的な脚本と映像によって再現し、思わず乗り出して観た。
抑えた演技の三船、森も、久我も昨今の俳優にないゴージャスな存在感と演技。
■『エンド・オブ・バイオレンス』(1997)

監督:ヴィム・ヴェンダース 出演:ビル・プルマン 、アンディ・マクドウェル、ガブリエル・バーン、フレデリック・フォレスト
、アンディ・マクドウェル、ガブリエル・バーン、フレデリック・フォレスト ほか
ほか
ヴェンダースが映画の街ハリウッドを舞台に映画プロデューサーの話を撮った。「いかにもハリウッドだ」がキーになるセリフ。
ちょっとブレた緑色の映像は前作『The end of the world』(タイトルも似てる)を思い出させる。
日常にあふれる暴力をひと通り描いて、ラスト静かな海にすべて沈めた、静かで穏やかな感動が広がる。
音楽はトム・ウェイツ他多才。キャストも豪華。
「敵は突然襲ってくると思っていた時、敵は僕自身だった。今、敵ができるとフシギなほど僕は解放された」
時々出てくるグループセラピーみたいなのが学芸会のちょっとした出し物のようで面白い。
父に毎日レイプされる話を歌のように話す女の子。
「本当は敵などいない。おかしいのはこの世の中のほうだ」
セックス、ヴァイオレンス、ガン、これでハリウッド映画は成立している。
本作にもその要素がちゃんと入っていて、ヴェンダースは「もうたくさんだ、未来にまで持ち越すのはやめよう」と終止符をうっている。
■『赤ひげ』(1965)

原作:「赤ひげ診療譚」山本周五郎 監督:黒澤明
出演:三船敏郎、保本登、加山雄三、森半太夫、土屋嘉男 ほか
昔は医療技術を人情で補っていた。今は技術は日々向上しても心ない医療が目立つ。
本当に親身になって病人の気持ちになって診てくれる名医を見つけるのは難しくなってしまった。
殿様連中は食べ過ぎと運動不足で病になり、貧困者は栄養失調と苦労から心も体も病となる。
病気は暮らし、しいては時代を映す鏡にもなる。
いまだに発展途上国はこのように知識と薬が乏しく、荒れた生活環境に苦しんでいる。
■『ビーン』(1997)
監督:メル・スミス 出演:ローワン・アトキンソン、ピーター・マクニール ほか
一応シリーズ中のウケのよかったギャグを使って、ビーンがアメリカで暴れまくるんだけど、なぜかフシギと笑えない。ヘンだな?
本国を舞台にしたTVシリーズは面白いのに。アトキンソン本人としてはどーなんだろ。
妙にハリウッド映画的なのがビーンらしくないんだな。普通のコメディドラマになってる。
他の俳優にまじってサイレントドタバタ風のビーンが浮いてるし、型にハマらないのが持ち味なのに、
ちゃんと職業もって生活してる姿は不似合い。こんなに笑えないなんて予想外!
■『THE X-FILES THE MOVIE』(1998)(劇場にて
監督:ロブ・ボウマン 出演:デイヴィッド・ドゥカブニー、ジリアン・アンダーソン、ミッチ・ピレッジ ほか
TVシリーズを大画面で観ましたってゆーのが正直な感想。
やっぱコレはシリーズ観てるX-FILERじゃなきゃ納得できない特異な世界。
それだけTVシリーズが毎週ものにしては毎回、小道具も凝っててかなり大掛かりに質の高いつくりになってるってことなんだけど。
確かに劇場用にいくつか大掛かりな外ロケでCG合成がある。
これはスペシャルでメイキングを観ちゃったからちょっと驚きが半減。
後に復習会を開かなきゃならないくらい、時々、理解困難に陥るエピソードの時があるけど、今作もそれ。
いくつかの進展はあってもシリーズの性質上、解決する終わり方はあり得ないから、
モルダーらが必死にあがいて自問自答する姿に同情心さえ湧いてくる。
一番ひっかかるのは、なぜ蜂を通して培養などしてたのか? なおさら人類滅亡の原因になるじゃん。
UFOの中の巨大さと後に残った巨大な雪原の穴がスケールでっかくて見所。
2人を大画面でどアップで観るのがちょっとフシギな感じ。
part2からのつづき。
若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪
なお、あらすじはなるべく省略しています。
■『beauty and harmony』@オーチャードホール

vocal:吉田美和
♪DARLIN'、バイバイ、冷えたくちびる、泣きたい、パレードは行ってしまった、奪取、つめたくしないで、
A HAPPY GIRLIE LIFE、生涯の恋人、beauty and harmony
やっぱ彼女にゃかなわない! NYでレコーディングしてコンサートは日本か?
海外にしちゃ前の席がチラッと映った時、日本人ばっかり。
私たちが知らないだけで'60年代からの大物アーティストが集まっているらしい。
ジャズあり、ポップスあり、ブルースあり、何でもござれのめーいっぱい詰まった超豪華なコンサート。
これをライヴで聴けた人はなんて特別な体験をしたことか!
国内じゃこれほどのパワフルでハイクオリティなステージは見れないもんね。やっぱTIME誌飾るだけある。
今までたくさんのアルバムを出して、記録作って、ツアー回ってきた現在の美和さんだから完成できたステージ。
海外でも充分通じるよね、これなら。メンバーも手放しの褒めよう。
海外で活躍する日本人の話を聞くのが好きなんだな、私たちは。
彼女は客を魅了すると同時に、過剰なほどメンバーも楽しませる。
ハイテンションな明るさでレコーディング中も、ライヴ中も200%元気印。メンバーの力をベスト以上に引き出す。
ギターソロには涙。メンバーに感謝の歌まで歌って、ラストの美しいアカペラでも涙。中村正人氏も同行。
「クリエイトしなくなったらメンバーじゃない」って言ったのってドリカムだったっけ?
かなりプロ志向も強い。ロバータ・フラックやエラ・フィッツジェラルドと比較されるくらいだから、相当なもの。
ライヴ前には「1人でも多く幸せにできますように」てお祈りする。
ビッグスターでもステージと観客全体を統合させられるヒトは少ないもんね。
まさにピーク絶好調の美和さんがめいっぱい詰まった究極の1本。
■『七人の侍』(1954)

監督:黒澤明 出演:三船敏郎、志村喬、加東大介、木村功、千秋実、宮口精二、稲葉義男 ほか
<前編>
やっぱ“世界のクロサワ&ミフネ”だわ。この活劇の面白さ+百姓と武士のドラマは世界のヒトにも通じると思う。
カラーだったら? 美しい青年武士が花畑に誘われるシーンは美しいけど、その他はむさいだろうね。
'54時点でここまで戦国時代をリアルに再現して、時代検証も苦労したことだろう。
三船のダイナミックな野性味あふれる活気ある演技に魅了された。
武士の無用なプライド、百姓の最低層の暮らし。同様に貧しい商人は、百姓より一応身分は上。
同情しつつもあざ笑う、それぞれの階級がハッキリ伝わってくる。
次々と7人が揃っていくいきさつ、村の地理を利用して野武士から守る計画をたてるまでのストーリーも面白い。
「百姓はずる賢い。でも、そんな風にしたのは、お前らが奴らから奪い、女を漁り、田畑を踏み潰してきたからだ、チクショー」
「人を守れる者は自分も守れる。人も守れない者は、自らも滅ぼす。今日から心するように」
「男のくせに花など摘んで」て自分も花枝を持ってるシーンも笑う。ちゃんと笑いのツボも分かってるよね。
<後編>
「また生き残ってしまった。また負け戦だった。勝ったのは百姓で私たちではない」
侍同士を共倒れにさせたという皮肉ながらもどこか爽快なラストがイイ。
死ぬ覚悟で離れの水車に残った長老を連れ戻しに戻った夫婦と子どもの様子を見に行ったFは、
子どもが助かり皆殺しにされたと知って、子どもを泣きながら抱きしめ、「俺も同じだった!」と素性を明かす。
侍に両親を殺され、復讐からか、同じ運命を嫌ってか、自らも侍の道を選んだが、
百姓の心を忘れきれず、両方に引き裂かれていた男の複雑なキャラクターを三船が見事に体現。
村男の妻が野武士に遊ばれ、火がついた家で叫ぶのをやめるシーンも強烈。
夫に不意に再会し、復縁よりプライドを守って火に身を投じるという悲惨なドラマも見所。
天才侍も飛び火には勝てない。戦争の歴史において、銃がより簡単に大量虐殺することに貢献したことがよく分かる。
戦がどれほど無意味で非生産的かということに比べ、農民たちは虐げられながらも高いプライドがあり、
ユーモラスでマヌケなうわべの下に、したたかで強い生命力があって驚いたと同時に嬉しい気がした。
追。後半、なぜ三船はつねにお尻丸出し状態なんだろう??w
■『魔界世紀ハリウッド』(1994)
監督:ポール・シュレイダー 出演:デニス・ホッパー、ジュリアン・サンド ほか
荒唐無稽ではあるけど、ハリウッドなら違和感ない。
実際、映画のマジックで今作もまるで現実のように描かれているし、
私たちの目もだんだんそれに慣れてきちゃって、ちょっとやそっとじゃ驚かなくなってる。
■『羅生門』(1950)


監督:黒澤明 出演:三船敏郎、森雅之
 、京マチ子、志村喬、千秋実、加東大介 ほか
、京マチ子、志村喬、千秋実、加東大介 ほか今年の年末WOWOWは黒澤シリーズ。ビデオもひと通りそろって海外向けのタイトルまでついて、
原題のローマ字表記でそのまま使っているのはカッコいい。
どの作品も確かに名作。ヒッチコックら他の巨匠に劣らない。
淀川さん他の世代の映画関係者も神と崇めた気持ちが分かる。
1つの殺人事件が真相とは別に、それぞれの関係者の勝手な言い分で複雑化し、どれが本当か分からなくなる。
貧困からくる悪心か? 人が生まれながらに持つといわれる原罪か?
でも、そこにはかすかに良心と情もあることに救いがあるのだと思う。
■『アステロイド』(1997)
監督:ブラッドフォード・メイ 出演:マイケル・ビーン、アナベラ・シオラ ほか
本当に見分けがつかない世紀末パニックムーヴィたちだが、それぞれ高収益のヒットになっているのは、
やはり人々の間に徐々に現実問題としての危機感が差し迫ってる表れか?
リアルなパニック映画をたくさん観れば、対策やイメージトレーニングできるかも!?
とりあえず地下シェルターが欲しいぞ。M.ビーンは久々見た。
いつでもヘリを調達できるって、持つべきものは権力あるBFってとこか?
一般市民のAは命はって家族より他人を優先してるのに、パニックで子どもを失った父に撃たれた救助隊員も悲劇。
銃社会のアメリカなら充分起こりうる。災害よりも、いつでも人を殺せる銃などによる人災のほうが怖い。
こーゆー時ってやっぱ女だけじゃ乗り切れないものなのかな?
ここでも主人公は常にアメリカ。まるでアメリカから引力が出ているように全部の隕石がアメリカめがけて落ちてゆくシーンはスゴイ。
ぜひ今作を参考にして隕石本体も破片も落ちてこないように今から備えといてほしい。
■『白痴』(1951)

原作:ドストエフスキー 監督:黒澤明
出演:三船敏郎、森雅之、原節子、久我美子、志村喬、東山千栄子、村瀬幸子、千石規子、柳永二郎 ほか
<第1部 愛と苦悩>
「皮肉だが、この世で真に善良であることは白痴に等しい」
なんだか最初から狐につままれたようなフシギな感じ。原作の長い前章でもカットしたのか、
それぞれ主要人物の重要なはずのそれまでのいきさつが描かれないままドラマはどんどん深刻なことになってゆく。
それでまた引きこまれているのかもしれない。
現代劇になるとちょっと様子が違う。でも、この頃の俳優って今よりずっと雲の上の存在でオーラが上品で違う。
噂に聞いていた原節子もE.バーグマンやG.ガルボに負けない艶っぽい美しさ。
皆、表情1つの動きで全てを語れる大物役者ばかり。これが欧米映画ならどうなるだろうと想像してみる。
原作本も気になる。まずは後半観てから。
<第2部 恋と憎悪>
「私たちのほうが白痴なのかもしれない」
ワンクッション置かないと、かなり重いテーマで受け留められるようになるまで容易じゃない。
亀田がまるで占い師か超能力者のように人の心を読み、未来を読むのがフシギ。
一切の欲を捨て、第三の眼でも開いたのか? 結局彼は男の友情を選んだ。死刑を迎えた時、
「なぜ皆にもっと優しくしてやれなかったのか、もし助かったらそうしてあげたい」と言っていた。
彼にとっては最高の幸福だったかもしれない。
白痴=知能がひどく劣っていること。今でいう精神薄弱者のことか?
人の脳はあまり強烈なストレス(恐怖、ショック)に耐えられなくなるとストップしてしまうらしい。
それでこれほどピュアで正直になれるなら、知能はあまり身に着けないほうがいいいようだ。
「ドフトエフスキーは真に純粋な男を描きたかった」
と冒頭のテロップに流れた。私は男が正直なゆえに悲劇に見舞われた話というより、
悲劇によって正直になった男が幸福になった話ととらえたい。
今や黒澤ファミリーとでも言えるおなじみのメンバーによって、これほど違った様々なドラマを観れるのは実に有意義。
男女の愛憎、哲学。世界の名作をシンプルながら劇的な脚本と映像によって再現し、思わず乗り出して観た。
抑えた演技の三船、森も、久我も昨今の俳優にないゴージャスな存在感と演技。
■『エンド・オブ・バイオレンス』(1997)

監督:ヴィム・ヴェンダース 出演:ビル・プルマン
 、アンディ・マクドウェル、ガブリエル・バーン、フレデリック・フォレスト
、アンディ・マクドウェル、ガブリエル・バーン、フレデリック・フォレスト ほか
ほかヴェンダースが映画の街ハリウッドを舞台に映画プロデューサーの話を撮った。「いかにもハリウッドだ」がキーになるセリフ。
ちょっとブレた緑色の映像は前作『The end of the world』(タイトルも似てる)を思い出させる。
日常にあふれる暴力をひと通り描いて、ラスト静かな海にすべて沈めた、静かで穏やかな感動が広がる。
音楽はトム・ウェイツ他多才。キャストも豪華。
「敵は突然襲ってくると思っていた時、敵は僕自身だった。今、敵ができるとフシギなほど僕は解放された」
時々出てくるグループセラピーみたいなのが学芸会のちょっとした出し物のようで面白い。
父に毎日レイプされる話を歌のように話す女の子。
「本当は敵などいない。おかしいのはこの世の中のほうだ」
セックス、ヴァイオレンス、ガン、これでハリウッド映画は成立している。
本作にもその要素がちゃんと入っていて、ヴェンダースは「もうたくさんだ、未来にまで持ち越すのはやめよう」と終止符をうっている。
■『赤ひげ』(1965)

原作:「赤ひげ診療譚」山本周五郎 監督:黒澤明
出演:三船敏郎、保本登、加山雄三、森半太夫、土屋嘉男 ほか
昔は医療技術を人情で補っていた。今は技術は日々向上しても心ない医療が目立つ。
本当に親身になって病人の気持ちになって診てくれる名医を見つけるのは難しくなってしまった。
殿様連中は食べ過ぎと運動不足で病になり、貧困者は栄養失調と苦労から心も体も病となる。
病気は暮らし、しいては時代を映す鏡にもなる。
いまだに発展途上国はこのように知識と薬が乏しく、荒れた生活環境に苦しんでいる。
■『ビーン』(1997)
監督:メル・スミス 出演:ローワン・アトキンソン、ピーター・マクニール ほか
一応シリーズ中のウケのよかったギャグを使って、ビーンがアメリカで暴れまくるんだけど、なぜかフシギと笑えない。ヘンだな?
本国を舞台にしたTVシリーズは面白いのに。アトキンソン本人としてはどーなんだろ。
妙にハリウッド映画的なのがビーンらしくないんだな。普通のコメディドラマになってる。
他の俳優にまじってサイレントドタバタ風のビーンが浮いてるし、型にハマらないのが持ち味なのに、
ちゃんと職業もって生活してる姿は不似合い。こんなに笑えないなんて予想外!
■『THE X-FILES THE MOVIE』(1998)(劇場にて
監督:ロブ・ボウマン 出演:デイヴィッド・ドゥカブニー、ジリアン・アンダーソン、ミッチ・ピレッジ ほか
TVシリーズを大画面で観ましたってゆーのが正直な感想。
やっぱコレはシリーズ観てるX-FILERじゃなきゃ納得できない特異な世界。
それだけTVシリーズが毎週ものにしては毎回、小道具も凝っててかなり大掛かりに質の高いつくりになってるってことなんだけど。
確かに劇場用にいくつか大掛かりな外ロケでCG合成がある。
これはスペシャルでメイキングを観ちゃったからちょっと驚きが半減。
後に復習会を開かなきゃならないくらい、時々、理解困難に陥るエピソードの時があるけど、今作もそれ。
いくつかの進展はあってもシリーズの性質上、解決する終わり方はあり得ないから、
モルダーらが必死にあがいて自問自答する姿に同情心さえ湧いてくる。
一番ひっかかるのは、なぜ蜂を通して培養などしてたのか? なおさら人類滅亡の原因になるじゃん。
UFOの中の巨大さと後に残った巨大な雪原の穴がスケールでっかくて見所。
2人を大画面でどアップで観るのがちょっとフシギな感じ。