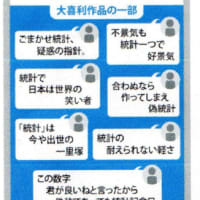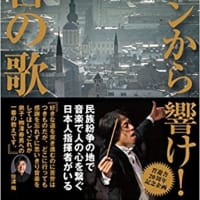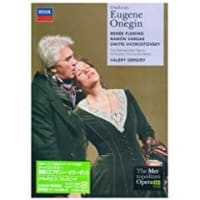日経の経済教室(8月18日付)吉川弘之先生が「科学、統合的知性の創造を」で、科学コミュニティが社会と向き合いかたについて、示唆に富む論を展開している。
科学者はそれぞれの領域を超え大所高所から広い視野にたって、協力作業を通じて、「独立、不偏、学派なし」の中立的助言を構成し、政策提言を行うべきである、と具体的な科学者が政策へコミットする際のフローを具体的に提示しながら説いている。
吉川先生は元東大学長であるが、学術会議会長、そして産総研の理事長をなさっていたこともあり、工学部の先生だが広い教養に裏打ちされたその文明論は強い説得力を持つもので、いつも先生が何をどう考え発言されるか個人的に注目している。さらに、先生はフェミニストでもあると私は思っている。
科学者の原発への助言は社会的助言が必要で、学会内での学説を戦わせるようなものではなく、中立的な助言をつくるための固有の場の必要性を説く。
平時はいいが、今回の福島第一の事故というような非常時においては、学者は専門バカであってはならないのであり、専門領域に埋没する日常的な研究とは異質のものを追求する姿勢が必要なのだ。自己の専門領域から一歩踏み出し、科学的知識の全体状況を俯瞰し、集合的知性を作り出すことが求められている。学術会議のそれぞれの専門委員会がどう今回、叡智を結集し協力し、科学者の立場から政策提言を行うことができるのか、3.11からこれまでどのような知の結集体として社会発信してきたのかというとかなり弱弱しいものであるように思う。
日本の科学者の真価が問われている。まさに学際的な見地から、それぞれのアカデミズムの「村」から脱出し、フクシマに向かう科学者の決意と総合力が今こそ問われているときはないだろう。
科学者はそれぞれの領域を超え大所高所から広い視野にたって、協力作業を通じて、「独立、不偏、学派なし」の中立的助言を構成し、政策提言を行うべきである、と具体的な科学者が政策へコミットする際のフローを具体的に提示しながら説いている。
吉川先生は元東大学長であるが、学術会議会長、そして産総研の理事長をなさっていたこともあり、工学部の先生だが広い教養に裏打ちされたその文明論は強い説得力を持つもので、いつも先生が何をどう考え発言されるか個人的に注目している。さらに、先生はフェミニストでもあると私は思っている。
科学者の原発への助言は社会的助言が必要で、学会内での学説を戦わせるようなものではなく、中立的な助言をつくるための固有の場の必要性を説く。
平時はいいが、今回の福島第一の事故というような非常時においては、学者は専門バカであってはならないのであり、専門領域に埋没する日常的な研究とは異質のものを追求する姿勢が必要なのだ。自己の専門領域から一歩踏み出し、科学的知識の全体状況を俯瞰し、集合的知性を作り出すことが求められている。学術会議のそれぞれの専門委員会がどう今回、叡智を結集し協力し、科学者の立場から政策提言を行うことができるのか、3.11からこれまでどのような知の結集体として社会発信してきたのかというとかなり弱弱しいものであるように思う。
日本の科学者の真価が問われている。まさに学際的な見地から、それぞれのアカデミズムの「村」から脱出し、フクシマに向かう科学者の決意と総合力が今こそ問われているときはないだろう。