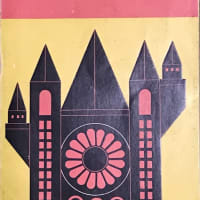2014年3月5日(水)
○ 容止若思 言辭安定
容止(立ち居ふるまい)は、ものを考えているようにおごそかに、
言葉は落ち着いてはっきりと。
反省、そうありたいものだ。
李注も引用する『礼記』に、「人の坐思する、貌(かたち)は必ず儼然(げんぜん)たり」とあり、「人が座って考えているとき、その様子は必ず厳かである」という意味だそうな。
試験監督というのは不思議な作業で、経験しておく意味があった。
ひとつは人の緊張がきわめて強い伝染性をもつことで、殊に試験前の注意事項を説明する時など、緊張も最高潮に達した受験生らの注目を浴びて、肌に痛いような感じがあった。
緊張や不安が伝染するからには、安心もまた伝染する。試験監督にあたるスタッフの「容止」が、受験生のパフォーマンスに微妙に影響を与えることもあるだろう。自分自身の肩の力を抜き、緊張の毒を減じて伝え返すよう心がけたものだ。
桜美林時代のある年にセンター試験の監督を担当した。広い教室の暖房や採光にも気を遣いながら、和やかを旨として作業にあたった。長い一日の最後の科目が終了し、疲労と安堵の息を吐いて退出していく百人あまりの受験生の流れから、男子がひとり離れてやってきて「今日はありがとうございました」と丁寧に礼を述べた。
こちらの配慮が伝わり、それをねぎらってもらえたことも嬉しかったが、それ以上にこの若者のために喜んだ。入学試験本番という緊迫の場面にあって、他人の労にちゃんと目を止め、それを感謝することのできる彼の、人としての成熟が嬉しいのである。
今頃どこで何をしているか、きっと良い役割を果たしていることだろう。
もうひとつが本題だった。
これは入試よりも、担当科目の学期末試験の際にいつも思ったのだが、一心不乱に試験に取り組んでいる学生たちは、みな実にいい顔をしているのである。無心に何かを考えることは、それ自体祝福された営みなのだ。『礼記』はそのことを伝えている。
そうした学生の姿を見るのが楽しみで、小テストを頻繁に課した・・・わけではなかったんですけどね。
3日(月) 次男、海外旅行に発つ。フランスの空気を吸いに出かけた。
4日(火) 長男、関西より帰る。誕生日に重なった。
5日(水) 両親、松山へ戻る。空港まで送る。
弥生三月、何だか空気が落ち着かない。
○ 容止若思 言辭安定
容止(立ち居ふるまい)は、ものを考えているようにおごそかに、
言葉は落ち着いてはっきりと。
反省、そうありたいものだ。
李注も引用する『礼記』に、「人の坐思する、貌(かたち)は必ず儼然(げんぜん)たり」とあり、「人が座って考えているとき、その様子は必ず厳かである」という意味だそうな。
試験監督というのは不思議な作業で、経験しておく意味があった。
ひとつは人の緊張がきわめて強い伝染性をもつことで、殊に試験前の注意事項を説明する時など、緊張も最高潮に達した受験生らの注目を浴びて、肌に痛いような感じがあった。
緊張や不安が伝染するからには、安心もまた伝染する。試験監督にあたるスタッフの「容止」が、受験生のパフォーマンスに微妙に影響を与えることもあるだろう。自分自身の肩の力を抜き、緊張の毒を減じて伝え返すよう心がけたものだ。
桜美林時代のある年にセンター試験の監督を担当した。広い教室の暖房や採光にも気を遣いながら、和やかを旨として作業にあたった。長い一日の最後の科目が終了し、疲労と安堵の息を吐いて退出していく百人あまりの受験生の流れから、男子がひとり離れてやってきて「今日はありがとうございました」と丁寧に礼を述べた。
こちらの配慮が伝わり、それをねぎらってもらえたことも嬉しかったが、それ以上にこの若者のために喜んだ。入学試験本番という緊迫の場面にあって、他人の労にちゃんと目を止め、それを感謝することのできる彼の、人としての成熟が嬉しいのである。
今頃どこで何をしているか、きっと良い役割を果たしていることだろう。
もうひとつが本題だった。
これは入試よりも、担当科目の学期末試験の際にいつも思ったのだが、一心不乱に試験に取り組んでいる学生たちは、みな実にいい顔をしているのである。無心に何かを考えることは、それ自体祝福された営みなのだ。『礼記』はそのことを伝えている。
そうした学生の姿を見るのが楽しみで、小テストを頻繁に課した・・・わけではなかったんですけどね。
3日(月) 次男、海外旅行に発つ。フランスの空気を吸いに出かけた。
4日(火) 長男、関西より帰る。誕生日に重なった。
5日(水) 両親、松山へ戻る。空港まで送る。
弥生三月、何だか空気が落ち着かない。