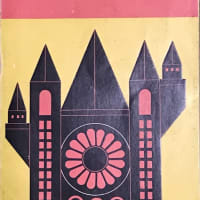2015年12月4日(金)
ドイツの宗教思想家というなら、キリスト教思想家ということだろうが、ヒントとしてはあまりに漠然としている。僕の思いつくいくつかの名前は神学者のそれで、神学者とキリスト教思想家は厳密に言えば同じではない。ニーチェは逆説的な宗教思想家と言えなくもないが、やっぱり違うんだろうな。ヤスパースはキリスト教的実存主義者などと称され、これまた候補になるかしら、戦争との関連で言うならボンヘッファーは有力候補かも知れない、等々。
まるで違いました。
***
真田は、広岡に向かってというより、ほとんど独り言のように話しつづけた。
「ドイツの宗教思想家の言葉に・・・火は鉄を試し、誘惑は正しき人を試す、というのがあります」
「でも、正しさを示すのは誘惑などという生やさしいものではなく、やはり火です。すべてを燃やしつくそうとする炎です」
「私たちの魂は正しき人のそれではありませんでした。火に試され、炎に灼かれた私たちの魂は・・・砂のようにボロボロと崩れてしまいました」
そして真田は、ハンドルを握る広岡の背後の座席で静かに眠り込んでしまう。
***
「炎は鉄を鍛え、誘惑は正義を鍛えます」
『キリストに倣いて』第1巻第13章の言葉である。トマス・ア・ケンピス(1380-1471)は、ケルン近郊のケンペンに生まれた。通り名のトマス・ア・ケンピス Thomas à Kempis はラテン/フランス語式で、ドイツ語なら Thomas von Kempen というところである。
『キリストに倣いて』は『キリストのまねび』とも訳され、キリスト教世界では歴史上、聖書についでよく読まれた書物などと言われるが、日本人で実際に読む者は多くあるまい。これを引用した真田の博学は驚くべきものだけれど、誘惑を火に比すべくもない生やさしいものと評するあたり、「ちゃんと読みました?」と訊いてみたい感じがする。
ケンペンのトマスがここに示した誘惑は、生やさしいものなどではない、人の魂をぼろぼろに灼き尽くすほどの激しい試みのことだった。真田たちはまさにそのような試練の摺り鉢で、容赦なく摺りおろされたのである。
それにしても迦具土神といい『キリストに倣いて』といい、昨日から炎の表象が紙面の一隅で燃え続けているように、ついつい読めてしまう。シリアのこと、アメリカのことがそこにつながる。