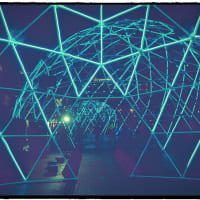ミスター・ピーノの【見るが勝ち通信】その113
私の知り合いであるミスター・ピーノさんは
海外滞在が長く、
外国語にもご堪能な方ですが、一週間程度で
物凄い量のものを、見る、読む、聴く。
私も見習いたいと思っております。
ピーノさんからいただいているメールマガジンを
ご本人の承諾を得てこのブログに転載しているものであります。
読者の皆様、感想等ございましたら
私が責任を持ってお伝えしますので
ぜひコメント欄にお願いします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◇今の季節は午前4時過ぎにジョギングをしていると、ちょうど冬の星座が
南の空にバッチリ見ることができます。オリオン座の三ッ星を左にたどると
明るい「シリウス」が見え、そこから左上のこいぬ座の「プロキオン」に行き、
右に進んでオリオン座の「ベテルギウス」を結ぶと、“冬の大三角形”です。
中学時代、夏は自宅から徒歩数分のプラネタリウムに通い、冬は10cmの
反射望遠鏡を抱え近くの空き地まで歩き、『天文ガイド』を購読してました。
土星の輪や月面を見るだけで幸せな気持ちになれたときがあったんです。
http://www.astromuseum.jp/sky/sky_ind_w.html
◇先日東京駅に行った際、『赤レンガ駅舎』の保存・復元工事が終了して、
地方から出てきた高齢者のひとたちが、新丸ビル前や中央郵便局前から
駅舎の全景を撮ったり、駅舎内の南ドームの天井レリーフ(浮き彫り細工)
を撮影したり、平日にもかかわらず観光客でにぎわっていました。 東京駅
で買う弁当はこのところ決まっていて『スペイン産ベジョータイベリコ豚重』。
これは、どんぐり(ベジョータ)を食べて育った、生ハムで有名なイベリコ豚
の肉を使った高カロリー弁当(1152kcal)で一度食べるとクセになる味(笑)
http://www.kanemi-foods.co.jp/eashion/menu/detail/18
◇高2の夏休み、初めて一人で欧州旅行をしたとき、「プリーツ(Preetz)」
というハンブルクとキール(Kiel)の間にある鈍行列車しか止まらない町に
一泊したことがあります。モスクワ発の2泊3日の夜行で到着したウィーン
の郊外にあるユースホステルで知り合ったドイツ人から、もし日本に帰国
する前にハンブルクに来るなら寄りなよと言われて、実際に行ってみると、
彼は牧師さんの息子で住居は教会の隣でした。 お互い片言の英会話で、
よく意思が通じ合えたな、と今なら思いますが、当時は必死だったのかも。
【コンサート】
■ヤマハ ジャズ フェスティバル(12/11/04、アクトシティ浜松大ホール)
今回の国内ツアーを最後に、プロ演奏家としての活動から引退することを
表明している大西順子のトリオが第1部で、代表曲の「ユーロジア」を演奏。
第2部は小林圭の軽めのジャズ・ヴォーカル+4(伴奏)で「枯葉」や「Shall
we dance?」。トリは、ヴァイオリンのクリスチャン・ハウズをゲストに迎えて
16人編成の高速ビッグバンド『BATTLE JAZZ BIG BAND』による「Jump」、
「Open the door」など。 30歳前後のメンバーが中心となり、アンサンブル
もソロも演奏に勢いがあり若さ一杯の全力投球で投げぬいた感じでした。
http://www.junkoonishi-art.com/message.html
【演劇】
■るつぼ <原題 The Crucible>(新国立劇場、12/11/03 ★★★★)
アーサー・ミラーの戯曲を宮田慶子が演出。 2部構成で、4時間弱の舞台。
17世紀末にピューリタンの信仰が厚いマサチューセッツ州の村で起こった
魔女裁判がテーマ。 無実の人々を魔女として告発する女性(鈴木杏)が、
徐々に“聖女化”され、過去に彼女と関係してしまった農夫(池内博之)は、
魔女の嫌疑をかけられた妻の潔白を証明するため、判事に自身の不義を
告白したところ逆に彼女から魔女として訴えられ、立場が二転三転します。
真実の訴えが群集心理(思い込み)により無力化する恐怖の世界でした。
http://www.nntt.jac.go.jp/play/20000618_play.html
【映画】
■リンカーン 秘密の書 <原題 ABRAHAM LINCOLN:Vampire Hunter>
(★★★☆) 第16代米国大統領となるリンカーンとヴァンパイア(吸血鬼)
たちとの戦いを描いたアクション映画。幼いころ借金返済の見せしめとして
ヴァンパイアに殺された母親の復讐物語。斧(オノ)を使って“吸血鬼狩り”
をするわけですが、すさまじいCG映像の連続で、頭はコロコロ血がドバー
と飛び散り、疾走する馬上と列車での緊迫感ある戦いが見せ場。 最後の
夫婦でこれから演劇を観にいく場面は、劇場でのリンカーンの暗殺を暗示
してます。上映前スピルバーグ作『リンカーン』の予告編には思わず苦笑。
公式HP(音声注意) ⇒ http://www.foxmovies.jp/lincoln3D/
■のぼうの城 (★★★★)
和田竜のオリジナル脚本を映画化。豊臣秀吉の家臣、石田三成が2万人
の兵を率いて、500人の兵で守る武州・忍城(おしじょう)に攻め込む話で、
史実をもとにしたフィクション。 野村萬斎が演じる城代、成田長親が(でく)
のぼう様と農民たちからも慕われ、奇策と家臣である侍大将(佐藤浩市、
山口智充他)たちと一丸となり迎え撃つ前半と「水攻め」をどのように打開
するかの後半が見どころ。“狂言師”としての野村の舞を楽しむことができ、
この映画の成功は何と言っても愛される主役に抜擢された彼の名演です。
公式HP(音声注意) ⇒ http://nobou-movie.jp/
■北のカナリアたち (★★★)
湊かなえの短篇を原案とした映画化。 吉永小百合主演。 6人しか生徒が
いない離島(礼文島ロケ)で起きた20年前の出来事と、現在を並行させて
司書として定年を迎えた元担任教師(吉永)が当時の生徒を訪ねる物語。
満島ひかり、宮崎あおい、森山未來、柴田恭平、仲村トオルなどが“脇役”
にまわり「歌を忘れたカナリア」(西条八十作詞)を歌うラストが印象的です。
子どもたちが歌う「クリスマス・イブ」(山下達郎)や、陽水の楽曲に違和感
がありましたが、封切り 2日目夕方の回で「観客2人!」にはビックリです。
公式HP ⇒ http://www.kitanocanaria.jp/
【Book】
■中川右介 「グレン・グールド」(朝日新書、12/10/30 ★★★)
11歳でトロントのピアノ・コンペティションで優勝してから、31歳で演奏会を
引退するまで、“コンサート・ピアニスト”としての20年間に焦点を当てた本。
ジェームズ・ディーン(1歳上)やエルヴィス・プレスリー(3歳下)にも言及し、
クラシック音楽界全体が世代交代する1955年以降を中心にアメリカツアー
の演奏とレコード録音、1957年のソ連ツアーでのリヒテルとの出会いなど、
特にカラヤンとバーンスタインとのコンサートにおけるやり取りが興味深い
です。 残念だったはあまりに俯瞰的な記述で後半が失速してしまった点。
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=14294
 |
グレン・グールド 孤高のコンサート・ピアニスト (朝日新書) |
| 中川右介 | |
| 朝日新聞出版 |
■平田オリザ 「わかりあえないことから」(講談社現代新書、12/10/20
★★★★) いま企業が就活する学生に求める「コミュニケーション能力」は、
「異文化理解能力」と「同調圧力」という矛盾するダブルバインド:二重拘束
になっていることを指摘。 公立学校で演劇によるコミュニケーション教育の
進め方を実践しながら、これからの時代に必要なリーダーシップは、「弱者
のコンテクストを理解する能力」だろうと考えます。 バラバラな人間がバラ
バラな価値観のままでどうにかしてうまくやっていく能力が求められており、
「同情から共感」へ「協調性から社交性」へ、人は演じる生き物であること。
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2881772
 |
わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か (講談社現代新書) |
| 平田 オリザ | |
| 講談社 |
【オマケ、今週の気になった言葉】
■演劇は、人類が生み出した世界で一番面白い遊びだ。きっと、この遊び
の中から、新しい日本人が生まれてくる。
(by 平田オリザ、上掲本「わかりあえないことから」 P230より)
英語の「play」という言葉。「戯曲:演じる」、「競技:競う」、「演奏:演奏する」、
「気晴らし:遊ぶ」、「賭け事:賭ける」ほか、さまざまな名詞と動詞の意味が
あります。 「play」という行為は、“勤勉実直”が美徳とされる日本ではえて
して否定的なニュアンスで捉えられ、「playboy:道楽者」も「player:遊び人」
も趣味やギャンブル・酒色に走るひとというイメージがある一方、別の意味
ではスポーツ競技(野球・サッカー他)を行う「選手」や、「俳優」や「演奏者」
といったひとたちも含まれます。「演劇」に限らずこれらの「play」が意味する
あらゆるものは、極めて人間的な行動で、生活の一部になくてはならない、
必要不可欠なものと考えてしまうのは、決して間違いではないと思います。
「遊び心」(何かに夢中になること)をいつもどこかに抱えていたい願望です。
では。