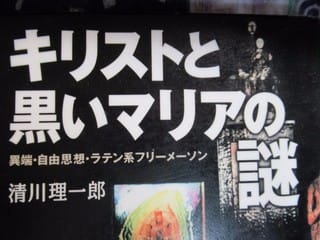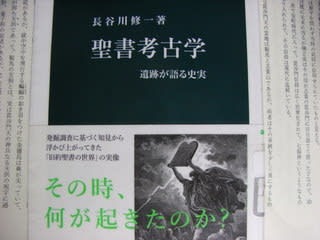2018-03-21 | 古代キリスト教
上の像は、わたしが買った、12世紀からスペインの「モンセラ」という町で祀られている「黒い聖母子像」の写しです。
毎日見ていると、お地蔵様みたいな気もしてきますが、いわゆる「西洋的マリア」とはずいぶん異なったものだと、つくづく思ってしまいます。
引き続き、「黒い聖母と悪魔の謎」馬杉宗夫氏著のご紹介をさせていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「ル・ピュイ」の「黒い聖母」は、伝説によれば、1254年に、聖ルイ王(ルイ9世)がエジプトから持ち帰り、「ル・ピュイ」に寄進したものとされている。
この像はもともと古代エジプト時代の「イシス神」であり、それを「聖母像」に作り替えたものと記されている。
しかし、この像の制作場所や年代は定かではない。
確かなのは、1096年以前に、「ル・ピュイ」の地にすでに「聖像」があったことである。
と言うのは、十字軍に出かける前に「自分が生きている限り、祭壇の尊敬すべき聖母像の前に、絶えることなくろうそくの火をともしておくこと」を要求した人の記録が残されているからである。
「ル・ピュイ大聖堂」の祭室外壁には、「ドルイド教」時代の浮き彫りと、それに面して「聖なる泉(井戸)」が置かれている。
この地が、いかに「巨石崇拝」や、「聖なる水の崇拝」の伝統の強い所であったのかが分かるのである。
「巨石(聖石)崇拝」と結びついた他の地は、ロカマドール、スペインのカタルーニャ地方のモンセラ、サンジェルヴァジィの台地などで、「巨石」が今なお存在している。
ボーズ平原に奇跡のごとく建つ「シャルトル大聖堂」にも、古くから崇拝されていた「黒い聖母」があった。
それは「地下祭室」に安置され、「地下の聖母」と呼ばれている像である。
像の下に「出産を前にした聖母」と記されている。
すなわち、伝説によれば、この像はキリストが生まれる以前に制作され、「ドルイド教徒」達が崇拝していたと言われている。
いわゆる「地下の聖母」は、「ドルイド教」時代に遡る最も古いもので、彼らの「大地の女神崇拝」と結びついていたものと思われている。
「シャルトル大聖堂」の「地下の祭室」には、4世紀頃の「井戸」があるように、そこは「ドルイド教徒」たちの「聖なる水」の信仰と結びついていたのである。
この「地下の聖母」の制作年代は定かでない。
「黒い聖母像」がある所は、古いドルイド教の伝統と、新しいキリスト教が同化した場所であることがわかるのである。
しかし、これらの「聖母」はなぜ「黒い」のであろうか?
その象徴的意味は何だったのであろうか?
この奇異に思える「黒い色」の意味を、あえて「聖書」の中に探してみるならば、「旧約聖書」の中に、それらしきものが見られる。
エルサレムの娘たちよ
わたしは黒いけれども 美しい
ケダルの天幕のように
ソロモンのとばりのように
「旧約聖書・雅歌 1章5節」
異教的とも思えるこの「雅歌」の文句については、中世以来、多くの解釈がなされている。
しかし「黒い聖母」がこの文章を典拠にしているという証拠は何もない。
キリスト教以外の宗教を見れば、“死の象徴”とも言うべき「黒」は、必ずしも悪い色としてとらえられていない。
古代神話における「大地の女神」は、しばしば「黒く」表現されている。
たとえば古代エジプト神話における「地母神イシス(死者の守護神であり、豊穣神でもあり、太陽神ホルスの母)」は、「黒く」表現された。
「幼児ホルス神」を抱いて座るこの「イシス像」の中に、キリスト教の「聖母子像」の原型を見る論者もいる。
「イシス信仰」は、地中海世界に広く伝播していったと考えられている。
ギリシャ神話の「大地の豊穣神・デメテール」と、「イシス神」を同一視する人もいる。
また「世界7不思議」の一つと言われた小アジアの「エフェソスのアルテミス(ダイアナ)の神殿」には、「太陽神アポロンの双子の妹にあたるアルテミス(古くは先住民族の「地母神」)の、「黒い像」が描かれていたと伝えられている。
「シャルトル大聖堂」の「地下祭室」にあった「黒い聖母」も、「ドルイド教の大地の女神、豊穣なる大地、その母なる女神・デメテール」の信仰を受け継いだものでなかったか?
「黒い色」は、すべて「大地の女神」に結び付いているのである。
大地は、「暗黒の闇」から「生命」を生み出す根源なのである。
また、各地に存在する「黒い石崇拝」も、これと無縁ではない。
イスラム教の聖都・「メッカ」のモスクにも、「黒い石」が「聖石」として飾られている。
興味深い現象である。
「黒い石」は、錬金術的な意味も持っていた。
錬金術師たちの最初の重要な仕事は、万有還元能力があるとされた「仙石」を作りだすことであった。
そのためには、まずその第一の原料を集める必要があった。
この原料は重く、割れやすく、その上砕けやすい、石に似た「黒い物質」であり、簡単に手に入るものとされていた。
錬金術師たちは、この最初の原料を探すためには「地下に」、「金属を含有する鉱床」に行かねばならない。
ゴール地方の錬金術師たちは、「ドルイド教」の神官を兼ねていた。
彼らは、「見者」「識者」「魔法を使う博士」であった。
彼らの儀式や仕事のためには、しばしば「地下」や「洞窟」が選ばれた。
このことも、「黒い聖母」がシャルトル、クレルモン、ロカマドール、モンセラなどのように、「地下」
や「洞窟」がある場所に見出されるという事実と一致して面白い。
「黒い聖母」は、「物質界」から「精神界」へと、我々を導く役割が担わされていた。
「黒い聖母」は大地からあらゆるエネルギーを吸収し、それを「天上界」の力と結びつける。
「緑色」は、大地から生まれてくる植物の色であり、物質と精神という異なった両者に調和をもたらす色である。
その緑色が、「聖母」の衣の色として与えられる。(後に青となったという)
他方「赤」は、太陽の色であり、愛やエネルギーを生み出す。
それは救世主キリストの衣の色となる。
すなわち「黒い聖母」は、物質界の「黒」=「現世」と、精神界の「赤」=救世主キリストとを結びつける仲介者としての役割をもっていた、とされる。
アルルの公会議(452年)、ナントの公会議(658年)、トレドの公会議(681年)、さらにカール大帝によって公布された法令(789年)などは、繰り返し、「樹木・石・泉・井戸を崇拝すること」を禁じている。
この事実は、ゴール(フランス)の地がキリスト教化された以降も、根強く「ドルイド教」の信仰が残っていたことを物語っている。
これら土着の民間信仰との衝突をさけるため、これらの地の「聖母マリア」は、「土着の地母神」との一致が求められ、あえて黒く塗られたのではなかろうか?
12世紀ロマネスク美術において、なぜこのように多くの「聖母像」が表現されるようになったのか?
そしてそれは、すでに存在していた「聖母表現」のどのタイプに従ったのか?
という問題が残っている。
「神の母」としての「聖母マリア」の「神性」が認められたのは、431年、「エフェソスの宗教会議」においてであった。
それ以来、東ヨーロッパのビザンチン世界では、「聖母マリア」表現が増えていったが、その大部分は「幼児キリストを抱いた聖母子像」としてであった。
西欧における最初の「聖母子像」は、800年頃、「アイルランド写本」の中に現れている。
その後、12世紀ロマネスク美術と共に、独立した「木製聖母子像」が現れ、またたく間に西欧中に伝播していくのである。
12世紀に西欧に現れた「聖母像」のタイプは、「玉座のマドンナ」であった。
「黒い聖母像」も、このタイプに従っている。
それはまさにヨーロッパに「聖母マリア崇拝」が高まり、「聖母マリア(ノートルダム=フランス語で「我らの貴婦人」)」に捧げられた大聖堂が建てられ始めた時と対応しているのである。
そして「聖母の衣」を保持するシャルトル大聖堂自身も、ヨーロッパにおける「マリア崇拝」の中心地になっていったのである。
(引用ここまで)
*****
わたしは、このテーマの本を何冊も読んだのですが、ここにも書かれているように、あのカトリックのシンボルともされる「シャルトル大聖堂」においても、「黒い聖母子像」が崇拝の対象となっているということに、非常に驚き、間違いではないかと、何度も確かめました。
wikipedia「シャルトル大聖堂」
ブログ内関連記事
「ストーンヘンジの夏至祭り・・神官ドルイドの復活(1)」(4)まであり
「葛野浩氏著「サンタクロースの大旅行」(1)・・サンタはブタに乗ってやってきた」
「クリスマスの、異神たちの影・・葛野浩昭氏「サンタクロースの大旅行」(2)
「サンタクロースが配っているのはあの世からのプレゼント・・葛野浩昭氏・・「サンタクロースの大旅行」(3)
「ゲルマンvsローマ、そして、、多様性が文化である・・植田重雄氏「ヨーロッパの祭りと伝承」」
「エハン・デラヴィの、十字架の研究(1)」
「バスク十字」と「カギ十字(卍)」・ヨーロッパ先住民族の十字マーク」
「1世紀前半のユダヤ教会堂跡、日本の調査団発見・・イスラエル・テル・ヘレシュ遺跡・「聖書考古学」」
「キリストはなにを食べていたのか?(1)・・ユダヤ教徒としてのイエス」(5)まであり
「「ユングは知っていた・UFO・宇宙人・シンクロニシティの真相」コンノケンイチ氏(1)・・無意識と宇宙」
「洗礼者ヨハネとグノーシス主義・・「ユングは知っていた・UFO・宇宙人・シンクロニシティの真相」コンノケンイチ氏(2)」
「ユダの福音書(1)・・ユダから見たキリスト」(2)あり
「クリスマス・イエスのお祝いに訪れた〝東方の三博士″は、誰だったのか?・・マギ・星の証言(1)」(4)まであり
「クリスマスはミトラ教の祭りの日・誰が誰を祝うのか?・・「マギ・星の証言」(2)」(4)まであり
「マグダラのマリアによる福音書(1)・・マリアはイエスの高弟だったのか?」(2)あり
「2012年(1)・・時を数えているのは誰なのか?」(6)まであり
「生きなければならないとすれば、それは重すぎる・・ユング派療法家 樋口和彦氏のことば」
「古代キリスト教」カテゴリー全般
上の像は、わたしが買った、12世紀からスペインの「モンセラ」という町で祀られている「黒い聖母子像」の写しです。
毎日見ていると、お地蔵様みたいな気もしてきますが、いわゆる「西洋的マリア」とはずいぶん異なったものだと、つくづく思ってしまいます。
引き続き、「黒い聖母と悪魔の謎」馬杉宗夫氏著のご紹介をさせていただきます。
リンクは張っておりませんが、アマゾンなどでご購入になれます。
*****
(引用ここから)
「ル・ピュイ」の「黒い聖母」は、伝説によれば、1254年に、聖ルイ王(ルイ9世)がエジプトから持ち帰り、「ル・ピュイ」に寄進したものとされている。
この像はもともと古代エジプト時代の「イシス神」であり、それを「聖母像」に作り替えたものと記されている。
しかし、この像の制作場所や年代は定かではない。
確かなのは、1096年以前に、「ル・ピュイ」の地にすでに「聖像」があったことである。
と言うのは、十字軍に出かける前に「自分が生きている限り、祭壇の尊敬すべき聖母像の前に、絶えることなくろうそくの火をともしておくこと」を要求した人の記録が残されているからである。
「ル・ピュイ大聖堂」の祭室外壁には、「ドルイド教」時代の浮き彫りと、それに面して「聖なる泉(井戸)」が置かれている。
この地が、いかに「巨石崇拝」や、「聖なる水の崇拝」の伝統の強い所であったのかが分かるのである。
「巨石(聖石)崇拝」と結びついた他の地は、ロカマドール、スペインのカタルーニャ地方のモンセラ、サンジェルヴァジィの台地などで、「巨石」が今なお存在している。
ボーズ平原に奇跡のごとく建つ「シャルトル大聖堂」にも、古くから崇拝されていた「黒い聖母」があった。
それは「地下祭室」に安置され、「地下の聖母」と呼ばれている像である。
像の下に「出産を前にした聖母」と記されている。
すなわち、伝説によれば、この像はキリストが生まれる以前に制作され、「ドルイド教徒」達が崇拝していたと言われている。
いわゆる「地下の聖母」は、「ドルイド教」時代に遡る最も古いもので、彼らの「大地の女神崇拝」と結びついていたものと思われている。
「シャルトル大聖堂」の「地下の祭室」には、4世紀頃の「井戸」があるように、そこは「ドルイド教徒」たちの「聖なる水」の信仰と結びついていたのである。
この「地下の聖母」の制作年代は定かでない。
「黒い聖母像」がある所は、古いドルイド教の伝統と、新しいキリスト教が同化した場所であることがわかるのである。
しかし、これらの「聖母」はなぜ「黒い」のであろうか?
その象徴的意味は何だったのであろうか?
この奇異に思える「黒い色」の意味を、あえて「聖書」の中に探してみるならば、「旧約聖書」の中に、それらしきものが見られる。
エルサレムの娘たちよ
わたしは黒いけれども 美しい
ケダルの天幕のように
ソロモンのとばりのように
「旧約聖書・雅歌 1章5節」
異教的とも思えるこの「雅歌」の文句については、中世以来、多くの解釈がなされている。
しかし「黒い聖母」がこの文章を典拠にしているという証拠は何もない。
キリスト教以外の宗教を見れば、“死の象徴”とも言うべき「黒」は、必ずしも悪い色としてとらえられていない。
古代神話における「大地の女神」は、しばしば「黒く」表現されている。
たとえば古代エジプト神話における「地母神イシス(死者の守護神であり、豊穣神でもあり、太陽神ホルスの母)」は、「黒く」表現された。
「幼児ホルス神」を抱いて座るこの「イシス像」の中に、キリスト教の「聖母子像」の原型を見る論者もいる。
「イシス信仰」は、地中海世界に広く伝播していったと考えられている。
ギリシャ神話の「大地の豊穣神・デメテール」と、「イシス神」を同一視する人もいる。
また「世界7不思議」の一つと言われた小アジアの「エフェソスのアルテミス(ダイアナ)の神殿」には、「太陽神アポロンの双子の妹にあたるアルテミス(古くは先住民族の「地母神」)の、「黒い像」が描かれていたと伝えられている。
「シャルトル大聖堂」の「地下祭室」にあった「黒い聖母」も、「ドルイド教の大地の女神、豊穣なる大地、その母なる女神・デメテール」の信仰を受け継いだものでなかったか?
「黒い色」は、すべて「大地の女神」に結び付いているのである。
大地は、「暗黒の闇」から「生命」を生み出す根源なのである。
また、各地に存在する「黒い石崇拝」も、これと無縁ではない。
イスラム教の聖都・「メッカ」のモスクにも、「黒い石」が「聖石」として飾られている。
興味深い現象である。
「黒い石」は、錬金術的な意味も持っていた。
錬金術師たちの最初の重要な仕事は、万有還元能力があるとされた「仙石」を作りだすことであった。
そのためには、まずその第一の原料を集める必要があった。
この原料は重く、割れやすく、その上砕けやすい、石に似た「黒い物質」であり、簡単に手に入るものとされていた。
錬金術師たちは、この最初の原料を探すためには「地下に」、「金属を含有する鉱床」に行かねばならない。
ゴール地方の錬金術師たちは、「ドルイド教」の神官を兼ねていた。
彼らは、「見者」「識者」「魔法を使う博士」であった。
彼らの儀式や仕事のためには、しばしば「地下」や「洞窟」が選ばれた。
このことも、「黒い聖母」がシャルトル、クレルモン、ロカマドール、モンセラなどのように、「地下」
や「洞窟」がある場所に見出されるという事実と一致して面白い。
「黒い聖母」は、「物質界」から「精神界」へと、我々を導く役割が担わされていた。
「黒い聖母」は大地からあらゆるエネルギーを吸収し、それを「天上界」の力と結びつける。
「緑色」は、大地から生まれてくる植物の色であり、物質と精神という異なった両者に調和をもたらす色である。
その緑色が、「聖母」の衣の色として与えられる。(後に青となったという)
他方「赤」は、太陽の色であり、愛やエネルギーを生み出す。
それは救世主キリストの衣の色となる。
すなわち「黒い聖母」は、物質界の「黒」=「現世」と、精神界の「赤」=救世主キリストとを結びつける仲介者としての役割をもっていた、とされる。
アルルの公会議(452年)、ナントの公会議(658年)、トレドの公会議(681年)、さらにカール大帝によって公布された法令(789年)などは、繰り返し、「樹木・石・泉・井戸を崇拝すること」を禁じている。
この事実は、ゴール(フランス)の地がキリスト教化された以降も、根強く「ドルイド教」の信仰が残っていたことを物語っている。
これら土着の民間信仰との衝突をさけるため、これらの地の「聖母マリア」は、「土着の地母神」との一致が求められ、あえて黒く塗られたのではなかろうか?
12世紀ロマネスク美術において、なぜこのように多くの「聖母像」が表現されるようになったのか?
そしてそれは、すでに存在していた「聖母表現」のどのタイプに従ったのか?
という問題が残っている。
「神の母」としての「聖母マリア」の「神性」が認められたのは、431年、「エフェソスの宗教会議」においてであった。
それ以来、東ヨーロッパのビザンチン世界では、「聖母マリア」表現が増えていったが、その大部分は「幼児キリストを抱いた聖母子像」としてであった。
西欧における最初の「聖母子像」は、800年頃、「アイルランド写本」の中に現れている。
その後、12世紀ロマネスク美術と共に、独立した「木製聖母子像」が現れ、またたく間に西欧中に伝播していくのである。
12世紀に西欧に現れた「聖母像」のタイプは、「玉座のマドンナ」であった。
「黒い聖母像」も、このタイプに従っている。
それはまさにヨーロッパに「聖母マリア崇拝」が高まり、「聖母マリア(ノートルダム=フランス語で「我らの貴婦人」)」に捧げられた大聖堂が建てられ始めた時と対応しているのである。
そして「聖母の衣」を保持するシャルトル大聖堂自身も、ヨーロッパにおける「マリア崇拝」の中心地になっていったのである。
(引用ここまで)
*****
わたしは、このテーマの本を何冊も読んだのですが、ここにも書かれているように、あのカトリックのシンボルともされる「シャルトル大聖堂」においても、「黒い聖母子像」が崇拝の対象となっているということに、非常に驚き、間違いではないかと、何度も確かめました。
wikipedia「シャルトル大聖堂」
ブログ内関連記事
「ストーンヘンジの夏至祭り・・神官ドルイドの復活(1)」(4)まであり
「葛野浩氏著「サンタクロースの大旅行」(1)・・サンタはブタに乗ってやってきた」
「クリスマスの、異神たちの影・・葛野浩昭氏「サンタクロースの大旅行」(2)
「サンタクロースが配っているのはあの世からのプレゼント・・葛野浩昭氏・・「サンタクロースの大旅行」(3)
「ゲルマンvsローマ、そして、、多様性が文化である・・植田重雄氏「ヨーロッパの祭りと伝承」」
「エハン・デラヴィの、十字架の研究(1)」
「バスク十字」と「カギ十字(卍)」・ヨーロッパ先住民族の十字マーク」
「1世紀前半のユダヤ教会堂跡、日本の調査団発見・・イスラエル・テル・ヘレシュ遺跡・「聖書考古学」」
「キリストはなにを食べていたのか?(1)・・ユダヤ教徒としてのイエス」(5)まであり
「「ユングは知っていた・UFO・宇宙人・シンクロニシティの真相」コンノケンイチ氏(1)・・無意識と宇宙」
「洗礼者ヨハネとグノーシス主義・・「ユングは知っていた・UFO・宇宙人・シンクロニシティの真相」コンノケンイチ氏(2)」
「ユダの福音書(1)・・ユダから見たキリスト」(2)あり
「クリスマス・イエスのお祝いに訪れた〝東方の三博士″は、誰だったのか?・・マギ・星の証言(1)」(4)まであり
「クリスマスはミトラ教の祭りの日・誰が誰を祝うのか?・・「マギ・星の証言」(2)」(4)まであり
「マグダラのマリアによる福音書(1)・・マリアはイエスの高弟だったのか?」(2)あり
「2012年(1)・・時を数えているのは誰なのか?」(6)まであり
「生きなければならないとすれば、それは重すぎる・・ユング派療法家 樋口和彦氏のことば」
「古代キリスト教」カテゴリー全般











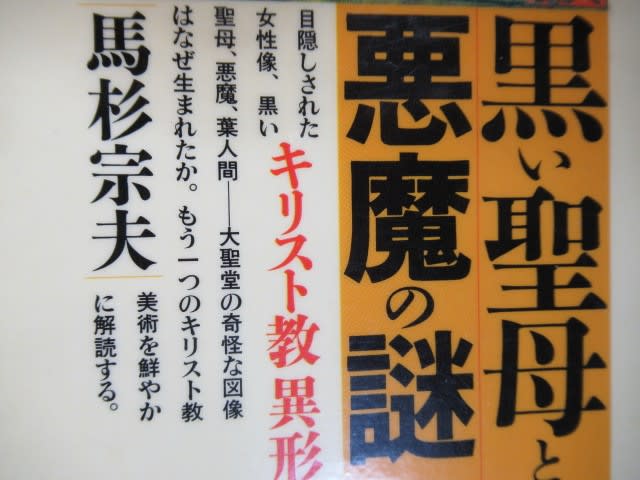
 ブログ内関連記事
ブログ内関連記事 「古代キリスト教」カテゴリー全般
「古代キリスト教」カテゴリー全般

 wikipedia「シャルトル大聖堂」
wikipedia「シャルトル大聖堂」