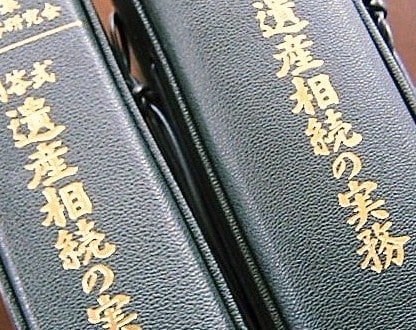本当の愉しさとは
----------------
苦労を経ないと味わえない。
と川北義則は書いている。
(『人生愉しみの見つけ方』)
氏の書く本はいつも
スーッと心の中に入ってくる。
難しいことを難しく書くことは
楽だが
難しいことを判り易く書くことは
大変なのだと思う。
さて
いつも楽々と生きて辛いことは
全部パスしている人間は、
一見愉しそうな人生を送っているように
見えるが、実は少しも愉しくはないのである。
そのことを一番よく知っているのは当人たちで
しばしば暴走の原因になったりする。
愉しい筈なのに愉しくないから苛立つ。
何故そうなるのか。
それは「愉しさ」とは相対的なものだからである。
旨いものばかり食べ続けていると
その旨さは当たり前のものになり
段々とまずく感じ始める。
実際、腹がすいてれば
何を食べてもおいしく感じるものである。
お金だってそうである。
お金がジャブジャブあり
好きなものが何でも買えるとしたら
買う楽しみは色あせ、消え失せてしまう。
苦労をしない人間は
当然、努力もしない。
努力をしないと人間の一番大切な
感性が萎えてしまい、次第に無機質な
人間へとなっていく。
そうした意味においても
「苦労は買ってでもせよ」の教えは
決して死語ではない筈である。
相続・告訴告発・離婚・内容証明
会社設立・在留資格・成年後見
↓
行政書士 青木法務事務所HP
http://www.aoki-houmu.com/