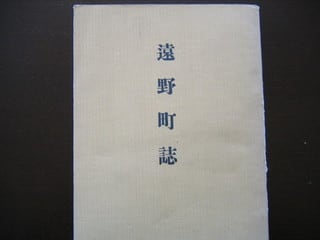信州の古刹「津金寺ー滋野氏宝塔」は
北佐久郡立科町にあります。
天台宗恵日山修学院津金寺。
境内にある石造宝塔3基は
承久2年(1220年)
嘉録3年(1227年)
の銘がしっかり刻まれています。
津金寺は滋野氏やその一族望月氏の祈願寺で
非常に綺麗に掃除がなされています。
境内も広く、春はカタクリ、秋は萩で、多くの来訪者があります。
子供の頃、私は小学校の授業を抜け出して「昼観音」に出かけ
あとで、先生にきつく怒られました。
あの頃の先生は「一本筋が通っていた」。そんな風に
懐かしんでいます。
北佐久郡立科町にあります。
天台宗恵日山修学院津金寺。
境内にある石造宝塔3基は
承久2年(1220年)
嘉録3年(1227年)
の銘がしっかり刻まれています。
津金寺は滋野氏やその一族望月氏の祈願寺で
非常に綺麗に掃除がなされています。
境内も広く、春はカタクリ、秋は萩で、多くの来訪者があります。
子供の頃、私は小学校の授業を抜け出して「昼観音」に出かけ
あとで、先生にきつく怒られました。
あの頃の先生は「一本筋が通っていた」。そんな風に
懐かしんでいます。