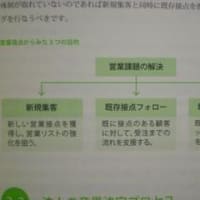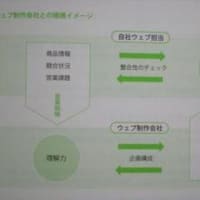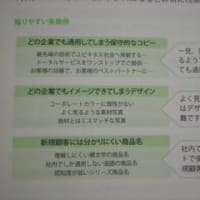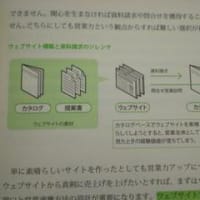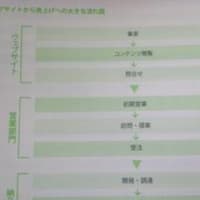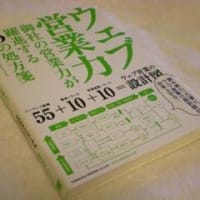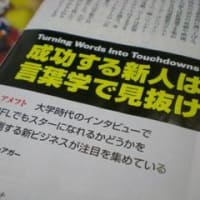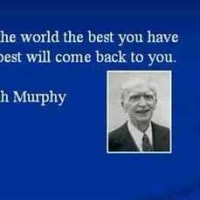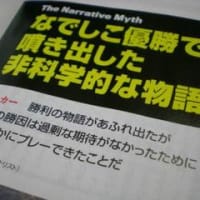「トヨタの成長メカニズムを解き明かす」
出版社名/日本経済新聞社 700円
良くも悪くも、奥田碩(ひろし)氏はその強烈な個性でトヨタを強大に発展させた名経営者です。
その奥田氏がトヨタの社長在任中に行った経営改革の軌跡をまとめたものが、この『奥田イズムがトヨタを変えた 』です。
この本の真骨頂は奥田氏に焦点を合わせるというよりは、どちらかと言うとトヨタグループの成長のメカニズムの解明といったところでしょうか。
世界に誇れる日本企業の代表格として、私達はトヨタの歴史と世界に果たすべき役割を知っておくことは無駄ではないと思います。
最後に奥田氏のプロフィールを以下に記します。
◆奥田碩
1932年12月29日 - )は、日本の実業家。勲等は旭日大綬章。社団法人日本経済団体連合会名誉会長。トヨタ自動車株式会社代表取締役社長(第8代)、同社代表取締役会長、社団法人日本経営者団体連盟会長(第9代)、社団法人日本経済団体連合会会長(初代)、内閣特別顧問などを歴任した。
◆社長就任まで
三重県津市出身。三重県立松阪北高等学校(現・三重県立松阪工業高等学校)を経て、1955年に一橋大学商学部を卒業しトヨタ自動車販売株式会社(現・トヨタ自動車株式会社)入社。大学時代は柔道部に所属し、六段の腕前を誇る。
トヨタ自販の経理部時代に上司とぶつかり、1972年秋、マニラに赴任する。ここで奥田は、フィリピンの政商で、現地でトヨタ車の組み立て・販売を独占するデルタ・モーターの社長・リカルド・C・シルベリオからトヨタへの延滞金を取り立てる任務に就く。肩書きは「経理アドバイザー」。これは困難な任務であり、事実上の左遷であったが、奥田は当時のマルコス大統領らとのコネクションを生かし、未納金の回収に成功した。
当時、マニラには豊田章一郎の娘婿・藤本進が大蔵省の駐在員として出向しており、奥田は章一郎が孫の顔を見に来るたびに同行し、このころから章一郎と奥田の関係が始まった。章一郎は奥田の才能を認め、「マニラでこんなやつがくすぶっているのか。本社の人事は何をしているんだ」とまで言ったという。
1979年に豪亜部長に昇格し帰国。1982年に取締役就任。85年にはアメリカ進出のための用地選定を任され、当時会長だった豊田英二から北米事業準備室副室長に指名される。全米からの応募の中から各知事との交渉に当たり、最終的にケンタッキー州工場の誘致に到る。1987年に常務取締役、1988年に専務取締役、1992年に取締役副社長となり、1995年に代表取締役社長に昇格した。
◆社長時代
社長時代にはそれまでどちらかといえば良い意味で保守的だったトヨタを改革したと言われている。
例えば、世界に先駆けてハイブリッド車「プリウス」を発売したことや、それまでトヨタが敬遠していたF1への参戦を表明したことなどである。奥田時代、当時国内販売で落ち込んでいたシェアを3年がかりで40%代まで回復させるなど、奥田の時代からトヨタは「攻め」の姿勢に転じて躍進を遂げ、現在の世界第1位の自動車メーカーの座を手にした。このことから、彼の経営手腕は一般的に高く評価されており、ハウツー本が出販されたり他のメーカーの中には彼の改革を手本にする企業まで出てきた。
奥田の諸改革には常に後ろ盾として豊田章一郎の姿があり、奥田も豊田本家の章一郎を求心力として旗印にし、常に豊田家を立てつつ改革を進めた。
その一方で、スポーツタイプの車種を全廃した戦略、モータースポーツを広告として捉えるやり方への批判、従業員に過度のサービス残業を強いて労働基準監督署の査察を度々受ける事態を招いたり、業績好調にもかかわらず外国人労働者や非正規雇用の確保で賃金の抑制を行うなど彼の経営姿勢を批判する声もきわめて多く、改革への評価と表裏一体である。
◆財界トップへ
1999年6月、次期社長に副社長だった張富士夫を指名して代表取締役会長就任。また同年社団法人日本経営者団体連盟会長就任。
その後2006年まで社団法人日本経済団体連合会会長を務め、7年にわたって財界トップの座にあったほか、歴代内閣で経済財政諮問会議や各種審議会、有識者会議の委員を数多く勤め、多数の企業の役員に名を連ねるなど政財界に大きな影響力を誇った。
他に、2001年株式会社東京証券取引所取締役就任、2002年株式会社UFJホールディングス取締役就任。株式会社楽天野球団経営諮問委員会委員、KDDI株式会社監査役・取締役、株式会社豊田自動織機監査役、東和不動産株式会社取締役、中京ゴルフ倶楽部株式会社理事、株式会社豊田中央研究所取締役(2006年まで)、株式会社デンソー取締役(2003年まで)、株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部理事等も務める。
◆発言など
『日経ビジネス』1995年7月17日号に「愛車のアクセル全開で憂さ晴らし」という記事が掲載された。その内容によると、アリストに乗る奥田が、先行車との「車間距離をぐっと詰め、パッシングの連続で押しのける」などの行為を常習的に行っていることが語られている。彼はテストコースで200キロ以上の速度を出す事もしばしばあり、当然右車線を走行していた事や高速道路で160キロ以上ものスピードで走っていた事も明かしており、「スピードは麻薬」「普段は黒塗りの役員車に乗っているが、トロトロ走る役員車に乗っているとイライラする」と迄発言しており、運転手に言い掛かりをつける事もしばしばある。彼にとってはこのアリストが、休日の脚だったそうだ。
『毎日新聞(2004年2月12日)』に『奥田経団連会長:牛丼フィーバーにチクリ 「単純な国民だ」』という記事が掲載された。その内容によると、BSE(牛海綿状脳症)の影響で、吉野家のほとんどの店で2月11日に牛丼販売が休止され、直前に客が「食べおさめ」の行列をつくったことについて、奥田は翌12日、東海地方経済懇談会後の記者会見で「テレビは一部の人の動きを面白おかしく報じていたようだが、(牛丼がなくても)死ぬわけでない。日本人は右から左へ早くふれやすい、単純な国民だと感じた」と発言。懇談会でも奥田は牛丼を教育上の問題点の例に挙げ、「日本人はどうしたのだろうか。やはり教育に力を入れなければならないと感じた」と語った。
皇室典範に関する有識者会議のメンバーを務める。(女性・女系天皇容認派)
ミサワホームの経営危機を巡る発言が結果的にミサワホームを産業再生機構入りに追い込んだとして、ミサワホーム創業者(元会長)三澤千代治側が竹中平蔵経済財政担当相(当時)、斎藤淳産業再生機構社長と共に公務員職権乱用罪で告発する事態が起こった。
ライブドアの日本経団連入会を認めた際に「企業倫理を学ぶのに役立ててほしい」と堀江貴文を評価していたが、1ヵ月後ライブドアに証券取引法違反が発覚すると「経団連として(ライブドア入会は)ミスだった」と釈明した。
2006年3月8日の記者会見では残虐なゲームソフトの影響で一部の若者が社会に適応できなくなりニートと化している可能性を指摘。経団連としてチェック体制を確立すべく検討を開始したと述べた。
拝金的な資本主義経済よりも、企業人は「武士道の精神」のような「心の規範」を持つべきと発言した[12]。
橋梁談合事件が起こった際には「談合は慣習、一気になくすのは難しい」「全国津々浦々に行きわたっている慣習のようなもので、地方では仕事を回し合っているワークシェアリング。本当にフェアな戦いをすれば、力の強いところが勝ち、弱いところは沈んでしまう」と発言[13]。
2006年11月19日の国際ロータリー第2760地区(愛知地区)大会の記念講演で「世界の現状と日本の針路」と題した部分の中で「均一性、画一性の社会は、規格品の大量生産には適していたが、今やそれは中国の強み」と指摘し、今後の日本は国民にも地方にも「多様性、独創性」(外国からの移民受け入れ)が必要だと訴えた。さらに、少子化について労働人口の急激な減少を懸念。女性や高齢者の雇用を掲げる厚生労働省の対策に「雇用のミスマッチが起きて対応できない」と批判して「外国人の力を借りるのは不可欠」との見方を示した。
2008年11月12日、「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」の席上で、テレビなどの年金報道について「厚労省叩きは異常な話。正直言ってマスコミに報復してやろうかな。スポンサーを降りるとか」[14]「(マスコミの)編集権に経営者は介入できないといわれるが、本当はやり方がある」[15]などと発言した。
2009年3月10日政府の経済財政諮問会議にて中国人旅行者らへのビザの発給要件緩和を早急に実施するよう求めた。
(※ウィキペディアより抜粋)
 奥田自身に関しての記述少なく、少し味気ない
奥田自身に関しての記述少なく、少し味気ない 最近のトヨタの戦略を知るにはよい
最近のトヨタの戦略を知るにはよい 多少持ち上げすぎかもしれませんが。。。
多少持ち上げすぎかもしれませんが。。。
この商品を買った人は、こんな本も買っています☆
▼
 《エネルギー過剰》な自伝。
《エネルギー過剰》な自伝。
 うちの社長に推薦してみよう・・・
うちの社長に推薦してみよう・・・
 純粋な心を持ち続け、今もなお色あせない経営哲学
純粋な心を持ち続け、今もなお色あせない経営哲学
 技術者であり経営者である人物
技術者であり経営者である人物
 ホンダの生い立ちが分かる絶好の本
ホンダの生い立ちが分かる絶好の本
出版社名/日本経済新聞社 700円
良くも悪くも、奥田碩(ひろし)氏はその強烈な個性でトヨタを強大に発展させた名経営者です。
その奥田氏がトヨタの社長在任中に行った経営改革の軌跡をまとめたものが、この『奥田イズムがトヨタを変えた 』です。
この本の真骨頂は奥田氏に焦点を合わせるというよりは、どちらかと言うとトヨタグループの成長のメカニズムの解明といったところでしょうか。
世界に誇れる日本企業の代表格として、私達はトヨタの歴史と世界に果たすべき役割を知っておくことは無駄ではないと思います。
最後に奥田氏のプロフィールを以下に記します。
◆奥田碩
1932年12月29日 - )は、日本の実業家。勲等は旭日大綬章。社団法人日本経済団体連合会名誉会長。トヨタ自動車株式会社代表取締役社長(第8代)、同社代表取締役会長、社団法人日本経営者団体連盟会長(第9代)、社団法人日本経済団体連合会会長(初代)、内閣特別顧問などを歴任した。
◆社長就任まで
三重県津市出身。三重県立松阪北高等学校(現・三重県立松阪工業高等学校)を経て、1955年に一橋大学商学部を卒業しトヨタ自動車販売株式会社(現・トヨタ自動車株式会社)入社。大学時代は柔道部に所属し、六段の腕前を誇る。
トヨタ自販の経理部時代に上司とぶつかり、1972年秋、マニラに赴任する。ここで奥田は、フィリピンの政商で、現地でトヨタ車の組み立て・販売を独占するデルタ・モーターの社長・リカルド・C・シルベリオからトヨタへの延滞金を取り立てる任務に就く。肩書きは「経理アドバイザー」。これは困難な任務であり、事実上の左遷であったが、奥田は当時のマルコス大統領らとのコネクションを生かし、未納金の回収に成功した。
当時、マニラには豊田章一郎の娘婿・藤本進が大蔵省の駐在員として出向しており、奥田は章一郎が孫の顔を見に来るたびに同行し、このころから章一郎と奥田の関係が始まった。章一郎は奥田の才能を認め、「マニラでこんなやつがくすぶっているのか。本社の人事は何をしているんだ」とまで言ったという。
1979年に豪亜部長に昇格し帰国。1982年に取締役就任。85年にはアメリカ進出のための用地選定を任され、当時会長だった豊田英二から北米事業準備室副室長に指名される。全米からの応募の中から各知事との交渉に当たり、最終的にケンタッキー州工場の誘致に到る。1987年に常務取締役、1988年に専務取締役、1992年に取締役副社長となり、1995年に代表取締役社長に昇格した。
◆社長時代
社長時代にはそれまでどちらかといえば良い意味で保守的だったトヨタを改革したと言われている。
例えば、世界に先駆けてハイブリッド車「プリウス」を発売したことや、それまでトヨタが敬遠していたF1への参戦を表明したことなどである。奥田時代、当時国内販売で落ち込んでいたシェアを3年がかりで40%代まで回復させるなど、奥田の時代からトヨタは「攻め」の姿勢に転じて躍進を遂げ、現在の世界第1位の自動車メーカーの座を手にした。このことから、彼の経営手腕は一般的に高く評価されており、ハウツー本が出販されたり他のメーカーの中には彼の改革を手本にする企業まで出てきた。
奥田の諸改革には常に後ろ盾として豊田章一郎の姿があり、奥田も豊田本家の章一郎を求心力として旗印にし、常に豊田家を立てつつ改革を進めた。
その一方で、スポーツタイプの車種を全廃した戦略、モータースポーツを広告として捉えるやり方への批判、従業員に過度のサービス残業を強いて労働基準監督署の査察を度々受ける事態を招いたり、業績好調にもかかわらず外国人労働者や非正規雇用の確保で賃金の抑制を行うなど彼の経営姿勢を批判する声もきわめて多く、改革への評価と表裏一体である。
◆財界トップへ
1999年6月、次期社長に副社長だった張富士夫を指名して代表取締役会長就任。また同年社団法人日本経営者団体連盟会長就任。
その後2006年まで社団法人日本経済団体連合会会長を務め、7年にわたって財界トップの座にあったほか、歴代内閣で経済財政諮問会議や各種審議会、有識者会議の委員を数多く勤め、多数の企業の役員に名を連ねるなど政財界に大きな影響力を誇った。
他に、2001年株式会社東京証券取引所取締役就任、2002年株式会社UFJホールディングス取締役就任。株式会社楽天野球団経営諮問委員会委員、KDDI株式会社監査役・取締役、株式会社豊田自動織機監査役、東和不動産株式会社取締役、中京ゴルフ倶楽部株式会社理事、株式会社豊田中央研究所取締役(2006年まで)、株式会社デンソー取締役(2003年まで)、株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部理事等も務める。
◆発言など
『日経ビジネス』1995年7月17日号に「愛車のアクセル全開で憂さ晴らし」という記事が掲載された。その内容によると、アリストに乗る奥田が、先行車との「車間距離をぐっと詰め、パッシングの連続で押しのける」などの行為を常習的に行っていることが語られている。彼はテストコースで200キロ以上の速度を出す事もしばしばあり、当然右車線を走行していた事や高速道路で160キロ以上ものスピードで走っていた事も明かしており、「スピードは麻薬」「普段は黒塗りの役員車に乗っているが、トロトロ走る役員車に乗っているとイライラする」と迄発言しており、運転手に言い掛かりをつける事もしばしばある。彼にとってはこのアリストが、休日の脚だったそうだ。
『毎日新聞(2004年2月12日)』に『奥田経団連会長:牛丼フィーバーにチクリ 「単純な国民だ」』という記事が掲載された。その内容によると、BSE(牛海綿状脳症)の影響で、吉野家のほとんどの店で2月11日に牛丼販売が休止され、直前に客が「食べおさめ」の行列をつくったことについて、奥田は翌12日、東海地方経済懇談会後の記者会見で「テレビは一部の人の動きを面白おかしく報じていたようだが、(牛丼がなくても)死ぬわけでない。日本人は右から左へ早くふれやすい、単純な国民だと感じた」と発言。懇談会でも奥田は牛丼を教育上の問題点の例に挙げ、「日本人はどうしたのだろうか。やはり教育に力を入れなければならないと感じた」と語った。
皇室典範に関する有識者会議のメンバーを務める。(女性・女系天皇容認派)
ミサワホームの経営危機を巡る発言が結果的にミサワホームを産業再生機構入りに追い込んだとして、ミサワホーム創業者(元会長)三澤千代治側が竹中平蔵経済財政担当相(当時)、斎藤淳産業再生機構社長と共に公務員職権乱用罪で告発する事態が起こった。
ライブドアの日本経団連入会を認めた際に「企業倫理を学ぶのに役立ててほしい」と堀江貴文を評価していたが、1ヵ月後ライブドアに証券取引法違反が発覚すると「経団連として(ライブドア入会は)ミスだった」と釈明した。
2006年3月8日の記者会見では残虐なゲームソフトの影響で一部の若者が社会に適応できなくなりニートと化している可能性を指摘。経団連としてチェック体制を確立すべく検討を開始したと述べた。
拝金的な資本主義経済よりも、企業人は「武士道の精神」のような「心の規範」を持つべきと発言した[12]。
橋梁談合事件が起こった際には「談合は慣習、一気になくすのは難しい」「全国津々浦々に行きわたっている慣習のようなもので、地方では仕事を回し合っているワークシェアリング。本当にフェアな戦いをすれば、力の強いところが勝ち、弱いところは沈んでしまう」と発言[13]。
2006年11月19日の国際ロータリー第2760地区(愛知地区)大会の記念講演で「世界の現状と日本の針路」と題した部分の中で「均一性、画一性の社会は、規格品の大量生産には適していたが、今やそれは中国の強み」と指摘し、今後の日本は国民にも地方にも「多様性、独創性」(外国からの移民受け入れ)が必要だと訴えた。さらに、少子化について労働人口の急激な減少を懸念。女性や高齢者の雇用を掲げる厚生労働省の対策に「雇用のミスマッチが起きて対応できない」と批判して「外国人の力を借りるのは不可欠」との見方を示した。
2008年11月12日、「厚生労働行政の在り方に関する懇談会」の席上で、テレビなどの年金報道について「厚労省叩きは異常な話。正直言ってマスコミに報復してやろうかな。スポンサーを降りるとか」[14]「(マスコミの)編集権に経営者は介入できないといわれるが、本当はやり方がある」[15]などと発言した。
2009年3月10日政府の経済財政諮問会議にて中国人旅行者らへのビザの発給要件緩和を早急に実施するよう求めた。
(※ウィキペディアより抜粋)
奥田イズムがトヨタを変えた (日経ビジネス人文庫)
posted with amazlet at 09.09.15
日本経済新聞社 売り上げランキング: 287543
おすすめ度の平均: 

 奥田自身に関しての記述少なく、少し味気ない
奥田自身に関しての記述少なく、少し味気ない 最近のトヨタの戦略を知るにはよい
最近のトヨタの戦略を知るにはよい 多少持ち上げすぎかもしれませんが。。。
多少持ち上げすぎかもしれませんが。。。この商品を買った人は、こんな本も買っています☆
▼
本田宗一郎夢を力に―私の履歴書 (日経ビジネス人文庫)
posted with amazlet at 09.10.20
本田 宗一郎
日本経済新聞社
売り上げランキング: 1808
日本経済新聞社
売り上げランキング: 1808
おすすめ度の平均: 

 《エネルギー過剰》な自伝。
《エネルギー過剰》な自伝。 うちの社長に推薦してみよう・・・
うちの社長に推薦してみよう・・・ 純粋な心を持ち続け、今もなお色あせない経営哲学
純粋な心を持ち続け、今もなお色あせない経営哲学 技術者であり経営者である人物
技術者であり経営者である人物 ホンダの生い立ちが分かる絶好の本
ホンダの生い立ちが分かる絶好の本