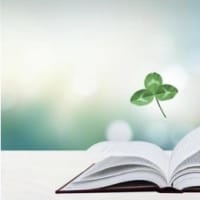私は頑固なので、誰が教えてくれても、偉いさんが書いてある本にあっても、自分が納得してみないとやりたがらない性分です。
そんな自分の意固地さがでてしまうのが、野菜づくりの場でも明らかになりました。今回は失敗談のお話です。
画像は2024年12月8日の種まき分の、25年2月20日時点。
第三弾のコマツナ、ダイコン、そしてシュンギク。はじめての品種に挑戦したのでウキウキしていました。当時は、まだ大豊作だった第一弾コマツナもまだ全収穫前。
最初は1週間前よりも、若葉がよく出ているな~とほくほく顔だったのですが…。よく考えたら、これ大丈夫なのか? と心配げに。
冬だから超鈍足で育つだろうけども、春を迎えるころにはスピードアップしてくれるだろう。
虫が湧かない季節だから食われることもないだろう。
例年暖かで、作業中はカイロもいらないぐらいだから、保温対策なんてしなくてもよいだろう。まあ、畝の脇に草マルチを敷いてみる程度で。
そんなハイパー手抜きではじめた第三弾の種まき。
発芽したのはほぼひと月ほど経ってから。しかし、ちょうど、すでに種まき分の収穫やら、間引きやら、植え替えから。さらには追加の畝づくりなどに勤しんでしまい、発芽が遅いのも助かる~(^^♪ なあんて思っていました。
ダイコン、コマツナ、そしてシュンギクの発芽がほのみえてから今日でほぼ二箇月近く。
シュンギクはまだだけども、ダイコンとコマツナには、あきらかに子葉というよりも、本葉みたいな形の葉が出てきているんですね。もともとの本葉をかなりミニチュアサイズにしたような。しかも色も濃くて、葉が固め。そう葉が固い! ふつう若葉ってもっと鮮やか爽やかなグリーンで葉は柔らかいはず…!
しかも、シュンギクに至っては。
ほんとにこの若葉がシュンギクのものかわかりかねます。何かの雑草の発芽じゃないのかと思ってしまったり。種袋にも教本にも発芽すぐの見本がないのでわかりづらい…。
実はこの現象、第二弾コマツナ群(11月10日種まき分)でも見られました。
畝3列目と4列目で発芽は比較的早かったのに、他の株に比べたら、明らかに小さすぎて、そこで生長がとまってしまったのが。葉も小さいのに、肉厚ぎみ。カルシウムを与えても大きくならない。なぜ…? もしや、もう、これが限界なのでは?
ダイコンはギザギザの輪郭があきらかになってきましたし、コマツナのほうは小さいのに葉が濃くて、葉脈もくっきりしています。
ちなみに、ダイコンはほんらいは春なら4月、夏秋ならば8~9月に種まきすべきものなんですね。おなじアブラナ科だけども、コマツナほど通年で栽培できるものではない。
もしやこれは、早く種まきしすぎたせいで、ここですでに生長しきった段階なのでは?
小さいので密集しがち。他の畝の世話にかまけて、まだ間引きはいいだろうと放置しているのですが…。これを間引きしても、今後、本当大きくなってくれるのだろうか?
実は第二弾コマツナ群でも、間引きが遅れてしまったたために、それ以上急激には育たなくなった株がありました。
やはり、冬まきはしっかり保温対策をして、標準の生育期間内に収穫できるようにしないと、株が小さいままで終わってしまうのかもしれません。
ほんらいは2箇月ぐらいで収穫できるはずのコマツナをすでに3箇月以上も地植えのままにして寒さにあてているのですから。
つまり、もうすでにお年寄り株になっているものに、せっせと肥料をやったり、水を与えても、無駄なのかも。
冬は畑を休ませた方がいいという古人の教えはやはり正しかったのでしょう。育てるのならば、温室なみの保温をしてあげないと、野菜だって、寒さで弱ってしまうのです。その結果、種の伸びしろを縮めてしまったのかも。
畝12~16列目のホウレンソウ群(1月2日種まき分)も、1月26日の春日和の日に発芽を確認したのですが。それから雪の日などを経験したせいか、伸びなくなってしまいました。
さらに畝1~2列目に1月9日種まきのシュンギクは、まったく発芽の兆しすらありません。シュンギクはもともと発芽が遅いというのを実感しましたが、ちょっと残念。あきらめて、春植えのジャガイモなどを植え付けるべきか考えあぐねています。
冬はあまり無理をして畑仕事をせずに、輪作の計画など練っていた方がよかったのかも。
このまま生育してくれないと、種を無駄にしてしまったことになります。あと、畝1~2列目はナス科と相性のいい混植としてネギの苗を植えてみたのですが、これも枯れてしまいがちなんですよね。ジャガイモの種イモ植え付け直前にやるんだった…。
種が運よく発芽してくれたからラッキーと甘く見ていましたが。
その後が順調に育つとは限らない。時間をかけていけば、いつかは実ると考えていたのは間違いでした。みかんの木みたいに放置していたら、いつのまにか実がなっていた、にはならないんですね。
やはり、自然は甘くないですし、植物には内蔵されたカレンダーがあるわけですね。生長の適温をしっかり守らないと、願ったような収穫が望めないと…。
ダイコンやコマツナが小さい株のままなのは、気温が上がらないせいのみならず。まだ若葉なのに、卵酢スプレーをしすぎたのもよくなかったのかも。ダイコンは葉だけが伸びて、根がしっかり育っていない恐れもあります。土も固いですしね、ここ。
まあ、これも痛い経験ですが、こうした失敗をくりかえして野菜づくりがうまくなればいいのですが…。
種もいろいろ蒔きたいけれど、土地に合うのかは実際にやってみないとわからないんですよね。ですから、ある程度、種や苗、肥料の投資は必要です。
ただこうしたシーズンオフの種まきなどは、全国農業新聞によれば、稲作などで時短作業として実験されて効果を発揮したケースもあるので。
慣例に囚われてではなく、たまにセオリー外しで冒険してみるのもいいかなと思ってみたりもします。
(2025.02.20撮影、同日記録)