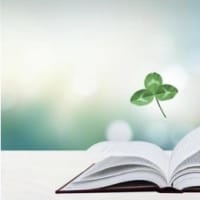【注】この記事は、大河ドラマ「光る君へ」が始まる前に、気分の赴くまま書いた雑記です。
2024年のNHK大河ドラマは紫式部が主人公。
日本最古の物語ともされる「源氏物語」の成立背景を、当時の平安王朝の政治を交えて描くもの。脚本家やディレクター含め女性スタッフ起用が多いのも話題なようですね。
関ケ原合戦の東軍西軍、あるいは幕末の幕府軍と尊王攘夷派など、日本では歴史上、国内を二分する戦乱がいくつかありました。鎌倉と室町とをつなぐ南北朝時代もそうですが、これも公家政権VS武家政権。その元をたどれば、平安末期の武家政権の萌芽がみられる源平の戦いに端を発します。
源氏なのか、平氏なのか。天皇家の親王が降下してきた末裔。
源氏にも清和だとか、多田だとか、甲斐とか、支流があって。日本各地に土着してその地方の地名を名乗って…嫡流が途絶えたり、幕末まで生き残ったりといろいろあるようです。好きな歴史漫画や小説があったりすると、ついつい史実のキャラをウェブ検索してしまう。そして、そのキャラの先祖あるいは末孫がどんな歴史をたどったのか調べるのが、楽しみになっていたりします。日本ほど血統が尊ばれて、家系図が残っている一族もあったりするお国柄も珍しいのかもしれませんね。移民があまりなくて、海外から侵略されずに済んだからかもしれませんが。
今野緒雪の百合ライトノベル「マリア様がみてる」の弟版というべき「お釈迦様もみてる」の舞台は男子校。
全校生徒が「源氏」=体育会系クラブ、「平家」=文化系クラブ のいずれかの所属し、しかも、烏帽子親と烏帽子子という上下関係をもつというシステムです。スピンオフ元のマリみて世界の姉妹(スール)制度をもじったのでしょうが、 先輩後輩の絆を任侠あるいは三国志ワールドのような義兄弟ではなく、日本の武家の、父子関係にしたのがなんとなくオトコ社会の厳しさであるように感じられますね。マリみて世界だと妹から姉にロザリオ突き返す下克上もあったりするけれど、シャカみてでは兄貴分は逆らえないような雰囲気があったような。
それはともかく、私が衝撃的だったのは。
この源氏=体育会系、平家=文化系という区分。とうしょ、むしろ、逆じゃないの?と思っていました。
といいますのも、「源氏物語」と「平家物語」の刷り込みがありましたから。
色男の光源氏が身分の上下なく多数の女性遍歴を重ねて栄華を極める「源氏物語」、数々の政治戦略や武力経済力を武器にして政権略奪をした平家一門と、鎌倉幕府を開きながら三代で絶えてしまった源氏の嫡流の盛衰を描いた「平家物語」。どうしても源氏が文化系、平家が武闘派系肉食の先入観があります。
しかし、史実上の源氏はたしかに源義家の代からして、一族内で争いごとばかり。
源頼朝も弟たちを滅ぼしていますし、頼家も実朝も、実母の介入があったにせよ、身内の揉め事で落命しています。平家筋の北条氏も同族内でイザコザはあったようですが、血筋を絶やすほどまでには至っていません。足利政権の、尊氏と直義兄弟の亀裂とか、応仁の乱のような血みどろの内乱までには発展していない。
「平家物語」に描かれた平氏一門は、武家なのに公家政権に飼いならされていて、身内びいきだった半面、お家騒動は生じにくかったのでしょう。文化の栄えた都に滞在していたので、東国や地方の事情は我関せずの、雅な貴族文化。たしかに平家は文化系。源平の合戦でも、木曽義仲や義経の野蛮児たちの奇襲にあらがえず壇ノ浦で滅びた件からしても。
日本の武家政権は源平が交代しているという説もあります。
室町幕府を終わらせた織田信長は平氏の流れを汲むが、徳川家康の生家の松平氏は源氏の末裔だったともいわれています。江戸時代は家計が困窮した武士が家系図を手放し、それを商人や成り上がりの豪農が入手して血統を偽った事もたびたびだったらしく、庶民レベルでの家系は信憑性が薄いともいわれています。お寺の過去帳などをたどれば何代か前までさかのぼることもできるでしょうが…。
源氏=血なまぐさい戦闘派、平家=平和を好む文化系という二分化。
鎌倉でも室町でも、さらには江戸幕府でもそうで。同じ氏族が世襲で政権を牛耳ると、武断派よりも文官タイプが幅を期すようになるというのは歴史の常道なのでしょう。現在の日本も、どちらかといいましたら平家化していますよね。ウクライナだとか、パレスチナの紛争が他人事のように思えるくらいには。
たしかに増税は厳しくて、少子高齢化もすすんで、会社の仕事はやりがいがなく、学校はきゅうくつで、家庭内でも不和はあるかもしれませんが。それでも、戦乱で家を焼かれたり、住む土地を奪われたり、家族にも裏切られて刃を向けられたり、主が代わって失職したり(これは現在でも倒産廃業や非正規切りであるけれども、多少の手当や給付金、税金の控除がある)、陰謀によって切腹せねばならないといった変化が日常に隣り合わせでもなくて、命の危険をすぐに感じてなくていいのはまだマシなのかもしれませんが。
歴史漫画や小説のような、時代の荒波に呑まれて飲まず食わずや生死の境をさまよって生存するキャラキャラクターたちを愛でたり、応援できているうちは、まだ日本は暮らしやすい国なのかもしれませんね。そう思わないと生き続けていられないと…。
(2023/12/12)
2024年のNHK大河ドラマは紫式部が主人公。
日本最古の物語ともされる「源氏物語」の成立背景を、当時の平安王朝の政治を交えて描くもの。脚本家やディレクター含め女性スタッフ起用が多いのも話題なようですね。
関ケ原合戦の東軍西軍、あるいは幕末の幕府軍と尊王攘夷派など、日本では歴史上、国内を二分する戦乱がいくつかありました。鎌倉と室町とをつなぐ南北朝時代もそうですが、これも公家政権VS武家政権。その元をたどれば、平安末期の武家政権の萌芽がみられる源平の戦いに端を発します。
源氏なのか、平氏なのか。天皇家の親王が降下してきた末裔。
源氏にも清和だとか、多田だとか、甲斐とか、支流があって。日本各地に土着してその地方の地名を名乗って…嫡流が途絶えたり、幕末まで生き残ったりといろいろあるようです。好きな歴史漫画や小説があったりすると、ついつい史実のキャラをウェブ検索してしまう。そして、そのキャラの先祖あるいは末孫がどんな歴史をたどったのか調べるのが、楽しみになっていたりします。日本ほど血統が尊ばれて、家系図が残っている一族もあったりするお国柄も珍しいのかもしれませんね。移民があまりなくて、海外から侵略されずに済んだからかもしれませんが。
今野緒雪の百合ライトノベル「マリア様がみてる」の弟版というべき「お釈迦様もみてる」の舞台は男子校。
全校生徒が「源氏」=体育会系クラブ、「平家」=文化系クラブ のいずれかの所属し、しかも、烏帽子親と烏帽子子という上下関係をもつというシステムです。スピンオフ元のマリみて世界の姉妹(スール)制度をもじったのでしょうが、 先輩後輩の絆を任侠あるいは三国志ワールドのような義兄弟ではなく、日本の武家の、父子関係にしたのがなんとなくオトコ社会の厳しさであるように感じられますね。マリみて世界だと妹から姉にロザリオ突き返す下克上もあったりするけれど、シャカみてでは兄貴分は逆らえないような雰囲気があったような。
それはともかく、私が衝撃的だったのは。
この源氏=体育会系、平家=文化系という区分。とうしょ、むしろ、逆じゃないの?と思っていました。
といいますのも、「源氏物語」と「平家物語」の刷り込みがありましたから。
色男の光源氏が身分の上下なく多数の女性遍歴を重ねて栄華を極める「源氏物語」、数々の政治戦略や武力経済力を武器にして政権略奪をした平家一門と、鎌倉幕府を開きながら三代で絶えてしまった源氏の嫡流の盛衰を描いた「平家物語」。どうしても源氏が文化系、平家が武闘派系肉食の先入観があります。
しかし、史実上の源氏はたしかに源義家の代からして、一族内で争いごとばかり。
源頼朝も弟たちを滅ぼしていますし、頼家も実朝も、実母の介入があったにせよ、身内の揉め事で落命しています。平家筋の北条氏も同族内でイザコザはあったようですが、血筋を絶やすほどまでには至っていません。足利政権の、尊氏と直義兄弟の亀裂とか、応仁の乱のような血みどろの内乱までには発展していない。
「平家物語」に描かれた平氏一門は、武家なのに公家政権に飼いならされていて、身内びいきだった半面、お家騒動は生じにくかったのでしょう。文化の栄えた都に滞在していたので、東国や地方の事情は我関せずの、雅な貴族文化。たしかに平家は文化系。源平の合戦でも、木曽義仲や義経の野蛮児たちの奇襲にあらがえず壇ノ浦で滅びた件からしても。
日本の武家政権は源平が交代しているという説もあります。
室町幕府を終わらせた織田信長は平氏の流れを汲むが、徳川家康の生家の松平氏は源氏の末裔だったともいわれています。江戸時代は家計が困窮した武士が家系図を手放し、それを商人や成り上がりの豪農が入手して血統を偽った事もたびたびだったらしく、庶民レベルでの家系は信憑性が薄いともいわれています。お寺の過去帳などをたどれば何代か前までさかのぼることもできるでしょうが…。
源氏=血なまぐさい戦闘派、平家=平和を好む文化系という二分化。
鎌倉でも室町でも、さらには江戸幕府でもそうで。同じ氏族が世襲で政権を牛耳ると、武断派よりも文官タイプが幅を期すようになるというのは歴史の常道なのでしょう。現在の日本も、どちらかといいましたら平家化していますよね。ウクライナだとか、パレスチナの紛争が他人事のように思えるくらいには。
たしかに増税は厳しくて、少子高齢化もすすんで、会社の仕事はやりがいがなく、学校はきゅうくつで、家庭内でも不和はあるかもしれませんが。それでも、戦乱で家を焼かれたり、住む土地を奪われたり、家族にも裏切られて刃を向けられたり、主が代わって失職したり(これは現在でも倒産廃業や非正規切りであるけれども、多少の手当や給付金、税金の控除がある)、陰謀によって切腹せねばならないといった変化が日常に隣り合わせでもなくて、命の危険をすぐに感じてなくていいのはまだマシなのかもしれませんが。
歴史漫画や小説のような、時代の荒波に呑まれて飲まず食わずや生死の境をさまよって生存するキャラキャラクターたちを愛でたり、応援できているうちは、まだ日本は暮らしやすい国なのかもしれませんね。そう思わないと生き続けていられないと…。
(2023/12/12)