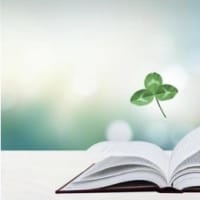世界で最古の二次創作は、中国の小説『金瓶梅』だとされています。
これは『水滸伝』に登場するある義侠の敵役となるはずの色欲な商人とその細君たちを描いた、なんとも酒池肉林なお話。さすが、西遊記やら、三国志演義やらを生み出した大国だけはあります。スケールが壮大過ぎて、眩暈がします。私はその内容を、さらに現代版アレンジされた漫画の電子版で一部だけ読んだことがありますが、まあ、レディコミのノリですね。…よい子のみんなは読まないで(笑)
さて二次創作それ自体が古い歴史をもつといえども、これが飛躍的に進歩したのは20世紀後半、もっと言えば今世紀に入ってからといえます。
私がブログ上で二次創作を手掛けた少し前のゼロ年代、すでに個人サイトは当然ながら、無料の掲示板などでファンノベルの投稿はよく見かけました。現在ではピクシブやツイッターなどの大手SNSが主流の場なのでしょうが、デジタル化によって、二次創作文化がより闊達になったのは誰もが認めるところでしょう。
紙で出版する同人誌とは違い、デジタル化の二次創作物の利点について、考えてみることにします。
・複数人に瞬時に公開でき、かつシェアできる
ネット上で掲載する利点はなんといいましても、その広報量でしょう。一点ものではありませんので、誰もが気軽に二十四時間アクセスできます。場所も選びませんし、検索でヒットすれば過去のものだって見られます。本人が削除しない限り、タリバンのアフガン遺跡爆破みたいに破壊されたりはしないでしょう。
・加筆修正がしやすくなった
水彩絵の具で滲みをつくるとき、境界がぼやけたり。網掛けで点描を散らすときに色移りしないようにマスキングしたり。鉛筆線の下書きを消すのが面倒だったり。そんな苦労はありません。私はお絵かきソフトで絵を描いたことはありませんが、フォトショやイラレみたく、レイヤーを複数段階にしておけば、複数の色分けバージョンを作成可能なのでは。文章でも原稿用紙のわくにとらわれないし、ワードでうるさい書式設定もいらないので執筆が楽ちんですね。
・保管保存がしやすくなった
デジタルの彩色はパソコンの画素によって色味が変わって見える可能性はありますが、色褪せしないし、拡大縮小もできるので管理がしやすくなりましたね。学生時代、美術部だった私は断捨離で油彩のキャンパスを破棄するのに難渋したので、デジタル絵の質量感のなさは素晴らしいと感じています。現在はデバイスを選ばずに作業を進めることもできますし、便利な時代ですよね。恥ずかしいスケッチブックを親御さんに見られた!なんて不幸な事故も少なくなったのかも(苦笑)
・多数での共同創作ができてしまう
今でもあるのかわかりませんが、リレー小説といいまして、複数人ですこしずつ書きつなげて一本の話にするというスタイルがありました。塗り絵にしてほしくて、単色の線画のみをアップしてしまう方もいます。Googleドライブ等のオンラインストレージを利用すれば、同時に編集できてしまうので、背景やロゴだけ別の人が入れるといった共同作業だってできるのでしょう。私はその昔、オタ友だちと二人で合作の二次絵ハガキを投書したことがありますが、顔の大きさを揃えるなどの配分に苦労したことがあります。オンラインならば、リアルタイムで台紙を共有でき、かつ、うっかり相手の描いた部分を侵食してしまうこともないですよね。すぐ消せますから。少年ジャンプ表紙のキャラクター集合絵みたいな、十数人以上の合作だってできちゃいそうです。
・競作がしやすくなった
ツイッターなどではお題を募って、参加者が二次イラストを持ち寄るという企画を見かけたことがありました。バレンタインなどの記念日やキャラのお誕生日祝いとして、個々のサイトで同時多発的に二次創作物が楽しめたりもしますよね。
・匿名での創作がしやすくなった
アニメ雑誌に投稿していたころ、もちろんペンネームなのですが、〇〇県△△市などと所在地が載ることがありましたよね。狭い地域だと身バレするおそれがあります。私は10代の頃、知り合いに会うのが嫌で、わざわざ隣の隣の自治体の本屋にアニメ雑誌を買いに行っていたことがあるくらいなので(爆)。ただし、うっかり創作サイトに個人情報を載せ過ぎないことが前提です。
・評価がすぐにわかる、応援メッセージが届く
同人誌を刊行するほどでもない二次創作者は、ネットがないときはアニメ雑誌への投稿が生き甲斐。出版社の編集部員が判断するので、選に洩れたら陽の目をみませんし、掲載されても一か月以上は先です。すでに終わっている展開の感想イラストだったりするとタイムラグがありますよね。ネット公開の鮮度や、人を選ばずに励ましの言葉があったりするのも、二次創作者には嬉しいものではないでしょうか。
・原作サイドの目に留まることもある
その昔、同人活動はあまり目立たしくしてはいけないという不文律があったようです。ただ現在は、著作権者さんによっては、積極的に個人サイトでの掲示板投稿やツイッターでのリツイートをされる方もいるようですね。ファンレターに二次絵を書いたり、自作の同人誌を送ったりするのが定番だった時代からすると驚きの現象です。原作者さんに発見されたくない場合は個人サイトに引きこもりすればよろしいので、選択肢があっていいですね。
・海外の二次創作まで探し出せる
ネット上で二次創作物を検索して驚いたのは、好きな作品のファンが世界中に遍在していること! 多言語でも現在はGoogleさんで翻訳もできちゃいますので、それとなく読めますよね。その国の文化圏のカラーというのもありまして、東南アジア圏のほうで仏画っぽい二次絵もあったり、興味深かったです。逆に日本人の書いた絵柄と遜色ない萌え絵もあったりして。身近にいなくても、全世界で二次創作者仲間を探すことだってできます。二次創作は万国共通なんですね。
・誰でも二次創作に参入できる
現在は小学生からタブレット学習していますから、作家さんデビューの低年齢化も進んでいますよね。素材はネット上でいくらでも学ぶことはできるので創作のネタはいくらもあります。似たり寄ったりになることもありますが、かつての同人誌発行と違い、お金も時間もかからないので、自宅で気軽に好きなだけ創作し、発表できます。
二次創作のデジタル化は作り手にとっても、受け手にとっても、メリットが多いものです。
一時期だけの刊行物である同人誌はイベントに行かねば、在庫が通販サイトにない限り、永遠に出会えないものになります。以前にも記事にしましたが、個人出版の本はあまりいい紙を使っていない可能性もあるので劣化がひどくなりがちです。もちろん紙の本ならではの良さもありますが、手の脂で汚れてしまったり、開き癖がついたりしてしまうものですよね。
私は同人誌は怖いので絶対に中古では買いません。どんな使い方をされているのかわかりませんので…。
もし著作権者さんが自作のスピンオフや番外編などで同人誌を出版される場合は、将来的に電子出版もできるように検討されればよいのではないでしょうか。2021年末に、ほんらいはコミケに行かないと買えない同某作品の同人誌がネット通販で買えて安堵した次第です。
この二次創作文化が今後どうなっていくのかは、今後、自分が創作をしなくなったとしても見届けたい思いはありますが。AIがかってに本人の脳内にアクセスしてつくってくれたり、SF映画みたくホログラムみたいに透明化して現実にイメージが浮くようになっていったり、つぶやいただけで勝手にアニメーション動画になってしまうとか、いろいろ凄いことが起きるのかもしれません。
コロナ禍やら、ロシア侵攻やら、地震やら、いろいろ世事万端心苦しいことはりますが、長生きはしたいものですね。
(2022/03/26)