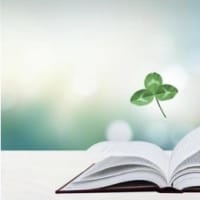インターネットの普及によって、二次創作の発表の敷居が格段に下がりました。
しかし、二次創作の歴史は、インターネットの登場よりもさらに古いはずです。大袈裟な言い方をすれば、和歌の本歌取りなどはパロディのはじまりですし、江戸時代には『偽紫田舎源氏』という、紫式部の『源氏物語』をおちょくったものが発禁処分に。『三国志演義』が、吉川英治などの名作になり、横山光輝の漫画になり、女体化されてアニメになったりもしますね。すぐれた原作は世代を超えて、さらに次なる物語を生む、このクリエイティヴィティ。おもしろいですね。
二次創作する人の憧れの場所というのがコミックマーケットですね。驚いたのですが、東京の幕張メッセで開催されたコミケの歴史は古く、もう半世紀近くは迎えているそうです。今のすでに大御所や中堅どころのアニメーターや漫画家でも知らない人はいないでしょう。音楽のコンサートもそうですが、あの手の人が過密集中する場所はテロにも狙われやすいので、私は出かけません。人ごみ大嫌いです。
現況のように、好き勝手に個人がネット上に自作をお披露目できる前。
おそらくファンたちは自分のないしょのスケッチブックに描き溜めたり、友だちとの交換日記や文通のレターに描いたり、アニメ雑誌などに投稿していたはずです。NHKアニメだと番組の最後にお便りコーナーがあって、イラストはがきが紹介されていました。
私の子どもの頃がそうですが、まあ、今でもこの習慣はあるでしょうね。
ちなみに私は子供の頃、絵友だちというのがいまして、合作でイラストを描いて投稿したこともありました。
いつか、いっしょに同人誌出そうとか語っていたりして。私のきょうだいも漫画みたいなの、描いていたような。地方圏だったので地場産業会館みたいな公的施設で行われたコミケ(地方即売会というらしい。今もあるのだろうか)があって、お隣県からきた女子大生のコピー本(コピー機で制作した簡単な同人誌。面つけしていなくて、束ねてホチキス止めしたままの、ガムテープ貼った背表紙だったので、かなり安価)に、お便りを書いたこともあります。お返事もちゃんと頂きました。二次創作者さんと交流した、はじめての想い出です。
しかし、ついに同人誌を刊行はしませんでした。
ちなみに子供の頃、絵は描いていましたが、二次創作どころか、ふつうの小説すら書いたことは全くありません。
家庭の事情とか進路とかいろいろあるのですが、強いていえば、絵を描くことに興味を失ったのでしょう。私よりもデッサンの上手い子が大学の親友だったのですが、コンクールで絵が入賞したのに、けっきょく普通の会社員になったり。美術館などを巡って名画に圧倒されたり。それに加えて、絵友だちの次にハマった作品に、私はハマれなかったり。
同人誌を発行するというのは、ちょっとした作家気分を体験できる作業ですね。
うるさい編集さんはいないけど、締切が! ネームが! 進行が! と生みの苦しみを味わうのも醍醐味。同人誌でなくとも、ブログ自体を本として出版できるサービスもあります。gooブログでも、有料サービスに申し込めばできるようですね。
しかし、私、学生時代に論文を研究誌に載せるときに編集主幹の教官と揉めたりしたことありますし、校正を重ねるのでうんざりしたこともあります。印刷物の企画編集の仕事をしたときに、休日もなく残業労働だったのでからだを壊してしまいましたので、二度と、出版物に関わるようなことはしたくない、自分は受容者でたくさんという思いがあります。ウェブで好き勝手にやってれば、締切もないし、頁数の制限もないですしね。
同人誌を発行されている方については行動力もあるし、あの人いきれの熱気のなかにとどまっていられる気力体力は感心します。同好の士との交流という面もあります。なにより、中小の印刷業者さんにとってはとてもいい商売相手なので、無下に批判すべき文化でもない。ただ、ご自身のキャリア形成については、きちんと考えていただきたいですね。30歳過ぎて、同人誌を出しているのは、それを副業にしているプロフェッショナルだけではないですか。素人が同人誌を発行しても、仲間内には渡せるかもしれませんが、それで食べていけませんよね。なんで、仕事の合間に地味にオフライン活動している人より、同人誌発行している学生さんかフリーターさんのほうが偉そぶってるのか、ものすごく疑問です。税金をきちんと払えず万年赤字の趣味を、仕事のように言い張る方には疑問を持ちます、私は。
ちなみに、最近の描き手といえば、あたりまえのようにパソコン使って描いていると思われがちなのですが、意外にもスマホの普及でPC慣れしていなくて、アナログで描いている人もいるらしい。CGの彩色は個性がなくなるので、私は昔ながらの水彩で描いた色味のほうが好きなのですが、ネットに載せた時に色味が映えないのかもしれませんね。
(2018/05/27)