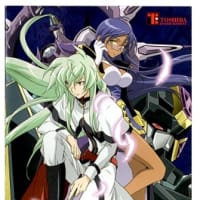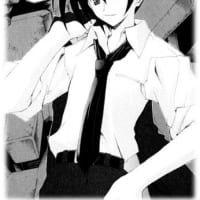先日、こんなニュースが目についた。
アニメバブル崩壊 DVD不振、新番組も減(〇九年五月四日 アサヒ・コム)
日本の輸出文化産業として厚い期待のかかるアニメ業界だが、〇六年をピークとして年間作品数もソフトの売上高も減少傾向にあるという。
アニメはTV放映を三〇分のCMと位置づけ、ビデオ、DVDそしてBDでの販売額が収入源となってきただけに、売上げの落ち込みは業界に深刻な打撃あたえ、リストラが懸念される。
記事はその原因を以下のように探る。
・製作本数は増えたが、どれも美少女、メカといった売れそうな要素を並べただけで似たり寄ったり
・ハイビジョン録画機の普及
・少子化のうえに、不況で若者の可処分所得が減ったため
・海外市場の伸び悩み
・ネットでの違法配信
制作者側からすれば、ネットの違法配信を糾弾したくもなろうが、これはあながち否定もできない。というのも、ファンがつくった動画のおかげで興味をもち、DVD購入に至るケースもありうるからだ。しかし、やはりネットでアニメは無料で観られるもの、情報はただで入手できるもの、という感覚で育った世代が多くなると、今後アニメ業界の行く末は厳しくなるだろう。
いちばんの原因は、なんといっても質の低下にある。
といっても、表現の技術などは三〇年まえよりは格段に進歩しているはずなのだが、それでも現在のアニメのほうがつまらなく感じてしまうのは、不幸なことに、そうした一定レベル以上の作品が大量に横並びしてしまったためだ。「宇宙戦艦ヤマト」や「機動戦士ガンダム」の時代は、ほかにおなじようなアニメが、二つも三つもなかったために代表作と称えられることができた。
だから、視聴者にしても、どれを選択してよいやらわからない。結果として、大手の出版社やゲーム・音楽会社と組んでタイアップを図っている作品がやはり生き残りやすくなるのだろう。
記事は打開策として日本動画協会専務理事の言葉を引用している。
「これからは量より質を重視し、国公立大学でアニメをじっくり教えるなど、官民が力を合わせて質の高い人材を育て、それを日本の強みとする道を考えるべきです」
私はこの発想に思わず吹き出してしまった。
国公立大学でアニメを教えるだって?そりゃ、不振の文化人を救うための就職先にはなるだろうし、少子化で倒産の恐れのある大学に入学者の呼び込みになるだろうが、けっしてそれがアニメ界の復興になるとは限らない。なぜならば、偏差値の高い大学を出たプライドのかたまり人間が、過酷な労働条件のアニメ業界でやっていけるわけないだろうからである。せいぜい趣味でソフトをつかって自己満足なアニメーションをつくり、ネットで発表して楽しむ人ばかりが増えてしまうのが関の山だ。今でもそうであるように。
どうせ教育支援するなら、人手不足が懸念される原画や動画をえがくアニメーターの育成だろう。絵がうまいのに学歴など関係ない。現在は韓国や中国など人件費の安い国に下請けさせているが、こうした後進国はすでにかなりの技術力をつけていて、いずれ主客が逆転してしまうだろう。そうなれば、自国で技術力のあるアニメーターを育てられなかった日本のアニメは終わりだ。この構造は、アニメだけでなく製造業全般について述べられる現象だ。
そもそも、もはや売れない産業ならば、保護する必要などはない。
農林水産業などと違って生活に絶対必要なものを提供しているわけではないのだから、質の低い作品をつくりつづけても生き残れるほうがおかしい。一部の良心的で好感度の高い作品以外は自然淘汰されてもしかるべきではないのか。
そしてまた、アニメはえてして能や歌舞伎のように、日本のお家芸というわけでもない。どちらかというと、フィギュアなど副次産業こそが日本独自の売りになっている。すばらしい作品だったら、海外から輸入したっていいと思う。日本の声優の吹き替え能力はかなり優れているのだから。
ちなみに、売れない最大の原因は、思うに視聴者の好みがランクアップしたこと。
ブログの普及で、つまらない作品の評判はすぐに伝わるようになった。
アニメだけでなく映画にもいえるが、すぐれた作品を生み出したスタッフがかならずしも次の作でも成功するとは限らない。今後、過剰な期待をいだくのは、もう虚しいのでやめにしよう。