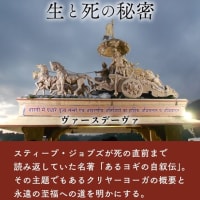愈々ヨーガ・スートラ(以下、本書)を主題とした第17章に入るが、本章を書き始めるに当り、先ずは参考とする書籍3冊を紹介しておく。
(イ) インテグラル・ヨーガ スワミ・サッチダーナンダ著
(ロ) 解説 ヨーガ・スートラ 佐保田鶴治著
(ハ) Kriya Yoga Sutra of Patanjali and the Siddhas M.ゴヴィンダン著
これらの中で、筆者がアマゾンを検索して最初に読もうと思った本は(イ)である。これは元々著者がアメリカでヨーガ教室を開催しながら、そこで解説した内容を本に纏めたものなので、当然ながら英語で書かれた原書を日本語に翻訳したものである。この中にはインドの昔話などが適切に引用されていると共に、話の内容もアメリカ人受けを狙ったユーモアに富んだものなので大変興味深いのであるが、正直なところ、最も肝心なサマーディに関する解説に就いて筆者は全くと言って良いほど理解できず、本ブログでも一度そのことに触れたことがある(第14章⑭ )。
次に筆者が挑戦した本は(ロ)である。これは、京都大学の哲学科を卒業して大阪大学の教授などを歴任された佐保田鶴治先生が著したもので、禅や哲学的な観点からの解説が多く、非常に論理的に書かれているので、筆者にとっては比較的判り易く理論面での理解が深まったように感じた。
因みに、(ハ)に就いては、毎月小金井市で開催されているクリヤー・クンダリニ・ヨーガのサットサンガにおいて、教科書として使われているが、これはこれで(イ)や(ロ)とは多少異なる見解を示してくれるので(現時点で読了してないが)大変興味深い。但し英文なので、ここで全てを翻訳しながら紹介するには手間が掛かりすぎる。 因って理論が整理できない時の参考程度に使うことにしたい。
結論としてどの本を中心に話を進めるのかに就いては、当初は理論的に書かれている(ロ)からの引用を中心に本章の解説を進めようと思っていたのであるが、多少仏教や禅宗に傾いているきらいがある。そこで改めて(イ)を読み返してみたところ、さすがに経文の訳は(イ)の方が判り易いことに気付いた。そこで経文の訳やその解釈は主として(イ)を中心に引用して行くが、適宜(ロ)からの理論面での解説や、必要に応じて(ハ)の見解も引用しながら重要なポイントを纏めて行きたい。尚、全ての経文に対する解説を行うことは出来ないし、そもそも本ブログは筆者の考えを整理する為のものであり、それを多少なりとも読者諸賢に参考にして頂く為のものなので、サマーディの境地を目指すヨギにはその好みに応じて少なくも(イ)か (ロ)のどちらか、或いは両者を購入し、座右の書として精読することを奨めたい。
① ヨーガとその歴史
ここでは先ず佐保田鶴治先生(以下、著者)の『解説ヨーガ・スートラ』(以下、同書)から、ヨーガという名前の由来や歴史などを概観しておきたい。以下引用であるが、必ずしも重要と思われない部分はこれまで通り、適宜・・・などで省略して掲載する。
ヨーガというインドの言葉は、「つなぐ」という意味の言葉から生まれた名詞で、その根本的な意味は「結合」ということである。ヨーガという言葉の派生的な意味としては「合一」「接触」「適用」・・・その他いろいろな意味がある。その他に「軛(くびき)」という意味もある。・・・西欧社会にヨーガ思想を宣布した偉大な指導者ヴィヴェーカナンダ師(筆者註:第13章⑨参照)はヨーガを「心理的統制によって、低い自我と高い自我とを結合すること」と定義した上で、「我々を神へ導く何らかの仕方の修養(カルチュアー)」という非常に広い意味規定を付けている。・・・その他にもヨーガを「神的存在との合一」という意味から定義しようとする人は多い。
その後著者は、「しかし、ヨーガという言葉の意味から、ヨーガという名称の内容を理解するのは、結局徒労に終わるであろう」として、数十に及ぶヨーガの流派から次の7つの流派をその特色と共に挙げた上で、
(1) ラージャ・ヨーガ 心理的
(2) ハタ・ヨーガ 生理的
(3) カルマ・ヨーガ 倫理的
(4) バクティ・ヨーガ 宗教的
(5) ラヤ・ヨーガ 心霊的
(6) ジュニャーナ・ヨーガ 哲学的
(7) マントラ・ヨーガ 呪法的
更に「この他に特色のあるものとしては、体育を主とするヴィアーヤーマ・ヨーガという一派もある。超心理学的な現象を特色とするクンダリニ・ヨーガも広く世界の注目を浴びている」ということで辛うじて最後にクンダリニ・ヨーガにも言及している。
次に、ヨーガの起源と歴史に関する部分の引用である。
「ヨーガの起源について語ることも存外むずかしい。ある人は、ヨーガの起源を、遠くインド・ヨーロッパ時代のアーリア人の社会に求めようとする。このようにヨーガの起源をインド国外に求めることには同意しないとしても、ヨーガ行法に似たものが少なくとも西暦紀元前2500年頃にインドに行われていたことを推測させる考古学的資料を無視することはできない。それは、下のインダス河畔のモヘンジョ・ダロの遺跡から発掘された多くの印章または護符の中に、後世のシヴァ神像に似た姿を刻りあらわしたものが五つ発見されたということである。・・・シヴァ神は後世ヨーガと深い関係におかれるが、もともと呪法の神であったように、かのインダス河畔に見出された神像も呪法と苦行の修行者の姿ではないかと思われる。所謂法力を修得するための或る種の行法のシステムが当時発達していて、それが後にヨーガと呼ばれる行法に発達したのだ、と考えることは出来ないことではない。」
としながらも、「しかし、このような古い時代にヨーガの起源を求めることはやはり行き過ぎのそしりを免れることが出来ないであろう」と結論付けている。
その後、ヴェーダ或いはバラモンの宗教との関連において、「われわれはヨーガの起源をバラモン伝統のうちに求めない訳にはゆかないのである。というわけは、ヨーガという名称そのものが、バラモンの血統を物語っているからである。」と言って、カタ・ウパニシャッドの記録を引用する(但し、以下は同書P184)。
「五つの知覚器官が意(思考器官)と共にその働きを静止し、覚(判断意識)も動かなくなったとき、人びとはこれを至上の境地という。かように、諸器官を固く抑制することをば、人びとはヨーガと見なしている。」 (カタ・ウパニシャッドⅢ.9-10)
「アートマン(真我、霊魂)を車主(乗りて)と知れ。肉体は車体、覚は御者、意は手綱なりと心得よ。賢者たちは、もろもろの知覚器官を馬とよび、諸知覚器官に対する諸対象を道路と呼んでいる。」 (カタ・ウパニシャッドⅢ.3-4)
然し著者は、「だからといって、ヨーガがバラモン体系だけを母胎として生まれたということは出来ない。」としてその理由を次のように述べる。
ヨーガとバラモンの伝統とは根本的な点で違っているからである。第一に、バラモン正統派は祭儀を中心としているが、ヨーガは祭儀には関係ない。この点でヨーガはむしろ仏教やジャイナ教の側に属する。第二に、バラモン正統派の中にも瞑想を中心とする一派はあるが、その哲学思想であるヴェーダーンタはヨーガの正統派ともいうべきサーンキャ・ヨーガの哲学とは種々の点でちがっている。・・・ヨーガがその根本的傾向において、むしろ仏教やジャイナ教に近いということは誰しも気のつくことである。ヨーガは祭儀のような社会的行動には無関係である。ヨーガは苦行や瞑想に従事する個人の道である。それは修道士の宗教だと言ってもよい。その究極目的は個人の解脱(絶対的自由の獲得)にある。これらの点は原始仏教やジャイナ教の教団と全く同じである。それでは、ヨーガと仏教、ジャイナ教との間にはどんな歴史的関係があるのだろうか?・・・仏教の伝説によれば、ブッダは悟りを開く前に、マガタ地方の有名な道士たちから教えを受けたと云うことであるが、それらの道士たちの行法や思想はヨーガのそれと一致する。しかし、これは伝説であるし、そこに見られるテクニックなども、ヨーガのそれに似てはいるが同じではない。・・・だから、これらの伝説及びヨーガと仏教の類似ということなどから結論できることは、ヨーガと仏教とが同じような思想運動の流れに属していた、ということだけである。
そして、著者は次のように結論付けている。
要するにヨーガは、仏教やジャイナ教の興起と前後して、バラモン社会の一部の人達によって作り上げられたのであろう。この人たちは、バラモン社会の中のいわば前衛部隊であった。彼らは、仏教やジャイナ教の母胎となった、かの東インド地帯の非バラモン的思想をようしゃなく取り入れ、異端すれすれの線まで自分を変容したのである。こうして、一旦ヨーガという名称の行法がバラモン社会に成立すると、この行法はたちまちのうちにバラモン社会の寵児となり、ヨーガはバラモン思想圏の公認の行法になる。それと同時に、最初のヨーガ思想とは似ても似つかない思想までがヨーガという名称と結び付くようになる。種々雑多なヨーガ派はこうしてうまれたのである。そればかりか、ヨーガという名称は仏教徒やジャイナ教徒にまで愛用されるようになる。
著者の主張するところは、大体以上である。
尚、ババジのクリヤー・ヨーガに就いては、無論ヨーガの行法として上記の流れを汲んでいることは間違いないが、これにタントラの行法が加わり、且つ南インド(タミルナードゥ)のシッダたちの影響を多分に受け継いでいるので、興味のある方は、別途『ババジと18人のシッダ』を参考にされたい。
このブログは書き込みが出来ないよう設定してあります。若し質問などがあれば、wyatt999@nifty.comに直接メールしてください。
(イ) インテグラル・ヨーガ スワミ・サッチダーナンダ著
(ロ) 解説 ヨーガ・スートラ 佐保田鶴治著
(ハ) Kriya Yoga Sutra of Patanjali and the Siddhas M.ゴヴィンダン著
これらの中で、筆者がアマゾンを検索して最初に読もうと思った本は(イ)である。これは元々著者がアメリカでヨーガ教室を開催しながら、そこで解説した内容を本に纏めたものなので、当然ながら英語で書かれた原書を日本語に翻訳したものである。この中にはインドの昔話などが適切に引用されていると共に、話の内容もアメリカ人受けを狙ったユーモアに富んだものなので大変興味深いのであるが、正直なところ、最も肝心なサマーディに関する解説に就いて筆者は全くと言って良いほど理解できず、本ブログでも一度そのことに触れたことがある(第14章⑭ )。
次に筆者が挑戦した本は(ロ)である。これは、京都大学の哲学科を卒業して大阪大学の教授などを歴任された佐保田鶴治先生が著したもので、禅や哲学的な観点からの解説が多く、非常に論理的に書かれているので、筆者にとっては比較的判り易く理論面での理解が深まったように感じた。
因みに、(ハ)に就いては、毎月小金井市で開催されているクリヤー・クンダリニ・ヨーガのサットサンガにおいて、教科書として使われているが、これはこれで(イ)や(ロ)とは多少異なる見解を示してくれるので(現時点で読了してないが)大変興味深い。但し英文なので、ここで全てを翻訳しながら紹介するには手間が掛かりすぎる。 因って理論が整理できない時の参考程度に使うことにしたい。
結論としてどの本を中心に話を進めるのかに就いては、当初は理論的に書かれている(ロ)からの引用を中心に本章の解説を進めようと思っていたのであるが、多少仏教や禅宗に傾いているきらいがある。そこで改めて(イ)を読み返してみたところ、さすがに経文の訳は(イ)の方が判り易いことに気付いた。そこで経文の訳やその解釈は主として(イ)を中心に引用して行くが、適宜(ロ)からの理論面での解説や、必要に応じて(ハ)の見解も引用しながら重要なポイントを纏めて行きたい。尚、全ての経文に対する解説を行うことは出来ないし、そもそも本ブログは筆者の考えを整理する為のものであり、それを多少なりとも読者諸賢に参考にして頂く為のものなので、サマーディの境地を目指すヨギにはその好みに応じて少なくも(イ)か (ロ)のどちらか、或いは両者を購入し、座右の書として精読することを奨めたい。
① ヨーガとその歴史
ここでは先ず佐保田鶴治先生(以下、著者)の『解説ヨーガ・スートラ』(以下、同書)から、ヨーガという名前の由来や歴史などを概観しておきたい。以下引用であるが、必ずしも重要と思われない部分はこれまで通り、適宜・・・などで省略して掲載する。
ヨーガというインドの言葉は、「つなぐ」という意味の言葉から生まれた名詞で、その根本的な意味は「結合」ということである。ヨーガという言葉の派生的な意味としては「合一」「接触」「適用」・・・その他いろいろな意味がある。その他に「軛(くびき)」という意味もある。・・・西欧社会にヨーガ思想を宣布した偉大な指導者ヴィヴェーカナンダ師(筆者註:第13章⑨参照)はヨーガを「心理的統制によって、低い自我と高い自我とを結合すること」と定義した上で、「我々を神へ導く何らかの仕方の修養(カルチュアー)」という非常に広い意味規定を付けている。・・・その他にもヨーガを「神的存在との合一」という意味から定義しようとする人は多い。
その後著者は、「しかし、ヨーガという言葉の意味から、ヨーガという名称の内容を理解するのは、結局徒労に終わるであろう」として、数十に及ぶヨーガの流派から次の7つの流派をその特色と共に挙げた上で、
(1) ラージャ・ヨーガ 心理的
(2) ハタ・ヨーガ 生理的
(3) カルマ・ヨーガ 倫理的
(4) バクティ・ヨーガ 宗教的
(5) ラヤ・ヨーガ 心霊的
(6) ジュニャーナ・ヨーガ 哲学的
(7) マントラ・ヨーガ 呪法的
更に「この他に特色のあるものとしては、体育を主とするヴィアーヤーマ・ヨーガという一派もある。超心理学的な現象を特色とするクンダリニ・ヨーガも広く世界の注目を浴びている」ということで辛うじて最後にクンダリニ・ヨーガにも言及している。
次に、ヨーガの起源と歴史に関する部分の引用である。
「ヨーガの起源について語ることも存外むずかしい。ある人は、ヨーガの起源を、遠くインド・ヨーロッパ時代のアーリア人の社会に求めようとする。このようにヨーガの起源をインド国外に求めることには同意しないとしても、ヨーガ行法に似たものが少なくとも西暦紀元前2500年頃にインドに行われていたことを推測させる考古学的資料を無視することはできない。それは、下のインダス河畔のモヘンジョ・ダロの遺跡から発掘された多くの印章または護符の中に、後世のシヴァ神像に似た姿を刻りあらわしたものが五つ発見されたということである。・・・シヴァ神は後世ヨーガと深い関係におかれるが、もともと呪法の神であったように、かのインダス河畔に見出された神像も呪法と苦行の修行者の姿ではないかと思われる。所謂法力を修得するための或る種の行法のシステムが当時発達していて、それが後にヨーガと呼ばれる行法に発達したのだ、と考えることは出来ないことではない。」
としながらも、「しかし、このような古い時代にヨーガの起源を求めることはやはり行き過ぎのそしりを免れることが出来ないであろう」と結論付けている。
その後、ヴェーダ或いはバラモンの宗教との関連において、「われわれはヨーガの起源をバラモン伝統のうちに求めない訳にはゆかないのである。というわけは、ヨーガという名称そのものが、バラモンの血統を物語っているからである。」と言って、カタ・ウパニシャッドの記録を引用する(但し、以下は同書P184)。
「五つの知覚器官が意(思考器官)と共にその働きを静止し、覚(判断意識)も動かなくなったとき、人びとはこれを至上の境地という。かように、諸器官を固く抑制することをば、人びとはヨーガと見なしている。」 (カタ・ウパニシャッドⅢ.9-10)
「アートマン(真我、霊魂)を車主(乗りて)と知れ。肉体は車体、覚は御者、意は手綱なりと心得よ。賢者たちは、もろもろの知覚器官を馬とよび、諸知覚器官に対する諸対象を道路と呼んでいる。」 (カタ・ウパニシャッドⅢ.3-4)
然し著者は、「だからといって、ヨーガがバラモン体系だけを母胎として生まれたということは出来ない。」としてその理由を次のように述べる。
ヨーガとバラモンの伝統とは根本的な点で違っているからである。第一に、バラモン正統派は祭儀を中心としているが、ヨーガは祭儀には関係ない。この点でヨーガはむしろ仏教やジャイナ教の側に属する。第二に、バラモン正統派の中にも瞑想を中心とする一派はあるが、その哲学思想であるヴェーダーンタはヨーガの正統派ともいうべきサーンキャ・ヨーガの哲学とは種々の点でちがっている。・・・ヨーガがその根本的傾向において、むしろ仏教やジャイナ教に近いということは誰しも気のつくことである。ヨーガは祭儀のような社会的行動には無関係である。ヨーガは苦行や瞑想に従事する個人の道である。それは修道士の宗教だと言ってもよい。その究極目的は個人の解脱(絶対的自由の獲得)にある。これらの点は原始仏教やジャイナ教の教団と全く同じである。それでは、ヨーガと仏教、ジャイナ教との間にはどんな歴史的関係があるのだろうか?・・・仏教の伝説によれば、ブッダは悟りを開く前に、マガタ地方の有名な道士たちから教えを受けたと云うことであるが、それらの道士たちの行法や思想はヨーガのそれと一致する。しかし、これは伝説であるし、そこに見られるテクニックなども、ヨーガのそれに似てはいるが同じではない。・・・だから、これらの伝説及びヨーガと仏教の類似ということなどから結論できることは、ヨーガと仏教とが同じような思想運動の流れに属していた、ということだけである。
そして、著者は次のように結論付けている。
要するにヨーガは、仏教やジャイナ教の興起と前後して、バラモン社会の一部の人達によって作り上げられたのであろう。この人たちは、バラモン社会の中のいわば前衛部隊であった。彼らは、仏教やジャイナ教の母胎となった、かの東インド地帯の非バラモン的思想をようしゃなく取り入れ、異端すれすれの線まで自分を変容したのである。こうして、一旦ヨーガという名称の行法がバラモン社会に成立すると、この行法はたちまちのうちにバラモン社会の寵児となり、ヨーガはバラモン思想圏の公認の行法になる。それと同時に、最初のヨーガ思想とは似ても似つかない思想までがヨーガという名称と結び付くようになる。種々雑多なヨーガ派はこうしてうまれたのである。そればかりか、ヨーガという名称は仏教徒やジャイナ教徒にまで愛用されるようになる。
著者の主張するところは、大体以上である。
尚、ババジのクリヤー・ヨーガに就いては、無論ヨーガの行法として上記の流れを汲んでいることは間違いないが、これにタントラの行法が加わり、且つ南インド(タミルナードゥ)のシッダたちの影響を多分に受け継いでいるので、興味のある方は、別途『ババジと18人のシッダ』を参考にされたい。
このブログは書き込みが出来ないよう設定してあります。若し質問などがあれば、wyatt999@nifty.comに直接メールしてください。