年末に「ブログはまめに更新することが大事ですよ」と言われた。数ヶ月はほったらかしにして、急に思いついて長いものを書き、またしばらく放置という現状は、告知やライターとして営業中である周知のためのブログとしては、いちばんダメなパターンらしい。
自分はやってないくせに何言ってんのさ……となったが、言われるとやはりシャクなもので、2020年はガラッと今までの考え方を変えて〈文章量より更新頻度〉を目標にしてみる。単純に、SNSでは長くなりそうなものは、ブログに回すということで。
年越しに数本の映画をまとめ見した。
その中の2本がとてもピタッときたという話を。
『砂漠の鬼将軍』
1951年-1952年日本公開
監督 ヘンリー・ハサウェイ
製作・脚本 ナナリー・ジョンソン
主演 ジェームズ・メイソン セドリック・ハードウィック ジェシカ・タンディ
『砂漠の鼠』
1953年
監督 ロバート・ワイズ
脚本 リチャード・マーフィ
主演 リチャード・バートン ジェームズ・メイソン ロバート・ニュートン
どちらも20世紀フォックスの戦争映画で、第二次世界大戦中の北アフリカ戦線が舞台。
北アフリカ戦線は、イタリア軍が植民地の拡大とスエズ運河の制圧を目的にエジプトに侵攻したのが始まりで、イギリス軍などの攻勢にあったところで、イタリアと枢軸国仲間のドイツが、エルヴィン・ロンメル大将の装甲師団を援軍に送り出した。このロンメルという人が「ナポレオン以来」と呼ばれる戦術のプロで、劣勢でも連合国軍側と互角以上に闘い、「砂漠の狐」の異名を轟かせた。
しかし最年少で元帥に昇進し、国民的英雄となったあとに運命は暗転。未遂に終わったヒトラー総統暗殺計画に関係していたことを疑われ、服毒自殺に追い込まれた。
この悲劇性もあいまって、敵ながらあっぱれだった男としてロンメルの人気は連合国側でも高くなり、こうしてハリウッドで『砂漠の鬼将軍』という、ロンメルが主役の映画が作られた。一貫して立派な男として描かれている。
2年後の『砂漠の鼠』はいってみれば姉妹編で、続けてジェームズ・メイソンがロンメルを演じつつ、彼が率いる戦車部隊に苦戦しつつ、援軍が来るまで砂漠でふんばる英・豪混成部隊が主役。
この時期の戦争映画は、今は名画座でもそうたくさん上映されるわけではなく、CS放送や配信でも品ぞろえがかなり手薄だ。僕自身、かなり久しぶりにこのジャンルを見た。DVDで持っていてよかった(パッケージで持っているけれど見ていない映画が、部屋にあと150本以上ある)。
どっちも戦時中の実戦を撮影したフィルムがふんだんに使われているし、美術プロダクションから傍役の隅々まで、数年前までの戦争を肌で知っている厚みが伝わる。ヘンリー・ハサウェイとロバート・ワイズ。どちらも(映画好きには)もちろんの一流どころだが、どちらも久々に監督作を見て、つくづく、うまい。
特にヘンリー・ハサウェイ。『アラスカ魂』(60)や『西部開拓史』(62)など、割ともっさりした大柄な西部劇のほうで僕はおなじみだったので、こんなにキビキビした戦争アクションをこさえられる監督だったのか、とびっくり。
例えば、真夜中の奇襲作戦の描写。見張りのドイツ兵に黒いマスクを被った歩兵が闇に乗じてだんだん近づき、ナイフを持ってとびかかるまでの一連を縦の構図でカメラが引いたままのワンカットでじっと捉え(つまり、決定的瞬間ほど画面の奥になる)、銃撃戦が始まったら途端にカットを畳みかけていくメリハリのキレ。
フォード、ホークス、ウォルシュ、マン(&のちのペキンパー)に比べたら格が一段劣る存在、ではないのかもしれないぞ、どうも。
などなどとこの2本を楽しみつつ、ああ、こういう場面があるならこの映画好き、となったのは、どちらにも〈男と男のディスカッション〉があることだった。
僕はどうにもこの、〈男と男のディスカッション〉が好きだ。
中学二年の時、『十二人の怒れる男』(57)をテレビ放送で初めて見て、生まれて初めて、アタマから見終わるまでの間、完全に釘付け状態を味わった。
それから何回見ているか数えていないが、一番好きなのは、陪審員8番(ヘンリー・フォンダ)の無罪の意見に納得する者が増えていくなか、陪審員4番(E・G・マーシャル)がてごわく有罪の自説を曲げないあたり。
ほかの有罪論者は、「スラム育ちの不良ならなんだってやるのさ」と思い込みや偏見を根拠にしているから、理屈としてはまったく弱いのだが、4番だけは「あなたの推論は見事だ」と8番の知性と粘りを認めつつ、「しかし状況証拠が揃っていませんよ。ゆえに私は納得できない」と冷静に退け続ける。
この徹底的に論理肌の4番が、新たな視点の登場に「あ……!」となるところが(僕にとっては)クライマックスで、8番に納得した途端、やはり冷静に自説が崩れたことを認め、無罪に転じるフェアな姿に、総毛立つほどしびれたし、今もあこがれる。
大人の、理想の姿だと思う。
これがあるので、〈男と男のディスカッション〉好きになった。
高度な位置で対等なレベルの男同士が意見や信条、思想で正面からぶつかり、譲らない。そういう〈理屈劇〉を見ると、アクションやヌードよりもコーフンする。
だから『漫画誕生』(18-19公開)のシナリオもああなった。
で、『十二人の怒れる男』を越える、とまではさすがにいかないが、今回見た2本の戦争映画の〈男と男のディスカッション〉もなかなかだったのだ。
『砂漠の鬼将軍』では、ロンメルの自宅を訪れた旧友の医師が、ヒトラー暗殺計画を進めていることを打ち明け、協力を求める場面。
医師は、ロンメルがヒトラーのイエスマンではないことを信じている。同時に、ヒトラーに愛でられた最高の軍人に秘密を伝えることが命取りになるのを覚悟している。決死の勝負に出ていることを、落ち着いた無表情と態度で隠している、セドリック・ハードウィックの張り詰めた鋭さ。
ロンメルのほうは、「私は軍人だ、政治に興味はない」と聞かなかったことにしようとするが、ヒトラーの独裁体制では戦闘に勝てないジレンマを誰よりも知っている。そこを医師に突かれて、顔色を変える。しかしどこに盗聴器が仕掛けられているか分からないので、煮え切れない返事のみを返す。このジェームズ・メイソンの、訴える表情と発する言葉が微妙に食い違っていくさまが見どころ。
『砂漠の鼠』では、部下の兵士達に対して徹底して理詰めで厳しい(部下の命を守るためなのは徐々に分かる)将校が、持ち場を離れて撃たれた仲間を助けに行った兵士を軍法会議にかけようとする。
それに反対するのは、部下のなかで一番足手まといの中年志願兵。実は将校と中年志願兵はかつて生徒と教師の関係で、将校はいまだに誰も見ていないところでは中年志願兵を「先生」と呼んで慕っている。
しかし、先生の助言であっても「命令違反は命令違反」と将校はつっぱねる。ハンパな温情を差し挟んで部隊が緩み、全滅することを何よりも恐れている。
「私は一兵卒、先生と呼ばんでください」と遠慮してきた中年志願兵だが、ここではあえて昔の「先生」に戻り、仲間のために前線に飛び込んだ、みなに慕われる好漢を処罰してしまう動揺のほうが隊にとってリスクは大きいのだよ、と教え子だった将校に温かく説く。
リチャード・バートンの頑固な怜悧さと、ロバート・ニュートンの庶民的な人間味が好いコントラストを生んでいて、実にいいディスカッション場面だった。
ここまで書いてきて気付いたが、上記の4人は全員イギリスの演劇人だ。
イギリスのトップクラスの舞台俳優に共演してもらえるから、こういう場面が用意されたのか。それとも、もともと映画にこういう場面が必要だから、それに見合う力のある俳優が求められたのか。いずれにしても、50年代前半までの(つまり、マーロン・ブランドやジェームズ・ディーンが出現するまでの)ハリウッドは、彫りの深い芝居を撮りたければイギリスから役者を呼ぶ、が主要な方程式だったのがわかる。
ついでに書いておくと、『砂漠の鼠』の男2人の関係が、ここ数年のあいだに僕が見た香港映画のなかで一番好きな『三国志』(ダニエル・リー 08-09公開)とよく似ているのに気付き、これにもワクワクさせられた。
『三国志』では、曹操の大群に包囲されながらも互角に戦う趙雲(アンディ・ラウ)は、率いる軍のなかで一番臆病な老兵(サモ・ハン)と二人きりになる時だけは鎧を脱いだ表情に戻り、老兵を「兄貴」と呼ぶ。若い雑兵時代に彼に面倒を見てもらい、彼の助言によって出世の道が拓けたのを、稀代の英雄となったあとも忘れていないからだ。
老兵のほうは、ちょっと先輩風をふかしてアドバイスしてやった覚えのある若造が、そのアドバイスを愚直に実践して将軍になったことに、嫉妬や憧憬、己の不甲斐なさのまじった複雑な思いを抱えている。
この男同士の関係の綾に物凄くコクがあって、やはり、かなりの僕の好みなのだ。
『三国志』のメインスタッフは、『砂漠の鼠』を参考に見ているんじゃないかしら、と想像する。
偶然だとしたら、それはそれで、僕はうれしい。
サラサラ書いておくつもりが、ついつい3,000字以上になり、また、まめな更新がしずらくなってしまった。やれやれ……。でも、たまに映画の感想を書くのは、楽しいですね。
















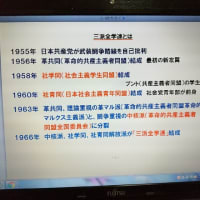
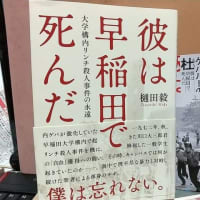

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます