4ヶ月ぶりのブログ。
どう利用していいか分からなくなって、ほったらかしにしがちなのだが。SNSでは長くなりそうなことを書けばいいのだ、と非常に当り前のことに気がついた。
にっかつロマンポルノの1本を有料配信で見たら、ジーンときてしまったので、メモを。
『モア・セクシー 獣のようにもう一度』
1981 にっかつ
監督 加藤彰
脚本 中野顕彰
主演 畑中葉子 横山エミー 河西健司 片桐竜次
横浜で美人局や当たり屋をやって暮らすヨーコと次郎は、ひょんなことから麻薬を仕込んだぬいぐるみを手に入れ、やくざに追われて横須賀に舞い戻る。昔のスケバン仲間たちに再会したヨーコは、逆に麻薬の取引現場を襲って現金を強奪してやろうと計画する―。

〈畑中葉子について〉
この人のロマンポルノ主演作を、ついに、初めて見た。触れたら指が吸い付きそうな白い肌で、すごくキレイだった。ころっころとした丸いほっぺたのまま活き活きと走り回っていた。一本調子な芝居がかえって可愛かった。
もう、これだけでジーンとなって満足した。
実はこの人に対しては、ちょっとこじれていたのだ。
1978年の日曜日。父親が車で札幌に用事があるのについていき、デパートでデュエット曲のキャンペーンをやっている最中なのを見た。歌手がマイクを持って歌うのを見るのは、あれが初めてだったと思う。小学4年生だ。
「カナダからの手紙」という新発売の曲です、と何度も司会が言うのを聞いて、カナダとはどこのことだろうと思った。
となりの男の人は覚えていない(つまり平尾昌晃先生なのか地方キャンペーンだけの代役なのかを覚えていない)。タヌキみたいに丸い顔をした女の子が、とにかく色白で、彼女のまわりだけ光っていたことだけが目に入った。要するに、ポーッとなった。
それから曲は、みるみるうちに大ヒット。発光体のようだった女の子―畑中葉子が一躍人気アイドルになったのはみなさんご存じの通りで、歌番組に出るほどシュッとした顔つきになっていくのを見るたび、札幌での、タヌキみたいだったけどキラキラした姿を思い出しては落ち着かないような、甘苦しい気持ちになった。
中学生になり、悶々とする対象が同級生になった頃、彼女は成人誌のグラビアに出るようになり、ソロで歌うシングルはちょっと内容が理解できないものになった。ロマンポルノ出演作の記事を買い始めたばかりの「キネマ旬報」で見た時は、本当に、どう思っていいかわからなかった。
あこがれていた清楚なおねえさんが、いつのまにかヌードで商売するようになった。いまだにこういうことは、どう捉えていいか分からない。その第1号が畑中葉子だった。
以来、ほぼ全く僕の脳裏からは存在が消えるのだが(実際に彼女も結婚して長いこと芸能界から離れていた)、2016年にひょんなことからほんの一瞬の縁ができる。
当時、BS民放の歌謡番組の構成をやっていて、音楽活動を再開した畑中さんがゲストに出ることになったのだ。
こういうキャリアのひとの場合、トーク収録ではとても気を使う。全くなかったことにするのが本人および事務所の意向という場合があるので。
台本を書く前に質問要綱を送り、それに答えてもらう文書上でのやりとりで、「セクシーな作品に出演」していたことにどこまで触れてよいかを聞くと、とてもサバサバとした、いかようにもお任せします、という意味の答えが返ってきた。
スタジオでの本番では、成長した子どもも母親のこれまでの仕事を理解し、これからの活動を応援してくれている、と話してくれた。
ちょっとだけあいさつしたご本人は、とても小柄だった。やっぱり色が白かった。
それから、これは礼儀?としても、なにか1本は当時の映画を見ておかねば、と思っていたのだ。早めに殺されてしまう一般映画のサスペンス『この子の七つのお祝いに』(82)は別として。
ところが、『モア・セクシー 獣のようにもう一度』の畑中葉子は、〈畑中さんのお若い頃〉という整理された認識を越えて、まっすぐにエロかった。すっ裸でドテッと無防備に寝ている姿に一瞬、『軽蔑』(63)のバルドーが重なった。美人局が失敗して、すっ裸で屋根から人の家の庭先に飛び降り、走って逃げるブザマな姿に、神代映画のヒロイン達と同じ愛嬌があった。堂々とロマンポルノのスター女優で、しかも今見てもそそらせてくれる。裸だけでなく、ピチピチしたホワイトジーンズのヒップの張り具合。
今になってようやく、畑中葉子にポーッとしなおすことができたのだ。感動だった。
〈他の要素について〉
実はこれだけ書いても、畑中葉子が横須賀の不良娘役というのが、最適な役柄だったかどうかは分からない。
それが途中で気にならなくなるほど、映画が、ストーリーが、面白かった。
さっき書いたあらすじ通り、ヨーコと次郎、仲間たちの危険な渡り合いは、ゆきあたりばったりの思いつきだ。夏のひまつぶしの延長にある。
映画には、特にプログラム・ピクチャーには、ジャンルの特質や年月を経ての変化がある程度以上に身体に入ると、それが自然と予備知識となり、その1本の独立した面白さ以上の感興が出てくる場合がある。
『モア・セクシー 獣のようにもう一度』は、僕が久々に見た、まさにジャンルの継続、連続の魅力があふれる映画だった。
(ここからは、それなりに旧作邦画に詳しい人対象の話になるが)ヨーコたちの、危険な賭けもゲームに過ぎない、殺されてしまう可能性は、難易度、スリルがあがった結果に過ぎないという風情は、まさに日活ニューアクションのそれだった。
加藤彰も、中野顕彰も、ずっと日活の作り手だ。しかし日活ニューアクションは手掛けていない。同僚達があだ花のように〈日活青春映画の末期としての死の遊戯〉を時にパセティックに、時にユーモラスに描いて評論家や映画ファンから熱烈に支持を受けていた頃にはなぜか2人ともその高揚から距離を置き、成人映画路線=ロマンポルノがスタートしてからは粛々と、地ならし運転の役目を果たしている。
映画に対しては常に中途半端な僕も、一応は『恋狂い』(71)、『学生妻・しのび泣き』『OL日記・牝猫の情事』(72)といった加藤彰の初期作は見ている。他のロマンポルノ監督と比べても女優さんを綺麗に撮る人、要所要所で凝った画面と心境がシンクロするよう手間をかける人、という好感を持っていたが、1本の中にこれだけ、描きたいことがある、という赤心を感じさせるロマンポルノ監督作は、初めて見た気がする。
描きたいことといっても、何度も書いているように、それはひと夏の無為なのだ。ヨーコは「俺は冗談では女は抱かねえ」と口説かれたら、「私は冗談で男に抱かれるよ」と笑顔で誘い返す。次郎って男がいることとは別。でも、次郎のためには身体を張る。
なぜかそこに後ろ暗い雰囲気が出ない。他の男に抱かれる=裏切り、とヨーコが思っていないんだから、それは裏切りにはならない。
日活ロマンポルノの初期にいち早く女性を対等に描いたのは加藤彰、と指摘する評を書いていたのは桂千穂だった。僕はそこを今までよく分かっていなかったのかもしれない。
現実に惚れた女性がヨーコみたいだったら、それは……タイヘンなんだけど。この映画のヨーコが汚れているようには見えない、そう見えないようにするってところに演出は注力している。貞操観念が存在しないヒロイン像から自由とは何かを探る哲学がある。そこは学ぼうと思う。
なにしろ加藤彰は、『月曜日のユカ』(64)の助監督をつとめてもいたのだ。
〈10年後の日活ニューアクション〉をその前後、中平康の女性映画、およびロマンポルノでの蓄積によって描く。この、作り手自身の青春の投影と、日活という映画会社の作風の変遷が濃厚にまじりあった(しかし、それゆえ素っ頓狂なほど劇的にならずに話は転がる。そのことで日活らしさというものが滲み出る)映画の、特にしみじみした場面は、海辺でヨーコたちが自転車に乗って遊ぶところ。
ここで、佐野元春の「ガラスのジェネレーション」が流れる。これこそ不意打ちで、参った。
自分達が描いているのは〈遅れてきた日活ニューアクション〉だ、言ってみれば楽屋落ちに過ぎない。しかし、オトシマエとしてやっておかねばならないのだ、と曲に託している。
ガラスのジェネレーション さよならレヴォリューション
加藤彰と中野顕彰は、何と決別したかったのだろう。元春と同じように70年代そのものか。少なくとも、『モア・セクシー 獣のようにもう一度』では、かつての主な図式―政治も復讐も捨てた男が、女を、ダチを殺された憤怒のリアリティのみに殉じるように死地に赴く―とは逆に、次郎を組織に殺されたヨーコが、死の遊戯を最後まで進める。そして、あっさりと成功して、あっさりと分け前を多めに仲間に渡し、自転車に乗って健康的に横須賀を去っていく。
ここでまた「ガラスのジェネレーション」が流れる。
次郎のほうがむしろ女性的で、古い仲間にすぐヨーコが溶け込むと、今まで二人きりでやってきたのに……と拗ねる。単独行動をして組織に捕まってしまう。ここでもやはり、日活が延々描いてきた、むしろ単独、孤立を望むヒーロー像とは逆の動きを描く意図がある。
(最近ではドラマのベテラン刑事役でおなじみの河西健司。若き日の頼りない男ぶりが、凄くいい)
いろいろ、すぐに解釈をさせないところがあって、その余韻も含めて、いいなあ、である。
さらにジャンルの連続で言うと。
ここまで書いても『モア・セクシー 獣のようにもう一度』には、かつてのあだ花的ジャンルの挽歌だけに印象がとどまらない、なんともいえん活力がある。
集団での喧嘩、乱闘シーンの、70年代までの邦画アクションと同じようでどうも違う、健康的といっていい元気の良さ。
この映画、高瀬将嗣が俳優兼業でアクション指導を始めたばかりの作品でもあるのだ。
体を張ったアクションの指向が、バイオレンス(観念の表現)よりもリアル(身体を張ってることそのものをエンタテインメントとして見せる)に移行しているのが如実に分かるさまは、高瀬の殺陣師としての大出世作『ビー・バップ・ハイスクール』シリーズ(85-88)の前哨戦といっていい。
『ビー・バップ・ハイスクール』が、日活の残党が集まった東映セントラルの作品であることを考えたら、ますます、『モア・セクシー 獣のようにもう一度』という、映画史に残る作品といった高い評価がそれほどあったわけではないものの中にある、日活の歴史の交通の豊かさに驚かされる。
映画ファンみんなが見てどう思うかはわからないけれど。
少なくとも、畑中葉子さんのファン、日活の歴史を踏まえたファンには、とてもチャーミングに感じられる映画だと思います。










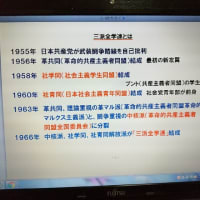
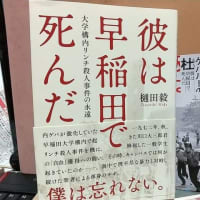






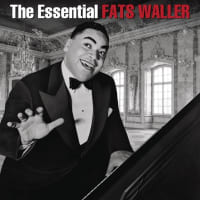

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます