最近、急に気まぐれをおこして、ジャン=リュック・ゴダールの『勝手に逃げろ/人生』(1979-80フランス公開)を見た。フランス=オーストリア=西ドイツ=スイスの合作。
ゴダールの映画に触れるのは、結果的には遺作となった『イメージの本』(2018)が日本で公開された2019年に、のこのこ映画館まで出かけて以来だ。それまでも、見ていたのは長編約40本のうち20本ちょい。オールジャンルで半可通な僕の割にはけっこう付き合ってきた部類に入るのだが、専門家からしたらお話にならない、そんなレベル。
ところが、そんなレベルで『勝手に逃げろ/人生』を見たら、とても面白かった。ゴダールについて少し考えた。
以下はそのメモです。もっぱら想像したこと、推測したことを書いているので、識者の批評や解題とは毛色が違うものとお考えください。
まず、自分のためのおさらいも兼ねて、ジャン=リュック・ゴダール(1930年パリ生まれ)の活動を大まかに整理してみる。
第1期…カルチエラタンのシネクラブやシネマテークに通い、映画評を書き、映画仲間を作り(その多くが後に高名になる)、短編映画を作っていた1950年代。
第2期…破調に満ちた長編第1作『勝手にしやがれ』(1959)が注目されて以来、フランス映画界の異端児、あるいは麒麟児の毀誉褒貶のなかで、〈ヌーヴェルヴァーグ〉のリーダー格として前のめりに活動した1960年代前半。
第3期…いよいよその才能は本物と広く認められ、女性誌がインタビュー記事を組むほどの流行作家、世界的な人気監督だった1960年代半ば。
第4期…商業性が強い映画界への幻滅にともなうかたちで、政治に傾倒した1960年代後半。
第5期…ビデオによる制作に入れ込み、テレビの教育番組などを作っていた(そしてそれがボツになったりしていた)1970年代。
第4・5期を経て、久々に手掛けた劇映画/商業映画が『勝手に逃げろ/人生』ということになる。
その後は、映画界の別格中の別格の存在と見なされて、何を作っても世界中から歓迎され、深読みされ、映画から再び離れようとしても美術館や国際映画祭などからの短編映像の依頼はひっきりなしに舞い込み、してまたそういうものをいざこさえると、どれもめざましい〈映画による映画論〉になってしまうし、スマホで撮ろうとYouTubeの動画を引用しようと、全てが〈高僧の御託宣〉として熱烈に称賛されてしまうもんだから、とうとうやめるにやめられなくなり、結局は最後まで〈マメに注文を受け続け、勤勉に応え続ける神話的人物〉という、いささか奇妙で、第1期の熱心さに回帰するようなかたちで生涯を終えたのは、映画がお好きな方はみなさんご存じの通り。
『勝手に逃げろ/人生』は大まかに捉えると、以下のような筋立て。
演出家のポール・ゴダール(ジャック・デュトロン)は今、テレビの仕事で成功しているのに憂鬱な停滞のなかにいる。恋人のドゥニーズ(ナタリー・バイ)は自分と別れて田舎暮らしをすることを決め、離婚した妻と娘との食事も気まずくて会話が弾まない。マルグリット・デュラスに出演してもらう企画を進めていたのに、デュラスに断られる。どうも、自分が嫌われているかららしい。ついイライラしてドゥニーズや妻、娘に当たってしまうが、傍から見るともともと女に甘えたところがあるから、みんなに疎まれている、自業自得のようだ。
一方、田舎から都会に出てきたイザベル(イザベル・ユペール)は、私娼をしながらいい物件を探している。やくざに分け前を強要されたり、さらに素性のはっきりしない仕事を紹介されたりしつつも、とても割り切った考えのもとで客の変態的な求めに応じる。
イザベルは男に何も期待していないし、むしろ〈言葉をしゃべる産業動物〉位に思っているから、男を憎むこともない。(こういう例えは、ドゥニーズが田舎に下見に訪れる場面での牛や馬のカットの即物的な美しさからもたらされる。ここらへんは、人もモノも等価に冷静に撮る、もしくはそうキャメラマンに求めるゴダールらしさの躍如といったところだ)
さて、この三者が、いよいよ別れることになったポールとドゥニーズが出ていく部屋を、イザベルが内見に来ることで顔を合わせる。
出ていく女・ドゥニーズと、入ってくる女・イザベルの間でなにげない世間話が交わされ、この映画のなかでほぼ初めて、あたたかいコミュニケーションが生まれた後、停滞して苛立つ男・ポールは急に事故を起こす。
この構成を、「各主題(三人の登場人物と三つの場所)が順々に提示された後、最後にすべての要素が統合されるという音楽的構成」と、スパッと言い表しているのは、『E/MブックスVol.2 ジャン=リュック・ゴダール』(1998 エスクァイア・マガジン・ジャパン)の遠山純生。半可通のくせにナマイキを言うが、さすがだなーと思う。
実際、あらすじを書いてみると、澱んだところや意味を計りかねるところがない、明瞭なストーリーなのに驚く。
そう、こんなに筋とテーマの絡まりが分かりやすいゴダールの映画は、僕はかなり久々だったし、おそらく全部を通しても珍しいと思われるのだ。それで、もっぱら、どうしてそうなったのかについて考えてみた。
『勝手に逃げろ/人生』の、筋に関わるメインスタッフは、次の面子だ。
製作 アラン・サルド
原案・脚本・監督・編集 ゴダール
脚本・編集 アンヌ=マリー・ミエヴィル
脚本 ジャン=クロード・カリエール
アラン・サルドは、70年代から近年までずっと活躍してきた大プロデューサー。
イザベル・アジャーニ主演の『ブロンテ姉妹』(1979)やイヴ・モンタン主演『ギャルソン!』(1983)、ジュリエット・ビノシュとジャン・レノが共演した『シェフと素顔と、おいしい時間』(2002)などのスター・ムーピーでヒットを飛ばし、クロード・ソーテやアンドレ・テシネらに成功をもたらした一方、より純映画作家的なロマン・ポランスキー、デヴィッド・リンチらに定期的に新作を作る機会を与え、『戦場のピアニスト』(2002)でカンヌ国際映画祭パルムドールを獲得した。要するに、シネコン系とミニシアター系の両方でホームランを打ち、名誉も得ている、かなり大したやり手だ。
このアラン・サルドが硬軟両面を手がけるきっかけになったのが、『勝手に逃げろ/人生』。以来、長編全作ではないが、多くのゴダール映画でプロデューサーをつとめることになる。
当時の、若いアラン・サルドにとって、〈ゴダールさんの劇映画カムバック作をプロデュース。〉は、それはもう、さぞかし野心的な計画だっただろう。
あくまで芸術的な満足のためであって興行的な利益は度外視 ―ではなかった気がする。
あのゴダール先生と……という実績は投資家に対しての信用になり、他の、儲かる企画が実現につながりやすくなるからだ。(急に音楽の例え話になるが)ワーナーが、別にもうヒット曲を作ろうとも思っていないポール・サイモンと契約を続けているのは、ポール・サイモンがいる会社という価値が株価に影響しているからだ。そういう話を前に読んだことがある。
とはいえ、ゴダールさん任せにして、今さらギンギンの政治アジテーション映画をまた作られ、どこの劇場もかけてくれないようなヘタは打てない。
それで連れてきたのがジャン=クロード・カリエールだ、と推測される。
当時のゴダール自身も〈生きる伝説〉と半ば神聖視されている名誉の面はいいとして、テレビ番組の放送を拒まれるなどが続けば、事務所の運営は苦しくなる。映画の商業主義を嫌ってテレビに新大陸のやりがいを求めたのに、いつのまにかテレビのほうも大きくなって、自分の好きにさせてくれる鷹揚な面を控えるようになったのは、ゴダールが映画に戻った背景として大きかったと思われる。
もちろん、映画界のほうがむしろ文化的意義や、娯楽映画に比べて多くこそないが一定数の需要は確実にあるという理由で、作家主義的な作品を守るようになった時代の変化もあるだろうし。
しかし、やはりゴダールとて、久々の劇映画でヘタは打ちたくない。やる気満々でサポートしてくれる若いアラン・サルドに「カリエールさんといっぺん打ち合わせだけでもしてみませんか? 僕は意外とおふたり、合うと思うし、組めばゼッタイ話題になると思うんですよねー」と言われて、断る理由はなかったのではないか。
とスイスイ妄想してしまうほど、ジャン=クロード・カリエールの名前をゴダールとのつながりで聞くのは意外だし、異色だ。
ゴダールの映画にこれほどの脚本家が参加している例は、他には『カラビニエ』(1963)のジャン・グリュオーがいるが、グリュオーは互いに映画評を書いていた時代から知っていて、脚本家としてはフランソワ・トリュフォーとずっと組んでいる、もろにお友達コネクションのひとりなので、カリエールとの協働がやはり目立つ。
ジャン=クロード・カリエールは、ジャック・タチのユロ氏ものの、最近風な言い方だとノベライズ(ずっと前に、ひとにプレゼントしたのであまり覚えていないが、邦訳が日本でも出ていた)などからキャリアを始め、なんといってもルイス・ブニュエルの一連の作品―『小間使の日記』(1964)、『昼顔』(1967)、『銀河』(1968)、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(1972)、『自由の幻想』(1974)、『欲望のあいまいな対象』(1977)で映画の歴史に名を残す人だ。ゴダールが映画から離れていた時代に、純映画指向な作家性と興行的な成功の両立は成り立つ、と証明してトップを取った人という言い方もできる。
そうして『勝手に逃げろ/人生』を思い返すと、これはゴダール監督作品と同じ位、ジャン=クロード・カリエール脚本作品でもあったんだな、とつくづく感心する。
男と女の行き違い。また男と女の、人と人の上下関係がもたらす冷酷さ。グロテスクな性的描写に現代ヨーロッパ社会の病理を投影させる、モラルと悪意がないまぜな構造。そして、にも関わらず滲み出る典雅さ。
ついでにカリエールが『勝手に逃げろ/人生』の後に脚本を書いた映画のことも言うと、女と男=動物のセクシャルな暗喩は『マックス、モン・アムール』(1986)でもっと明確に表現され、男ひとり、女ふたりの行きずりが続くような関係は、『存在の耐えられない軽さ』(1988)でさらに文芸的な味わいに達した。
ゴダールも負けていない。ブニュエル=カリエール組の映画のほうで見事に象徴的だった、ブルジョワ達が途方に暮れたように歩いた田舎の一本道を、人生をやり直そうと決めた女がひとり自転車で走る姿を捉える、清新なショットで更新したと同時に、道は単なる道でしかない、と、芸術映画が映像に何かと文学的象徴を求めるクセに釘を刺してみせた。
カリエールお得意のグロテスクで滑稽な性的場面も、あえて無情な交換=ビジネスの場としてドライに撮り、自作『彼女について私が知っている二、三の事柄』(1966)に引き寄せるとともに、政治の問題はもはや自分が政治映画を撮っていた時代よりずっと深く個人の生活や人間関係のなかに入り込み、その影で見えにくくなった。それ位、私だって分かっているのだよ、とカリエールやアラン・サルドに答えてみせた。つまり、ことの本質を掴んでさえいれば、扇情的な場面を一切エロくなく撮っても面白くすることができる、と立証してみせた。
(そうして実際、この後のゴダールの映画は、いわゆるエロ目的ではない場面に出てくる女性でもムラムラとするほどエロティックである、という強力な興行上の隠れ武器を持つことになる)
いやーさすが両雄、いい勝負してるじゃないですか、という感じ。
で、おそらくお互いに、尊重し合うことで共通の了解があったのが、ゴダールの1970年代からの公私のパートナー、アンヌ=マリー・ミエヴィルが共同脚本で関わった部分だろう。
あらすじ紹介の箇所で書いたことの繰り返しになるが、ドゥニーズとイザベルが言葉を交わす場面は、ほんとに凄くいい。なんてことなく世間話しているだけなのになぜだろう、と思うが、なんてことないところが、いいのである。
おそらく完成した1980年当時よりも、日本で初めて劇場公開された1995年よりも、今見たほうが良さの分かる場面だ。シスターフッドとは何かを男性が理解しようと思う時、この場面が参考になるんじゃないかと思う位。
ナチュラルにミソジニー的、男性優位主義的なところがあった(と僕は直感で思っている)ゴダールの男として悪いところは、ミエヴィルと一緒にいることでずいぶん揉まれ、中和され、助けられている。
ミエヴィルが主演・監督し、ゴダールを夫役にして恋愛自由主義的な夫婦のありようを虚実行き交うように描いた『そして愛に至る』(2000)という映画がある。2002年の公開時に見て、僕は凄く良かったのだが、熱心なゴダールのファンもあまり話題にしない、やや戸惑った捉え方をしているのが印象に残った。この映画も、今見たほうが適正な評価が与えられる気がする。
しかし、である。『勝手に逃げろ/人生』でいい結果を生み、再出発のスタートを成功させたにも関わらず、ゴダールが力のある脚本家と四つに組む機会はこれが最後になった。
女とうまく関係を結べないポールの姓はゴダールであり、テレビの仕事をしながら屈託している……つまり、観客が容易に、映画界本格復帰前のジャン=リュックの自己省察的な物語であると解釈できること。
ラスト、ポール・ゴダールが路上に倒れ、なのに愛する女は助けずに立ち去ってしまう……やはり、観客が容易に、長編デビュー作『勝手にしやがれ』を連想できること。
どうして、こんなに露骨な道具立てをしたのだろうか。
ふたつの理由が考えられる。
ひとつ…ゴダール自身が劇映画カムバックにあたって、原案の段階で赤心をさらけ出してみせた。
ふたつ…カリエールやアラン・サルドのほうから、悪戯ッ気、挑発、あるいは敬意を込めて、ゴダール作品らしさを補強するために加えた。そして、ゴダールは受けて立った。
佐野亨編『心が疲れたときに観る映画』(2017・立東舎)という本に参加させてもらい、林芙美子原作の成瀬巳喜男『稲妻』(1952)について書いた時、田中澄江が脚色したヒロイン・清子(高峰秀子)のキャラクターが、小説に描かれているよりも林芙美子自身に似ている面白さを僕は少し、書き添えた。
それとケースが近いというか、その映画作家の、らしさの部分は、人の手が入ることでさらに増幅されることは、ままあると思うのだ。
いずれにしても、この効果はいい意味で大きく、『勝手に逃げろ/人生』は劇映画カムバック作であると同時に、第二の長編デビュー作という評価も得られることになった。
有名な言葉「作家は処女作に向かって成熟する」のごとく、ゴダールの映画の主人公は常に愛する者との関係に不全をきたし、路上で命を落としてきた。
まるで『勝手にしやがれ』のようじゃないか ― ある人は『女と男のいる舗道』(1962)で、またある人は『軽蔑』(1963)でその反復に気付き、カリスマ作家になってもなお癒されない生来の人間不信にまるで自分だけが気付いたような、甘く悲痛な思いにかられ、熱烈なファンの母性本能をかきたてる。
ああ、ジャン=リュックったら。インタビューではいつも皮肉屋なのに、ほんとうは孤独な寂しがり屋さん!
……第3期までのゴダールにはこういう、実に太宰治的なイヤラシサがあるのだが、まるでその魅力が戻ったようなしめくくりを用意しているんだから、第4期以降は離れたファンへのサービスとしては、このラストは最高である。
そして、同時にこの成功が、ゴダールを再び反映画的な態度へと向かわせることになった。
ここからは推測尽くしで書いてきたこの文章の、最大の推測、忖度となる。
確かにカリエールとの協働作業は良かった。こんなに、映画のなかでの引用が少ないものは珍しい。
(ヌーヴェルヴァ―グで映画に〈自意識〉を持ち込んだゴダールにとって、引用は「自分と映画の間にあるもの」だった。僕らは人と話をする時に「この前、誰それさんのコラムを雑誌で読んだんだけどさ」「まるであの映画のラストみたいな心境だったわけよ」などと、実はかなり夥しく引用を行っている。ゴダールにとって引用は、その映画を自分の作品として忠実に作り上げるために欠かせないものであり、しかし「自分と映画の間にあるもの」がよそから来た腕のいい脚本家ならば、自ずと引用は減るのである)
しかし、自分はもう、ヒトのホンを撮る演出家に徹して、その文学的・文芸的な完成度を高めることには徹しきれない、とゴダールは気付いた。きれいに撮れているカット、いいアクションが撮れているカットほど、スローモーションをかけていじりたくなってしまった。
ラストにしても、ポール・ゴダールは、死んだかどうかは実はハッキリしていない。ちんぴらミシェルのように路上に倒れながらも、「……あれ、死ぬ前に見えるという走馬灯が出てこない」とポールはつぶやくのだ。
これが、乾坤一擲のセルフ・パロディのギャグとしてもう少しだけパチーンと決まって観客に届いていれば、1980年代以降のゴダールの歩みは、吹っ切れた形で変わっていたと思うのだが、あいにく曖昧で韜晦じみた、不発のショットとセリフになってしまった。
生涯の友でありライバル、フランソワ・トリュフォーは、同じ時期に『終電車』(1980)を作り、自身最大のヒット映画とし、セザール賞独占という大きな社会的名誉まで得た。
ゴダールは、文句をつけようと思えば、いくらでもつけられただろうし、僕が読んでいないだけで実際にかなりつけている気がする。おいおい、かつて〈フランス映画の墓掘り人〉と異名をとったほど爪の甘い娯楽映画に辛辣だった男が、こんなベタついた笑いと感動のメロドラマを作りやがった……って。
しかしそれは、『終電車』は、実に味わいのよいものだった。ナチス占領下の愛と恋。銃口を向けられても舞台を続ける役者の意気地。機知と笑いとユーモアと。カルネ、ルビッチ、ルノワールの映画の大柄な魅力を真に後継できるのは、結局はヌーヴェルヴァーグ一味しかいないのだ、とトリュフォーは宣言して、見事に成功してみせた。ゴダールより先に、である。
SF/ファンタジー映画の魅力を再発見し、西部劇に代わる一大メジャー・ジャンルに押し上げたジョージ・ルーカスの功績は、アメリカ映画の歴史において不滅のものとなるだろうが、映画の作り手としての腕は、弟分のスティーヴン・スピルバーグのほうが一枚も二枚も上。
こうした論評は、比較的早い段階、1970年代後半からもうあったと僕は記憶している。ルーカスがさっさと〈長講・銀河大戦傳〉の続きの演出は人に任せ、全体統括に回ったのは、そういう声がけっこう図星だったことも影響しているのではないか、と想像される。
『終電車』と『勝手に逃げろ/人生』をまっとう至極なお客目線で比較されて、ゴダール氏は結局、ふつうのドラマ、ふつうの映画はいざ撮ろうと思っても撮れないのだ、と言われたくない。プライドが許さないだろうし、ヘタしたら今後の作家としての活動にも支障をきたしてしまう……。
次作『パッション』(1982)以後を僕はロクに見ていないので、さすがにこれ以上の妄想は控えよう。
ただ僕は、ふつうの映画を撮れない=腕が劣る、という話をしたいわけではないのだ。
そもそもゴダールがふつうの映画を撮れる才気の人間であれば、彼はおそらく映画を撮らず、もともと大学で専攻していた民族学などの学問を頑張っていた。映画に興味も持たなかったかもしれない。ふつうの映画を作るような人間にはなりたくない、という思いこそがゴダールを映画に向かわせたのだ。そう僕は思っている。
今年(2022年)は、映画ライターの仕事の面では、熊井啓と深作欣二について考えることが割と多かった。どちらも1930年生まれ。そういうことがあって同じ1930年生まれのジャン=リュック・ゴダールについて、年末になって急に、しかもこんなに長い文章では初めて、書いておきたくなったようだ。僕の作家論っぽい文章は往々にして、作風・画風の美学的検討よりも世代論のほうに傾く。
ジャン・コレの『現代のシネマ1 ゴダール』(竹内健訳 1969 三一書房)を、いつだったか西荻窪の書店ロカンタンで入手したものの、未読の山のなかに置いて手をつけないままでいた。
『勝手に逃げろ/人生』の面白さから、やはりつい先日、初めてページを開いたら、
「われわれは、一九五〇年頃に二十歳であったことの意味を知っている」
の一文が目に飛び込んだ。
1930年生まれ。
もう、一通りは整った近代文明の豊かさを、人類史上初めて、幼児期から十分に味わっている世代である。
大きな戦争が近づき、やがて始まった時の興奮と、長引く重苦しさ、死を考えながら暮らすことの意味を早くから味わっている世代でもある。
そして映画が、過酷な現実よりも圧倒的に楽しく、素晴らしいものであることをどの世代よりも深く知っていた。
だから戦後、焼け跡から建設の時代が始まるなかで、「一九五〇年頃に二十歳であった」青年は、映画が戦前、戦中と同じ精神のまま楽しくあり続けようとしていること、現実より楽しいものという自信を失っていないこと ― そうして現実にどんどん追い抜かれていくことに、激しく苛立った。
熊井啓は、映画の持つ社会公器の面に賭け、冤罪事件を起こした警察権力を糾弾することから監督人生を始めた。
深作欣二は、アメリカナイズされたアクションコメディが自分にも作れるかどうかを試した後、アメリカが占領下の日本に敷いたコントロールの網が、占領政策が終った後も断ち切れずに動いていることを、娯楽アクション/サスペンスの文脈で告発することで、映画監督としての軸を定めた。
ジャン=リュック・ゴダールはと言えば、もっと苛烈だった。映画を、現実よりも楽しいものを、殺そうとすることが出発点だった。
戦争と破壊の時代においては、確かに映画はそれで良かったし、そこが良かった。
でも、映画を見るとは、ひたすら受動的な、消極的な行為である。戦後の建設の時代にまで、そうであってはいけない。だから私は(イタリアのロッセリーニ先輩のお仕事を参考にして)映画の中に現実を持ち込もう。ドキュメンタリーだけでなく、劇映画も撮影所の外に出て作る時代の先兵となろう。そうして現実をどんどん映画の中に侵食させ、人々の映画を見る目が、現実をしっかりと見る目へと弁証法的に発展していくのを後押ししようではないか。
現実を忘れさせることが目的で作られた楽しいもの、映画は、すべからく、これから我々が作っていく豊かな現実の前に敗れ去るのだ。
……この壮大な理想、野心は、当然僕らが知っているように、挫折に終わった。
映画はなんというか、もっと柔軟でしたたかだった。ゴダールが映画を殺すために仕掛けた何本もの矢 ―この映画のどの場面にも、カメラの裏側に常に作り手がいますよ、と観客を物語に没入させず、シラけさせる〈自意識〉の導入。屋外撮影、手持ちカメラ、画面と録音のズレ、ジャンプカットなどなどは、ことごとく吸収され、現代映画の幅と魅力をより拡げるための糧となった。
そんなしぶとい映画を全否定するため、今度はビデオによる制作を始めたものの、映画はやがて、自分はフィルムではなければいけないもの、という自覚も何も忘れてしまい、ビデオで撮られたとしても(映画館で不特定多数の人が見るもの、というルールに沿ってさえいれば)自分は映画だもん、と居直るに至った。
そうなると途端に、1970年代からビデオで作っていたゴダールは、映画の生きる道をいち早く示してくださっていた偉人、ということになった。
さらにムキになって、スマホで撮ろうとYouTubeの動画を引用しようと……というのは、前半に書いた通りである。
これ以上見事に、映画を心から憎み、とことん闘ったすえに、誰よりも映画に愛されてしまったために敗れた者は歴史上いない。ジャン=リュック・ゴダールの作品は、だから凄くて、痛いのだ。
『勝手に逃げろ/人生』は、音のズレ(見ている人に聴こえないものが登場人物達に聴こえていたり、見ている人にも登場人物達にも聴こえる音の主体が出てこなかったり)の演出が凄く面白い映画で、これについても書いておきたい気持ちがあったのだが、もうやめておきます。
『勝手に逃げろ/人生』の音については、『フィルムメーカーズ21 ジャン=リュック・ゴダール』(2020・宮帯出版社)のなかで、山本浩貴(いぬのせなか座主宰)という方がとても精緻に分析してくれているので、ぜひそちらをお読みください。
















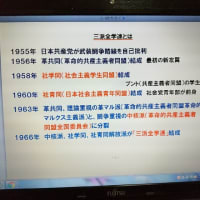
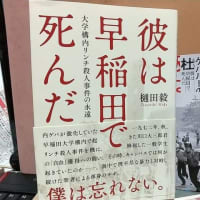

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます