国債を発行するシーンとして財政法4条によると、
・(大まかに)公共の事業・出資・貸付に公債発行、借入ができる
とされているようです。
そして公共事業とは、“後世の国民が利用できる”ことが大前提とされています。
まとめると、【国債(建設国債)とは、国民が後世に渡って利用できる事業において発行できる公債】と言えそうです。
いわゆる【赤字国債】とされている、“財政の赤字を埋めるための国債”はこの財政法4条に当てはまらず、
昭和40年度における財政処理で、初めて、赤字国債を発行するために施行された【公債特例法(時限1年)】を毎年制定(時限1年のため毎年制定する)して、今まで凌いできました。
この赤字部分が返済のあてのない借金で今日まできたわけです。
特例公債(赤字国債)は“特例”ですから、いつか必ず返済していかなければなりません。
本来は返済予定を立てなければ借金できるはずもなく、そこを未来に棚上げした結果が、間もなく1000兆円を超す公的債務の原因の一端を担ってしまっています。
本来の健全財務であるべき【国債】(毎年必ず黒字であるべき、という意味ではない)と、
不健全財務の証【赤字国債】が混ざってしまったことが問題と言えるでしょうか。
第二次補正予算案で自民党が提唱する【復興再生債】ですが、上記の【赤字国債】を回避する案となります。
しかしここで問題なのは財政法4条です。
東日本大震災からの復興は“国民が将来に渡って利用できる事業”にあたるはずです。
【復興再生債】が“国民が将来に渡って利用できる事業”であるか否かを切り分けられなければ、
逆のパターンである【赤字国債】から逃れられる気はしません。
“国民が将来に渡って利用できる事業”は、数字の上で赤字であっても国民の利益です。
“国債を発行しない”ことを“ありき”としてはいけません。
大事なのは、それが“国民が将来に渡って利用できる事業”かどうかです。
つまり、【復興再生債】とは【赤字国債】を蓑(みの)で隠し、健全な【国債】を冒涜するシステムと言えないでしょうか。
被災からは確りと【国債】で復興し、国民の後世に役立つ事業に特化した予算を組み、そうした事業の優先順位とプライマリバランスを見比べ“仕訳”する、
民主党の存在意義はそこであるべきです。
表層的な仕訳ではなく、国民の後世に“当面役立たない事業”とケンカをしてもらいたいものです。
ボクは無党派ですが、政権は“政権”と捉え、民主主義を冒涜するような非建設的な批判はしたくありません。
やるなら選挙で。
結果には従うより他なりません。
・(大まかに)公共の事業・出資・貸付に公債発行、借入ができる
とされているようです。
そして公共事業とは、“後世の国民が利用できる”ことが大前提とされています。
まとめると、【国債(建設国債)とは、国民が後世に渡って利用できる事業において発行できる公債】と言えそうです。
いわゆる【赤字国債】とされている、“財政の赤字を埋めるための国債”はこの財政法4条に当てはまらず、
昭和40年度における財政処理で、初めて、赤字国債を発行するために施行された【公債特例法(時限1年)】を毎年制定(時限1年のため毎年制定する)して、今まで凌いできました。
この赤字部分が返済のあてのない借金で今日まできたわけです。
特例公債(赤字国債)は“特例”ですから、いつか必ず返済していかなければなりません。
本来は返済予定を立てなければ借金できるはずもなく、そこを未来に棚上げした結果が、間もなく1000兆円を超す公的債務の原因の一端を担ってしまっています。
本来の健全財務であるべき【国債】(毎年必ず黒字であるべき、という意味ではない)と、
不健全財務の証【赤字国債】が混ざってしまったことが問題と言えるでしょうか。
第二次補正予算案で自民党が提唱する【復興再生債】ですが、上記の【赤字国債】を回避する案となります。
しかしここで問題なのは財政法4条です。
東日本大震災からの復興は“国民が将来に渡って利用できる事業”にあたるはずです。
【復興再生債】が“国民が将来に渡って利用できる事業”であるか否かを切り分けられなければ、
逆のパターンである【赤字国債】から逃れられる気はしません。
“国民が将来に渡って利用できる事業”は、数字の上で赤字であっても国民の利益です。
“国債を発行しない”ことを“ありき”としてはいけません。
大事なのは、それが“国民が将来に渡って利用できる事業”かどうかです。
つまり、【復興再生債】とは【赤字国債】を蓑(みの)で隠し、健全な【国債】を冒涜するシステムと言えないでしょうか。
被災からは確りと【国債】で復興し、国民の後世に役立つ事業に特化した予算を組み、そうした事業の優先順位とプライマリバランスを見比べ“仕訳”する、
民主党の存在意義はそこであるべきです。
表層的な仕訳ではなく、国民の後世に“当面役立たない事業”とケンカをしてもらいたいものです。
ボクは無党派ですが、政権は“政権”と捉え、民主主義を冒涜するような非建設的な批判はしたくありません。
やるなら選挙で。
結果には従うより他なりません。










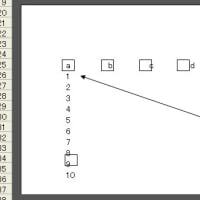
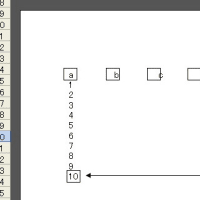
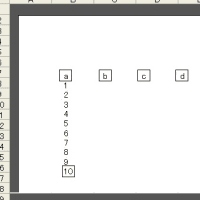





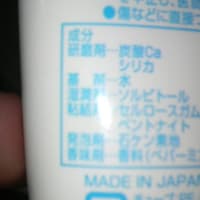
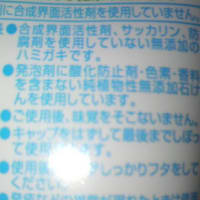
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます