前記事では確率の積の法則について、自己流の考え方を書いた。この記事が正しいのかどうか俺には判断出来ない。一応は正しそうだ、と思ってはいるけども。
で、確率の積の法則って分数の掛け算なのだなぁ、とおもった。そんなの当たり前でしょ!って言われたら、そうなですね!って答えるしか無いのだけど、分数の掛け算ってなんだかしっくり来ない気がするんだよね。
3/4×4/5=(3×4)/(4×5)
分母同士と分子同士を掛けると答えが出る。なんでそうなるの?と。
前記事の面積の出し方で考えると、
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
分母同士の掛け算というのものが、総数を表していることが分かる。分子同士の掛け算は、そのうちのどの範囲なのか?を表わす。この辺をもっと上手く教えてくれる先生がいたとしたら、分数計算をもっと理解しやすくなると思うのだけど、どうでしょう?
割り算になるともっと悲惨。今更思ったのだけど、括弧付けないとダメだったね。
(3/4)/(4/5)
とかわけわからない。割る数の分母と分子を入れ替えて掛ければ良い、とかを覚えても、直感的に理解が出来ない。
A/A
であれば、答えが1であることも理解しやすい。なので、
(1/2)/(1/2)
も、同じ数同士で割っているのだから答えは1だよね、って理解出来る。
でもなんで割る数の分母と分子を入れ替えて掛ければ良いの?これって最近どこかで表題だけ読んだ気がする。それとは別だけど、
分数で割り算をする時、何で割る数をひっくり返すの? (初投稿!!)
3の、何回引けるか、という考え方は比較的理解しやすい。とても面白い考え方だと思った。
道草学習のすすめ : 分数の割り算、ひっくり返してかけるのはなぜ? ~ドラえもんグッズの威力~
割合として考える。これなんかは応用すれば面積で視覚的に説明出来そう。いやはやしかし、分数の割り算を今日始めて理解したよ(苦笑)
大事なのは発想だろうと思う。でも発想が湧かないから分からない。どうやったら発想が生まれるのか?はどうやったら教えられるのだろう。または俺自身の身につくのだろう。多くの教育者の悩みではないかと思う。
中学3年生の姪っ子は公式とかをきちんと覚えている。でも使い方が分からない。なので、問題文から読めることだけを、どれだけ簡単な途中式であっても書くようにし、その途中式が一体何なのか、注釈を入れて考えてご覧、と教えてみた。
ある意味、プログラミングと同じなのだろう。俺はプログラミングを専門的に勉強したわけじゃないので、聞きかじりと想像で書いてしまうのだけど、エクセルVBAで拙いプログラムを書いた時に、注釈を書いておくといいよ、という説明を真に受けてなるべくきちんと注釈を書くようにしておいた。
その後、プログラムを運用した際に、後から機能を付け足すときに注釈がどれだけ大切かを痛感した。プログラムにコメントを入れるのは、思考の形跡を残すことのようだ。そういえば俺がブログを書くのもそれに近い。気持ちだけで終わってるけど。
つまり、論理的な思考というものは、出来る限り視覚的に振り返ることの出来る形に残しておくことが大事だと言えるだろう。
論理的な思考が苦手な人は、論理的な思考の出来る人が、あたかも答えに向かって最短で思考しているかのように見えるようだ。少なくとも俺から見た論理的な思考の苦手な人はそう思っているように見える。論理的な思考の得意な人を倣おうとして思考手順を端折る傾向にある。そして何について思考しているのかを自分が見失う。あれ、これって俺か・・・説明出来ても実行出来ない良い例(笑)
論理的な思考をとても上手に出来る人というのは、言い換えれば途中式を書かなくても方程式が解けるくらい、頭の中が整理されているのだろう。頭のなかが整理されていない人が真似しようとしても、余計頭のなかが雑然としてしまう。教える側は、すでに整理されているから教えることが出来る。こんなところにも、分かってしまうと分からないことが分からなくなる、という穴があったわけだ。
とにかく公式を覚えなさい、計算をどんどんやって慣れなさい、というのは、まずは頭の中を整理しなさい、ということ。なぜ部屋を片付けなきゃならないのか分からず、親から部屋を片付けなさいと言われるようなもの。
倣わせるのは、頭の中の整理の仕方だろう。丸暗記や反復練習はダメだ、とは言えないだろう。丸暗記や反復練習だけではダメだろうけど。
仮説を立てる。思考のプロセスを書く。一つの方向に進む。頓挫する。
頓挫した時に戻ろうとするのだけど、仮説に対する思考のプロセスは閃きであることが多く、どこでこの思考が生まれたのかは思い出すという作業だけでは困難だろう。そこで思考の得意な人は、どこのどのタイミングでこの思考プロセスが生まれたのか、注釈しておく。
ここから先はこの分岐、だからこの分岐の先で間違っていることが判明したら、この注釈まで戻ろう、ということを、言うなればヘンデルとグレーテルのパンのような印を残す。ヘンデルとグレーテルの場合は、動物たちがパンを食べてしまったけど。
おそらく、残す目印も意識的にしないとならないのだろう。動物ではなく風が強く吹く場所であれば、重たい石で目印にした方がいい。常に最適な目印になるものがあるわけではないから、その場所の特徴をそれぞれの認識しやすい概念で置換えておく。
ただしそれは自分にとって認識しやすい概念で置換えただけなので、人に説明するときには逆の置換えが必要になる。
自分にとって認識しやすい概念を、伝えたい相手にとって認識しやすい概念に置き換えて説明する。これが会話だ。
通常、俺たちはこうした手順を無意識的に行っている。赤い丸い果物に記号名を付ける行為は、その記号名の持つ自身にとっての意味(美味しい、甘い、ちょっと酸っぱい時もある、身体に良い、皮がある、種がある、etc)が体験的に結びついて、赤い丸い果物という具象的な概念を抽象化したことになる。
抽象化したりんごという概念を、相手にとって認識しやすい概念に置き換えるには、相手にとってりんごとはなにか?をこちらが探って、ようやく相手に「ほら、木に生る果物で~」と言える。相手がりんごは木に生るということを知らなければ、この会話は成立しない。
つまり、数学であっても、途中式や思考途中の場面にコメントを入れておく、ということが、相手にどういうプロセスで思考したのかを示すために最低限必要な礼儀だとも言える。逆に言えば相手がこちらの概念を、どのような概念として認識しているのかを探る行為が重要だということ。
自分の考え方は自分にとって当たり前かも知れないが、他人にとっては当たり前でない事のほうが多い。とりわけ概念的な思考の扱いには注意が必要だろう。自分の概念に寄りかかって思考しないようになるには、幼少期からの教育がとても大事なのだろうと思う。
で、確率の積の法則って分数の掛け算なのだなぁ、とおもった。そんなの当たり前でしょ!って言われたら、そうなですね!って答えるしか無いのだけど、分数の掛け算ってなんだかしっくり来ない気がするんだよね。
3/4×4/5=(3×4)/(4×5)
分母同士と分子同士を掛けると答えが出る。なんでそうなるの?と。
前記事の面積の出し方で考えると、
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
● ●●●●●●●●●●●
分母同士の掛け算というのものが、総数を表していることが分かる。分子同士の掛け算は、そのうちのどの範囲なのか?を表わす。この辺をもっと上手く教えてくれる先生がいたとしたら、分数計算をもっと理解しやすくなると思うのだけど、どうでしょう?
割り算になるともっと悲惨。今更思ったのだけど、括弧付けないとダメだったね。
(3/4)/(4/5)
とかわけわからない。割る数の分母と分子を入れ替えて掛ければ良い、とかを覚えても、直感的に理解が出来ない。
A/A
であれば、答えが1であることも理解しやすい。なので、
(1/2)/(1/2)
も、同じ数同士で割っているのだから答えは1だよね、って理解出来る。
でもなんで割る数の分母と分子を入れ替えて掛ければ良いの?これって最近どこかで表題だけ読んだ気がする。それとは別だけど、
分数で割り算をする時、何で割る数をひっくり返すの? (初投稿!!)
3の、何回引けるか、という考え方は比較的理解しやすい。とても面白い考え方だと思った。
道草学習のすすめ : 分数の割り算、ひっくり返してかけるのはなぜ? ~ドラえもんグッズの威力~
割合として考える。これなんかは応用すれば面積で視覚的に説明出来そう。いやはやしかし、分数の割り算を今日始めて理解したよ(苦笑)
大事なのは発想だろうと思う。でも発想が湧かないから分からない。どうやったら発想が生まれるのか?はどうやったら教えられるのだろう。または俺自身の身につくのだろう。多くの教育者の悩みではないかと思う。
中学3年生の姪っ子は公式とかをきちんと覚えている。でも使い方が分からない。なので、問題文から読めることだけを、どれだけ簡単な途中式であっても書くようにし、その途中式が一体何なのか、注釈を入れて考えてご覧、と教えてみた。
ある意味、プログラミングと同じなのだろう。俺はプログラミングを専門的に勉強したわけじゃないので、聞きかじりと想像で書いてしまうのだけど、エクセルVBAで拙いプログラムを書いた時に、注釈を書いておくといいよ、という説明を真に受けてなるべくきちんと注釈を書くようにしておいた。
その後、プログラムを運用した際に、後から機能を付け足すときに注釈がどれだけ大切かを痛感した。プログラムにコメントを入れるのは、思考の形跡を残すことのようだ。そういえば俺がブログを書くのもそれに近い。気持ちだけで終わってるけど。
つまり、論理的な思考というものは、出来る限り視覚的に振り返ることの出来る形に残しておくことが大事だと言えるだろう。
論理的な思考が苦手な人は、論理的な思考の出来る人が、あたかも答えに向かって最短で思考しているかのように見えるようだ。少なくとも俺から見た論理的な思考の苦手な人はそう思っているように見える。論理的な思考の得意な人を倣おうとして思考手順を端折る傾向にある。そして何について思考しているのかを自分が見失う。あれ、これって俺か・・・説明出来ても実行出来ない良い例(笑)
論理的な思考をとても上手に出来る人というのは、言い換えれば途中式を書かなくても方程式が解けるくらい、頭の中が整理されているのだろう。頭のなかが整理されていない人が真似しようとしても、余計頭のなかが雑然としてしまう。教える側は、すでに整理されているから教えることが出来る。こんなところにも、分かってしまうと分からないことが分からなくなる、という穴があったわけだ。
とにかく公式を覚えなさい、計算をどんどんやって慣れなさい、というのは、まずは頭の中を整理しなさい、ということ。なぜ部屋を片付けなきゃならないのか分からず、親から部屋を片付けなさいと言われるようなもの。
倣わせるのは、頭の中の整理の仕方だろう。丸暗記や反復練習はダメだ、とは言えないだろう。丸暗記や反復練習だけではダメだろうけど。
仮説を立てる。思考のプロセスを書く。一つの方向に進む。頓挫する。
頓挫した時に戻ろうとするのだけど、仮説に対する思考のプロセスは閃きであることが多く、どこでこの思考が生まれたのかは思い出すという作業だけでは困難だろう。そこで思考の得意な人は、どこのどのタイミングでこの思考プロセスが生まれたのか、注釈しておく。
ここから先はこの分岐、だからこの分岐の先で間違っていることが判明したら、この注釈まで戻ろう、ということを、言うなればヘンデルとグレーテルのパンのような印を残す。ヘンデルとグレーテルの場合は、動物たちがパンを食べてしまったけど。
おそらく、残す目印も意識的にしないとならないのだろう。動物ではなく風が強く吹く場所であれば、重たい石で目印にした方がいい。常に最適な目印になるものがあるわけではないから、その場所の特徴をそれぞれの認識しやすい概念で置換えておく。
ただしそれは自分にとって認識しやすい概念で置換えただけなので、人に説明するときには逆の置換えが必要になる。
自分にとって認識しやすい概念を、伝えたい相手にとって認識しやすい概念に置き換えて説明する。これが会話だ。
通常、俺たちはこうした手順を無意識的に行っている。赤い丸い果物に記号名を付ける行為は、その記号名の持つ自身にとっての意味(美味しい、甘い、ちょっと酸っぱい時もある、身体に良い、皮がある、種がある、etc)が体験的に結びついて、赤い丸い果物という具象的な概念を抽象化したことになる。
抽象化したりんごという概念を、相手にとって認識しやすい概念に置き換えるには、相手にとってりんごとはなにか?をこちらが探って、ようやく相手に「ほら、木に生る果物で~」と言える。相手がりんごは木に生るということを知らなければ、この会話は成立しない。
つまり、数学であっても、途中式や思考途中の場面にコメントを入れておく、ということが、相手にどういうプロセスで思考したのかを示すために最低限必要な礼儀だとも言える。逆に言えば相手がこちらの概念を、どのような概念として認識しているのかを探る行為が重要だということ。
自分の考え方は自分にとって当たり前かも知れないが、他人にとっては当たり前でない事のほうが多い。とりわけ概念的な思考の扱いには注意が必要だろう。自分の概念に寄りかかって思考しないようになるには、幼少期からの教育がとても大事なのだろうと思う。










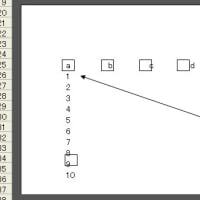
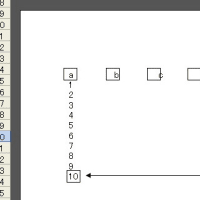
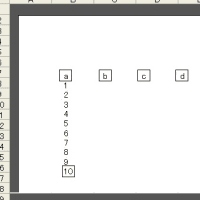





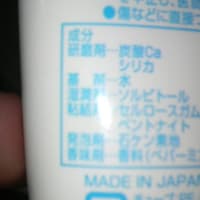
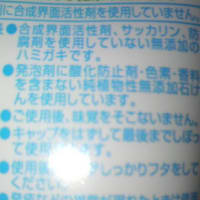
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます