http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011042300256
情報統制という声が多くなりそうですかね。
ボク個人としては、自分や自分の周りの人たちが生き延びるための“直感”のほうを大事にしています。
いちいち情報に振り回されても仕方ないです。
もちろん情報は情報として大切にしますが。
いち個人が手を繋げる命には限りがあると思っていますし、それぞれの役割を大切にしなければならないとも思っています。
それを多様性という表現に結び付けたりしています。
悲しもうが楽しもうが、人の命は有限です。
ここ10年で、ボクの身の回りでは毎年1人以上の人が亡くなっています。
娘と同い年だった子もいました。
命の終わりに決まりはありません。
命を失った時が命の終わりです。
もし、5才で亡くなった彼女の命に対して“早すぎる死”という言葉を飾り付けたら、
彼女の命の意味まで無くしてしまいそうに感じています。
彼女は5年間、毎日を精一杯楽しく生き、両親とおばあちゃんと4人で旅立ちました。
「それが運命だった」と言いたいわけではありません。
娘が生まれてしばらくして、その子を抱かせてもらいました。
亡くなってから、その子のおもちゃを戴きました。
彼女は多くに愛され、幸せでした。
それ以外に何があるでしょうか。
生きていくボクらの慰みに“早すぎる死”と形容することに意味はあります。
生きていくボクらが学ぶために“死”について考えることは大切です。
でも、彼女にとっては早すぎるも遅すぎるもあるわけがありません。
“死”が何なのか考えることもありません。
ボクらは“死”に対して怖さを感じますが、その怖さは“生”の実感であり、“死”と“生”を切り離して生きることは不可能です。
与えられた情報は、時として未来を予測させます。
予測したことでより良い未来を目指せます。
でもそれが本当に“より良い未来”かどうかは誰にも分かりません。
分からないけど、より良い未来に歩むのが人間です。
では、“今”は良い“今”ですか?
人間がより良い未来に歩く生き物であるなら、未来を迎えてない以上“今”が最良であるはずです。
もし“今”に絶望するなら、人類全体の一部であるあなたの歩く先は、同じく絶望に満ちます。
どれだけ絶望に満ちている“今”にも、“生”の喜びを感じられるなら、未来がどれだけ絶望に満ちていても、あなたは喜びに満ちた未来を迎えます。
5才で亡くなった彼女は、日々楽しく生き、ランドセルを背負い入学を楽しみに生きていました。
光に満ちた世界にいました。
ただ、亡くなってしまいました。
ボクらはどうでしょうか。
生きています。
それなのに、なぜ未来を絶望するのでしょうか。
なぜ亡くなった彼女の死を“早すぎる死”と決めるのでしょうか。
彼女は希望に満ちていた。
ボクらは絶望を感じる。
つまりですね、“死”は絶望じゃないんです。
生きているから絶望を感じるんです。
生きている以上、絶望は切り離せないんです。
未来を予測してもそこには絶望しか無く、その予測に従うか従わないかを“今”一生懸命選択することだけが大切なことなんです。
絶望するくらいなら選択するべきなんです。
その選択の先は絶望です。
でもその絶望の瞬間に、“次なる今”から“更なる未来”への選択をしなきゃならないんです。
実はこの絶望は、心の余裕から生まれているんです。
選択していないから絶望するんです。
今やるべきことと、未来への距離感が絶望で、距離感を測る暇なんて、懸命な選択肢の中にはありません。
情報を過信し過ぎてないか?自分に問います。
その情報は未来を選択する材料にすぎないです。
材料に振り回されるくらいなら、材料なんていらないです。
もし材料を得たなら、自分の直感で感じて選択していきたいです。
繰り返していくと、世の中の情報と自分の直感が、いかに乖離しているか実感します。
生きるって、その実感がスタートラインなんじゃないかと思っています。
選択肢に圧迫されて苦しむのではなく、選択肢の先にある未来への“今”を楽しむことが、“幸せ”なんだと思います。
※うまくまとまりませんでした。
毎日毎日働いて、薄っぺらな給料から支払い支払いで、その1ヶ月が来月もきて、繰り返されて1年2年と過ぎていく。
そんな考え方はつまらないです。
そうしたうわべの生活よりも、自分に与えられた環境の中で自分だけの文化を育むことのほうが、生きている実感が湧きそうだと感じました。
日本の文化ってそうやって作られてきたはずです。
抑圧されたり、自然から打ちのめされたり、飢餓に苦しんだり、
日本の島国という閉鎖的な環境が、外部から奪うのではなく与えられた環境で生きる知恵に特化した風土を作っているのです。
グローバルに開かれた世界の中で失った日本の良さを見直す方向、拡大する経済から豊かさを見出だすのではなく、循環する経済が日本人の心の豊かさに繋がるのだと思います。
その社会と、グローバルな世界の中で平準化されていく“情報”とがどうやって並列していくか、
前哨戦として、原発の“推進”と“反対”が“日本の愚かさと良さ”を“日本の賢さと悪さ”に換えた象徴ではないかと感じます。
愚かに日々を慎ましやかに。
起きたことも慎ましやかに。
起きることも愚かに。
情報統制という声が多くなりそうですかね。
ボク個人としては、自分や自分の周りの人たちが生き延びるための“直感”のほうを大事にしています。
いちいち情報に振り回されても仕方ないです。
もちろん情報は情報として大切にしますが。
いち個人が手を繋げる命には限りがあると思っていますし、それぞれの役割を大切にしなければならないとも思っています。
それを多様性という表現に結び付けたりしています。
悲しもうが楽しもうが、人の命は有限です。
ここ10年で、ボクの身の回りでは毎年1人以上の人が亡くなっています。
娘と同い年だった子もいました。
命の終わりに決まりはありません。
命を失った時が命の終わりです。
もし、5才で亡くなった彼女の命に対して“早すぎる死”という言葉を飾り付けたら、
彼女の命の意味まで無くしてしまいそうに感じています。
彼女は5年間、毎日を精一杯楽しく生き、両親とおばあちゃんと4人で旅立ちました。
「それが運命だった」と言いたいわけではありません。
娘が生まれてしばらくして、その子を抱かせてもらいました。
亡くなってから、その子のおもちゃを戴きました。
彼女は多くに愛され、幸せでした。
それ以外に何があるでしょうか。
生きていくボクらの慰みに“早すぎる死”と形容することに意味はあります。
生きていくボクらが学ぶために“死”について考えることは大切です。
でも、彼女にとっては早すぎるも遅すぎるもあるわけがありません。
“死”が何なのか考えることもありません。
ボクらは“死”に対して怖さを感じますが、その怖さは“生”の実感であり、“死”と“生”を切り離して生きることは不可能です。
与えられた情報は、時として未来を予測させます。
予測したことでより良い未来を目指せます。
でもそれが本当に“より良い未来”かどうかは誰にも分かりません。
分からないけど、より良い未来に歩むのが人間です。
では、“今”は良い“今”ですか?
人間がより良い未来に歩く生き物であるなら、未来を迎えてない以上“今”が最良であるはずです。
もし“今”に絶望するなら、人類全体の一部であるあなたの歩く先は、同じく絶望に満ちます。
どれだけ絶望に満ちている“今”にも、“生”の喜びを感じられるなら、未来がどれだけ絶望に満ちていても、あなたは喜びに満ちた未来を迎えます。
5才で亡くなった彼女は、日々楽しく生き、ランドセルを背負い入学を楽しみに生きていました。
光に満ちた世界にいました。
ただ、亡くなってしまいました。
ボクらはどうでしょうか。
生きています。
それなのに、なぜ未来を絶望するのでしょうか。
なぜ亡くなった彼女の死を“早すぎる死”と決めるのでしょうか。
彼女は希望に満ちていた。
ボクらは絶望を感じる。
つまりですね、“死”は絶望じゃないんです。
生きているから絶望を感じるんです。
生きている以上、絶望は切り離せないんです。
未来を予測してもそこには絶望しか無く、その予測に従うか従わないかを“今”一生懸命選択することだけが大切なことなんです。
絶望するくらいなら選択するべきなんです。
その選択の先は絶望です。
でもその絶望の瞬間に、“次なる今”から“更なる未来”への選択をしなきゃならないんです。
実はこの絶望は、心の余裕から生まれているんです。
選択していないから絶望するんです。
今やるべきことと、未来への距離感が絶望で、距離感を測る暇なんて、懸命な選択肢の中にはありません。
情報を過信し過ぎてないか?自分に問います。
その情報は未来を選択する材料にすぎないです。
材料に振り回されるくらいなら、材料なんていらないです。
もし材料を得たなら、自分の直感で感じて選択していきたいです。
繰り返していくと、世の中の情報と自分の直感が、いかに乖離しているか実感します。
生きるって、その実感がスタートラインなんじゃないかと思っています。
選択肢に圧迫されて苦しむのではなく、選択肢の先にある未来への“今”を楽しむことが、“幸せ”なんだと思います。
※うまくまとまりませんでした。
毎日毎日働いて、薄っぺらな給料から支払い支払いで、その1ヶ月が来月もきて、繰り返されて1年2年と過ぎていく。
そんな考え方はつまらないです。
そうしたうわべの生活よりも、自分に与えられた環境の中で自分だけの文化を育むことのほうが、生きている実感が湧きそうだと感じました。
日本の文化ってそうやって作られてきたはずです。
抑圧されたり、自然から打ちのめされたり、飢餓に苦しんだり、
日本の島国という閉鎖的な環境が、外部から奪うのではなく与えられた環境で生きる知恵に特化した風土を作っているのです。
グローバルに開かれた世界の中で失った日本の良さを見直す方向、拡大する経済から豊かさを見出だすのではなく、循環する経済が日本人の心の豊かさに繋がるのだと思います。
その社会と、グローバルな世界の中で平準化されていく“情報”とがどうやって並列していくか、
前哨戦として、原発の“推進”と“反対”が“日本の愚かさと良さ”を“日本の賢さと悪さ”に換えた象徴ではないかと感じます。
愚かに日々を慎ましやかに。
起きたことも慎ましやかに。
起きることも愚かに。










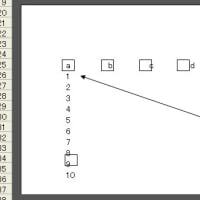
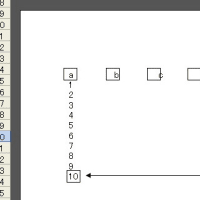
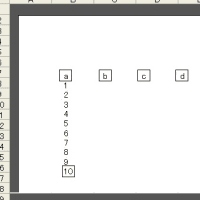





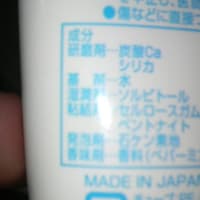
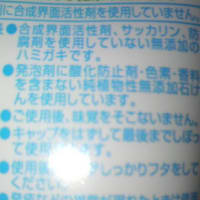
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます