現在の経済は連動経済です。
いやまぁ経済ってのはそもそも連動するんですが(笑)
でも、あまりに物理的距離の遠い地域の良し悪しが、今夜のボクの晩のおかずの良し悪しに影響するような経済(たとえばの話です)、
つまりはこれが金融経済の特徴だと思います、そうした影響の複雑化で安定させてきた経済には限界があるのでしょう。
ボクは、ぼやっとした構想として「ライフ・マイレージ」という造語を考えます。
フードマイレージは言わずもがなざっくり言えば「地産地消」です。(本来は食品の流通距離を意味する)
ライフマイレージとは、ざっくり言えば「生きるを傍に」です。
別の言葉では「自己完結と自己完結の助け合いというコミュニティ」です。
いいんです、まだ口だけです(笑)
「生きる」という最小単位は食事だと思います。
食事をする(=生きる)ためには働かなければなりません。
食品を生産する人ばかりではないので交換経済を原点に、派生に派生を重ねて今の経済システムができました。
その過程で食品の流通は安定し、人間は食事以外に頭を使う余裕が生まれました。(少し語弊あります。この余裕が生まれたのは経済強者、先進国です。)
同時に、食事に対する意識が薄れ、食事が=生きることに直結しているのにもかかわらず、その部分を他人に丸投げして生きています。
働いてお金を稼げば食品を買えますが、それはシステムという入れ物でして、システムが破綻した時やシステムから外れてしまった時に食事が出来なくなる(=生きていけない)ことは、大変問題があるのです。
お金があれば食事をできる、でもお金が無くなったら?お金に価値が無くなったら?食品を売ってくれなくなったら?食品が生産されなくなったら?
こうした不安を払拭する一番の方法は全員が食品生産に関わることですが、しかし今さらそうした状況に至るのは無理があります。
そこで次善策として「ライフマイレージ」という考え方になるのです。
たとえば生産者と消費者が契約を結び安定した需給を目指すことなどは、ライフマイレージという考え方にかなり近い状態です。
ここで、生産者→消費者に流れる「食品」と、消費者→生産者に流れる「お金」
消費者から生産者に、お金ではない価値を払う社会を考えます。
え!?物々交換?って話しになりますが、ベースはそれに近いです。
ようは小さなコミュニティの中で、それぞれが自分の食事を自分で・または限りなく自分の近くで調達し限りなく自己完結を目指す。
その中で足りない部分を互いに補完し合う、そうした、ある意味現在でも行われている田舎の風景のような。
「あ、玄関に芋がある。こりゃ誰々さんが置いてってくれたな。よし、うちは誰々さんとこに大根持っていくべ。」
そんな社会。
「あ、玄関にプレステ3が置いてある!こりゃソニーさんが置いてってくれたな!よしうちはプリウスを誰々社に(略)」
ほのぼのしません?(笑)
お金が介在することは利便性を著しく高めますが、弊害もあります。
その弊害に直面しているのが現在のグローバルであるなら、ボクら末端の、切り捨てられてもおかしくない下々民はですね、「生きる」を誰かに握られちゃいけないのです。
もちろんある程度握られた「振り」は大事。というか握られずに生きるのは多分無理。
だからある程度搾取されることは容認する。
でも、「生きる」を完全に握られちゃいけないと思います。
自分一人で生きていく覚悟の中で誰かと助け合うのと、自分の「生きる」を完全に握られた状態で誰かと助け合うのとでは、バランス強度がだいぶ違うと思うんです。
結局、バランス強度をグローバル化に求めた経済は、「生きる(ここでの生きるはお金)」を地球の裏側の企業に握らせ、自分もどこか遠くの企業の生きるを握っているからおかしなことになるのだと思うのです。
日本がこれからも日本としてやっていく秘訣・秘策として、全員が「それ」をやっちゃいけない。
「それ」をやる人はある程度搾取される。
しかし、全体の利益で考えた場合、ライフマイレージという「生きるを自分の傍に」置く発想を持つことは極めて大事ではないかと。
まだ朧気なんで言葉にすると脆弱ですが、うっすらとした構想を膨らませて楽しんでます(笑)
拍手ボタン
いやまぁ経済ってのはそもそも連動するんですが(笑)
でも、あまりに物理的距離の遠い地域の良し悪しが、今夜のボクの晩のおかずの良し悪しに影響するような経済(たとえばの話です)、
つまりはこれが金融経済の特徴だと思います、そうした影響の複雑化で安定させてきた経済には限界があるのでしょう。
ボクは、ぼやっとした構想として「ライフ・マイレージ」という造語を考えます。
フードマイレージは言わずもがなざっくり言えば「地産地消」です。(本来は食品の流通距離を意味する)
ライフマイレージとは、ざっくり言えば「生きるを傍に」です。
別の言葉では「自己完結と自己完結の助け合いというコミュニティ」です。
いいんです、まだ口だけです(笑)
「生きる」という最小単位は食事だと思います。
食事をする(=生きる)ためには働かなければなりません。
食品を生産する人ばかりではないので交換経済を原点に、派生に派生を重ねて今の経済システムができました。
その過程で食品の流通は安定し、人間は食事以外に頭を使う余裕が生まれました。(少し語弊あります。この余裕が生まれたのは経済強者、先進国です。)
同時に、食事に対する意識が薄れ、食事が=生きることに直結しているのにもかかわらず、その部分を他人に丸投げして生きています。
働いてお金を稼げば食品を買えますが、それはシステムという入れ物でして、システムが破綻した時やシステムから外れてしまった時に食事が出来なくなる(=生きていけない)ことは、大変問題があるのです。
お金があれば食事をできる、でもお金が無くなったら?お金に価値が無くなったら?食品を売ってくれなくなったら?食品が生産されなくなったら?
こうした不安を払拭する一番の方法は全員が食品生産に関わることですが、しかし今さらそうした状況に至るのは無理があります。
そこで次善策として「ライフマイレージ」という考え方になるのです。
たとえば生産者と消費者が契約を結び安定した需給を目指すことなどは、ライフマイレージという考え方にかなり近い状態です。
ここで、生産者→消費者に流れる「食品」と、消費者→生産者に流れる「お金」
消費者から生産者に、お金ではない価値を払う社会を考えます。
え!?物々交換?って話しになりますが、ベースはそれに近いです。
ようは小さなコミュニティの中で、それぞれが自分の食事を自分で・または限りなく自分の近くで調達し限りなく自己完結を目指す。
その中で足りない部分を互いに補完し合う、そうした、ある意味現在でも行われている田舎の風景のような。
「あ、玄関に芋がある。こりゃ誰々さんが置いてってくれたな。よし、うちは誰々さんとこに大根持っていくべ。」
そんな社会。
「あ、玄関にプレステ3が置いてある!こりゃソニーさんが置いてってくれたな!よしうちはプリウスを誰々社に(略)」
ほのぼのしません?(笑)
お金が介在することは利便性を著しく高めますが、弊害もあります。
その弊害に直面しているのが現在のグローバルであるなら、ボクら末端の、切り捨てられてもおかしくない下々民はですね、「生きる」を誰かに握られちゃいけないのです。
もちろんある程度握られた「振り」は大事。というか握られずに生きるのは多分無理。
だからある程度搾取されることは容認する。
でも、「生きる」を完全に握られちゃいけないと思います。
自分一人で生きていく覚悟の中で誰かと助け合うのと、自分の「生きる」を完全に握られた状態で誰かと助け合うのとでは、バランス強度がだいぶ違うと思うんです。
結局、バランス強度をグローバル化に求めた経済は、「生きる(ここでの生きるはお金)」を地球の裏側の企業に握らせ、自分もどこか遠くの企業の生きるを握っているからおかしなことになるのだと思うのです。
日本がこれからも日本としてやっていく秘訣・秘策として、全員が「それ」をやっちゃいけない。
「それ」をやる人はある程度搾取される。
しかし、全体の利益で考えた場合、ライフマイレージという「生きるを自分の傍に」置く発想を持つことは極めて大事ではないかと。
まだ朧気なんで言葉にすると脆弱ですが、うっすらとした構想を膨らませて楽しんでます(笑)
拍手ボタン










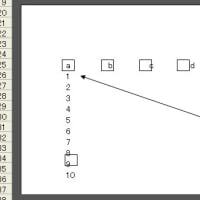
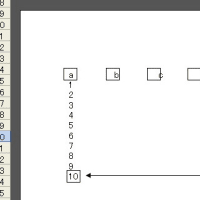
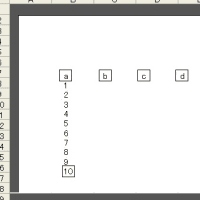





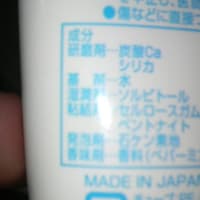
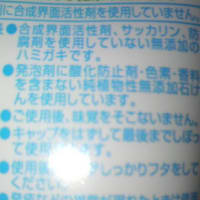
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます