「売られている正月飾りから」を年末から正月にかけて記したが、年末に店頭を賑わしていた正月飾りも、初売りにはすべて姿を消した。そんななか、駒ヶ根市のカインズーホームに仕事始めに立ち寄ると、「どんど焼き」と掲げた商品コーナーが入口で目に入った。もちろん正月飾りに比較すればそのスペースも狭く、商品も少なかったが、「何が並んでいるのだろう」と見てみると、鉄網がその主役であった。ようは餅を焼くための網であって、かつてのどんど焼きなら用品らしからぬものも、今はどんど焼きの定番なのか、と思わせるような印象をもった。ほかには着火用のライターが並んでいたが、「これは」と思うような「どんど焼き」用品は見つけられなかった。よそでもこうしたどんど焼きコーナーがあるのか、と少し注目してみたが、同じカインズでも他店には見られなかった。「駒ヶ根らしさ」なのかどうかはわからない。
実は、正月飾りが売られていた年末に、既に小正月用品が売られている姿を見ている。唯一であったが、松川町のホームセンター「すまいる」の正月飾りを販売している一角にそれを見た。年が開けると正月用品は撤去され、小正月用品だけ残されていたわけであるが、おそらくこのあたりの特徴を表す店頭の姿だろう。その光景はこんな感じだ。

たったひとつの棚ではあるが、前述の「どんど焼き」商品に比較すると、まさに小正月らしさを見せている。「本やり飾り付け用品」と掲げられた商品札を上段から羅列してみよう。
〇ゴムふうせん
〇おはながみ(6色セット)
〇おはながみ(五色鶴 単色500枚入り 赤、桃、黄、橙、黄緑、緑、青、水色、紫、白、黒)
〇おりがみ(「徳用」と「教育」)
〇紙風船(6枚入り 本槍の飾り付けに)
〇カラー紙テープ(5色組)
〇カラー紙テープ(10色 10巻入り)
〇フジロンパール障子紙(美濃判28×90cm 22枚入り へい束を作るのにおすすめです)
〇御中折紙(約25.2×30.3cm 20枚入り お飾りやお供えの敷き紙などに)
〇麻ひも単品
〇麻ひも&丸扇セット
〇踊り傘(藤うず巻φ82cm 本やりの飾り付けにどうぞ)
〇和傘(無地 φ84cm 本やりの飾り付けにどうぞ)
〇牡丹紅炮(20連×10箱)
〇牡丹紅炮(20連)
そもそも「本やり」とは上伊那南部から下伊那北部にかけてのどんど焼きの呼称で、通常は「ほんやり」、あるいは「ホンヤリ」と書く。「本やり」と明示されていると、知っている人は分かるが、知らない人は何のことかわからない。これら商品、実はホンヤリエリアにおいても、花紙や紙テープ、あるいは紙風船はあまり使わないところも多く、極めつけが傘である。傘をホンヤリで使うところは限定される。それがここでは用品棚に並ぶというのだから、いかにこの地域らしさが出ているかがわかる。










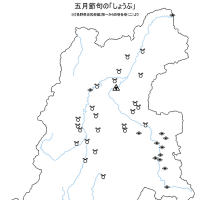
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます