萱岡雅光氏は『西郊民俗』218・219号(西郊民俗談話会)において「都市祭礼の魅力と存続-砺波夜高祭の事例報告-」と題してた論文を発表している。夜高祭はいくつもの行灯を山車のように作り上げ、それを車輪のついた台に載せて曳く祭りで、ネプタとかキリコといった祭りに共通するものと言われている。祭りそのものを見たことはないものの、わたしが最も興味を抱いたのは、この祭りが“おさなぶり”、いわゆる田植後の農休みに行われていることである。砺波平野一帯で行われていると言われるこのまつりの起源伝承として萱岡氏は次のような例を引いている。「承応二年に、福野(現南砺市)で神明社が建てられ、伊勢から分霊を迎える際に分霊を載せた一行が倶利伽羅峠に差しかかったところで、日暮れになった。その時に村人が行灯を持って迎えた」といい、それが発展したものだという。起源となった福野町の場合はさなぶりと直接は無関係だったかもしれないが、周囲に広まった背景には植えつけの終わった一休みの楽しみであったと部外から察するわけである。行灯は毎年作り変えられることから、製作期間が必要になるわけで、短いところで1カ月、長いと4カ月もこの祭りのために準備をすることになる。萱岡氏は夜高祭の伝承伝播に着目するのではなく、祭りが継承されていく背景に着目し、人々の祭りとの関わり方を明らかにしようと試みている。
砺波夜高祭は礪波市中心部の出町で行われるもので、「出町の夜高」とも呼ばれている。毎年6月第2金・土曜日の2日間行われるもので、2日間の人出は6万人にも及ぶという。曳きまわす山車のことを「ヨータカ」と呼ぶようで大行灯小行灯合わせて20ほどのヨータカが曳きまわされる。もともとは各町内ごとに曳かれていたものが戦後間もないころから集まって曳きまわされるようになったものという。そしてヨータカ同士のぶつかり合いがが各所で行われたというが、後に商工会が関わるようになって曳きまわしは指定されるようになり、ぶつかり合いも指定の場所で行なわれるようになったという。起源伝承から風流として発展したものは、時の規制に合わせて変化してきたわけで、都市の祭らしい発展と言えるだろう。そして都市においても起きるのが継承という問題である。継承という視点に立って砺波夜高祭で行灯を曳きまわす町から、三つの例をあげて萱岡氏は比較する。
その前に少し砺波夜高祭の立ち位置のようなものに触れておこう。起源となったとも言われる福野町の夜高祭では行灯の製作や、曳きまわしに外部の者が加わるということはほとんど無いという。もし関わったとしても縁のある人たちということになるだろう。さらには派手な演出行為も避けることとしている。例えばドライアイスを吐かせるとか拡声器を使うということもしない。簡単に言えば古式を伝統的に伝える福野町夜高祭に対して、自由な変化を許容する砺波夜高祭ということになるだろうか。行灯に塗られる色の種類が砺波のものは最も多いという。したがって福野町の人々にしてみれば砺波のものは「祭ではなく薄っぺらいイベント」ということになる。
続く











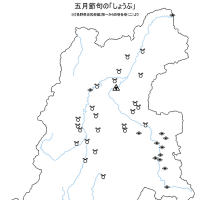















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます