昨日は「囃子舞台」について触れたが、そもそも呼称が適正かどうかは何とも言えない。「囃子と舞台」とした方が良かったかもしれない。舞台のことについて悉皆調査で触れられておらず、また囃子には舞台曳行用のものがあることにも触れられてはいない。もちろん「とりさし」についても一切記載はない。では記載のあった獅子舞について、ここでは触れることにする。
「とりさし」が午後8時に始まり、10分ほどで終わり「とりさし」が踊られた舞台上で獅子舞となる。最初は頭と幌持ちの二人で舞始めとなる。幌持ちが幌を高く持ち上げで左右に頭を振る。5分ほどの舞である。次いで頭一人になって右手に幣束、左手に鈴を持って舞台を左右に動き払うような所作で舞う、いわゆる悪魔払いである。数分すると『長野県の民俗芸能―長野県民俗芸能緊急調査報告書―』の悉皆調査にも記されていた「火吹き」が登場する。ひょっとこの面を付け、両手に短い細い棒を持って滑稽に獅子と相対する。火吹きが獅子と絡むのは1分余のこと。再び幌持ちが獅子頭の後ろに入ると、蚤取りを舞って舞納めとなる。最後の部分が『長野県の民俗芸能―長野県民俗芸能緊急調査報告書―』でいう「終舞」なのかもしれないが、区切りはない。15分ほどの獅子舞である。「殿野入春日神社囃子舞台」でも記した通り、時間にすれば午後7時に始まった囃子の方が遥かに長い。舞台に伴う囃子、そして「とりさし」、最後に獅子舞と続くが、果たして過去の姿がどうであったかは定かではないが、舞台曳行と獅子舞は、ここでは別物と捉えられる。その上で「とりさし」の位置づけは、となるが地元でも「とりさし」が獅子舞の付属物とは考えていない。舞を行うための立派な舞台があることからも、かつての芸能祭の一連の中に仕組まれたそれぞれの芸だったと捉えれば、やはり別のものという捉え方で良いのだろう。そう捉えると『長野県の民俗芸能―長野県民俗芸能緊急調査報告書―』における悉皆調査には不備があるとも言えそうである。






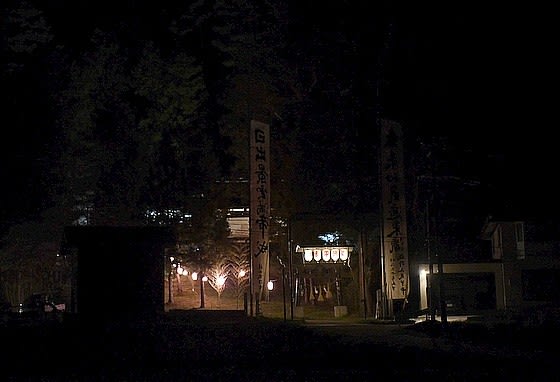
令和6年4月13日撮影











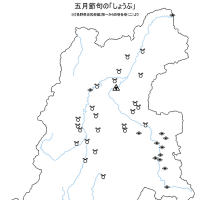















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます