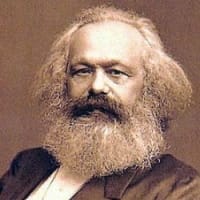本ブログ 総目次へ戻る
このカテゴリの目次へ戻る
この間の物価上昇を日銀の異次元金融緩和のせいにする議論がある。円安は日米金利差のせいだから日銀が金利を上げて円安を「是正」すべきだ、という議論である。幸いなことに専門家集団である日銀はそのような議論には耳を貸す気配はない。(*この問題は文末に取り上げる)
では日銀は何を見ているのだろうか?
まずは消費者物価指数(総合)は以下の通り。2022年に急上昇した消費者物価は2023年になって落ち着き最近は下降気味である。

次は消費者物価と正社員の新規求人数と為替の関係。2022年12月からのものである。

新規求人数と物価には弱い「正の相関」があり、2023年に限れば為替と物価には、それより強い「負の相関」があることが見てとれる。
次は物価を財とサービスに分けたもの。

財は為替の影響を大きく受けるが、国内でほぼ完結しているサービス業は為替の影響を受けにくい。しかもサービス物価の大半は賃金である。コロナでマイナスとなり、ようやく2023年の7月になって元の水準に戻している。
次は正社員の新規有効求人倍率。新規とは直近一ヶ月の新規求人・求職だ。

コロナからの回復はリーマンショックらの回復に比べて早いが、この間の為替による物価上昇でいったん停滞している。
統計が出そろったので・・・金融緩和の出口論 続き
では、半ばネタとして
「X=424,400となる。5月の正社員新規求人件数(季節調整値)は404,397人だから2万人求人件数が増えればCPI=2%という目標を達成できることになる」と指摘したがあながちネタでもないようである。未だに40万人前後でウロウロしている。
最後に賃金を見る。
毎月勤労統計の所定内賃金である。

2022年から顕著になった所定内賃金の上昇傾向が2023年も続いている。
現在の物価上昇は外在的な為替と内在的な労働力のひっ迫による賃金の上昇という二つの原因がある。これは日銀の見立てでもある。
外在的な要因がにぶり、内在的な要因へとバトンをタッチしつつあるというのが筆者の見立てである。この賃金上昇が続くかどうかは、実は財政のあり方にかかっている。一国で不可避的に発生する「余剰資金」を財政がいかに吸収するのかにかかっているのだ。
日銀の金利政策は今が踏ん張りどころ。賃金が上昇傾向を見せているのに金融引き締めに転じたら、それこそ今まで何をしてきたか分からない。
金融政策だけで景気をどうこうすることはできない。ここは財政の頑張りだ。「PB達成少し後ろに倒す」と囁けばいいのだ。
求められているのは金融政策と財政の協調である。右手と左手が別のことをやっていた「アベノミクス」からの最終的決別だ。
文頭の注:
*金利操作によって、例えば1ドル=100円に固定しようとするのは、「金本位制への復帰」と同じことである。まともに経済学を学んだ者には一顧だに値しない主張だ。このあたりはケインズの「ケインズ説得論集,日経新聞出版社,2010」に詳しい。
あわせて「デフレ不況をいかに克服するか ケインズ1930年代評論集、文藝春秋」もお勧めする。