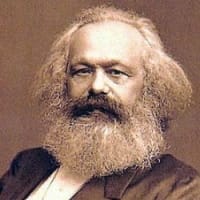第2節 商品に体現された労働の二重の性格
一見したところでは、商品というものは使用価値と交換価値という二つの物の組み合わせに見える。のちに、労働もまた商品と同じ二つの性質を持っていることが分かってくる。それは労働が価値に表現されている限りにおいてであって、使用価値の創造者としては同じ特質は持っていないのだが。私は、まず最初に商品に含まれる労働のこの二重の性格を指摘し批判的に分析した。この観点は政治経済学の理解の明確な転換点となるから、より詳細に分析せねばならない。
1着の上着と10ヤードのリネンという二つの商品をとってみよう。前者は後者の2倍の価値があるとすると10ヤードのリネン=W、上着1着=2Wとなる。
上着は特定の欲求を満たすための使用価値である。それは特定の種類の生産活動の結果として、その目的、作業の態様、素材、手段、結果によって決定された結果として存在している。生産物を使用する中で生まれる有用性を作り出す労働、価値を与えることで自らを表す労働、これを有用労働と呼ぼう。この関連の中ではわれわれは労働の有用性のみを考慮する。
上着とリネンは定性的に二つの違う使用価値を持っている。同じように二つの違う形態の労働が二つの物を作る。縫製と紡績である。二つの物が定性的に違わず、各々が違う種類の労働によって生産されているのでなかったら、二つの物はお互いに商品関係であることはできない。コートはコートと交換できず、一つの使用価値は同じ種類の他の使用価値と交換されることはない。
使用に供したときに生じるさまざまに違った価値の種類は、分類学上の目、属、種のように社会的分業の中のどこに属しているかに応じて分類された有用労働の様々な種類に対応している。分業は商品生産にとって必須のものである。かといって逆に商品生産は分業にとって必須とは言えない。原始的なアメリカ先住民の共同体では社会的分業は商品生産なしに行われていた。または、身近な例をとれば、全ての工場で労働は編制によって分割されているが、従事者相互の個人的生産物がお互いに交換されることによってこの分業が動いているわけではない。生産物がお互いにとって商品となるのは、違う種類の労働の結果であり、あらゆる種類はお互いが独立して実行されており、かつ私的個人の利益のためだからである。
まとめるならば、あらゆる商品の使用価値は有用労働、すなわちある特定の生産活動を特定の目的をもって働かせるような有用労働を含んでいる。商品に体現された有用労働が定性的にお互いに違っているかぎり、使用価値は商品としてはお互いに対立しないのである。生産物が一般的に商品の形態を取るような社会では、すなわち商品生産者の社会では、個人生産者によって営まれている、彼ら自身の利益のための独立した労働の有用形態の定性的違いが、一つの複合的体系、すなわち社会的分業へと発展するのである。
ともかく、上着は仕立屋が着ようとその顧客が着ようとその使用価値を果たす。しかし、上着とその労働の関係についてはそうではない。社会的分業の独立した一部門として縫製業が特別な職業となっているような環境の下では、上着とそれを生産する労働の関係は、使用価値と同じではない。衣服が必要なところでは、人類は何千年にもわたって仕立屋という職業なしに衣服を作ってきた。しかし上着とリネンは、他の全ての物質的財と同じように自然が自動的に作り出したものではなく、その存在を、特定の目的をもって営まれ、特定の天然資源を人間の特定の欲求に適合させるような活動、すなわち特別な生産活動によっている。それゆえ労働は使用価値の創造者である限り、有用労働となる。これはどのような社会形態を取ろうとも人類の存在にとっての必要条件である。またこれは、それなしには人間と自然との間の物質循環もあり得ず、それゆえ生命も存続しえない、自然によって負わされた永遠の必然性である。
上着やリネン等々の使用価値、すなわち商品の本体は二つの要素―物質と労働―の組み合わせである。いまもし使用価値から有用労働を取り去ってしまうと、人間の助けなしに自然によって形成された物質的土台のみが残る。この物質的土台は物質的形態が変わっていたとしても自然と同じようにしか働かない。それどころか形態を変えるという作業さえ自然の力の助けを借りている。要は、労働は物質的富の唯一の源泉ではなく労働が作り出した使用価値の唯一の源泉でもない。ウィリアム・ペティが主張したように、労働は富の父であり大地は母なのである。
いよいよ商品の使用価値の側面から商品の価値へと分析の対象を移していこう。
われわれは上着はリネンの二倍の価値があると仮定した。しかしこれは単なる量的違いに過ぎず今となってはわれわれの対象ではない。が、上着の価値が10ヤードのリネンの二倍なら、20ヤードのリネンは上着と等価であるということになろう。上着とリネンが価値を持つかぎり、上着とリネンは、本質的には同質の労働の客観的表現である実体のようなものである。しかし縫製と紡績は定性的には別種の労働である。が、同じ人が縫製も紡績もこなし、二種類の労働が同じ個人の労働の調整の違いに過ぎず、各個人に特定の固定された機能がふられておらず、ある日には上着を作り、別の日にはズボンを作っているだけのような社会の状態では、労働は個人の労働の様々な変化に過ぎなくなる。さらに言えば資本主義社会では、様々な需要に従って、人間の労働の所与の割合が縫製や紡績の形態に割り振られていることは明白である。この変化は軋轢なしには生まれなかったろうが、必然のものでもある。
生産活動は、その特有の形態すなわち労働の有用性を捨象すれば、人間の労働力の投入に他ならない。縫製も紡績も、生産活動としては定性的には違っていても、等しく人間の頭脳、神経、筋肉の投入であり、その意味で人間の労働である。二者は人間の労働力の異なった投入の仕方である。もちろん、どのように変容していようと同じものであるこの人間の労働力は多様な態様で投入することができるように発展のある段階に到達していなければならない。しかし商品の価値は、抽象的概念としての人間の労働、その人間の労働の支出を表現している。そして、それはちょうど社会において将軍や銀行家が重要な役割を果たしている一方、とるに足らない人間はお粗末な役割しか果たしていないが、単なる人間の労働も同じようにお粗末な役割しか果たしていないのである。それは単純な労働力の支出であり、すなわち平均的な、いかなる特定の習熟(any special development)からも切り離された、誰でも普通の人間なら持っている器官に存在する労働力の支出である。単純な平均的労働力は異なった国々、時代によって様々な性格を持つのは当然であるが、特定の社会では所与のものとなる。熟練労働は単純労働を強化したものと、またはさらに言えば単純労働をかけ合わせたものとみなされる。所与の量の熟練労働はより大きな量の単純労働と等価だとみなされるのだ。経験はこの分解が日常的に進行していることを教える。もっとも熟練した労働の生産物である商品も、その価値において一定量の単純な非熟練労働の生産物と等しくなる。種々の労働が標準的な非熟練労働へと分解されていく種々の割合(分解の進行度)は生産者の背後で不断に進行し、社会的過程を通して確立されていき慣習によって固定されていく。単純化のために、これからはあらゆる種類の労働を非熟練単純労働とみなそう。これによっていちいち単純労働へと還元する煩わしさから逃れられる。
異なる使用価値から抽象された価値として上着とリネンを見た場合、その価値によって表された労働も紡績と縫製という有用な形態の違いを無視して構わないだろう。使用価値としては上着とリネンは布地と糸の特別な生産活動の組み合わせである。一方、価値としては上着とリネンは、区別のつかない労働の等質的な凝固物に過ぎない。後者の価値に体現された労働は布地と糸の生産的関係の効用としては認識されず、人間の労働力の投入対象として認識されるだけである。
縫製と紡績は上着とリネンという使用価値の創造に当たって不可欠の要素である。縫製と紡績は異なった性質の二種類の労働であるが、その特殊な性質から抽象されるかぎりにおいて、人間労働という等質性を持つかぎりにおいて縫製と紡績は同種の価値の実体をなす。
しかし、上着とリネンは単に価値であるだけではなく、ある尺度を持った価値である。先ほどは一着の上着は10ヤードのリネンの倍の価値があると仮定した。この価値の違いはなんだろうか?これはリネンには上着の半分の労働しか含まれていない、したがって後者の生産においては労働力は前者の生産に必要な時間の二倍投入されているということである。
それゆえ、使用価値に関しては商品に含まれる労働は定性的に勘定されるのに対して、価値としては定量的に、人間労働を純粋な単純な量に分解されて勘定される。前者の場合は「いかに」「何を」という問題なのに後者の場合は「いくら」「何時間」という問題なのだ。商品の価値の尺度は、そこに体現される労働の量にのみ表されるので、全ての商品はある割合を取れば全て等価となる。
上着を生産するのに必要な全ての様々な異なった種類の有用労働の生産力に変化がないとすれば、上着の価値はその生産数に応じて増えていくだろう。一着の上着を作るのにX日かかるとすると二着の上着には2X日かかる等々。ここで上着の生産に必要な労働の期間が二倍あるいは半分になったとしよう。最初の場合は以前の場合の二倍の価値があることになり、二番目の場合は二着の上着が以前の上着と同じ価値ということになる。しかしどちらの場合も同じ有用性を提供しており、上着に体化された有用労働は同じ質を持っているのだが。その生産に投入された労働量は変化したのである。
使用価値の量的増加は物質的富の増加である。二着の上着は二人の人に着せることができるが、一着の上着は一人だけである。しかし物質的富の増大は、同時にその価値の下落を意味するかもしれない。この矛盾する動きは労働の性質の二つの側面にその起源を持っている。もちろん労働が物を作り出す力は、労働の具体的有用性、生産量に比例した所与の時間の特定の生産的活動の結果に由来している。それゆえ有用労働は、その生産性の増加や減少に応じて生産物の豊富な源泉も上下に変化するのだ。他方で、この生産性のいかなる変化も価値で表された労働には影響を及ぼさない。というのは生産力は労働のある決まった有用性の形態の賜物であるが、有用性の形態から抽象を行った途端、労働のその形態とはもはや何の関係も持たないからである。物を作り出す力は多様であるかもしれないが、同じ労働、同じ時間持続した労働は同じ価値をもつ。しかし、同じ期間の労働も、物を作り出す力が向上すれば増え、落ちれば減るように、違った価値を持つだろう。労働の収穫を増大させ結果として労働の生産物である使用価値の量も増大させるような生産力の変化は、増大した使用価値の量の価値総額を減少させるだろう。そのような変化が生産に必要な労働時間を短縮するなら。そして逆もまた真なのである。
一方で、全ての労働は、生理学的な意味で、人間の労働力の支出であり、その等質な抽象的人間労働という性格の中で商品の価値を創造し形成している。一方では全ての労働は、特定の形態、特定の目的、具体的有用労働という性格の中で商品の使用価値を生産しているのだ。