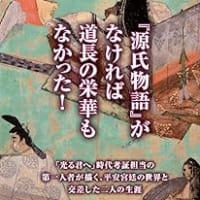宇治が京に暮らす貴族たちの別業地になったのは、源融が宇治に別荘を構えて以降と言われる。源融といえば源氏物語の光源氏のモデルと言われる人物、源氏物語には宇治十帖があり、宇治が物語のメイン舞台となる。その時代に栄華を極めていたのが藤原道長、頼通で宇治の別業を平等院という寺として設営、末法に備えた。本書では別業地、源氏物語、平等院という切り口から宇治を捉えている。
京に遷都して以来数十年経過すると、京の街には変化が生まれた。1.左京に比べ右京は湿地が多く早くに廃れてしまった。(当時の朱雀大路、現在の千本通より西側は明治になる頃まで人家はまばらだった。) 2.左京でも四条以北に人家は集中していた。(京都の街は全体として北が高く南が低いため南は湿気が多い。今出川通の標高は東寺の塔の高さ。)3.地価も格差が生まれ金持ちは四条以北の上京に大邸宅を構えた。4.京の町中を避けて郊外に居を構える貴族も増えた。 奈良時代に宗教の影響が強くなり政治に悪影響を与えた反省から、平安時代には京の町中には東寺、西寺以外の寺の建設は認められていなかったので、貴族に影響力を持つ東大寺、春日社、興福寺、長谷観音、石山寺などへの往還頻度が増した。参詣途中にある休憩地、宿泊地として宇治の地は注目を集めた。
814年、嵯峨天皇は栗隈野(南宇治)で狩りをした後、桓武天皇の息子である明日香親王の宇治別業に立ち寄っている。そして嵯峨天皇の息子、源融が宇治院と呼ばれ後に道長頼通により平等院となる建物を所有、その後陽成院、宇多天皇、朱雀天皇も天皇退位後の別院として所有、さらに宇多天皇の孫に当たる一条左大臣源重信から道長に渡った。紫式部もこの経緯を知っていて、源氏物語では宇治十帖の舞台として宇治院を登場させ、光源氏から長男夕霧に譲られ、薫や匂宮も利用したとしている。
宇治の北部にある木幡には宇治37陵と呼ばれる陵墓が散在、現在も宮内庁により管理されている。埋葬される人物がわかっている許波多神社内36号陵は関白藤原基経、花揃の35号陵は菅原道真を左遷に追い込んだ、基経の息子時平、その他20名が関連付けられている。道長の属した藤原北家の太祖冬嗣と夫人の墓も宇治にあるとされるが場所は不確定である。現在でもJR木幡駅から黄檗方向に向かって府道の主に東側には住宅開発できない森として陵墓が残っているのでウォーキングするとほぼ全てが確認できる。
道長は藤原氏の墓所として1004年木幡に浄妙寺を建設した。場所の選定には安倍晴明と加茂光秀に陰陽道による卜占を命じた。その場所は「鳥居は北方より河に出て、その北の平らな所で東は道である」と記述される。この鳥居は当時五ケ庄柳山にあった許波多神社で、河は堂ノ川、現在の木幡小学校敷地を中心とした広大な土地である。初代の別当は寺の名付け親でもあった天台宗の僧勧修、寺の額は能筆で有名だった藤原行成が南門は楷書、西門は草書で書かれた。供養の願文は当時の最高学者大江匡衡が作文、堂内に安置された普賢菩薩は定朝の師である仏師康尚、何もかもが一流づくしであった。当時の政治や貴族たちの生活には想像以上に宗教が入り込んでいた。別業には必ず御堂と呼ばれる持仏堂が営まれ、三昧堂にこもり仏と対話し救いを求めた。浄妙寺はそれ以降室町時代まで一門の墓所とされたが、藤原氏没落とともにそれ以降の記述はなくなり、今では寺の跡形もない。
平安時代の貴族に娘が生まれると、「后がね」と呼ばれ天皇のお妃候補に挙げられることを第一優先度と考え、幼少より最高の教養を身につけさせた。それがかなわない場合には受領(ずりょう)に嫁ぐ、受領とはXXの守、各国の行政責任者で引き継ぎの際に引き継ぎ書類を受領することから「受領」と呼ばれた。娘の教育係に任命されたのがこうした受領の娘、紫式部や清少納言、藤原孝標の娘などがこうした教育係を受け持つ傍ら、日記や物語を書いたというわけである。紫式部は学者で越前守、文章博士・式部丞であった藤原為時の娘、父とともに任地にも赴任。和歌、白氏文集、日本書紀、などを熟読。目立つことは嫌いで、心は満たされない傾向、やや厭世的。清少納言は周防守・肥前守で36歌仙の一人清原元輔の娘で、周防には父とともに赴任。当意即妙、漢詩集の豊富な知識、楽天的、主人の定子からの質問には誰よりも早く回答、自分の見識を披露することに快感を覚えた。二人には共通点が多い。貴族の娘の教育係として御所に出仕すると、自分が仕える中宮などの住居を出入り、そこには人事異動の猟官活動に勤しむ男たちの姿もある。白髪混じりで自分の父と同じ年頃の男たちが、中宮への取り成しを女房たちに頼んでいる姿に、「あはれ」を感じた。現代で言えば役員秘書で秘書室勤めの女性秘書たちが婚期を逃してしまう大きな理由ともつながる。こうした女性たちが夢の中で描く理想の男性像を架空のストーリーに仕上げ、現実の男たちの惨めさ、女たちの嫉妬などを日記にしたためたのである。源氏物語や枕草子はそれ以降の女性たちにも大きな影響を与えた。
源氏物語 東屋の巻で宇治の御堂が完成し薫と浮舟が京の邸宅より宇治を訪れる場面での経路は次の通り。牛車で当時東福寺近辺にあった法性寺、九条河原から大和街道を南へ進み、深草大亀谷から木幡を通って約6時間かけて宇治に到着している。九条河原から船で宇治津と呼ばれた巨椋池の港に向かうケースもあった。宇治を表現する表現、景色を表す名詞には、紅葉、網代、鵜飼、柴舟、水車、宇治橋などがあり平安時代以降の数多くの絵画にこうしたものが宇治の景色として描かれている。宇治十帖には宇治の10箇所が巻名として登場する。場所が特定できる場合もあるが、現在石碑などが設置されているのは次の通り。北側から浮舟が三室戸寺、手習が奈良線三室戸踏切横、蜻蛉が莵道大垣内、椎本が東内の彼方神社境内、東屋は京阪宇治駅東に東屋観音、総角(あげまき)は宇治上神社北、夢の浮橋は宇治橋西詰、橋姫は宇治蓮華の橋姫神社内、早蕨が宇治神社東北隅、宿木は平等院東南の宇治川河畔。三室戸寺から宇治橋までが1km、宇治橋から宿木の石碑までが700m、宇治神社、宇治上神社は平等院から塔の島経由で川を渡り400m程度なので、全部歩いて回っても軽く一日ウォーキングコースである。宇治を観光で訪れるにしても、少しでも宇治十帖のストーリーを知っていれば、感じ方も異なるはず。例えば宇治十帖の橋姫、しっかりとした後見もなく父に死なれ、二人で暮らす姉妹大君と中君の前に薫と匂宮が現れる。薫との恋に生きたかった大君、匂宮との恋に心乱された中君、宇治十帖の巻名に橋姫が使われた以降、和歌の世界で橋姫は「人待つ愛し姫君」となる。宇治橋の西詰には橋姫碑が建てられている、ということを知っていれば、桜や紅葉の美しさに加え、大君、中君の憂いと悲しみをひょっとしたら感じ取れるかもしれない。
道長が亡くなった後、頼通は道長の宇治別業を寺と改めた。三井寺の平等院に因んで名付けたという。寺としたのは道長の菩提を弔い、末法到来に備えるため。平等院と聞くと鳳凰堂と呼ばれる阿弥陀堂を思い浮かべるが、その境内には寝殿を改築し宇治川にせり出した釣殿を持つ大日如来が安置された本堂、阿弥陀堂の池を挟んで向かいに阿弥陀如来を見るための小御所、その他頼通の子師実や寛子などにより五大堂と多宝塔が建てられ、平等院はその他玄奘三蔵法師が所持していた袈裟を収めた宝蔵、万葉集から拾遺抄にいたる和歌集を収めた経蔵、愛染堂、法華堂、寝殿僧坊、不動堂などが配置された大寺院であった。源氏物語と別業のイメージから宇治には「憂愁の宇治、憂し宇治」と和歌にも詠まれる。頼通は1074年に宇治で亡くなり、中世の修羅の世界は近づいていた。その後、後一条、後朱雀、後冷泉と道長を外戚とする天皇が続いた後の後三条は藤原家と距離を置く。そして白河、堀川、鳥羽、崇徳とつながる系譜では、摂関政治から上皇による院政へと移行していく。頼通の子忠実は摂関家に勢力を取り戻そうとするが、その子忠通との確執が保元の乱・平治の乱の原因を作る。平治の乱以降、敗北した藤原摂関家は没落、武士の時代へと移っていくとともに、宇治の別業、平等院の地としての位置づけも大きく変化する。
こうした歴史を知って喜撰法師の歌を読むと思いもまたひとしおである。「わが庵(いほ)は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり」