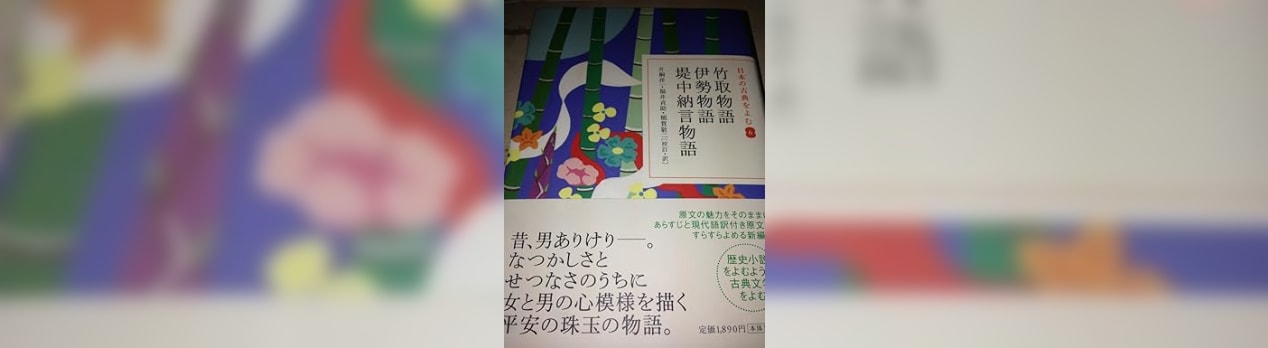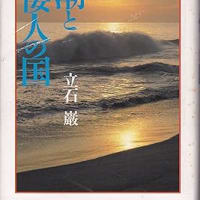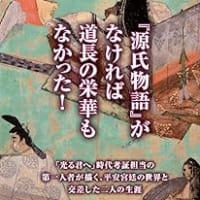竹取物語は平安初期の編纂と言われ仮名手で書かれた最初の物語。舞台は散吉(さぬき、大和の地名)で翁は造(みやつこ)といい、ある日竹林で見つけた3寸の小さな女の子を見つけて家に持ち帰る。3ヶ月で美しい女性に成長。この間には竹取の翁はたびたび竹の中から黄金を見つけ、徐々に裕福になっていたので、朝廷から御室戸の斎部の秋田を呼んで裳着の儀式とともに「なよ竹のかぐや姫」と名付けてもらった。物語の意味を象徴するような序盤部分、「竹」は早く成長し、「なよ竹」は吹き付ける風にも折れずに耐え抜く、斎部氏は朝廷に出入りする儀式を司る役割であり、内裏などで働く女房などを選ぶ役割も持つ。この美しい娘の噂はすぐに広がり、多くの求婚者たちが翁、媼の前に現れる。
翁の前に現れたのは5人の求婚者で、かぐや姫に会ったこともないのに熱心である。かぐや姫は結婚する気などはなくいずれに対しても難色を示すが、相手がいずれも立派な肩書の男性陣なので翁も媼も前向き。かぐや姫は親代わりで育ててくれた翁の説得に応じて、5人にそれぞれの達成困難とも思われるような課題を示し、相手の心のうち、誠意を試す。
石作りの皇子には仏の御石の鉢を求めた。裏の意味としては釈迦が出家の覚悟を決めて托鉢したときのように、出家する覚悟を示してほしいという意味。出家するなら結婚はできないでしょう、という掛け言葉。それに対して、天竺で探して持ってきますと伝えて、3年ほどの後、大和の十市にある山寺から賓頭盧の真っ黒の石作りの鉢を手に入れて、錦の袋に梅の花をつけて持参。都(と)落ちの理由は錦と花が象徴する女性問題で左遷されていたのにそこでも女性問題を起こしたということ。すぐに見破ったかぐや姫は、出家の意志が足りませんでしたね、と和歌を詠んで断る。
倉持の皇子には蓬莱の玉の枝、蓬莱は想像上の遠い国であり普通はたどり着けないところにある、こちらも想像上の金の幹、銀の枝、その先にある玉を持ってきてほしいと。皇子は職人を雇ってそっくり同じものを作らせて、冒険譚まで作り話をして持参。職人たちには官位と作業代金を支払う約束が果たされていないと翁の家にまで押しかけてきたので嘘がバレる。蓬莱の玉の枝とは理想の家庭や家族のことであり、すでに既婚者であった皇子には、妻や子たちを大切にしなさい、というかぐや姫からのアドバイスだった。それに気が付かなかった皇子にかぐや姫は呆れてしまった。
阿部御主人(みうし)には火鼠の皮衣、広い家を持ち財力があった阿部御主人は右大臣、商人に大金を支払って手に入れる。火鼠(ひねずみ)は妻を出産でなくしたことの象徴であり、七日で手に入れた皮衣は妻の初七日も過ぎぬうちに次の女性に求婚しているという意味。もっと女性を大切に思ってほしい、というのがかぐや姫からのメッセージ。燃えないはずの皮衣はあっけなく燃えてしまい、阿倍御主人はがっかり。
大伴大納言御行には龍の頸の玉を求めた。大納言は家来たちに報奨と食物を与え、龍の頸の玉を取ってくるように命じた。そして家を建て替え前からいた妻たちも別居させ準備していた。家来たちはいつまで経っても帰ってこないので自分で探索に出かけた。しかし大納言は船で大嵐に遭遇し九死に一生を得る経験をした。離別した妻たちも大笑い、世間からも馬鹿にされた。お金で何でも解決しようとするなど馬鹿げたことだというのがかぐや姫からのメッセージ。
石上中納言麿足には燕の子安貝を求めた。麿足は燕の親が卵をかえす瞬間を捉えて燕を掴むことに成功し捕まえる。「子安の貝」を得たから紙燭を持て、と叫んだが、掴んでいたのは燕のクソだった。麿足は自分の妻が子を産んだときでも、子供の顔が見たいと言って妻をいたわるよりも子供の顔を見たがったのではないか、というメッセージ。麿足は燕を掴んだときにハシゴから落ちて腰をうち、その後遺症で大変弱ってしまった。気の毒に思ったかぐや姫は消息を伺う和歌を送るが、「貝は取れずも甲斐はあったと思いたい、救ってほしい」と返答しながら絶命した。
五人の求婚者に託したかぐや姫の望みは、誠意、自分の家族への愛情であり、本当にそうしたものを求婚者たちが持っていたとしたら、誰一人として戻ってこないはずだった。こうした噂を聞いた帝は内侍の中臣ふさ子にかぐや姫をひと目見てくるように命じた。勅使と会うことを断ったかぐや姫に゙対し、帝は翁を通して出仕を命じ、翁に官位を与えることを約束したが、「そうであれば私は死にます」とかぐや姫は答えた。何としてもかぐや姫を欲しくなった帝は、翁と計らって、狩と称して姫に会いに行く。翁はいつの間にか造麿と呼ばれており、すでにこのとき官位を授かったものと想像できる。
帝は造麿の家に入りかぐや姫と出会うことになる。連れて行こうとする帝に抗うかぐや姫。「私はこの国の人ではない」と言いながら「影」になる。驚いた帝は連れて帰ることは諦める。その後3年ほど、帝とかぐや姫は何度か和歌の交換を続け、かぐや姫は帝に恋心を抱くようになる。翁は心労ですっかり年老いてしまう。そして8月15日の夜にかぐや姫に月からお迎えがくる日が来る。帝は中将高野のおおくにを遣わし、2000人の警固人を派遣、月からの使者から姫を守ろうとする。しかし天からの使者はそんな警固をものともせず、天の羽衣を姫に渡して月に連れて帰る時が来る。かぐや姫は不死の薬と手紙を壺に入れて帝に渡し、月に帰ってしまった。帝は天に一番近いという駿河の国にある山の頂上でこの壺と手紙を焼くように士(ツワモノ)たちに命じる。たくさんの士たちが山に登ったことから、その山は「士に富む山=富士山」と呼ばれるようになった。富士山から立ち上る煙はその時の壺を焼く煙だという。
竹は姫を象徴し、姫を求める男たちはパートナーを求める鳥たち、という竹取物語。
伊勢物語は9世紀末から10世紀末までに成立した在原業平の歌を中心として展開する物語集。元服したある男は、奈良の春日山で見た姉妹を垣間見て恋をする場面から始まる「初冠」。入内前の二条の后藤原高子に恋をしたある男は、女のもとに通い詰め、ある時連れ出そうとする。連れ出した先の夜、一夜を過ごす寺の中で女が鬼に食われてしまい、逃避行は成就しない。思いを遂げられなかったある男は東国に新たな住まいを求めて旅をする「東下り」。男は道中、三河の八橋、武蔵と下総の間を流れる隅田川などで、京に残してきた女を思い歌を読む。「名にしおはばいざ言問はむ都鳥わが思う人はありやなしやと」。しかし東国においても現地の女と情を交わすのだった。幼馴染と結婚するが、その後新しい女に熱を上げた男。しかしその新しい女が慣れてきて、男の前でも自分で飯をよそうのを見て嫌気が差してまた通うことをやめてしまう「筒井筒」。伊勢の斎宮と情を通じてしまう「狩りの使い」。波乱に満ちた人生を送ったこの男の辞世の句。「つひにゆく道とはかねて聞きしかどきのうけふとは思はざりしを」。
堤中納言物語は10の短編を収めた物語集。
「花桜折る少将」では美しい月明かりの中で見た屋敷の中の姫君に恋をした。姫は故中納言の娘で近々入内するという。中将(タイトルとは違い)が、家人に命じて連絡を取り、姫を連れ出したと思ったら、その祖母の尼君だった。
「虫めずる姫君」では按察大納言の娘は虫が大好き。まわりの女官たちは嫌がって近づかないが、姫君は近所の童子たちを集めては虫を取らせる。眉を抜いたりお歯黒をすることには関心がなく、虫は繭となりそして蝶となるのだから、その過程こそ面白いと主張を変えない。こうした噂を聞いた上達部は、蛇に似せたオモチャを忍ばせた手紙を送り驚かせようとするが、姫君はそれを見て逆に楽しむような返歌を送り返す。興味をそそられた上達部は友人と一緒に姫を一目見ようと出かける。屋敷では虫と本当に一心に遊ぶ姫がいて、化粧っけのなさ、虫好き気性を残念がる。いも虫もそのうち蝶になるだろうに、と挨拶の歌を送って帰ってしまった。
「はいずみ」仲の良い夫婦がいた。懇意な人の家の娘に入れあげたこの夫、連れ添った妻を家から追い出して、新たにこの娘を家に入れようと画策した。行く宛もない妻は、知り合いの昔の家人を頼って、大原に向かう。粗末な家に移り住んだことを聞いた夫は様子を見に行き、その粗末さに驚き元の妻を不憫に思い連れ戻す。帰ってきて新たに連れてこようとしていた娘に会いに行った夫の急な訪問に驚いた娘は、白粉と間違えて灰墨(はいずみ)を顔に塗りたくって迎えてしまう。驚いた夫はショックでそそくさと家にかえってしまう。
源氏物語の朧月夜は在原業平のエピソードをモチーフにしているようだし、竹取物語のかぐや姫のメッセージも、何人もの姫を相手にしていた光源氏の相手の立場に立ったような気がする。「堤中納言物語」の年代は不明とのことだが、こうした仮名手の物語は社会に流通していたことが想像できる。「はいずみ」のことを彷彿とさせるエピソードは大河ドラマで紫式部と夫の藤原宣孝との場面で描かれていた。花桜折るの女の家から帰る場面は「蓬生」であり、家から連れ帰るのは「若紫」でもあろう。こうした平安時代の物語や書き物を平安の山脈と評したのは「知られざる王朝物語の発見 物語山脈を眺望する」の神野藤昭夫先生。山脈は高く長く続いているようだ。