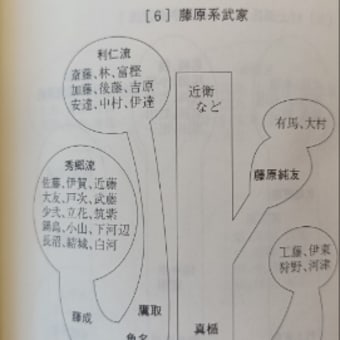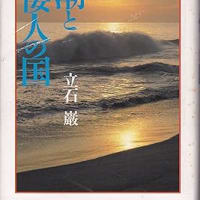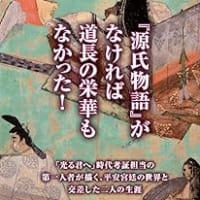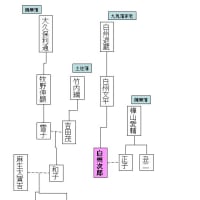慶喜は大阪城で英国公使ハリー・パークスを饗応した。その時の様子をアーネスト・サトウは「将軍はそれまで私が出会った日本人の中でもっとも貴族的な容貌をそなえていた人物のひとりであり、秀でた額、形のよい鼻、まさに紳士そのものであった。軍備に関して固く口を閉ざす老中よりも将軍のほうがずっと率直だ」と感じ入っている。晩餐会が開かれた部屋に36歌仙の絵が飾られていた。パークスが興味深げに見ているので、慶喜は「伊勢の額」を取り外させパークスに進呈しようとした。パークスが組みになっている一つを外すのはもったいない、と固辞すると、慶喜は「空白ができたとしても、その絵がイギリス公使の手に渡っている、と考えれば大きな喜びである、受け取って欲しい」と言った。これ以上美しい好意の表明はあるだろうかと同行していたミットフォードは賛嘆したという。日本外交史上最高の評価を受けたと筆者は言っている。
龍馬を暗殺したのは誰か。先日のNHK特集では見廻組与頭佐々木只三郎だとしていたが、それを実質的に命じたのは松平容保、しかし殿様がそんなことまで命じるはずがないので、只三郎が自分で殿の立場と気持ちを忖度して実行したものだと。その後ろには薩摩藩、土佐藩、彦根藩などが想像できるが藪の中である。
幕末、各藩は莫大な借金を抱えていた。薩摩藩は500万両(2500億円)、これを長期返済計画を立てて250年返済計画を立てていたという。明治維新で藩がなくなり返済終了となったのだが、版籍奉還に各藩が応じた結構大きな理由がこれだったのかもしれない、と筆者は推測する。
1854年、駿河沖で大地震がありロシアのディアナ号は下田で停泊中津波に巻き込まれ大破、大きな被害にあって結局沈没した。これは安政の東海地震である。この地震は32時間のインターバルで東南海地震が連動して起きた。ディアナ号を再建したいロシアに幕府は協力、ロシアから提供された設計図をベースに日本の船大工200人が建造1ヶ月半で完成した。戸田で作られたので「ヘダ号」と名付けられた。以降、日本で洋式帆船をつくる際の手本となったという。また、プチャーチンはこの対応に感謝、北方領土交渉で択捉以南の4島を日本領と認め、サハリンは国境を定めず日露の雑居地とした。この日露交渉の日本側の立役者が川路聖謨であった。一橋派だったため安政の大獄で蟄居、江戸城開城の知らせを聞いてピストル自殺したという。
鳥羽伏見の戦いでの錦の御旗の謎、それはなぜ下級武士までがみんな錦の御旗を知っていたのか、ということ。そもそも大政奉還の直前に大久保利通と長州の品川弥二郎が岩倉具視に依頼され12組の錦旗を作っておいたもの。天皇が下賜したのはこの偽物だった、裏で操ったのが岩倉具視だったというのである。戦いに先立って薩長が「錦の御旗がでるぞ」という噂を流していた、という話もあるという。錦の御旗を見た幕府側の武士たちは戦意を一気に喪失したというから効果てきめんであった。
江戸城無血開城は勝海舟と西郷隆盛の会談による、となっているが、その裏で骨をおったのは和宮と天璋院篤姫だったと。江戸に向かう官軍の大将、有栖川宮熾仁親王と西郷隆盛に工作したというのだ。江戸には輪王寺宮能久親王(後の北白川宮)が唯一の宮家としていた、徳川家の宗門である天台宗の総元締めであった。慶喜が寛永寺に幕末蟄居したのは輪王寺宮が門主としていたためと考えられるという。輪王寺宮は官軍に慶喜の助命と東征中止を嘆願するために駿府城にいた有栖川宮熾仁親王に面会、東征中止は無理だが助命はしてやろう、との回答を得た。これも影の功労者である。
江戸幕府側の人材で明治新政府に登用された人物は多い。箱館戦争に敗れた榎本武揚は国際知識を見こまれて北海道開拓使や海軍卿などに任命された。大鳥圭介は開拓使、工部技官、学習院長、枢密院顧問に、永井尚志は元老院大書記官になった。渋沢栄一は一橋家の家臣から幕閣に取り立てられ、その後大蔵省に出仕、財政制度を確立した。慶喜のブレーンだった西周は山縣有朋に迎えられ兵部省に出仕、元老院議官になった。政治総裁だった松平春嶽は明治元年初日に新政府の議定、民部官知事、大蔵卿などを歴任して明治三年に退官している。宇和島藩の伊達宗城は外国事務総督に任じられた。明治新政府は幕府の政治家をちゃんと中枢において引継ぎをしたのである。
確かに徳川家からみた幕末史であり、今まで読んだことのない情報、資料などが参照されていて面白い。
徳川家が見た幕末維新 (文春新書)