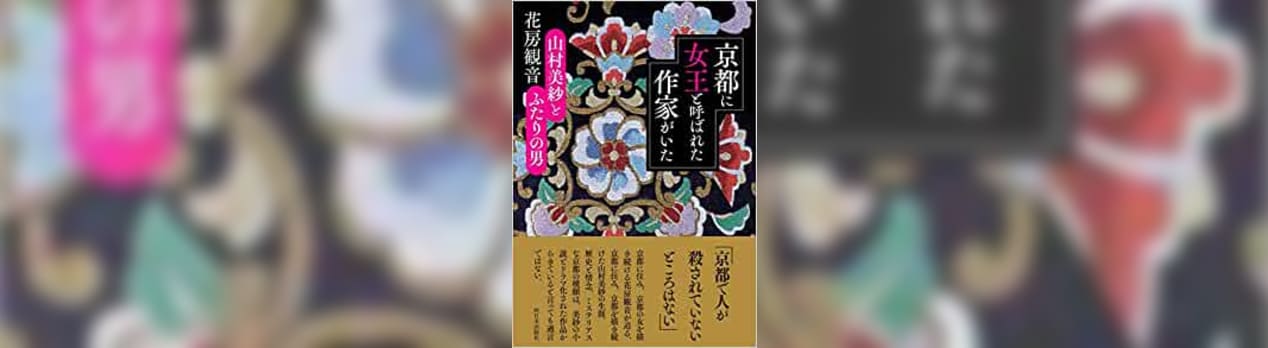1996年に心不全で急死した山村美紗、遺産総額は7億円を超えた。相続したのは夫の山村魏(たかし)が3.7億円、長女の紅葉に2.8億円、次女の真冬に1億円だったという。山村美紗のパートナーは西村京太郎だったのでは、と思う読者もいるかも知れないが、魏さんとは同居生活を続け、二人の子を育て上げて最後まで良い関係だった。
山村美紗が作家としてデビューしたのは1974年、江戸川乱歩賞候補作だった「マラッカの海に消えた」がデビュー作となる。その頃は宇治にマンションを保有して、マンションの一階に夫の魏と二人の子供と同居、同じマンション6階に執筆のための部屋を持っていた。魏は京都私立東山高校の教師として長く勤めたが、美紗ももとは国語教師、二人は京都市立伏見中学校で知り合い職場結婚、その後、魏は東山高校に就職した。美紗は教師の傍ら江戸川乱歩賞などに小説を書き応募していたが、なかなか入賞にまでは至らない。紅葉が生まれたのが1960年、美紗は教師生活10年を経て、執筆活動に専念するため1964年退職した。魏は美紗の作家としての才能を認め、作家生活を支える決意をする。
美紗が自身と同じように駆け出しだった西村京太郎に出したファンレターがきっかけで二人は知り合い、小説家としてタッグを組むようになる。タッグとは文字通りの協力関係で、男女関係があったのかは本人同士にしかわからないが、魏は後年、二人は小説家としてのパートナーだったはずだと書いている。小説家としてのパートナーとは、対出版社、編集者であり、執筆上の悩みや助言なども互いに得ていた。1986年には東山にあった旅館を買取り改装、本館に美紗、別館に西村京太郎が暮らすようになり、本館向かいのマンションには美紗の家族が暮らして作家生活を支える。しかし、その家族のことは編集者たちにも伝えることはなく、魏という夫の存在を長く知らない編集者も多かった。京太郎との協力関係は業界では有名になり、編集、出版、広告、執筆料交渉などあらゆる意味で、作家による出版社へのバーゲニングパワーとして有効に働いた。二人の関係が公になるのは、「噂の真相」誌が二人の関係について記事にし始めたため。
二人の名前は2004年に発表が取りやめになるまで長者番付で否が応でも目立っていた。1986年、近畿の文筆家2位が京太郎で2.5億円、6位が美紗で3774万円、一位は赤川次郎。94年には、全国作家部門で、1位赤川次郎、2位京太郎2.2億円、3位内田康夫、4位司馬遼太郎、5位山村美紗8624万円。美紗は一切節税努力をせず、長者番付で上位に来ることで知名度向上を狙っていた。美紗が欲しかったのは直木賞だったが、あらゆる小説賞とは無縁の流行作家だったことが、美紗のプライドを傷つけ続けた。そのためにも売れ続ける必要があった。美紗は京太郎に「書きたい作品ではなく、売れる作品を書くのよ」と励ました。美紗の父は京大教授、生まれはソウルで、戦後引き上げ後は苦労したが、父の知り合いの紹介で京都に来てからは、京都の文化に馴染んでいった。京都では歌舞伎、グルメ、寺社、茶の湯などあらゆる文化を体験していった。祇園や銀座で飲んでいても、作品のプロットやネタを仕入れる努力を怠らなかった。美紗の作品は、昭和高度成長時代のアンノン族、京都ブームと見事にシンクロして売れに売れた。テレビや映画に作品の多くが取り上げられた。
長女の紅葉は早稲田大学に入学後、「消えた花嫁」で女優デビュー、卒業後は国税庁に就職するが、87年には結婚退職。女優として活動を始める。美紗は93年には女流作家として長者番付トップとなるが、体を壊し、虫垂炎、喘息などで苦しむようになる。魏は95年には東山高校を退職し、美紗を全面的にサポートするようになる。しかし96年、帝国ホテルにて美紗は作品執筆途中で逝去する。
作家としてのパートナーを失った西村京太郎は、すぐに湯河原に転居、現在の妻に出会う。魏は、美紗を失い目的を見失いかけるが、夢枕に美紗が何度も現れて、自分を絵に描いてほしいと懇願するため、経験したこともない絵画の勉強を始める。魏は2003年、二度目の妻となるモデルの祥と出会う。あまりに美紗に似ているため、美紗を描くときのモデルとして契約、そして結婚することになる。魏80歳、祥41歳だった。その後二人は、美紗を題材とした絵画展を開催、本書内容は以上。絵画展は2021年7月にも京都大丸で開催されている。
美紗の墓は京都の泉涌寺にあり、「美」と刻まれているという。賞を取りたかった山村美紗の強い思いは、この「美」という文字に浮き出ているように感じてしまう。流行小説家を目指している作家の卵であれば、本書内容は役立つかもしれないが、電子書籍の時代では難しいかもしれない。美紗の魅力は、醸し出す雰囲気だったのだろうと思う。松本清張も、高木彬光も、もちろん、夫の魏も美紗の持つ京都文化の強い香りに惹きつけられた。東山の美紗の邸宅はそうした雰囲気をより強く盛り上げたことだろう。