
降りつむ 永瀬清子
かなしみの国に雪が降りつむ
かなしみを糧として生きよと雪が降りつむ
失いつくしたものの上に雪が降りつむ
その山河の上に
そのうすきシャツの上に
そのみなし子のみだれたる頭髪の上に
四方の潮騒いよよ高く雪が降りつむ
夜も昼もなく
長いかなしみの音楽のごとく
なきさけびの心を鎮めよと雪が降りつむ
ひよどりや狐の巣にこもるごとく
かなしみにこもれと
地に強い草の葉の冬を越すごとく
冬をこせよと
その下からやがてよき春の立ちあがれと雪が降りつむ
無限にふかい空からしずかにしずかに
非情のやさしさをもって雪が降りつむ
かなしみの国に雪が降りつむ。
詩人・永瀬清子、2020年は没後二十五年になります。
1906(明治39)年2月17日、永瀬清子は岡山県赤磐郡豊田村大字松木(現・赤磐市)に永瀬連太郎と八重野の長女として出生、戸籍名は清という。生家は素封家として知られ、母方の祖父は明治初期に県会議員を務めた。
清子は2歳から16歳まで電気技師の父連太郎の赴任先金沢で育った。父の転勤で名古屋へ移り『上田敏詩集』を読んでから詩の世界に開眼、愛知県第一高等女学校高等科英語部在学中から佐藤惣之助に師事し「詩之家」同人となった。同校を卒業した1927(昭和2)年に結婚、大阪に新居を構えた頃、詩壇はシュールレアリスムやモダニズムの影響下にあり、「詩と詩論」が席巻していた。清子は当時の思潮に対して冷静な距離を保ったため、容赦のない批判を浴びたが、1930(昭和5)年『グレンデルの母親』を世に問い、早くも独自の才能を顕現した。
翌年夫の転勤で上京、友人の勧めで北川冬彦主宰の「時間」同人となり、左翼文学の攻勢の中、穏やかな抒情詩に決別すべく第一次「時間」を解散した北川に同調した。「時間」が名を変えた「磁場」・「麺麭」は清子の命名による。
1940(昭和15)年清子が女性詩人として名声を獲得した詩集『諸国の天女』の序文は、高村光太郎によるもので、高村とは清子が生涯敬慕した宮沢賢治の追悼会での出会いが縁となった。またこの詩集によって仏文学翻訳の第一人者山内義雄や宮本百合子に認められることとなり、既に昭和初期清子は深尾須磨子や長谷川時雨など、当時随一の女性文学者たちの仲間入りを果たした。
戦後は、生地松木へ移り農業に初めて従事しながら、藤原審爾・山本遺太郎らと1946(昭和21)年同人誌「文学祭」を発刊、翌1947(昭和22)年吉塚勤治らの「詩作」創刊に参加、また「日本未来派」同人となった。『星座の娘』・『糸針抄』・『大いなる樹木』・『美しい国』・『焰について』など次々に作品を発表しつつ、1952(昭和27)年「黄薔薇」を創刊、後進を育成した功績は大きい。
1955(昭和30)年インドでのアジア諸国会議に参加、1963(昭和38)年から1977(昭和52)年まで世界連邦都市岡山県協議会事務局に勤務、世界平和のために尽くす。この間詩作の泉を涸らすことなく『海は陸へと』・『永瀬清子詩集』他著書多数を刊行。1982(昭和57)年日本現代詩人会から先達詩人として顕彰された。1987(昭和62)年81歳で『あけがたにくる人よ』が地球賞を、翌年同詩集でミセス現代詩女流賞を受賞。
1995(平成7年)、89歳で永眠。命日の2月17日を、清子を慕う人々は「紅梅忌」とよぶ。










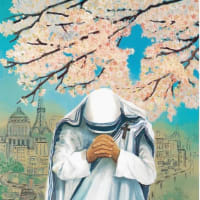




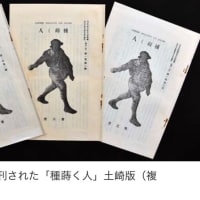
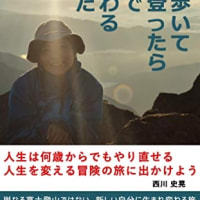


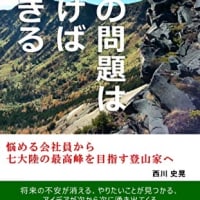
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます