周利槃特(しゅりはんどく)
『知によって生死を離れ、
愚癡(愚痴:ぐち)に還って極楽に生まれる』法然上人
『垢(あか)を流し、塵(ちり)を除きながら、自らの愚を自覚し、真の知恵者となる』
「なぜ兄弟の目にあるちりをみながら、自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には梁があるのにどうして、兄弟にむかってあなたの目からちりを取らせてください、と言えるのか」
マタイによる福音書7章
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye....
周利槃特(シュリハンドク)は、 仏説阿弥陀経に、お釈迦様の弟子たちの名の七番目に出てくる人である。
十大弟子の一人に数えられる方であるが、この人はいわゆる勉強のできない人であり、さらには自分の名前も書けない。自分の名前を呼ばれても周りの人から言われて自分のことだとやっと気づくようであった。
もちろん、お釈迦様の教えを聞いてもすぐに忘れてしまう。でも、悟りを求める心は人一倍あった。
周利槃特(シュリハンドク)は兄に誘われてお釈迦様の弟子となった。この兄は聡明であったのだが、周利槃特は一つの教えさえも記憶できなかった。つまり、修行の作法や方法も何も覚える事ができなかった。その後も、何年も修行を続けたが、自分の才能の無さに絶望したので、教団を去ろうとしたのだか、お釈迦様が、『自らの愚を知る者は真の知恵者である』という言葉を聞き思いとどまる。
そこで、お釈迦様が与えた修行は、
一本の箒(ほうき)を与えられ、 垢(あか)を流し、塵(ちり)を除く、と唱えながらの掃除を一心不乱に掃除をした。
掃除を初めてから何年もたったある日、釈迦様に「 きれいになったでしょうか?」と尋ねた。
答えは「ダメ」でした。お釈迦様には「どれだけ隅から隅まできれいにしても駄目だといわれる。それでもあきらめずに黙々と掃除を続けた。
ある日、子どもたちが遊んでいてきれいに掃除をしたばかりの所を汚してしまった。思わず箒(ほうき)を振り上げ怒鳴った。「 こら!どうして汚すんだ。」その瞬間、本当は、何が汚れているのかに気がついたのだ。汚れが落ちないのは人の心も同じなのだと悟り、とうとう仏の教えを理解して、阿羅漢果を得ていった。お釈迦様は、一生懸命に掃除をしている周利槃特の姿を見かけては手を合わせて拝まれました。
周利槃特(シュリハンドク)はどのようにして、日々の心の塵や垢を除いたのか。
日々の生活のなかで、こころとは、きれいにしてもきれいにしても、また汚れてくるものである。ここに、掃除をするは理由にある。
掃除をするのは、汚れることを前提にしている。つまりら心の垢を流し、心の塵を除くことをし続けること。これが周利槃特(シュリハンドク)の行ってきたことなのだ。修行(人の生き方)とはそのようなものではないのだろうか。
だんだんと階段を上れるような修行を考える方々が多いいのかもしれない。しかし、周利槃特(シュリハンドク)の生きる姿も参考になる。
『よしあしの 文字をもしらぬ ひとはみな まことのこころなりけるを
善悪の字しりがほは おほそらごとのかたちなり』
親鸞上人 正像末和讃
以下は、http://www.otani.ac.jp/yomu_page/kotoba/nab3mq000002c343.htmlより
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり
「善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり」
親鸞「正像末和讃」
(『真宗聖典』511頁)
この言葉は、親鸞の和讃の一節です。その全文は次のようなものです。
よしあしの文字をもしらぬひとはみな まことのこころなりけるを
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり
(よしあしという文字を知らない人はみんな、真実の心を持った人です。善悪の文字を知ったかぶりして使うのは、かえって大嘘の姿をしているのです。)
この和讃は、親鸞88歳の時の作です。晩年にかけて著作を何度も書き直して思索を深めた親鸞が、知れば知るほどに「まことのこころ」を見失ってしまうと、自らの姿を戒め、慚愧(ざんぎ)した言葉です。
私たちは、少しの知識を得れば、すぐ分かったつもりになります。学べば学ぶほど博識になった気になり、他人より偉くなったような気分にもなります。こうしたことは、私たちにありがちなことではないでしょうか。しかし、そのような人の有り様(さま)には、大切な何かが見失われているように思います。
これは悪いとか、あれは善いなどと知り得た知識によって判断し、分かったつもりになるようなことは、大学における学びにおいても言えることではないでしょうか。大学では、昨日よりも今日、今日よりも明日と、私たちは少しでも知識を獲得し、真理を探求しようと努めています。しかし、人は学べば学ぶほどに、知らず知らずに傲慢(ごうまん)にもなり、何が本当に大切なのかを見失うことがあるのかもしれません。
同じことは、学び教わる側だけではなく、学び教える側にも言えることではないでしょうか。知識を振り回し、分かった顔をして自己満足している教師と学生の姿は、「まことのこころ」を見失った、まさに「おおそらごとのかたち」でしょう。
この和讃は、親鸞が自らを省みて述べた短い言葉ですが、真理を求めて学問する者ですら陥る、そんな落とし穴の存在を教え示しているように思います。本気に探求する者だからこそ自らを確かなものと信じて邁進(まいしん)するのでしょう。しかし、それが誰もが賞賛する知的な営みと態度であるがゆえに、余計に気づくことが難しい落とし穴があるのです。
「まことのこころ」を見失わずに、学び続けること。それは至難(しなん)の業(わざ)かもしれません。それでも、私たちは学び続け、思索しなくてはなりません。悲しいかな、私たちは、それほどに傲慢な存在なのです。そこに、この和讃に込められた親鸞の慚愧と、自らを戒めたこころが感じられるのです。
上記で取り上げた、周利槃特(シュリハンドク)の喩え話は、人間の『知識』や『知恵』とは悟りを得るためには、むしろ妨げになることもあるのだと示している。
『知によって生死を離れ、
愚癡(愚痴:ぐち)に還って極楽に生まれる』法然上人
『垢(あか)を流し、塵(ちり)を除きながら、自らの愚を自覚し、真の知恵者となる』
「なぜ兄弟の目にあるちりをみながら、自分の目にある梁を認めないのか。自分の目には梁があるのにどうして、兄弟にむかってあなたの目からちりを取らせてください、と言えるのか」
マタイによる福音書7章
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye....
周利槃特(シュリハンドク)は、 仏説阿弥陀経に、お釈迦様の弟子たちの名の七番目に出てくる人である。
十大弟子の一人に数えられる方であるが、この人はいわゆる勉強のできない人であり、さらには自分の名前も書けない。自分の名前を呼ばれても周りの人から言われて自分のことだとやっと気づくようであった。
もちろん、お釈迦様の教えを聞いてもすぐに忘れてしまう。でも、悟りを求める心は人一倍あった。
周利槃特(シュリハンドク)は兄に誘われてお釈迦様の弟子となった。この兄は聡明であったのだが、周利槃特は一つの教えさえも記憶できなかった。つまり、修行の作法や方法も何も覚える事ができなかった。その後も、何年も修行を続けたが、自分の才能の無さに絶望したので、教団を去ろうとしたのだか、お釈迦様が、『自らの愚を知る者は真の知恵者である』という言葉を聞き思いとどまる。
そこで、お釈迦様が与えた修行は、
一本の箒(ほうき)を与えられ、 垢(あか)を流し、塵(ちり)を除く、と唱えながらの掃除を一心不乱に掃除をした。
掃除を初めてから何年もたったある日、釈迦様に「 きれいになったでしょうか?」と尋ねた。
答えは「ダメ」でした。お釈迦様には「どれだけ隅から隅まできれいにしても駄目だといわれる。それでもあきらめずに黙々と掃除を続けた。
ある日、子どもたちが遊んでいてきれいに掃除をしたばかりの所を汚してしまった。思わず箒(ほうき)を振り上げ怒鳴った。「 こら!どうして汚すんだ。」その瞬間、本当は、何が汚れているのかに気がついたのだ。汚れが落ちないのは人の心も同じなのだと悟り、とうとう仏の教えを理解して、阿羅漢果を得ていった。お釈迦様は、一生懸命に掃除をしている周利槃特の姿を見かけては手を合わせて拝まれました。
周利槃特(シュリハンドク)はどのようにして、日々の心の塵や垢を除いたのか。
日々の生活のなかで、こころとは、きれいにしてもきれいにしても、また汚れてくるものである。ここに、掃除をするは理由にある。
掃除をするのは、汚れることを前提にしている。つまりら心の垢を流し、心の塵を除くことをし続けること。これが周利槃特(シュリハンドク)の行ってきたことなのだ。修行(人の生き方)とはそのようなものではないのだろうか。
だんだんと階段を上れるような修行を考える方々が多いいのかもしれない。しかし、周利槃特(シュリハンドク)の生きる姿も参考になる。
『よしあしの 文字をもしらぬ ひとはみな まことのこころなりけるを
善悪の字しりがほは おほそらごとのかたちなり』
親鸞上人 正像末和讃
以下は、http://www.otani.ac.jp/yomu_page/kotoba/nab3mq000002c343.htmlより
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり
「善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり」
親鸞「正像末和讃」
(『真宗聖典』511頁)
この言葉は、親鸞の和讃の一節です。その全文は次のようなものです。
よしあしの文字をもしらぬひとはみな まことのこころなりけるを
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり
(よしあしという文字を知らない人はみんな、真実の心を持った人です。善悪の文字を知ったかぶりして使うのは、かえって大嘘の姿をしているのです。)
この和讃は、親鸞88歳の時の作です。晩年にかけて著作を何度も書き直して思索を深めた親鸞が、知れば知るほどに「まことのこころ」を見失ってしまうと、自らの姿を戒め、慚愧(ざんぎ)した言葉です。
私たちは、少しの知識を得れば、すぐ分かったつもりになります。学べば学ぶほど博識になった気になり、他人より偉くなったような気分にもなります。こうしたことは、私たちにありがちなことではないでしょうか。しかし、そのような人の有り様(さま)には、大切な何かが見失われているように思います。
これは悪いとか、あれは善いなどと知り得た知識によって判断し、分かったつもりになるようなことは、大学における学びにおいても言えることではないでしょうか。大学では、昨日よりも今日、今日よりも明日と、私たちは少しでも知識を獲得し、真理を探求しようと努めています。しかし、人は学べば学ぶほどに、知らず知らずに傲慢(ごうまん)にもなり、何が本当に大切なのかを見失うことがあるのかもしれません。
同じことは、学び教わる側だけではなく、学び教える側にも言えることではないでしょうか。知識を振り回し、分かった顔をして自己満足している教師と学生の姿は、「まことのこころ」を見失った、まさに「おおそらごとのかたち」でしょう。
この和讃は、親鸞が自らを省みて述べた短い言葉ですが、真理を求めて学問する者ですら陥る、そんな落とし穴の存在を教え示しているように思います。本気に探求する者だからこそ自らを確かなものと信じて邁進(まいしん)するのでしょう。しかし、それが誰もが賞賛する知的な営みと態度であるがゆえに、余計に気づくことが難しい落とし穴があるのです。
「まことのこころ」を見失わずに、学び続けること。それは至難(しなん)の業(わざ)かもしれません。それでも、私たちは学び続け、思索しなくてはなりません。悲しいかな、私たちは、それほどに傲慢な存在なのです。そこに、この和讃に込められた親鸞の慚愧と、自らを戒めたこころが感じられるのです。
上記で取り上げた、周利槃特(シュリハンドク)の喩え話は、人間の『知識』や『知恵』とは悟りを得るためには、むしろ妨げになることもあるのだと示している。










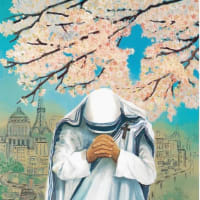




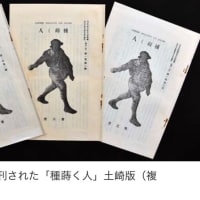
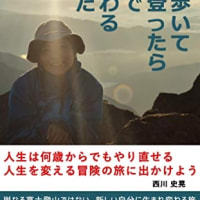


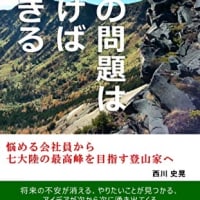
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます