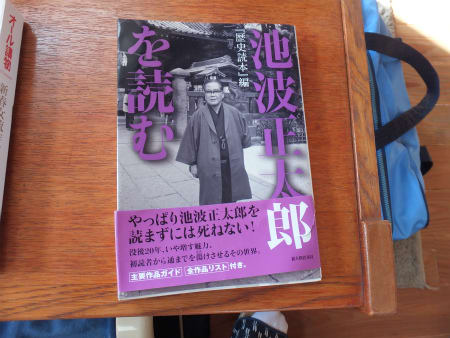昨日は夜半からの雨が朝になっても結構、激しく降っていた。醒ヶ井の梅花藻を見に行くつもりだったがこれはあかんと諦めた。が、雨は8時過ぎには上がった。もう雨の心配がなくなった10時前にそれではと女房と出かけた▼昨年は8月12日に行ったが少し遅く感じた。今年は10日ほど早い。雨の後と言うことか水量は多い。写真1-3は流れの中で咲く梅花藻である。去年に比べると葉の色が真緑で綺麗に感じる。写真4は水槽に咲いていたもののアップである。どうも花の色が2種類あるようだ。写真3の流れにある梅花藻は黄色である▼写真5、6は水槽で飼われているハリヨ(針魚)である。写真6は今年生まれたものか、まだ小さい。流れの中でハリヨを見つけようと探した。諦めた頃に砂地にいるのを発見した。魚を見る時はいつも子供に戻っている自分を感じる▼何かの稚魚が流れの端で固まって泳いでいた。掬って持ち帰りたい衝動を抑えるのに苦労した。やはり童心になっている。→別HP”望郷+田舎暮らし日記”の”醒ヶ井の梅花藻・ハリヨ”に写真6枚を追加しました。 http://inakaikeda.iza-yoi.net/baikamo.html