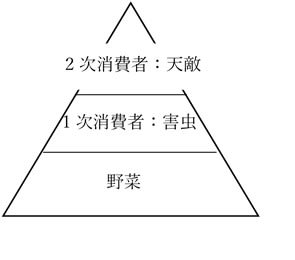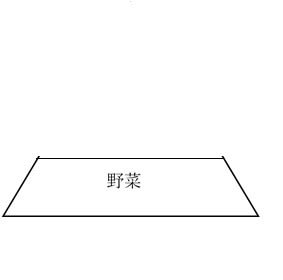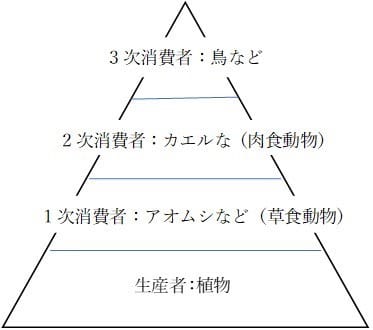育苗ハウスで大切に育てられた苗たちが次々と外の世界に旅出って行きます。
まず最初はトマトを5/26に定植しました。

コンテナに入れて

ポットにたっぷりの水をあげて

定植。

あらかじめ刺しておいた支柱から5~10cm離して植える。
通常トマトは、本葉8~9枚で最初の花房が出た頃に定植するんですが、
今回は、育苗ポットが少し小さく、苗の老化が怖いので早めの定植となりました。
苗の老化とは。。。
小さいポットに長期間、苗が植えられていると、根がポット全体に回り茶色く変色します。
根がそのような状態になった苗を老化苗といいます。
そういった老化苗を定植しても、新しい根が出にくく、うまく成長しないことが多いそうです。
なので今回は本葉5~6枚の若苗で定植です。
植え方なんですが、
通常は、支柱を背にして、花房を手前に向けて植え付けるんですが、
今回の苗は、まだ花房がないので、とりあえず植えて、花房ができたら手前に向くように修正すると。
第一本葉を手前に向けると花房が手前を向くことが多いですが、
それも品種によって違うので、とりあえず今回は双葉が畝と並行になるように植えます。

畑面よりほんの少し根鉢が出るくらいの深さで植える。
で本日は、ピーマン、万願寺ししとう、ナスを定植です。
株間は、ナスが60cm、ピーマンとししとうは50cmで植えます。
ナスは本葉6~7枚、ピーマンとししとうは本葉8~10枚の状態です。
ピーマンとししとうは交配する恐れがあるので離して植えます。
植え方はトマトと同じで、畑面より少し出るくらいの深さで、双葉が畝と並行になるように植えます。

ナス

ピーマン
大体1a(30坪)に200株くらい植えるんですが、植えるスピードが大事になってきます。
午前中に400株以上植え、のどがカラカラになりました。


株を定植した後に支柱を立てました。
そのあと納入されたばかりのマルチャーでマルチ張りの練習。

自然農法らしくないというツッコミは無しでお願いします(^^;)
本日はこれにて。
つづく
まず最初はトマトを5/26に定植しました。

コンテナに入れて

ポットにたっぷりの水をあげて

定植。

あらかじめ刺しておいた支柱から5~10cm離して植える。
通常トマトは、本葉8~9枚で最初の花房が出た頃に定植するんですが、
今回は、育苗ポットが少し小さく、苗の老化が怖いので早めの定植となりました。
苗の老化とは。。。
小さいポットに長期間、苗が植えられていると、根がポット全体に回り茶色く変色します。
根がそのような状態になった苗を老化苗といいます。
そういった老化苗を定植しても、新しい根が出にくく、うまく成長しないことが多いそうです。
なので今回は本葉5~6枚の若苗で定植です。
植え方なんですが、
通常は、支柱を背にして、花房を手前に向けて植え付けるんですが、
今回の苗は、まだ花房がないので、とりあえず植えて、花房ができたら手前に向くように修正すると。
第一本葉を手前に向けると花房が手前を向くことが多いですが、
それも品種によって違うので、とりあえず今回は双葉が畝と並行になるように植えます。

畑面よりほんの少し根鉢が出るくらいの深さで植える。
で本日は、ピーマン、万願寺ししとう、ナスを定植です。
株間は、ナスが60cm、ピーマンとししとうは50cmで植えます。
ナスは本葉6~7枚、ピーマンとししとうは本葉8~10枚の状態です。
ピーマンとししとうは交配する恐れがあるので離して植えます。
植え方はトマトと同じで、畑面より少し出るくらいの深さで、双葉が畝と並行になるように植えます。

ナス

ピーマン
大体1a(30坪)に200株くらい植えるんですが、植えるスピードが大事になってきます。
午前中に400株以上植え、のどがカラカラになりました。


株を定植した後に支柱を立てました。
そのあと納入されたばかりのマルチャーでマルチ張りの練習。

自然農法らしくないというツッコミは無しでお願いします(^^;)
本日はこれにて。
つづく