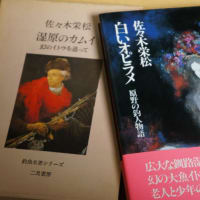釣師・開高健のファンにとって銀山湖(奥只見湖)は『フィッシュ・オン』(朝日新聞社刊)の舞台としてあまりに有名だが、小説家・開高健のファンにとっての銀山湖はむしろ『夏の闇』(新潮社刊)の構想を練った山間の湖という印象のほうが強いかもしれない。
釣師・開高健のファンにとって銀山湖(奥只見湖)は『フィッシュ・オン』(朝日新聞社刊)の舞台としてあまりに有名だが、小説家・開高健のファンにとっての銀山湖はむしろ『夏の闇』(新潮社刊)の構想を練った山間の湖という印象のほうが強いかもしれない。70年の一夏(6~8月)を、小説家は下界の世俗から隔絶した銀山平(新潟県北魚沼郡湯之谷村)で過ごした。電気もガスも水道もない。電話もない。テレビも冷蔵庫も洗濯機もない。郵便はもちろん電報さえも遅れて届く。当時の銀山平はまさに陸の孤島状態だった。小説家はそれが気に入った。小説の構想を練るには、原稿を書くには、うってつけだった。
「鬱状態に持っていかないと小説が書けない人だった」
と、坂本忠雄氏(35年生まれ)は述懐する。新潮社に入社して2年目(60年)に開高健の担当になり、『夏の闇』の担当編集者でもあった人物だ。原稿の督促が厳しかったのか、小説家に“カツアゲの坂本”とあだ名された辣腕である。
「どこかに籠もって、人との関係をいっさい断ち切って、そうやって原稿に集中しないと書けない人でしたね。人がいたら絶対に書けない。そういう意味では銀山湖は条件にぴったりだった」
文章から浮かび上がってくる饒舌さ。写真から見て取れる陽気さや人なつこさ。それとはまったく違う小説家の顔だ。
「小説を書いているときの開高さんは、他のことをしているときとは全然違う。鬱病患者みたいな感じで、ものもいわずにじっとしている。その集中力はすごかったですよ」
坂本氏も銀山湖へは何度か足を運んだ。もちろん、原稿の督励、督促のためだ。
「でも、山籠もりしている間は彼は1字も書けなかった。ランプのもとで一生懸命やっていたみたいだけど、書けなかった。彼はいってましたよ。『ノンフィクションをやりすぎたな』って。描写が狂ってる、なまっているともいってた。たとえば目の前にある瓶を書くときに、ノンフィクションばかりやっていると『一つしか書けないんだ。これではあかのんや』と。小説を書くときは想像力を自由に働かせていろいろな書き方を考えなければいけないんだけど『それができないんや』といってましたね」
このとき小説家の頭のなかには書きたいテーマが二つあった。《二つとも霧のなかに全身をかくしているが顔だけはこちらを向いている。》(フィッシュ・オン)
そのひとつが、『新潮』の71年10月号に全400枚が一挙掲載された純文学書下ろし作品『夏の闇』である(もうひとつは不明)。パリで10年ぶりに再開した「私」と「女」が、「私」が滞在していたパリの学生街の旅館に籠もり、「女」が客員研究員として勤務していたドイツの大学の職員用アパートに身を潜め、部屋の中にいる間は全裸で過ごそうと取り決めをし、ひたすら交わり、眠り、食べるだけの日々を描いた作品である。
これは、小説家が頭のなかだけで創作したフィクションではない。実際のモデルと実体験をもとにした私小説だと考えられている。ある意味で赤裸々なノンフィクションとも受け取れる作品なのである。それだからこそ小説家は事実をいかにフィクション化するかに腐心し、苦慮したのではないのだろうか。(以下、略)