応援しているブランニュージャパン(BNJ)にも参加するYES!プロジェクトが
興味深いイベントを開催するそうです。
ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。
第7回YES!ナイト
『国を支える価値を創る ~ 一人ひとりの日本ブランド戦略』
*日時 :2009/3/6(金) 19:00 - 21:00
*場所 :グロービス経営大学院東京校
http://www.globis.co.jp/company/tokyo.html
*定員 :150名
*参加費 :無料(要予約)
*パネリスト 佐藤 ゆかり 衆議院議員 (自由民主党)
鈴木 寛 参議院議員 (民主党)
堀 義人 YES!プロジェクト発起人代表 /グロービス経営大学院学長
*主催 : YES!プロジェクト http://www.yesproject.com/
▼お申し込みはこちらから: http://www.yesproject.com/yesnight7.html
興味深いイベントを開催するそうです。
ご興味のある方は、ぜひご参加下さい。
第7回YES!ナイト
『国を支える価値を創る ~ 一人ひとりの日本ブランド戦略』
*日時 :2009/3/6(金) 19:00 - 21:00
*場所 :グロービス経営大学院東京校
http://www.globis.co.jp/company/tokyo.html
*定員 :150名
*参加費 :無料(要予約)
*パネリスト 佐藤 ゆかり 衆議院議員 (自由民主党)
鈴木 寛 参議院議員 (民主党)
堀 義人 YES!プロジェクト発起人代表 /グロービス経営大学院学長
*主催 : YES!プロジェクト http://www.yesproject.com/
▼お申し込みはこちらから: http://www.yesproject.com/yesnight7.html













 そして日本をいい方向に変えていきましょう。ぜひ、政治をロックしていきましょう!
そして日本をいい方向に変えていきましょう。ぜひ、政治をロックしていきましょう! このRTPが、そんな役に
このRTPが、そんな役に
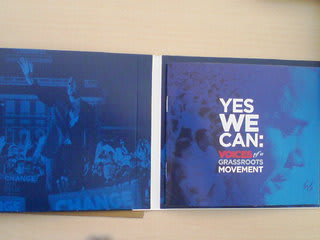
 バラク・オバマ選挙キャンペーン応援のCD”YES WE CAN: VOICES OF a GRASSROOTS MOVEMENT inspired by Barack Obama and his movement for change”を入手しました。
バラク・オバマ選挙キャンペーン応援のCD”YES WE CAN: VOICES OF a GRASSROOTS MOVEMENT inspired by Barack Obama and his movement for change”を入手しました。

 しかも、CD購入者は、どのような寄付をするかを決めるプロセスに、↓のHPから参加できるそうです
しかも、CD購入者は、どのような寄付をするかを決めるプロセスに、↓のHPから参加できるそうです 。
。 、どのような条件で、いくらもらえるかを知れる目安になる。また色々と考えさせられる
、どのような条件で、いくらもらえるかを知れる目安になる。また色々と考えさせられる




 。
。




