最近はジャズの旧譜の再発売もあまりなく、更新もすっかり滞っていました。5月下旬にタイム・レコード・ジャズ・クラシックスというシリーズが発売されましたが、その中からピート・ルゴロの作品を取り上げたいと思います。タイム・レコードは1950年代末から60年代初頭にかけて存在した短命のレーベルですが、ソニー・クラーク、ケニー・ドーハム、スタンリー・タレンタインらビッグネームの作品が揃っていることもあり、ジャズファンからは一目置かれているレーベルかもしれません。ただ、それらの作品は既に所有済みのため、今回私が購入したのは本作です。ピート・ルゴロと言われても一般のジャズファンはピンと来ないかもしれませんが、主に西海岸で活躍したアレンジャーで、スタン・ケントン楽団にも在籍。ジューン・クリスティ(本ブログでも過去に「フェア・アンド・ウォーマー」を紹介)やフォー・フレッシュメンらボーカル作品の編曲でも名を挙げています。他に映画音楽やTVドラマの編曲も多く手掛けており、実際この作品も「スリラー」というTVドラマのサントラだそうです。昔のアメリカのTVドラマと言えば「スパイ大作戦(Mission Impossible)」や「アンタッチャブル」なんかは有名ですが、この「スリラー」というのは聞いたことがありませんねえ・・・
肝心の内容ですが、ケントン楽団でアレンジャーを務めたこともあり、同楽団のメンバーを多数起用しています。すなわちトランペットのドン・ファガーキスト、トロンボーンのフランク・ロソリーノ、テナーのボブ・クーパー、アルトのバド・シャンク、ギターのローリンド・アルメイダ、ヴァイブのラリー・バンカー等ですね。いずれもウェストコーストを代表する名手ばかりです。とは言え、あくまでドラマのサントラということもあって、各人が長々とソロを取る場面はなく、ストリングスをバックにしたゴージャスなサウンドの中、各楽器の短いソロが随所に挟まれるといった感じです。なので、本格的なジャズ作品を期待すると少し肩透かしを食らうかも。とは言え、ルゴロの作った曲はどれも魅力的で、普通にサントラとして聞いても楽しめます。メインテーマでもあるおどろおどろしい“Theme From Thriller”、ラテン調の情熱的な“Voodoo Man”、美しいバラードの“Girl With A Secret”、本作中最もジャズ度が高いスインギーな“Twisted Image”、ローリンド・アルメイダのギターが哀愁を誘う“Rose's Last Summer”、ラリー・バンカーのヴァイブが印象的な“Worse Than Murder”等小粒ながらもキラリと光る曲が揃っています。
本日はJAZZ MASTERS COLLECTIONシリーズからハーブ・ゲラーの作品をご紹介します。ゲラーと言えば50年代の西海岸を中心に活躍した白人アルト奏者ですが、一般的なジャズファンの認知度はいかほどでしょうか?同時期に活躍したアート・ペッパーやバド・シャンクに比べればワンランク低いのが実情かもしれませんね。ただ、実力は決して彼らに劣りませんよ。スタイル的にはチャーリー・パーカーの影響を強く受けており、当時流行のウェストコーストジャズよりもだいぶハードバップ寄りなのが特徴です。アルバムとしては奥方であるピアニストのロレイン・ゲラーと共演したエマーシー盤「ゲラーズ」、ケニー・ドーハムやハロルド・ランドと共演したハードバップ色の濃い「ファイアー・イン・ザ・ウェスト」が知られていますが、ジュビリー・レコードに1957年に吹き込んだ本作も知られざる傑作です。クインテット編成でメンバーはゲラーのほかに、ヴィクター・フェルドマン(ヴァイブ)、ウォルター・ノリス(ピアノ)、リロイ・ヴィネガー(ベース)、トニー・ベイズリー(ドラム)という顔ぶれです。後にピアニストとしても活躍するフェルドマンは同年にイギリスから移住してきたばかりで、本作ではヴァイブに専念しています。また、ノリスもフリー・ジャズの旗手オーネット・コールマンと共演したりしていますが、ここではもちろん正統派のプレイに徹しています。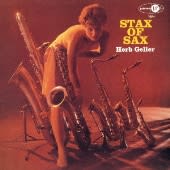
全5曲。レコードで言うA面3曲がゲラーの自作曲で、B面2曲がスタンダード曲という構成です。1曲目は“Nightmare Alley”というユニークなタイトルの曲。哀調あふれるマイナーキーのメロディの曲で最初はスローテンポ、途中から倍速となり、ゲラーをはじめメンバーの熱いソロが繰り広げられます。2曲目の“A Cool Day”はいかにもウェストコーストらしい爽やかなミディアムテンポの曲で、ノリス→ゲラー→フェルドマンの順で軽快にソロを取って行きます。3曲目“The Princess”もシャープなウェストコーストジャズという感じ。4曲目“Change Partners”はフレッド・アステアがヒットさせたというスタンダード曲。モダンジャズでの演奏は珍しいですが、なかなか魅力的なメロディを持つ名曲です。原曲はロマンチックなバラードですが、ここではアップテンポで演奏されており、ドライヴ感満点の名演となっております。ラストを飾る“It Might As Well Be Spring”は言わずとしれたリチャード・ロジャースの名曲。ノリス→フェルドマンの端正なソロに続くゲラーの歌心あふれるアルトが胸に沁みます。4本のサックスの前で金髪美女が奇妙なポーズを取るジャケットのセンスはいただけませんが、サヴォイと並ぶ珍ジャケの宝庫であるジュビリーならではのご愛敬です。内容的にはウェストコーストの隠れ名盤と言ってよいでしょう。
本日はベツレヘムの再発シリーズから、LAの名門クラブ、ジャズ・シティで行われたライブ録音集をご紹介します。バードランド、ヴィレッジ・ヴァンガード、カフェ・ボヘミア等を擁するニューヨークに比べれば地味ですが、当時のLAにも多くのジャズクラブがあり、このジャズ・シティはその代表格だったようです。ただ、ウェストコーストジャズが50年代後半に下火になったのとシンクロするかのように、このクラブも1957年に閉店してしまいます。本作はその閉店を惜しんで、当時の西海岸の著名ジャズメン達が集まって演奏したライブを録音したものです。ただし、3曲とも全て異なるメンバーですので、おそらく同じ日のライブではなく別々に録音されたものと思われます。
まず、1曲目の“I'm Glad There Is You”はアレンジャーのラッセル・ガルシアが指揮するストリングスをバックに、ドン・ファガーキストがブリリアントなトランペットを聴かせるムードたっぷりのバラードです。途中で挟まれるハワード・ロバーツのギターソロも良いアクセントになっています。2曲目はミディアム・テンポに料理されたスタンダード“It Had To Be You”。こちらはフランク・ロソリーノ(トロンボーン)、チャーリー・マリアーノ(アルト)、ルー・レヴィ(ピアノ)、マックス・ベネット(ベース)、ローレンス・マラブル(ドラム)のクインテットによる演奏です。西海岸No.1の実力者ロソリーノのパワフルなトロンボーンと、当時はパーカー直系のバリバリのバッパーだったマリアーノの情熱的なアルトによるアドリブ合戦が繰り広げられ、12分近い熱演となっています。ルー・レヴィらリズムセクションも堅実なサポートを見せています。
そして締めはガーシュウィンのスタンダード“Lady Be Good”(というより同曲のコード進行をもとに書かれたバップ曲“Rifftide”)で、こちらはなんと総勢9人ものメンバーが17分にわたって熱演を繰り広げます。ソロ順で言うとペッパー・アダムス(バリトン)、ドン・ファガーキスト(トランペット)、ハーブ・ゲラー(アルト)、ハービー・ハーパー(トロンボーン)、ビル・パーキンス(テナー)、クローラ・ブライアント(トランペット)、クロード・ウィリアムソン(ピアノ)、カーティス・カウンス(ベース)、メル・ルイス(ドラム)で、中でも泉のようにフレーズがわき出てくる絶好調のハーブ・ゲラーと、バックでメンバーを煽り続けるメル・ルイスのドラミングがグッジョブ!ですね。マニア的には、録音の少ない黒人女流トランペッターのブライアントの参加にも注目です。以上、寄せ集め感はありますが、演奏はどれも素晴らしいですし、スタジオ録音が中心だったウェストコーストのジャズメン達がライブで熱く燃える様が体感できるのも非常に貴重です。もしウェストコーストジャズ=白人中心の軟弱なジャズ、と思っている人がいれば、そんな偏見を取り払うのに最適な1枚かもしれませんね。
とかく日本のジャズファンから過小評価されがちのウェストコーストジャズですが、それでもアート・ペッパー、チェット・ベイカー、バド・シャンクは知名度もありますし、評価も確立しているような気がします。次に来るコンテ・カンドリ、フランク・ロソリーノ、リッチー・カミューカ、ハーブ・ゲラーあたりも玄人筋には評価が高いですね。ただ、西海岸には他にも実力派のジャズメンがたくさんいます。今日ご紹介するベツレヘムのオムニバス企画盤「ジャズ・シティ・ワークショップ」はそんなマイナーな面々の痛快な演奏が収められた1枚です。1955年録音でメンバーはハービー・ハーパー(トロンボーン)、ラリー・バンカー(ヴァイブ)、マーティ・ペイチ(ピアノ)、カーティス・カウンス(ベース)、フランク・キャップ(ドラム)、ジャック・コスタンゾ(ボンゴ)の6人。正直名前だけで「おっ?」と思わせるプレイヤーは1人もいませんね。アレンジャーとして有名なペイチもピアノの評価はそこまで高くないですし、バンカーもヴァイブよりドラマーの印象が強く、ハーパーはモードにリーダー作がありますが、逆に言うとそれぐらいしか聴いたことがない。でも、内容は期待を大きく上回る出来でした。
全8曲。スタンダード曲が中心ですが、アップテンポとバラードがうまく組み合わされて非常に聴きやすい構成です。特に1曲目の“Zing! Went The Strings Of My Heart”、ラストの“Them There Eyes”などアップテンポの曲では、アレンジ重視でアドリブが弱いというウェストコーストジャズへの偏見を吹き飛ばすようなパワフルな演奏が繰り広げられます。ペイチの自作曲“The Natives Are Restless Tonight”ではさらにジャック・コスタンゾのラテン・パーカッションが大きくフィーチャーされ、野性的なリズムで曲を盛り上げます。他ではいかにもウェストコーストらしい明るく健康的な“Serenade In Blue”、トロンボーンによるバラード演奏が美しい“Laura”、そして1曲だけミッキー・リンという女性シンガーが加わったスインギーな“That Old Black Magic”など名演ぞろいです。ウェストコーストジャズの隠れ名盤として自信を持ってお薦めしたいと思います。
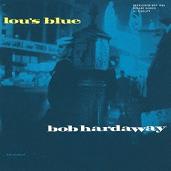
全8曲。全てにマーティ・ペイチがピアノで参加しており、軽妙洒脱な演奏でリーダーを盛り立てます。さらに前半4曲ではラリー・バンカーがヴァイブで参加。マックス・ベネット(ベース)、アート・マーディガン(ドラム)を加えたクインテット編成です。後半4曲はバンカーが今度はドラムに回り、ベースのジョー・モンドラゴンとのカルテットです。8曲のうち6曲がスタンダードで、冒頭の“Irrestible You”はじめ明るくポジティブなウェストコーストサウンドが楽しめます。“Spring Is Here”“I Cover The Waterfront”などバラード演奏も悪くないですね。ただ、本作のハイライトはハーダウェイの自作曲でタイトルにもなっている“Lou's Blue”。疾走感あふれるハードドライヴィングなナンバーで、ハーダウェイ→バンカー→ペイチと軽快にソロが受け渡されていきます。3分半ほどの短さの中にウェストコーストジャズの魅力が詰まった隠れ名曲と言っていいでしょう。













