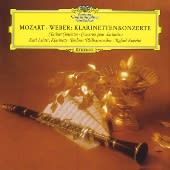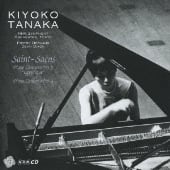
CDは非常に数少なく、出回っているのはジャン=フィリップ・コラール&プレヴィンの協奏曲全集くらいですが、私はあえて日本人ピアニストの田中希代子さんのCDをアマゾンで購入しました。田中希代子さんと言っても私達アラフォー世代のクラシックファンには馴染みがありませんが、50年代から60年代にかけて「東洋の奇跡」と呼ばれ世界的に活躍した日本人ピアニストだそうです。難病の膠原病と言われる病気にかかったため、70年代以降は演奏活動から遠ざかったようですが、その演奏技術が確かであることは1965年録音の本CDを聴けばすぐにわかります。演奏はNHK交響楽団でフランスの名匠ピエール・デルヴォーが指揮しています。なお、本盤には同じくNHK響をディーン・ディクソンが指揮したピアノ協奏曲第4番も収録されていますが、こちらの曲はまあまあと言ったところです。